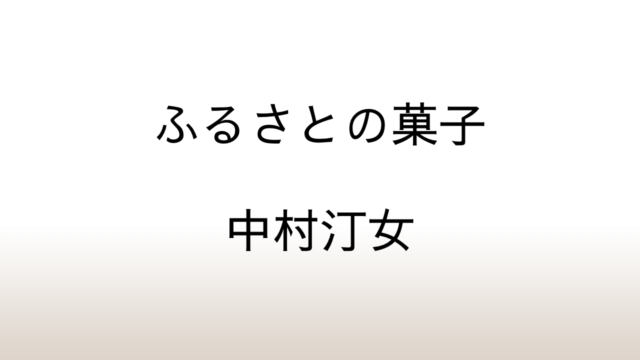福原麟太郎「命なりけり」読了。
本作「命なりけり」は、1957年(昭和32年)10月に文藝春秋新社から刊行された随筆集である。
この年、著者は63歳だった。
庄野潤三が愛した福原麟太郎のエッセイ
庄野潤三の闘病記『世をへだてて』(1987)は、福原麟太郎の随筆の紹介から始まる。
英文学者ですぐれた随筆家であった福原麟太郎に「秋来ぬと」という随筆がある。福原さんの数ある著書の中でも私が本棚から取り出して頁を繰ることの多い随筆集『命なりけり』に収められている。(庄野潤三『世をへだてて』/「夏の重荷」)

「秋来ぬと」は、福原麟太郎の闘病記と言っていい。
秋来ぬと目にはさやかに見えねども、風の音にぞ驚かれぬる。古今集秋の部のまっ先にある立秋の歌である。今年くらい、立秋の待たれたことはない。(福原麟太郎「秋来ぬと」)
「今年くらい、立秋の待たれたことはない」とあるのは、主治医から「この秋になれば元へ帰りますよ」と言われていたからだ。
前年の七月から心臓病を患っていた作者は、満一年を経て、まだなかなか全快とは言いかねる状態で、「夏を越すということが、私の目の前の重い荷物であった」という不安を抱いている。
庄野さんの『世をへだてて』は、福原麟太郎のこうした不安に、自分自身の不安を重ね合わせて綴られているのだ。
もっとも、本書『命なりけり』そのものは闘病記ではない。
新聞や雑誌等に掲載された文章を集めたもので、「これは私の随筆集のうちで一ばん個人的なものである」と、「あとがき」に綴られている。
半生を振り返った「遍歴」は読みごたえがある。
私は汽車で二十分ほどの隣の町の駅から汽車通学をしていたものだから、五時三十五分の汽車に乗る必要があった。母は四時頃から起きて支度をしてくれていた。(福原麟太郎「遍歴」)
福原麟太郎の母校は広島県立福山中学校(現在の福山誠之館高校)で、後輩に井伏鱒二がいた(井伏鱒二に「福原の麟さん」という随筆がある)。
ちなみに、福原麟太郎は明治27年生まれで、井伏鱒二は明治31年生まれ。
在学期間は重なっていなかったらしい。
かつて、高校生だった作者も、現在は老境に入りつつある(「私などの年配になると、まわりの人たちがどんどん死んで、古くからの友人や年とった知己は見る見る減ってゆく」)。
けれども、そういう新しい友人が亡くなった人びとの跡を埋めるものではない。その人たちの残したわが胸の空虚は、いつまでも空虚なのである。そして、そういう空虚のしきりに感じられる時には、みんなあの世へ行っているんだ、もうそろそろ自分も出かけても、それも楽しいだろうという気にもなるのである。(福原麟太郎「遍歴」)
あきらめとか覚悟とかいうよりは、人生を生き切った男の充実感が、そこにはある。
人間というものは実に生長しない。ただ年を取るだけである。昨日思ったことを今日も思っている。二十三歳の思想と六十三歳のそれと、大して違ってはいない。ただ遍歴をしたのだ。(福原麟太郎「遍歴」)
「それが、人間をいとしいものに思わせる」と、作者は続けている。
われわれは、みんな、同級生であった。(略)学校を出て以来、この四十年はなればなれに暮らしながら、結局は、人生という曠野を同じように、四十年遍歴して来たというわけになるのだ。話しあってみると、みんな同じことであったに相違ないのだ。(福原麟太郎「遍歴」)
「この四十年はなればなれに暮らしながら、結局は、人生という曠野を同じように、四十年遍歴して来た」という素晴らしいフレーズが、さらりと出てくる。
ここに、福原麟太郎の随筆の素晴らしさがある。
学生時代の思い出が、最後に「遍歴」という言葉をもって締めくくられる構成もいい。
福原麟太郎は、1894年(明治27年)に生まれた。
大正というのが私どもの青年時代で、もすこし過去へさかのぼれば明治の終り、日露戦争のあとから、関東大震災へかけての間は、何といっても、良い時代であったように思う。それは自分の青春がなつかしく思われるというだけのことかもしれない。それを良い時代であったと思いうるのは、よしんば私たちだけであったにしても、私たちに取っては、たしかに良い時代であったのである。(福原麟太郎「炉辺」)
自分の青春時代を良い時代だったと考えるのは、誰しも同じことかもしれない。
「それを良い時代であったと思いうるのは、よしんば私たちだけであったにしても、私たちに取っては、たしかに良い時代であった」とあるのは、つまり、人生のひとつの真理なのだ(我々世代にとって「バブル時代が良い時代であった」と思われるのと同じように)。
そんなのが大正の時代だ。その時代に、今からかえりみると、われわれ日本国民は、日本という国に信頼を置いていた。わが国というものが確固としてあり、その日本こそ、誇るに足る国であった。そこが今の日本と違うところであった。(福原麟太郎「炉辺」)
「今の日本」とは、戦争に負けた日本である(敗戦国)。
国民が、日本という国に信頼を置かなくてどうするか、自分の国を誇りに思うことができなくてどうするかという、忸怩たる思いが滲んでいる。
大正時代を振り返りながら、作者は、現在の日本国を論じているのである。
同じ文脈の中で、作者は文学を論じてみせる。
谷崎潤一郎には思想が無いという。思想なんか無くともよろしいのである。そこに一つの生活が描かれていれば、その生活の中から思想などいくらでも汲み出せるのである。(福原麟太郎「炉辺」)
思想は読者が汲み取るものであって、「それは人生から、叡智を汲みとるのと同じことである」と、作者は綴っている。
文学の読み方に、きちんと筋が通っている。
私には森鷗外という人の文学が、そんなにすぐれたものとは思えない。(略)私はむしろ初期の創作や翻訳を愛すると答えた。(福原麟太郎「炉辺」)
歴史小説と向き合った「人生の晩年における静かな学究的興味として同感できる」けれども、文学としての森鷗外に、作者は共感することができなかったらしい。
一方で、夏目漱石には、学生の頃から親しんでいた。
十二月九日は漱石忌である。夏目漱石が亡くなったのは、大正五年のこの日であった。私は当時二十二歳の青年であった。(福原麟太郎「炉辺」)
福原麟太郎は『夏目漱石』(1973)という著書を出すほど、漱石に愛着を感じていた(研究ではなく、あくまでも愛着で、庄野潤三との対談も収録されている)。
「炉辺」から「遍歴」へと続く長い随筆は、福原麟太郎という文学者を理解するに、十分な文章となっている。
過ぎ去った時間のことを考えている
「新しい家」は、庄野潤三『世をへだてて』にも登場している随筆だ。
そろそろ小さなお客様方がクリスマス・トリーのそばへ集まって来るころであった。私は二階にいて友人達と話していたが、だしぬけにミヅが頓狂な声で、タマが帰りました、タマが帰りました、と叫んだのをきいた。(福原麟太郎「新しい家」)
行方不明の猫(タマ)が帰ってきたとき、女中(ミヅ)は「タマさんタマさん、あんたはどこへ行ってたの」と言いながら、ぼろぼろ涙をこぼしたそうである。
「治水」も、庄野潤三が特に高く評価した随筆のひとつだ。
朝寝をして起きて見ると、雨である。おや雨かい、と言ってやっと階下へ下りて行って煙草を喫い、新聞を見、ようやく洗面所へ立って、ひげ剃りにかかる序でに窓の外を眺めると、春の雨の特徴は持っているけれども、かなりひどく降っている。庭を見ると、だいぶ水たまりが出来ている。(福原麟太郎「治水」)
1961年(昭和36年)5月10日、河盛好蔵『フランス文壇史』の出版記念会で、初めて福原麟太郎と会ったとき、庄野さんは「治水」の話を持ち出した。
私の日記には、そのあとに、「『メリ・イングランド』『治水』というのを面白く読みましたと云うと、あれ(治水)を読んで貰ったのはうれしい。自分ではいいと思っているのですが、今日まで誰も何とも云ってくれないと云われた」としるされている。(庄野潤三「治水」/『クロッカスの花』所収)

二人の対談でも、同様の話題が出ている。
【庄野】福原さんが昭和九年にお書きになった「治水」という随筆は、わたくし、福原さんの数ある名編の中でも、一番にあげたいと思う随筆なんです。【福原】それは、読んでくださってありがとうございました。(福原麟太郎・庄野潤三「対談 瑣末事の文学」/庄野潤三『山の上に憩いあり』所収)
自然なうねりを作って、辛抱強く道を開いていかなければならないと、庭の水溜りのことを綴っているこの随筆は、実は、そのまま一つの人生の象徴のようになっている(「さあ、水路がついたぞ、水門を開くぞ、という時の彼らの歓喜は実に想像に難くなかった」)。
イギリスのエッセイを愛した庄野潤三だからこそ、この短い作品に惹かれたのだろう。

表題作「命なりけり」も、ひとつの闘病記となっている。
日本の青年たちは、その時代時代のベアトリーチェを持っていた。蘆花の「思い出の記」の敏子とか、漱石の「虞美人草」の糸子とか、三重吉の「桑の実」のおくみとかと並んで、礼子もいた。それは、青年の時代は、誰にも一度しか無いという話にもなるのである。(福原麟太郎「命なりけり」)
「礼子」は、江馬修『受難者』(1916)に出てくる女主人公の名前である。
礼子は、作者が入院している東京大学病院の寄宿舎にいる看護婦で、入院生活を送りながら作者は、『受難者』という小説を熱中して読んだ24歳の頃の自分を思い出している。
彼女は私ばかりではない、われわれの世代の恋人でもあったと言っていい。私は婦長さんと話をしていると、その小説の場面のあれやこれやが目に浮んで来た。婦長さんが、つまり、礼子であるかも知れなかった。(福原麟太郎「命なりけり」)
入院の回想が、そのまま青春の回想へと繋がっていく。
ここに、福原麟太郎の随筆の素晴らしさがある。
福原麟太郎の随筆は、話題の面白さだけで持っているのではない(そんなエッセイなら、人はすぐに飽きてしまう)。
人生の深みを感じさせる構成に、読者は魅了されているのだ。
古本屋で見つけた『命なりけり』には、古い新聞記事の切り抜きが挟まっていた。
福原麟太郎「源の融の予言に従って(わが庭の記)」という随筆で、庭に立つ福原さんの写真が掲載されている(1957年12月4日の鉛筆書きあり)。
67年前の新聞記事を読みながら、僕は過ぎ去った時間というもののことを考えている。
「それを良い時代であったと思いうるのは、よしんば私たちだけであったにしても、私たちに取っては、たしかに良い時代であったのである」という福原麟太郎の言葉を思い出しながら。
書名:命なりけり
著者:福原麟太郎
発行:1957/10/15
出版社:文藝春秋新社