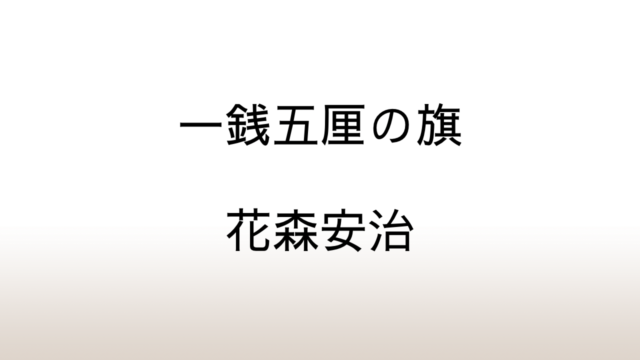小沼丹『懐中時計』読了。
本作『懐中時計』は、1969年(昭和44年)4月に講談社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は51歳だった。
収録作品及び初出は次のとおり。
「黒と白の猫」
・1964年(昭和39年)5月『世界』
「タロオ」
・1966年(昭和41年)5月『風景』
「蝉の脱殻」
・1966年(昭和41年)11月『文学界』
「揺り椅子」
・1965年(昭和40年)7月『日本』
「エヂプトの涙壺」
・1955年(昭和30年)6月『知性』
「断崖」
・1956年(昭和31年)6月『文学界』
「砂丘」
・1956年(昭和31年)8月『文芸』
「影絵」
・1966年(昭和41年)12月『群像』
「自動車旅行」
・1965年(昭和40年)3月『文学界』
「懐中時計」
・1968年(昭和43年)6月『群像』
「ギリシヤの皿」
・1968年(昭和43年)11月『群像』
1969年(昭和44年)、第21回「読売文学賞」受賞。
小沼丹の転機と「大寺さん」の登場
本作『懐中時計』は、小沼丹にとってエポックメイキングな作品集となった。
これまで『村のエトランジェ』(1954)、『白孔雀のいるホテル』(1955)、『黒いハンカチ』(1958)、長篇『風光る丘』(1968)と刊行されてきた単行本は、いずれも、おもしろい物語(ストーリーテーリング)を意識して書かれた作品が主だったのに対し、本作『懐中時計』では「作らない物語」が含まれるようになったからだ。
小説は昔から書いているが、昔は面白い話を作ることに興味があった。それがどう云うわけか話を作ることに興味を失って、変な云い方だが、作らないことに興味を持つようになった。自分を取巻く身近な何でもない生活に、眼を向けるようになった。(小沼丹「『懐中時計』のこと」)
きっかけは、1963年(昭和38年)4月に、妻(和子)が急死したことだった。
小沼さんは、和子夫人の死を題材とした作品に取り組むが、「湿った風が吹いて来たり、べたべたくっつくものが顔を出したり」して、うまくいかない。
ようやく小説が完成したのは、著者の分身である「大寺さん」が登場してからのことだった(「黒と白の猫」)。
この作品集には、おもしろい話を作ることに興味があった時代の作品(「エヂプトの涙壺」「断崖」「砂丘」)と、それ以降の作品が混在している。
つまり、小沼丹の転機を、この作品集では読むことができるということだ。
著者の化身たる「大寺さん」は、「黒と白の猫」「タロオ」「蝉の脱殻」「揺り椅子」で主役を務めている。
また、表題作「懐中時計」はじめ、「影絵」「自動車旅行」「ギリシヤの皿」は、大寺さんではなく、著者本人が主役として登場しながら、懐かしい人々を案内している。
「エヂプトの涙壺」「断崖」「砂丘」との違いを味わいつつ、読み比べてみると、後期・小沼文学の醍醐味を一層楽しむことができるのではないだろうか。
黒と白の猫│妻の急死と大寺さんの登場
小沼丹の文学的転機となった重要な作品。
大学でドイツ語を教えている先輩教師(米村さん)やロシア語を教えている先輩教師(吉田さん)との交流を通して、妻が急死した時分のことを描いている。
「──全く、妙なことになっちゃった」大寺さんは細君の死の前后の話を簡単にした。(略)「──兎も角、死ぬにしてもちゃんと順序を踏んで死んで呉れりゃいいんだけれど、突然で、事務引継も何もありゃしない」(小沼丹「黒と白の猫」)
大寺さんと郊外の墓地を見に行く大学生と高校生の娘は、長篇『更紗の絵』では「ちっぽけな女の子」として登場している子どもたちだ。
全体の進行係に「黒と白の猫」を据えることで、妻の死をさらりと描くことができた。
ロシア語教師(吉田さん)は、横田瑞穂がモデルとなっている。
下の娘(秋子)を「養女にくれないか」ともちかけた米村さんのモデルは不明。
タロオ│飼い犬が導き出す生前の妻の思い出
この小説の最大のポイントは、やはり最後の段落に尽きるだろう。
大寺さんの細君はその二ヵ月ばかり前に突然死んだのである。大寺さんは、近所に大きな団地が出来るので幼稚園を始めようと思っている、というAの話を聞きながら、タロオをルック・サックに入れて持って来て呉れたTも五、六年前に死んだっけ、と思った。そして、みんなみんないなくなった、と云う昔読んだ詩の一行を想い出したりした。(小沼丹「タロオ」)
「タロオ」は、大寺さんの家で飼っていた犬の名前である。
仔犬のときにもらわれてきたタロオの思い出を語りながら、大寺さんは、元気だった頃の妻の思い出を語っていたのではないだろうか。
—タロオが死んだとき、とAは云った。お知らせしようかなんて、うちで話していたんです。そしたら、奥さんがお亡くなりになったと云うんで、吃驚しちゃいまして……。(小沼丹「タロオ」)
犬の思い話が、最後の最後に、大寺さんの細君の死を引き出している。
タロオも、タロオをくれたTも、そして、大寺さんの細君も、みんなみんないなくなってしまった—。
この「みんなみんないなくなった」という短い一行が、この小説のすべてと言っていい。
「みんなみんないなくなった」は、庄野潤三や福原麟太郎が愛したイギリスの作家(チャールズ・ラム)の詩「古なじみの顔」からの引用で、短篇「四十雀」にも登場している。

子どもたちは「小学生になったばかりの娘と幼稚園の娘」として登場。
蝉の脱殻│死んだ人たちへの弔い
死んだ人たちへの弔いの気持ちを、黒揚羽や鬼やんまに託して描いている。
この二、三年の間に、大寺さんは細君とそれから両親を続いて亡くした。数ヵ月前に三度目の葬式を済せたとき、大寺さんは、「──やれやれ、草臥れた」と、何度も独言を云った。(小沼丹「蝉の脱殻」)
酒を飲めない電気屋(光音堂)は、随筆「テレビについて」にも登場している。
翌日、電気屋の主人は約束通り横田家にテレビを持って行った。ところが、奥さんとお嬢さんが驚いて、何かの間違いでしょう、と云う。(小沼丹「テレビについて」/『小さな手袋』所収)
酔った勢いでテレビを買った吉田さんは、ロシア文学者(横田瑞穂)がモデルで、随筆「テレビについて」によると、この後、庄野潤三もテレビを買ったらしい。
猥談で盛り上がる入院患者のグループ(ロビイ会)は、横田瑞穂が入院したときの実話に題材を採っているらしい。
「大楠公」が愛唱歌だった齢下の友人(西田さん)のモデルは不明。
揺り椅子│遠い昔に生きた仲間たちの思い出
小沼丹の作品では、ほんの些細な何かをきっかけに、主人公が、いきなり過去の世界へと放り込まれてしまうことがある。
本作「揺り椅子」において、タイム・スリップのきっかけは、阿佐ヶ谷駅前にあるプールだった。
それは、中央線が高架式となったばかりのことで、この日初めてプールを高いところから見下ろしたとき、そのタイム・スリップはやって来たのだ。
物語の語り手は「大寺さん」であり、物語の主人公は、大学予科で仲間だった(T)である(「──早く齢を取りたいよ」Tはそんなことを云った。)。
「──遠い昔のことだ」と大寺さんは思った。何だか揺り椅子を揺する度に、昔に戻る気がする。大寺さんは秋の夜新宿でTに会ってから、その后一度もTを見ていない。Tが生きているかどうかも知らない。知っているのは、Tが兵隊になったと云うことだけである。(小沼丹「揺り椅子」)
二軒長屋の一軒の階下を借りて、Tは姉さんと二人で暮らしていた。
もちろん、「──早く齢を取りたいよ」と言った、あの頃のTの苦しみを、大寺さんたちは理解していなかった。
その理由を、大寺さんが何となくでも悟ることができるのは、もっと、ずっと後のことだったから。
物語の最後の場面で、大寺さんは、揺り椅子に揺られながら遠い昔を思い出している。
どこに行くのか? 大寺さんは知らない。Tはどんどん歩いて行って、やがて姿を消してしまう。どこに消えたのか? 大寺さんには判らない。揺り椅子に坐って、大寺さんは庭の柿を長いこと見ていた。(小沼丹「揺り椅子」)
大寺さんには、タイム・スリップ癖があったのかもしれない。
さしずめ、揺り椅子はタイム・マシーンだったのだ。
エヂプトの涙壺│嫁を寝取られた夫の悲哀
ストーリーテーリングに興味があった時代の作品。
嫁を寝取られた夫の悲哀を、サスペンスタッチで描いている。
「──俺は考えているんだ。どうしたらいいかをね……。考えているんだ」と、ササ氏は云った。(小沼丹「エヂプトの涙壺」)
小沼丹が勤務していた早稲田大学がモチーフとして引用されているらしい。
主人公の友人(ササ氏)は、50歳に近い英文学の先生で、「ディケンズに現れた英国の国民性に就いて」という演題で講演している。
断崖│嫁を寝取られた男の復讐劇
ドロドロした男女の愛憎模様をサスペンスタッチのミステリー小説で描き出している。
嫁を寝取られた病院長の復讐劇は、火曜サスペンス劇場とかでドラマ化されそう。
「──あの窓の外に」と院長は云った。明日の朝、蝉が死んでいるかもしれない。院長は低い声で笑った。しかし、僕は笑わなかった。(小沼丹「断崖」)
釣れない釣りをしている病院長の釣り姿には、師・井伏鱒二の姿が投影されていると読んだ。
BGMの「薔薇色の人生」が、効果的なアイロニーを生み出している。
砂丘│男を独占したい女の孤独
海岸の小さな部落にやってきた主人公は、海辺の村で不思議な女と出会う。
そして、女に誘われるようにやってきた、若い男の運命──。
マキが僕の脇腹を突附いたとき、宿の主人が呟いた。「──ワキさんのお嬢さんだ」僕らは、ワキさんのお嬢さんを見詰めた。鍔の広い麦藁帽子の下の彼女の顔は、矢張り端麗すぎるほど美しかった。(小沼丹「砂丘」)
小沼丹の昔の作品を読むと、どこか、ゾッとさせられるような怖さがある。
一人きりになった後の女の孤独な人生に、作者の関心は向いていたのだろう。
影絵│関西の古寺に住む伯母の思い出
関西の山の中に住む伯父夫婦の家を訪ねたときの体験が題材となっている。
発狂した少女が鴉に化けた話など、旅先に取材した民話的なエピソードが興味深い。
その后、僕はその山のなかの古寺を訪れたことは無い。だから、伯母を実際に見たのは、その夏の十日間に過ぎない。それから十年ばかりの間に、伯父も伯母も死んだのである。(小沼丹「影絵」)
東京の伯母の法要で、古寺の伯母がひょっこり姿を現したエピソードは、他の作品でも読むことができる。
自動車旅行│旅先で出会った女性の寂しさ
友人の車で関西地方をドライブ旅行中に、渥美半島の海岸の旅館に宿泊したときの体験に題材を採った作品。
本書中では異色の作品だが、酔った女中とのやりとりを中心に、小沼丹らしい惚けた感じが楽しい(ちょっと井伏鱒二の作風に近い感じあり)。
「──美人だね」親爺はそう云った運転係の友人を見て、成程、と云うように点頭きました。「──男好きのする顔で満更悪くないでしょう? しかし、あれはパアだね……」パアだね、にはわれわれも面喰った。(小沼丹「自動車旅行」)
日常を遠く離れた旅先には、なぜか不思議な民話的世界が広がっている。
懐中時計│亡くなった友人(上田友男)の思い出
同じ学校の同じ学部に勤めていた数学教師(上田友男)の思い出を綴った作品。
作中で二人の間を結び付けているのは、一個の懐中時計だ。
この物語の主人公は、友人(上田友男)だが、小説としての焦点は、二人を結び付けている懐中時計に当てられている。
人との交友を題材にするとき、小沼丹は、こうして人間以外のものを主題に据えることが得意だった。
懐中時計の話題は、二人の友人同士の距離感を顕著に示唆してみせる。
多分、その翌日の夕方だったろう、上田友男の所属する学部から電話が掛かって来た。何の用事だろう?と思ったら、それが上田友男の死を知らせる電話であった。──上田友男先生がお亡くなりになりましたので、お知らせいたします、と女の声が云った。(小沼丹「懐中時計」)
冒頭では、二人で大いに酔っぱらって、著者は記憶と腕時計を失ってしまうほどだが、物語の終盤において、上田友男は病気を理由に酒をやめてしまっている。
時間が容赦なく流れていく様子を、懐中時計は、冷静に見つめているわけで、ここに小沼文学の大きな特徴が現れている。
書かれていることは、どうしようもないくらい情緒的なのに、主人公が物体としての懐中時計だから、必要以上にベタベタとなったりしない。
もちろん、著者は、主題と一定の距離を置くために、このような手法を取っているのだろう。
僕は傘を上げて、辛夷の花を見た。図書館の古びた壁を背景に、花や蕾が白く浮んで雨に濡れていた。傘を元に戻して、歩き出そうとしたら、くすん。と、上田友男が鼻を鳴らすのが聞えた。一体、彼奴は何が可笑しかったのかしらん? 僕はそんなことを考えた。(小沼丹「懐中時計」)
上田友男は、一体何がおかしくて、鼻をくすんと鳴らしたのか。
いつものように、その答えは書かれていない。
解説付きの人生なんて、ちっともおもしろくないに決まっているのだ。
「上田友男」のモデルは、「上村」という数学教師だったことが、横田瑞穂のエッセイに明かされている。
上村君は有段者とかで、学内でも有数の碁の名手だということだった。年配も小沼君とほぼ同じで、頑丈な身体つきで、不敵な面構えの持ち主だったが、ぽっくり若死にしてしまった。(略)あとで小沼君はその名作「懐中時計」のなかに淡々と、しかも鮮やかに描き出している。(横田瑞穂「小沼丹君のこと」/『山桃』所収)
横田瑞穂は、本書中のいくつかの作品で「吉田さん」として登場。
ギリシヤの皿│チェーホフの「鴎」が好きだった女
「大学を出る迄数年間、女房の実家にいた」という古い知人(中山二郎)と、その恋人らしき女性との思い出を綴った作品。
中山の実家(酒を造っている)のある町の骨董屋で買った「ギリシヤの皿」が、舞台回しを務めている。
鴎が飛んでいる、と思ったら、途端に遠い記憶の底から、一人の女の顔がぼんやり浮んだから吃驚した。「──あれは、かもめ、じゃないかな?」(小沼丹「ギリシヤの皿」)
突然、行方をくらました女優の記憶が、鴎を見た瞬間によみがえるところは、いかにも小沼丹という感じだ(「『あたしは、かもめなの』という台詞が好きなんです」)。
酒造会社を経営しているのに、酒がまったく飲めないという中山の父親も、良いバイプレイヤーを務めている。
本書収録中で最も新しい作品で(1968年11月)、洗練された小沼文学という印象を与える好短編である。
寂しさを愛する人へ
小沼丹は、人生の綾を巧みに描く小説家だが、通奏低音のように響いてくるのは、亡くなった人たちに対する弔いの意志である。
言い換えると、それは、死んだ人たちを懐かしく思い出す気持ち、ということでもあるかもしれない。
特に、最初の妻を亡くした後の喪失感は、記憶の底に沈む人々をそっと救いあげる技術を編み出したらしい。
逆説的に言えば、懐かしい人々を懐かしく思い出すものは、作者の中にある喪失感である。
小沼さんは、自身の中に潜む寂しさを埋め合わせるために、記憶の中の人々を掘り起こしていたのだろうか。
もしかすると、小沼丹の小説を好む人は、寂しさを愛する人かもしれない。
寂しいという気持ちは決して悪くないものだ、ということを、小沼丹の小説は教えてくれる。
書名:懐中時計
著者:小沼丹
発行:1991/09/10
出版社:講談社文芸文庫