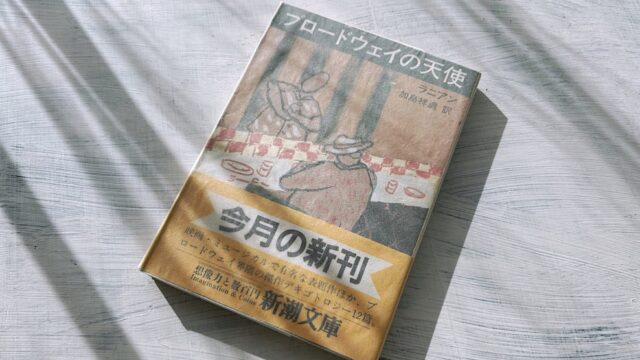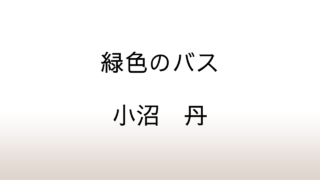吉村昭「羆嵐」読了。
本作「羆嵐」は、1977年(昭和50年)5月に新潮社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は50歳だった。
実際のヒグマ被害事件を題材とした歴史小説
本作「羆嵐」は、実際のヒグマ被害事件を題材とした歴史小説である。
時代は1915年(大正4年)12月。
舞台は、北海道苫前郡苫前村にある三毛別の六線沢という小さな部落だった。
北海道の開拓は、明治初期から本格的に始まっていたが、内地からの移住者は、戦後まで断続的に絶えることがなかった。
海岸線から開拓の進んだ苫前村も、鰊漁を主力産業とする港町として近代化が進んでいたが、本作の舞台となった<六線沢>に開拓者たちが入ったのは、明治44年春のことである。
もともと、東北地方の農家だった彼らは、水害による飢饉で移住を余儀なくされ、政府の移民奨励政策に従って、北海道に移住してきた人々だった。
最初、彼らは指定された築別近くの御料地に入植し、小さな集落を形成していたが、暮らしが落ち着き始めた頃、大規模な蝗害が発生、農地を失った。
政府の指示により、彼らが新たに開拓することになった土地が、この六線沢だった。
村落全体の15戸が移住して、大正4年の冬で5年目を迎えた六線沢は、ようやく村落らしい営みをできるくらいまでになっていた。
ここで興味深いのは、六線沢の集落では、入植後まだ一度も葬式を出したことがない、ということだ。
村落の者たちは、四年以上も前にその地に入植したが、今もって一個の死者も埋葬することをしていなかった。村落には、いつの間にか二個所に小さな墓標の寄りかたまりができていたが、それらはすべて石屋に刻んでもらった先祖代々之墓としるした石標にすぎず、その下に埋葬死体はなかった。(吉村昭「羆嵐」)
開拓地は、骨を埋めて初めて、自分たちの土地になると言われている。
六線沢で初めて出した葬式は、日本害獣史上で最大の惨事として伝えられる、ヒグマ事件の被害者たちだった。
ヒグマは、六線沢の人々を二度に渡って襲撃している。
最初にやられたのが、島川家の人々だった。
かれらの間から呻きに似た声がもれた。顔をそむける者もいた。それは、遺体と呼ぶには余りにも無残な肉体の切れ端にすぎなかった。頭蓋骨と一握りほどの頭髪、それに黒足袋と脚絆をつけた片足の膝下の部分のみであった。(吉村昭「羆嵐」)
人間の肉体の味を知ったヒグマは、次に、中川の家に避難してきている人々を襲った。
わずか二日間で計6名の死者を出したヒグマ事件は、たちまち苫前村全体をパニックへと陥れていく。
ヒグマを仕留めた後の銀四郎の孤独
女性の肉体の味を覚えたヒグマは、執拗に女性を狙うという。
「最初に女を食った羆は、その味になじんで女ばかり食う。男は殺しても食ったりするようなことはしないのだ」銀四郎は、片手で合掌しながら言った。(吉村昭「羆嵐」)
近隣の集落から集まった救援隊も警察も、凶暴なヒグマに怖気づいて役に立たない。
本作は、三毛別の区長の視点から、ヒグマを恐れる人々の心を克明に描き出している。
そして、ヒグマに立ち向かうただ一人の男が、乱暴者として周囲から疎まれていたクマ猟師の銀四郎だった。
小説の後半は、この孤独な猟師の心情が、主な焦点となる。
ヒグマを仕留める場面は一瞬で、むしろ、ヒグマを仕留めた後の、銀四郎の孤独こそが、この物語の主題なのかもしれない。
気象の激変に、男たちは眉をしかめていた。冬期の気候は不安定であったが、風の強さはかれらが今まで経験したこともない激しいものであった。「クマ嵐だ。クマを仕とめた後には強い風が吹き荒れるという」男の一人がおびえたように言ったが、銀四郎は口をつぐんでいた。(吉村昭「羆嵐」)
村の救世主として現れた銀四郎は、期待どおりにヒグマを仕留めた後、再び孤独な猟師として村を去っていく。
史実に人間ドラマを加えた、洗練された歴史小説である。
書名:羆嵐
著者:吉村昭
発行:1982/11/25
出版社:新潮文庫