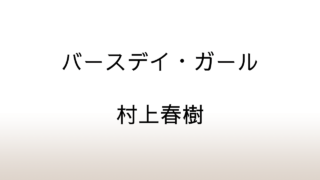村上菊一郎「マロニエの葉」読了。
本作「マロニエの葉」は、1967年(昭和42年)9月に現文社から刊行された随筆集である。
この年、著者は57歳だった。
酒と文学の仲間たち
庄野潤三の作品を読んでいると、村上菊一郎の名前が随所に登場する。
四月二十九日はいい天気に恵まれた。小田急の各駅停車で新宿から来た井伏さん、小沼、吉岡、村上菊一郎さんらを生田の駅で迎え、「まん中の道」を歩いて家まで案内した。(庄野潤三「私の履歴書」)
1961年(昭和36年)4月、東京の石神井公園から神奈川県川崎市生田へ転居した際の家開きの宴には、井伏鱒二や小沼丹、吉岡達夫らと一緒に、村上菊一郎も参加している。

村上さんは酔っぱらうと、私の長女の名前を呼んで、「夏子さーん」というのがクセであった。まだ長女が青山学院の生徒であった頃の話である。(庄野潤三「星に願いを」)
村上菊一郎は、早稲田大学のフランス文学者で、小沼丹(英文学)や横田瑞穂(ロシア文学)とは職場の同僚という間柄だった。
フランス文学の翻訳書には、現在でも読み継がれているものが多い。
また、広島県三原市の出身で、県立福山誠之館中学、早稲田大学では、井伏鱒二の後輩ということにもなる。
杉並区善福寺に居を構えて、阿佐ヶ谷会のレギュラーメンバーでもあったから、むしろ、井伏鱒二人脈の一人として知られているかもしれない。
本作『マロニエの葉』は、雑誌『宴』に連載されたヨーロッパ紀行を中心に、新聞や雑誌に発表された随筆が収録されている。
目次を読むと、最初に「井伏さんのこと」という標題が目につく。
井伏さんは翌年の夏、いちはやく東京に引揚げて行かれたが、それまでの半年間、私は藤原審爾、小山祐士、古川洋三、木山捷平などの疎開組といっしょに、井伏さんを中心に、毎月一回、置酒歓語の集いを持って、敗戦の憂さを忘れることができた。(村上菊一郎「井伏さんのこと」)
「因の島」の警察署長に招かれて、賭博犯一味の逮捕現場に遭遇したときも、村上菊一郎は一緒だったらしい(このときの体験が、井伏鱒二『因の島』という小説になった)。
疎開中には、井伏鱒二とふたり、「酔心」蔵元に招待されたこともある。
主人はうやうやしく「井伏先生、どうぞ十分に召上って下さいまし。自家用酒はあの蔵の中に一杯ございますから」と挨拶した。井伏さんは私の膝をつねって「キクイッツァン、抜かるでないぞ!」と注意した。(村上菊一郎「故郷の話」)
作者(村上菊一郎)の実家も酒蔵だったが、経営がうまくいかなかったらしい。
わたしの研究室には井伏さんの描かれたわたしの肖像画が額に入れて懸けてある。昭和三十六年三月、小林龍雄教授(井伏さんと早大仏文科同期)の渡仏歓送会を中野の料亭でひらいた夜、井伏さんが戯れに色紙に毛筆で描かれたものである。(村上菊一郎「書画と植木」)
井伏鱒二作の肖像画は、本書『マロニエの葉』の口絵で見ることができる。
作者(村上菊一郎)は、井伏さんの書も所有していたらしい。
井伏さんは一瞬、なんというあわれむべき恐妻家だろうと鼻白んだ表情をされたが、それでも奥さんに命じて志那紙を取出させ、次のように一筆認ためて下さった。「送り状 遅きを許せよ かしこ 井伏鱒二 村上夫人様」(村上菊一郎「書画と植木」)
井伏邸で飲み明かしたという証明書を、作者は井伏さんに求めたのである。
井伏さんから寒竹を分けてもらった話も楽しい。
井伏さんの寒竹に関しては、小沼丹の随筆にも書かれているとおりだが、「わたしの場合も事情はまったく同じである」と、作者は綴っている。
たしか十余年前に、わたしは小沼君といっしょに寒竹の数株を分けて頂いたのだった。(村上菊一郎「書画と植木」)
酒と文学と植木の好きな風流人のコミュニティが、そこにはある。
谷崎精二を囲む「竹の会」が発足したとき、「地理的関係から浅見淵氏、小沼丹氏、小生の三人が世話人役を引受け、早大南門前の茶房『早稲田文庫』で、小宴をひらいたのがこの会のはじまりだった」とある。
木山捷平氏は記念の署名帳に、パチンコのせいか神経痛のせいかつまびらかにしないが、「今宵わが指痛む!」と記せば、続いて小沼氏は、「今宵わが胸痛む」と書こうかと隣りの小生に相談して茶目っぽく笑う。(村上菊一郎「竹の会」)
木山捷平の右手薬指が、新庄嘉章の暴行によって負傷するのは、1964年(昭和39年)2月の「竹の会」だから、このときの「今宵わが指痛む!」とは関係がない(1955年の随筆)。
「竹の会」については、小沼丹の作品でも詳しく読むことができる(『藁屋根』所収)。

同じく早稲田大学でフランス文学を教えていた新庄嘉章とは、酒仲間でもあったらしい。
梯子酒の悪癖では、去年の秋新庄教授と新宿で飲み出して一しょに西荻窪へ辿りつくまでに、中央線の各駅で下車して八軒を記録した。(村上菊一郎「酒の悲しみ」)
よほど酒が好きだったのか、酒にまつわる文章が多い。
数年前、ある酒席で、上林暁さんが「酒は私の一の友、二の友、三の友である」と色紙に書いてくれたことがある。(酒徒五つの楽しみ)
村上菊一郎の酒は、仲間と楽しく飲む酒だったようだ。
胃をわずらってしばらく禁酒していたロシヤ文学の横田瑞穂さん(通称ミズホイッチ・ヨコチンスキー)が「酒が飲めないと世の中ってあんなに味気ないものですかねえ。自殺したいほどでしたよ」と述懐していたが(略)(酒徒五つの楽しみ)
やはり、大学関係者の酒席が多い。
午後、大隈会館で、小沼、横田、室の諸氏とビールを飲んで小憩。新築中の文学部研究室を下検分に行く。夕方、打ちつれて新宿『樽平』にくりこむ。(村上菊一郎「日記について」)
「室氏」とあるのは、小沼丹の作品にも登場する室淳介のこと。
早稲田と慶応の先生方で飲み比べをしたときの話もある。
ワセダ勢は佐藤輝夫ヴィヨン博士を監督に、斎藤一寛、恒川義夫、川島順平、河合亨、安井源治、室淳介、稲田三吉、品田一良、小生とO・B、と新鋭あわせて十名意気揚々と座につけば、迎えるケイオー勢は、監督の佐藤朔ボードレール博士以下、横部得三郎、二宮孝顕、白井浩司、大浜甫、永戸多喜雄、若林真、高畠正明、原田芳郎、原宏とこれまた同じく十名の精鋭が手ぐすね引いて待構えていた。(村上菊一郎「酒の早慶戦」)
早慶両大学の仏語仏文学関係者による忘年会が、毎年、恒例となっていたらしいが、この夜は、新庄嘉章、小林龍雄、青柳瑞穂、大久保洋が欠席だった。
「ハモニカ横丁をしのぶ会」というのもあった。
新宿「高野」の横の焼け跡に戦後立並んだ十数軒のバラック建ての間口の狭い飲み屋街のことを、人呼んでいみじくもハモニカ横丁といい、そこで飲む怪しげなカストリ焼酎は、当時のわたしたちの憂さのすてどころだった。(村上菊一郎「初夏の宵々」)
当夜は、ベニヤ板の模擬店七軒が再現されて、池島信平文春社長からマダム連に対して表彰状が贈られたという。
戦後の出版業界に関わった人たちの逞しさが感じられるようなエピソードである。
時代を超えて旅に出かけたい
本書の前半には、ヨーロッパ紀行の文章が並ぶ。
村上菊一郎がフランス・パリに滞在したのは、東京オリンピックのあった年(1964年/昭和39年)で、早稲田大学の関係者に見られた半年間の海外留学だった(ロンドンに滞在した小沼丹も『椋鳥日記』を書いている)。
午後四時ふたたび地下鉄に乗り、シュリ・モルランで下車し、すぐ目の前にあるセーヌ河の中の島「サン・ルイ島」に渡って、ひっそりとしたアンジュー河岸沿いの石畳の道を漫歩する。九番地の建物には、オノレ・ドーミエが住んでいた家という標識がかかっている。(村上菊一郎「パリ日記抄」)
とりとめのない旅行日記に、興味深いものが多い。
セーヌ河の下流の、パリ西南の隅っこにミラボー橋がかかっている。なんのへんてつもない殺風景な橋ではあるが、対岸のオートゥユ街に住んでいた詩人アポリネールが、「ミラボー橋」という詩を書いて以来すっかり有名になってしまった。(村上菊一郎「パリの空の下セーヌは流れる」)
アポリネールの失恋の相手は、女流画家マリー・ローランサンで、こういう文章を読んでいると、フランス文学を読みたくなるから不思議だ。
表題作「マロニエの葉」は、職場の同僚(小沼丹)へのお土産の話。
ぼくは作家の小沼丹君からパリのカフェのジョッキ敷きをできるだけたくさん集めてきてくれと頼まれていた。(村上菊一郎「マロニエの葉」)
小沼丹君がコップ敷き(コースター)を蒐集していたのは有名で、村上菊一郎のパリ土産についても、自分のエッセイに綴っている。
ところで小沼君は無料の土産ものばかりねだる癖があると見えて、次の手紙では「ドイツ留学の友人から菩提樹(リンデンバウム)の葉をもらいました。大兄はパリのマロニエの葉を持ってきて下さい」といってよこした。(村上菊一郎「マロニエの葉」)
本書表紙にあるマロニエの葉の写真は、作者が、小沼丹へのパリ土産として持ち帰ったものである。
先日の午後は津島園子さんをそのアパルトマンに訪問した。津島園子さんといっては知る人も少ないだろうが、太宰治の長女である。(村上菊一郎「パリのさくらんぼ」)
朝市の露店に、太宰の好きだったさくらんぼが並んでいるのを見て、作者は桜桃忌の近かったことを思い出す。
現地でも、日本人同士の交流は多かったらしい。
ぼくは六月下旬の一夜、芹沢光治良氏の次女、滞仏五年の二十二歳のピアニストである玲子さんに案内して貰って、パリ滞在中の寺崎浩さんといっしょに、この地区の有名な地下酒場へ出かけた。(村上菊一郎「続パリあれこれ」)
『巴里に死す』で有名な芹沢光治良は、戦前のソルボンヌ大学に学んでいる(東京帝国大学卒業後に入省した農商務省を退職して渡仏)。
「芹沢光治良氏の次女である玲子さん」とあるのは、「四女」で誤りで、ピアニストの岡玲子のことだと思われる。
夏休みを利用して、同僚の弓削三男君が、夫人コレットさんを伴って、ソ連経由でパリにやってきた。コレットさんはパリジェンヌで、五年ぶりの里帰りである。弓削君は前に九州大学で教鞭をとっていた関係上、久留米の詩人ドクター石田光明氏、福岡の洋裁学院長S女史、その知人のN女史、九州大学出身の留学生奥村嬢が弓削君夫妻と同行でパリに現われ、寺崎さんの帰ったあとのぼくの身辺は急に賑やかさを取戻した。(村上菊一郎「美しい港町オンフルール」)
日本の文化人の名前が並んで賑やかな様子が目に浮かぶが、なにしろ、中年男の単身旅だから、現地のパリジェンヌに気を惹かれることも少なくなかった。
ぼくは店に入って冷たいロゼ(もも色)のぶどう酒と簡単な一品料理を注文した。娘さんは栗色の髪でフランス女特有のしゃくれた鼻の先をしているが、健康そうな丸顔で中肉中背、年のころは二十四、五であろうか、地味な黒っぽい上着の下に胸のふくらみが色っぽい。(村上菊一郎「パリの岡惚れ」)
この女性は、後に子持ちの人妻と分かって「いっぺんに熱が冷めてしまった」とあるからおかしい。
わたしは一軒の店で手頃な大きさのコーヒー挽きを見つけ、値段をきくと一二フラン(約九百円)だという。一〇フランに値切ってみたが、材質はくるみ材でいまでも十分に使用できる品だからとうてい負けるわけにはいかないとの返事だったので、そのまま買い求めてしまった。(村上菊一郎「のみの市」)
のみの市で買い物したのは、これひとつだったが、このコーヒー挽きは、帰国後も自宅で重宝したという。
パリの百貨店「サマリテーヌ」ではベレー帽を買った。
十一月四日、庄野英二の野間児童文学賞授賞式のつどいにももちろん着用して出席した。そしてその宵は、受賞の当人と弟の庄野潤三が待っているという新宿のトンカツ料理屋へ、小沼丹(作家)、横田瑞穂(ロシア文学者)、伊馬春部(劇作家)の面々といっしょにはせ参じて、内輪の祝宴をもよおした。(あわれベレー帽)
宴席で伊馬春部にねだられて、作者はお気に入りのベレー帽を譲るが、酔った伊馬春部はベレー帽のことなど、まったく記憶になかったらしく、当夜のうちに、どこかへ置き忘れてしまったという。
本書には、ヨーロッパ以外の紀行文も多い。
「病みつき」は、学生の石口君に誘われて魚釣りへ出かける話。
帰りの電車の中では、私の肩に何遍も角帽をぶつけて居眠りをする石口君を眺め、立川基地のパンパン嬢がしきりに笑っていた。笹の葉で蔽った魚籠の中の獲物は、車窓から吹込む秋風にほのぼのと匂った。(村上菊一郎「病みつき」)
戦後まもない時代の魚釣り風景が伝わってくる。
駅から松江大橋のほうへぶらぶら歩いてゆく途中、とある瀬戸物屋の店先に東京では珍しい二合入りの徳利が数本並んでいるのが目についた。土ぼこりをかぶってはいるが、美しい呉須の色から察するに有田焼の陶器らしい。(村上菊一郎「松江の旅」)
高度経済成長期、地方へ行けば、まだまだ掘り出し物の見つかる時代だった。
山陽線福山駅から福塩線の電車に乗り換えて二十分ぐらい行くと万能倉(まなぐら)という奇妙な名前の小駅がある。その部落の街道に面した小さな薬局の主人が詩人木下君である。(村上菊一郎「木下夕爾追悼」)
木下薬局から街道をさらに一時間も北へ向かって歩いていくと、井伏鱒二の故郷「加茂村」へたどり着くのだという。
海外紀行も良いけれど、日本の地方都市を訪ねる紀行文には、現在では失われてしまった懐かしさがある。
高度経済成長は、あまりも、日本の地方を(均一的に)変えてしまったのだ。
「尋ね人顚末記」は、志賀直哉『暗夜行路』に登場するお婆さん(田組アイ)を探したときの体験を綴っている。
見るからに汚い馬小屋に似た粗末な三軒長屋が眼の前にある。土堂町三百八十四番地である。半世紀以上の風雨にさらされ、柱も傾き、壁も落ちかかり、いつこわれるかわからないような大変なぼろ家、これが日本文学史の記念すべき遺跡?であるのか。(村上菊一郎「尋ね人顚末記」)
志賀直哉『暗夜行路』の舞台となった長屋には、この後、文学碑が建てられることになったという。
村上菊一郎の故郷・三原市は、志賀直哉が『暗夜行路』を書いた尾道市の隣町だった。
時代を超えて旅へと出かけたくなるような、そんな随筆集である。
書名:マロニエの葉
著者:村上菊一郎
発行:1967/09/30
出版社:現文社




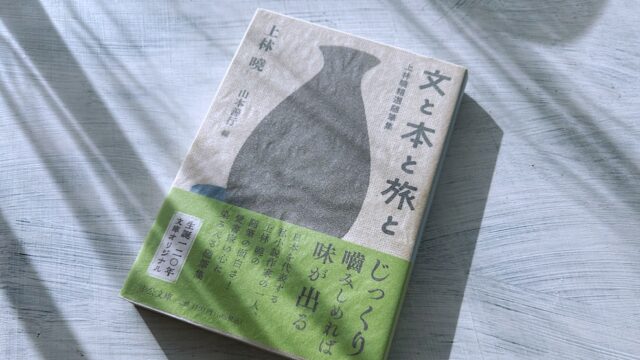

-150x150.jpg)