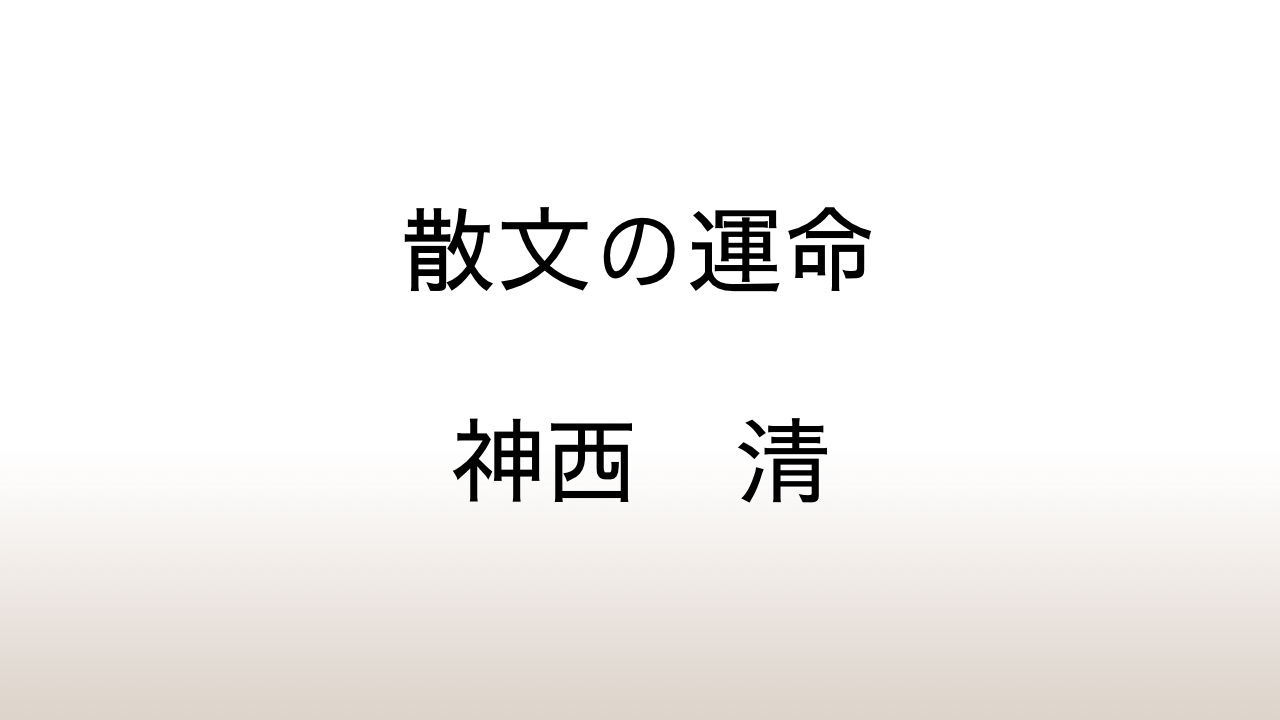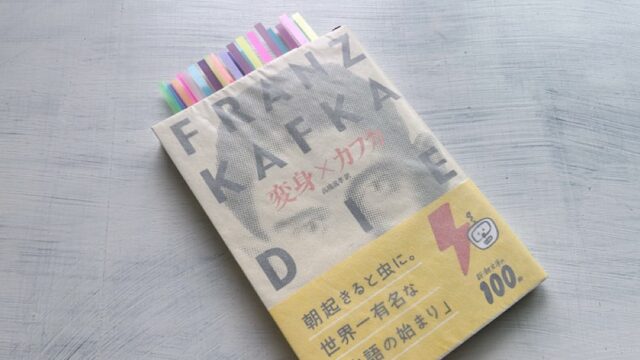神西清「散文の運命」読了。
本作「散文の運命」は、1957年(昭和32年)、講談社から刊行された随筆集である。
この年、著者は53歳で没している。
僕の小説は瑪瑙を切ったようなものだよ
本書は、神西清の文学的評論や作家論をまとめた随筆集である。
内容的には、万葉集など日本の古典から太宰治や三島由紀夫などの現代作家、そして、チェーホフを初めとするロシア文学まで、非常に多岐に渡る充実の文学論集となっている。
しかし、「散文の運命」を通読したときに感じるものは、作家論を通じて表わされる神西清という一人の文学者の人間性ではなかっただろうか。
それが最も良く理解できるのが、親友・堀辰雄について書かれた複数の文章だろう。
それから何年かたって堀君が牛込の家に、僕を訪ねてくれたことがある。春だったようだが、くろっぽいさらりとした着物に角帯をしめ、腰に印伝皮のタバコ入れをはさむといういでたちであったから、こんどは僕の母が、呆気にとられるという始末だった。くらくならないうちに彼は辞去したが、そのあとで天どんの盆をさげにきた僕の母は、「まあ、あれが堀さんかい。あれで大学へ通いなさるのかえ」と、真顔で僕にたずねたものである。(上西清「年少の頃」)
「まあ、あれが堀さんかい。あれで大学へ通いなさるのかえ」という、お母さんの台詞がいい。
お洒落な堀辰雄に対する憧れのようなものが、彼のエッセイからは感じられるのである。
印象に残ったのが「瑪瑙を切る」という文章である。
「僕の小説は瑪瑙を切ったようなものだよ──」ある夜のこと、堀辰雄が夢に出て来てそんな意味のことを僕に言った。……この言葉が今でも僕の耳の底に妙な余韻をのこしているところを見ると、ひょっとしたらこれは夢じゃなくて、現実の堀が言ったのだったかもしれない。(上西清「瑪瑙を切る」)
堀辰雄は「自分についてにせよ他人についてにせよ、これほどの名句の十や二十ぐらい、名刺代わりにいつでも上着のポケットの中に用意している男だ」と、著者は続けている。
文学を読むにあたって、このくらいの表現力は身に付けておきたいものだと思った(昔の人は、本当に粋なことを言う)。
さらに、堀辰雄のエピソードをもうひとつ。
『聖家族』の限定版に署名をするためのペンとインキを、堀辰雄は神西清と一緒に探して歩く。
伊東屋の二階で、神西の勧めるペン先が見つかるが、肝心のペン軸が品切れでないという。
結局、堀辰雄は、神西推薦のペンを丸善から入手するが、それは『聖家族』の署名には使われなかったらしい。
さらに数日を経て、僕は限定版『聖家族』の貴重なる一本の恵贈を受けました。添書に曰く、「この署名に使ったペンとインキは出版屋の二階にころがって居たものなり。ペンはあたり前のペン、インキは銀行で手形を書くとき使用するものの由」云々。(上西清「「聖家族」署名まで」)
文学に対する二人の誠実な姿勢を伝えるエピソードだと感じた。
なにより、堀辰雄の、上西清に対する信頼ぶりが伝わってくるような話ではないか。
太宰文学の本質は、つきつめて言えば君、祈りだよ
太宰治に対する著者の考え方は、<洋画家>と<私大講師>の会話の形式を取って描かれている。
そうだ、太宰文学の本質は、つきつめて言えば君、祈りだよ。僕はさっき「離愁」なんていう言葉を使ったが、あんなことじゃまだまだ言い足りないのだ。一つの強烈な矢じるし、身も世もあらず飛翔する一本のヴェクトル、──つまり祈りなんだよ。(上西清「斜陽の問題」)
これは、1948年(昭和23年)1月号の『新潮』に発表された太宰治論である。
前年の1947年(昭和22年)12月に発売された太宰治の『斜陽』はベストセラーとなるが、上西清「斜陽の問題」は、まさしくその渦中において発表された太宰治論だった。
今でこそ、「太宰治」も『斜陽』も定番の地位を獲得しているが、終戦直後、太宰治はまだまだ都会の作家であり、文学的な評価が定まるには至ってなかったとも言われる。
むしろ、この『斜陽』こそが、文壇における太宰の地位を確固とした作品だったのかもしれない。
「太宰文学の本質は、つきつめて言えば君、祈りだよ」という言葉は、分かりやすくて親切な言葉だと思った。
書名:散文の運命
著者:上西清
発行:1957/8/31
出版社:講談社