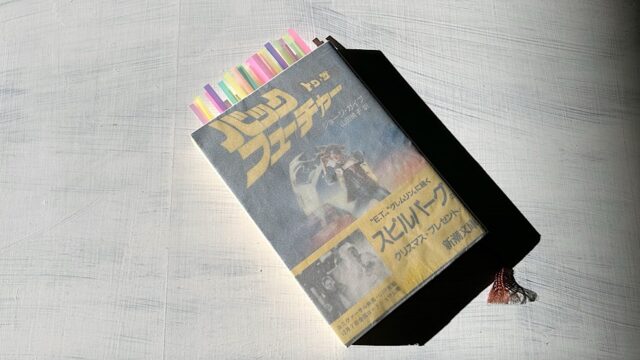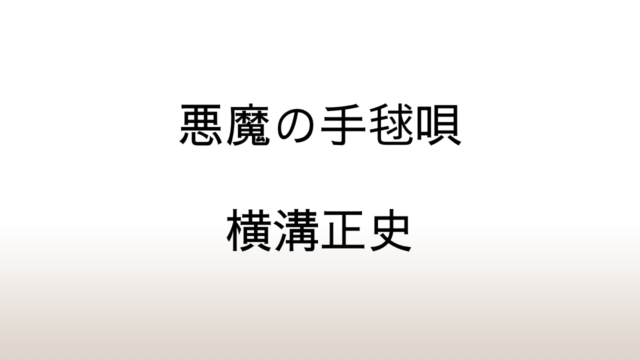ジャック・シェーファー『シェーン』読了。
本作『シェーン』は、1949年(昭和24年)にアメリカで刊行された長篇小説である。
この年、著者は42歳だった。
1953年(昭和38年)公開の西部劇映画『シェーン』の原作小説である(ジョージ・スティーヴンス監督、 主演はアラン・ラッドだった)。
スターレット夫妻とシェーンとの三角関係
本作『シェーン』は、西部開拓地で暮らすスターレット夫妻と旅の男(シェーン)との三角関係を描いたラブロマンスである。
映画『シェーン』の魅力は、主演男優(アラン・ラッド)の演技力に尽きるが、原作小説を読むと、奥深いストーリーがあったことに気がつく。
筋書きの中心となっているのは、人妻(マリアン・スターレット)と旅人(シェーン)との難しい恋愛関係だった。
母はためらった。それから、顔を上げた。「ええ、はっきり言った方がいいわね。私にはあんたが要るんです」(略)彼はじっと母を見た。「マリアン、あんたは何を頼んでいるのかわかってるんですか」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
クリスをボコボコにしたシェーンが、物事をこれ以上混乱させないために、スターレット家から出て行こうと考えていたとき、彼を引き止めたのは人妻(マリアン)だった。
彼女は、もちろん、自分に対するシェーンの感情をはっきりと理解していた。
シェーンは深く息を吸って、ゆっくり吐いた。彼は母親に笑顔を見せたが、ぼくにはその笑顔が何となく痛ましく見えた。「ジョーは、あんたのような奥さんを持って鼻が高いでしょうな、マリアン」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
人妻(マリアン)に手を出せない以上、スターレット夫妻と同居生活を続けることは、シェーンにとって大きな苦痛だったはずだ。
同時に、それは、夫を愛しながらシェーンをも愛してしまった、人妻(マリアン)の苦しみでもあった。
母の声は高くなり、後ろと前を見ながら、自制心を失っていた。「こんな男を二人も持った女っているかしら」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
もちろん、マリアンは強く自分を律することのできる女だったから、簡単にシェーンと寝たりはしない(そこが今どきの不倫妻とは違う)。
彼女は、自分の心を殺しながら、夫(ジョー・スターレット)を愛し続ける。
「マリアン、苦しむのはおよし。あの男の道とおれの道がぶつかった時には、どうすればいいかぐらいは心得てる。どうなろうと、大丈夫だ」「ジョー…ジョー! 接吻して、しっかり抱いて、放さないでちょうだい」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
愛妻(マリアン)の心を誰よりも理解していたのは、夫(ジョー)だった。
「おれはな、マリアン。お前の力であの男の戦いを勝たせてやってもらいたいんだ。お前なら、できるんだ」父は淋しそうにちょっと笑ってみせて、その姿はぼくの頭上に世界中で一ばん大きな人間のようにそびえ立っていた。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンを一人の男として尊敬していたからこそ、ジョーはマリアンの心を許そうとしていた(淋しそうに笑いながら)。
「マリアン。おれが知らないと思うのか?」「でも、あんたにはわからないわ。本当はね。わかるはずがないのよ。だって、私にもわからないんだもの」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
二人の男と一人の女は、それまでどおりの関係を保とうと努力する。
この西部小説は、そんな複雑な三角関係によって支えられてた。
牧場主(ルーク・フレッチャー)の連れてきたガンマン(スターク・ウィルスン)が、マリアンを侮辱したとき、シェーンの怒りは沸点に達していたのかもしれない(「スターレット、よく考えな。(略)窓のとこにいるあの女も勝手にされるぜ」)。
「そうだ」と、シェーンが静かに言った。「男なら黙っていない」彼は母だけを見ているのではなかった。父と母を見ていた。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンは、マリアンへの愛を押し殺してまで、スターレット夫妻を守ろうと覚悟していた。
三人はお互いの顔を見なかった。ひと言も交わさなかった。(略)三人は自分自身の気持ちを知り、それぞれ、ほかの二人が事情をよくのみ込んでいることを知っていた。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンが自分の心を制していたのは、彼もまた、ジョー・スターレットを一人の男として認めていたからだ。
ウィルスンとの決闘へ出かけるとき、マリアンは自分の本心を打ち明けようとする。
「これから私がすることも、あなたが、いま言うことで決まるのよ。あなたはこのことを、ただ私のためだけにするの?」シェーンはしばらくためらっていた。(略)「ちがう、マリアン。あんただけを心の中で別に考えて、それで私が男になれると思うのですか?」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンさえ、自分の気持ちを打ち明けていれば、彼らは熱いキスを交わしていたに違いない(あるいは、もっとそれ以上のことも)。
しかし、シェーンは、やはりシェーンだった。
宿敵(ウィルスン)とフレッチャーを撃ち殺した後で、シェーンは少年ボッブに言った。
「これからは、坊やの仕事だ。お母さんとお父さんのとこへお帰り。強く正直に育って、しっかり親の世話をするんだ。二人ともだよ」「ええ、シェーン」「いまとなっては、おれがあの二人にしてあげられることは一つしかないんだ」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンにできることは、二人の前から静かに姿を消すことだった。
二人が育んできた愛を、二人が培ってきた家庭を壊してしまう前に。
やせ我慢と言えば、それまでかもしれない。
しかし、それが開拓時代のアメリカを生きた男の美学だった。
過去からやって来て、過去へと戻っていった男
西部劇映画を知ることは、アメリカの歴史を知ることでもある。
時代は、西部開拓時代だった。
彼がぼくたちの住んでいた盆地へ馬を乗り入れて来たのは一八八九年の夏のことだった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
アメリカの「フロンティア消滅宣言」(国土の未開拓地(フロンティア)がなくなったことをアメリカ政府が公式に発表した)が出されるのは1890年のことだから、1889年のワイオミング州を舞台とする『シェーン』は、まさしく最後のフロンティア物語だった。
1830年代から始まったアメリカ西部の開拓は、ゴールドラッシュや南北戦争(1861年~1865年)を経て、大陸横断鉄道の建設事業に象徴される本格的な開発時代を迎える。
1862年に成立した「自作農法」は、西部地域の開拓を促進する一方で、広大な土地で牛を飼う牧場主と、新しく土地に定着する農民との間でトラブルを引き起こす一因ともなった。
牧畜は、カウボーイのイメージによって西部を象徴するものであるが、それまでの解放牧地からの転換を強いられる。農業技術の進歩により、これまで農地としては不適格と思われた土地の開墾が可能になり、移住した農民が有刺鉄線を張って農地を囲い込むようになったのである。(吉田広明「西部劇論」)
当然、先に入植していた牧畜業者と新たに移住した農民との間で争いが置き始める。
『シェーン』は、そんな時代の物語だった。
不朽の名作『シェーン』は、そうした古い牧場主と新しく入植した農民との戦いを描いた。流れ者のシェーン(アラン・ラッド)と殺し屋のウィルソン(ジャック・パランス)の決闘は、いわば双方の代理戦争というべきものであった。(芦原伸「西部劇を読む事典」)
ジョー・スターレットは、新しい時代の農民である。
「開けっぴろげの牧場は永久に続くもんじゃない。柵ができてくる。広い土地で牛を飼うのは、一流の牧場業者ならいい金になるだろうが、それも、実際には大して有利なことじゃない。土地ということを考えれば、つまらん仕事だ。広い土地が必要でもうけは少ない。かならず落伍するんだ」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
ルーク・フレッチャーとジョー・スターレットとの争いは、「古い時代」と「新しい時代」との争いだった(映画ではジョー・スターレットのライバルは「ルーフ・ライカー」となっている)。
多くの西部劇映画が時代の変わり目を描いているように、『シェーン』もまた、時代の移り変わりの中から生まれてきた物語だった。
「ふん」と母は、ぼくにというよりは自分に言った。「物を覚えたよ。ここはダッジ・シティじゃないわ。汽車が停まる町でもない。ここはジョー・スターレットの農場なんだね。私はここにいることを自慢していいのだわ」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
カンザス州の「ダッジシティ」は、1870年代に生まれた典型的なキャトルタウン(牛の町)である。
鉄道が西部まで延びたことで、牛の市場を目指して訪れる仲買人や牧童たちが、そこには集まっていた。
スターレット農場のある町は、発展途上の町だった。
ぼくたちの町は小さく、まだ、町の形をなしていなかった。大きくなりつつはあったが、まだ、街道に沿ってわずかの建物が集っているにすぎなかった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
新しい時代を見据えて、そこは、これから大きくなっていく町だ。
それは、いつか大人になるだろう少年(ロバート・マクスファーン・スターレット、愛称ボッブ)に似ていたかもしれない。
この物語の語り手が、ジョーやマリアンといった大人たちではなく「少年ボッブ」だったということが、彼らが生きていた時代を象徴していたとも言える(映画では語り手の少年は「ジョーイ・スターレット」となっていた)。
そこは、まさしく「成長時代」の西部開拓地だった。
主人公(シェーン)は、過去からやってきた男である。
「どこでも同じだ」と彼は呟いた。それはひとり言を言っていたのだ。「古いものは滅びてゆくんだ」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
古い時代と新しい時代の狭間で、シェーンは行き詰まっていた。
父ははっきりと彼の顔を見た。「あんたは何から逃げているのかね」シェーンはながい間、前の皿を見つめていた。ぼくには、悲しみの影が彼をかすめたように思えた。それから、彼は眼をあげて、父をまっすぐ見た。「いや、私は何からも逃げてはいない。あんたのいう意味ではね」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンが逃れようとしていたのは(過去の)自分自身からである(「いや、ウィル。クリスが怖かったんじゃない。自分が怖かったんだ」)。
かつて、古い時代を生きたシェーンにとって、新しい時代は生きにくい時代だった。
それでも、彼は、彼なりに新しい時代を生き延びていくために、過去の自分を封印しようとしていたのだ。
彼は過去について一言も言わなかった。名前でさえ、謎だった。ただ、シェーンなのだ。名前であるのか、苗字であるのか、あるいは、家族の誰かの名前であるのか、何もわからなかった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンは、アメリカ南部の出身者だった。
「私の両親はミシシッピから出てアーカンソーに移住したんです。だが、私は放浪癖があって、十五の時に家を飛び出した。それ以来、フランネル・ケーキといえる物は食べたことがありません」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
シェーンが姿を消した後で町の人々は、シェーンの正体について様々な噂をした。
通りすぎる旅のものの話から、彼はアーカンソーからテキサスを股にかけていたシャノンという賭博打ちで、人殺しとしても名が高く、いつどうして姿を消したかは誰も知らないというような噂も広がった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
しかし、シェーンはシェーンであり続けようとしていた。
もしも、ジョー・スターレット(あるいはマリアン・スターレット)との出会いがなければ、そして、ルーク・フレッチャーとのトラブルがなければ、彼はシェーンのままでいることができたかもしれない。
しかし、彼は過去から逃れることはできなかった。
ウィルスンとの決闘へ出かけるとき、彼は既に昔の彼へと戻っている。
彼は、ぼくが最初の日に見た黒く険しい男だった。誰も知らない孤独の過去から、ひっそりと出て来た見知らぬ男だった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
もちろん、シェーンは、自分が過去から逃れることのできない男であることを、誰よりも理解していただろう。
「人を殺せば、後へは戻れないんだよ、ボッブ。正しかろうが、まちがっていようが、いちど烙印を押されたら、後へは戻れないんだ」(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
ジョーイが「シェーン、カムバック!」と叫ぶシーンは、アメリカ映画史に残る名場面として記憶されている。
一時期、映画のラストシーンについて「最後の決闘で撃たれたシェーンは死んでしまったのではないか?」という推測もあったが、原作小説でも、シェーンの死をほのめかす記述はない(ついでに言うと、ボッブ少年が「シェーン、カムバック!」と叫ぶシーンもない)。
ぼくは彼の姿を追って、目を見すえた。(略)後ろのポーチにはひとびとがいたのだが、ぼくの意識の中にあったのは、道路のはずれに小さくなって、かすんでゆく黒い影だけだった。雲が月にかかり、彼の姿は闇にとけて見えなくなった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
過去からやってきた旅人(シェーン)は、過去の中へと戻っていったのだ。
彼は開けゆく大西部の魂から抜け出して、ぼくたちの小さな盆地に馬を乗り入れ、その務めを果たしたとき、ふたたびもと来たところへ戻っていった男であった。それがシェーンなのだった。(ジャック・シェーファー「シェーン」清水俊二・訳)
古い時代からやって来た男(シェーン)が、新しい時代の象徴として戦い、古い時代の残像たるルーク・フレッチャーを滅ぼすというストーリー展開は、ある意味におけるパラドックスだ。
そこに、シェーンが、古い時代を振り払おうとしていた覚悟を読み取ることができる。
かつて自分が生きた「古い時代」を滅ぼすことが、主人公(シェーン)に与えられた最大のミッションだった。
それは、アメリカという国が、かつて持っていたものへの(あるいは既に失ってしまったものへの)ノスタルジーだったかもしれない。
自分の書くものについて、シェーファーは次のように記している。「私が書こうとしていることは、アメリカがかつてどんなタイプの人間を持っていたかということである。そして、私がそういう人間について書くのは、私たちはいつでも、もう一度そういう人間になれると確信しているからである」(清水俊二「シェーン」訳者あとがき)
西部開拓時代のアメリカは、ある意味において、アメリカの原点だった。
多くの西部劇映画が、そのことを証明している。
シェーファーはかつて、バージニア州に農場を持っていたことがあり、その農場を「シェーンウェイ」と呼んでいた。「シェーン」という名前は、ここから生まれたのであろう。(清水俊二「シェーン」訳者あとがき)
本作『シェーン』は、時代の移り変わりの中で生きにくさを抱えた男が、新しい時代に翻弄される姿を描いた西部小説である。
それは、ひとつの時代を記憶するための、ある種のドキュメンタリーだったのかもしれない。
書名:シェーン
著者:ジャック・シェーファー
訳者:清水俊二
発行:1972/09/30
出版社:ハヤカワ文庫