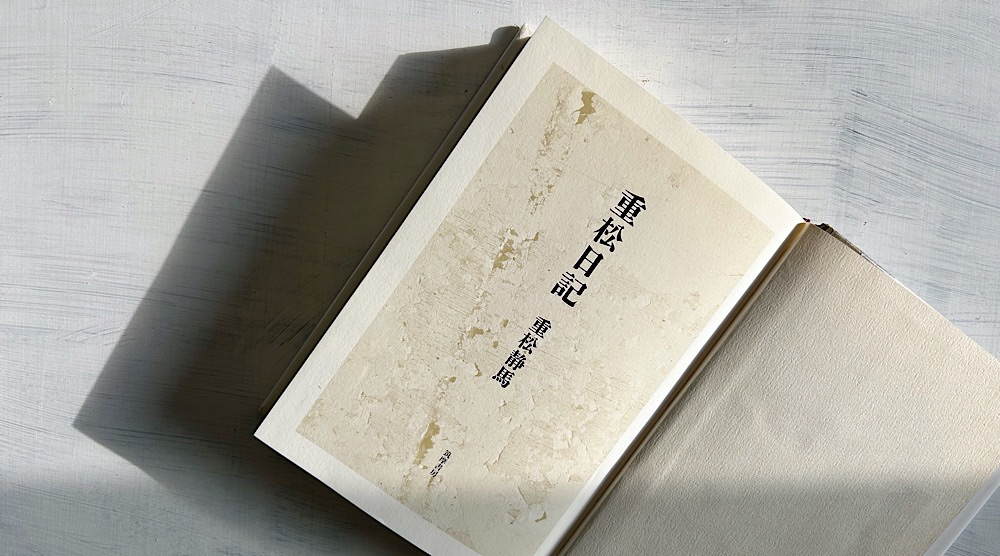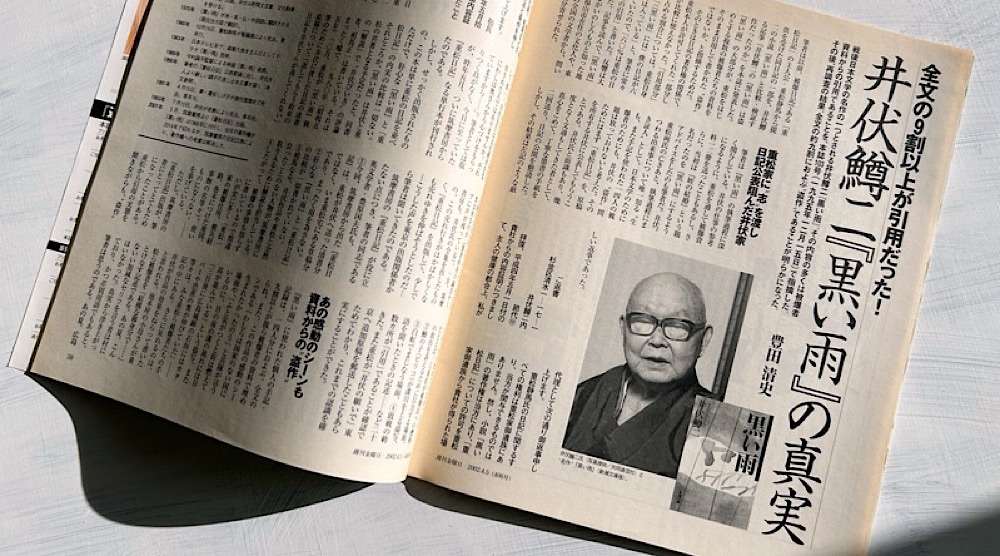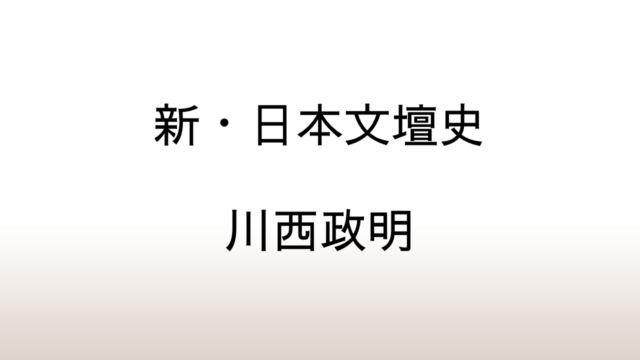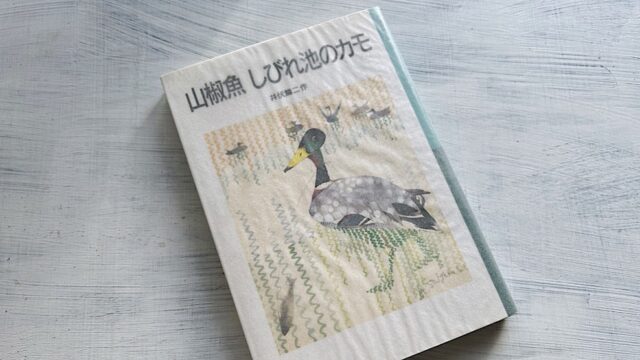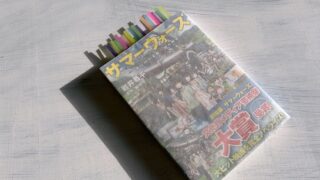井伏鱒二の名作『黒い雨』は、かつて、盗作疑惑に揺れたことがある。
今年は原爆投下から80年。
井伏鱒二の故郷にあるふくやま文学館では、特別展『被爆80年 井伏鱒二「黒い雨」』を開催予定だが、この機会に、『黒い雨』の盗作疑惑とは何かを振り返ってみた。
『黒い雨』盗作疑惑とは何か?
井伏鱒二の名作長篇『黒い雨』のオリジナル性に疑問を投げかけたのは、広島在住の歌人(豊田清史)だった。
自身も被爆者である豊田清史は、著作『『黒い雨』と「重松日記」』(1993)の中で、小説『黒い雨』は井伏鱒二オリジナルの小説ではない、と主張している。
論点は2つある。
ひとつは、井伏鱒二自身が「『黒い雨』は小説ではなくてドキュメントである」と告白している、ということ。
執筆の当初は小説であったが、次第にルポルタージュ化し、ついに一九八六年(昭和61年)三月、『井伏鱒二全集』の第六巻『黒い雨』において井伏氏は ”覚え書” と後記にわざわざ念書をされ、「黒い雨、この作品は小説ではなくてドキュメントである」と厳しく規定されている一章に私は注目するのである。(豊田清史「『黒い雨』と「重松日記」」)
著者(豊田清史)は、よほど「ドキュメント」という言葉に執着したらしい。
本書内でも、何度となく、このエピソードを繰り返している。
特に『黒い雨』の研究者たちが、まずつまづくのは作品と事実、場所、日時などが全く把握できないという苦情である。この作品はドキュメントとして読んでくれとの、作者の希望がある以上、右の苦情は問題であり、この点について私なりに調べあげ、解明した。(豊田清史「『黒い雨』と「重松日記」」)
『自選全集』の単なる「覚書」が、いつの間にか「作者の希望」になっている。
作品『黒い雨』が、著者井伏氏によって「これはドキュメントである」と決定づけられたので、この作品はとても問題を生んだ。(豊田清史「『黒い雨』と「重松日記」」)
かように、『自選全集(覚書)』の「『黒い雨』はドキュメントである」という文章は、豊田説の大きな論拠となっている。
論点のふたつめは、『黒い雨』の6割が資料からの引用だった、ということである。
周知のとおり、『黒い雨』は、実際の被爆体験を持つ人々に取材して生まれた原爆文学である。
資料の中心となったのは、重松静馬の書いた被爆日記(いわゆる「重松日記」)で、『黒い雨』の重要なシーンは、すべて、この日記からの引用であると、著者(豊田清史)は主張している。
全頁数 三七九頁
井伏氏の創作記事 一九八頁
資料による引用 一八一頁
重松日記 一〇七頁
妻しげ子の報告書 一一頁
岩竹日記の転記 三八頁
その他の資料、報告書 二五頁
(豊田清史「『黒い雨』と「重松日記」」)
『黒い雨』379ページ中、井伏鱒二による創作は198ページ(52.2%)で、残りの181ページ(47.8%)は、資料からの引用だったと、著者(豊田清史)は検証している(つまり、全体の5割が引用だった)。
さらに、「重松日記」の作者(重松静馬)も、資料に基づく引用の多さを指摘していたという、著者(豊田清史)の証言がある。
「先生(豊田のこと)、『黒い雨』に六割は僕の日記が入っていると思いますよ。お宅へ日記を送ったとき、そのまま自費出版しとったらナシのつぶてでしたよ」(豊田清史「『黒い雨』と「重松日記」」)
豊田清史の検証によれば、『黒い雨』において「重松日記」の占める割合は28.2%(107ページ)だが、日記の作者の体感としては「六割は僕の日記が入っている」ということになったのかもしれない。
さらに、豊田清史は著作『知られざる井伏鱒二』(1996)の中でも、『黒い雨』ドキュメント説を繰り返した。
それは僕があなたの作品に使われた資料を、長年にわたって詳しく調べてみました結果、「重松日記」「岩竹日記」その他の被爆者の手記が作品の約七割強を占めているからです。(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
前作『『黒い雨』と「重松日記」』から三年の間に、資料からの引用部分は「約七割強」へと膨張している。
全頁数 三七三頁
井伏氏の創作記事 一四四頁
資料による引用 二二九頁
重松日記 一二二頁(作品の六割、ほとんどそのまま使ってある)
妻しげ子の報告書 一一頁(戦時中の食生活の手記)
岩竹日記の転記 三八頁(日記を一字も変えず載せてある)
その他の資料、報告書 五八頁(原爆体験記、原爆の実相、佐藤進、田渕実夫手記ほか)
(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
特徴的なのは「重松日記 一二二頁(作品の六割)」で、重松静馬本人の「六割引用説」との整合性を意識していたらしい(ただし、122ページでは、作品の32.7%である)。
なお、「資料による引用229ページ」は総ページ数の61.4%であり、「作品の約七割強を占めている」という主張のエビデンスとはなっていないことにも注意が必要だろう。
主人公の重松静馬(作品では閑間重松)も、「作品『黒い雨』には、自分の日記が、ほぼそのまま六割は使ってある」としばしば僕に話した。(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
前作では「六割は僕の日記が入っていると思いますよ」だった重松の発言が、本作では「自分の日記が、ほぼそのまま六割は使ってある」という証言へと変化している。
さらに、著者(豊田清史)は、『黒い雨』の重要シーンにも言及する。
実は作品『黒い雨』の感動シーンの記事は、ことごとく重松日記にある。(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
つまり、本作『知られざる井伏鱒二』では、「七割引用」と「感動シーンの引用」という二つのポイントが、『黒い雨』のオリジナル性を否定する根拠となっている、ということだ。
作品『黒い雨』は実質を知れば知るだけ、この作品の七割以上が、殆どこれら被爆者の資料を並べて、記述されており、しかも、その描写の実質や感動のシーンも、重松を中心に、資料に縋っているのであって、このことは文学作品において、空前のことと言えるのである。(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
豊田清史の二冊の著作による『黒い雨』批判論は、文壇の一部から支持を得た。
その代表例が、猪瀬直樹『ピカレスク 太宰治伝』(2000)である。
『黒い雨』は重松日記を中心に、さらに岩竹医師の被爆日記と同夫人の看護日記を加えると、全体の約三分の二になる。日記をリライトしたのだからドキュメントと断るしかなかったのであろう。(猪瀬直樹「ピカレスク 太宰治伝」)
「全体の約三分の二になる」は、豊田清史の「6割引用説」に拠ったものらしい。
さらに、作者(猪瀬直樹)は、「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」という兵士の言葉に着目する。
どうだろうか。こうした台詞は、戦後民主主義でよく繰り返されたものではないのか。死体を片付ける二人の兵士が、なぜ、突然、言い出すのか。二人の兵士たちの個性の説明もないのに、不自然なのである。(猪瀬直樹「ピカレスク 太宰治伝」)
もっとも、豊田清史の主張によると、「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」という名台詞の出典は「重松日記」にあったという。
特に二人の死体を運ぶ兵隊が「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」この兵隊の会話は、この作品「黒い雨」を貫くアフォリズムである」とは、識者や評論家の一致した感想であるが、この言葉は、井伏氏の見方や創文ではなく、重松の日記が底本なのである。(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
ただし、2001年(平成13年)になって出版された『重松日記』(重松静馬)に「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」という言葉は出てこない。
同じように『黒い雨』のオリジナル性を否定していながら、豊田清史と猪瀬直樹とでは、細部の解釈で異論があった。
両者に共通しているのは「小説全体の約六割が(豊田説では七割強が)資料からの引用だった」ということである。
それでは、名作『黒い雨』は、果たして井伏鱒二オリジナルの小説とは言えない作品だったのだろうか?
『黒い雨』が盗作ではない理由
『黒い雨』の盗作疑惑は、研究者たちの検証によって盗作ではないことが、既に実証されている。
論拠はふたつ。
ひとつは、『黒い雨』の執筆にあたり、井伏鱒二は「重松日記」の作者(重松静馬)の許諾を得ており、他者の著作物を無断で使用したという事実は、まったくないということである。
むしろ、井伏鱒二は、重松静馬を『黒い雨』制作上の協力者とみなしており、出版社からは取材協力費も支払われている。
たいていの場合、モデルにする人を招んで一席を設け速記をとるとき、取材費としてこの費用は社が出すのです。ですから「日記」に対して社が出すべきです。一年ぶん十五万円なら妥当ではないかと思います。(「重松静馬宛井伏鱒二書簡(S39/10/26)」/『重松日記』所収)
さらに、井伏鱒二は、書き上げた原稿のチェックを、重松静馬に依頼している。
新潮の駄文、もしお読みになってお気づきの点、または無理なところがあったら早速御様子賜わりたく御願いします。ただ、書きあげてしまうまでは御知り合いの人へは、なるべく読んでもらわないように取りはからって頂きたいのです。(「重松静馬宛井伏鱒二書簡(S39/12/15)」/『重松日記』所収)
そもそも、日記の採用は、重松静馬から井伏鱒二へ希望があったものであり、盗作疑惑の生じる余地はない。
ふたつめの根拠は、文学的見地から『黒い雨』と『重松日記』とは、完全に別物である、ということだ。
豊田清史による盗作疑惑事件を受けて、『黒い雨』の原典『重松日記』(2001)が出版されて、読者は二つの作品を読み比べることができるようになった。
『黒い雨』は、『重松日記』を出典としているから、大きなストーリーは同じと言っていいし、個々のエピソードも『重松日記』から採用されているものが多い。
実際の事件に取材して書く場合、ストーリーとエピソードが重複することは、多くの作品で見られることだが、文学作品のオリジナリティとは、そもそも、ストーリーやエピソードだけで決まるものではない。
取材で得たストーリーとエピソードを使って、どのように作品にしていくかというところにこそ、文学作品としての意義がある。
硬質で記録的な『重松日記』に対し、『黒い雨』は戦争に翻弄される庶民にフォーカスして描かれた、完全なる物語である(ドキュメントを求める人は、それがつまらないと言うかもしれないが)。
喩えて言うと、『重松日記』は戦争から掘り出されたままの原石であり、『黒い雨』は原石に磨きをかけた宝石である。
『重松日記』には『重松日記』の魅力があり、『黒い雨』には『黒い雨』の魅力がある。
それからもう一つ、実名にしてはよくないかどうかもお知らせください。むろん物語は虚構の上で書くつもりです。(「重松静馬宛井伏鱒二書簡(S39/9/19)」/『重松日記』所収)
元来、井伏鱒二は、随筆のような小説を書く作家である。
随筆とも日記とも記録とも判別のつかないような小説を書くところにこそ、井伏鱒二という作家のオリジナリティがあった。
いろいろの挿話を拝借して私は小説を書こうと思っていましたが、無断で盗んではいけないし、それに実際のことを知らないのでそのままにしておりました。(「重松静馬宛井伏鱒二書簡(S39/3/29)」/『重松日記』所収)
『黒い雨』は、実際の事件に取材して書かれた創作である。
その骨格となるのが『重松日記』だった。
小説の筋書はつくり話にして事件もつくりごとにするつもりです。「日記」にある悲惨な情景はできるかぎり摂取して、人、馬、牛、鳥、魚など生物の惨状はそのまま絵取らなければならないと思います。(「重松静馬宛井伏鱒二書簡(S39/10/26)」/『重松日記』所収)
原爆投下直後の広島の実情は、『重松日記』から引用しなければならない。
なぜなら、そこには、想像だけでは書くことのできない、リアルな現実があったからだ。
もちろん、小説を構成する素材としては、『重松日記』以外にも、多くの被爆者から聞きとった体験談が無数に組み合わせて使用されており、それが『黒い雨』という作品を、薄っぺらではない骨太の作品に仕立て上げている。
日記の作者(重松静馬)は、日記を浄書したものを井伏鱒二に送っているから、厳密に言うと、重松家に遺されていた原本を元に出版された『重松日記』と、井伏鱒二が参考にした「重松日記」とは別物である。
重松静馬の遺志により「重松日記」原本は長い間、門外不出の文書として重松家の手文庫の底に眠っていた。(相馬正一『重松日記』解説)
日記の作者が、浄書に当たって日記をまったく書き換える必要もないだろうから、『黒い雨』の理解を進めるうえで、『重松日記』は十分に参考となる著作である。
ベールを束ねた様なクラゲの脚が、急速に拡大してゆく。市内全体を襲来しそうだ。誰かが、下のは夕立らしいと云う。そうかなあと、よく視ると、粒状のものが集合しているようだ。だが、夕立ちとは思えない。今迄に、かつて見たことのない異様なもので、襲来してあの粒で打たれたら、生命はいくらあっても駄目だろう。(重松静馬『重松日記』)
洗っても落ちない汚れをもたらした「黒い雨」は、『重松日記』には登場しない(夕立で穴の開いた新聞紙は出てくる)。
一方で、『黒い雨』にはないエピソードにも、注目すべきものがある。
工場長が、お布施を出すなどと冗談を云うので、僕も模様入りのテーブルかけを指して、あれでも肩にかけて、袈裟代用として読経しようかと云うと、居合わせた者がどっと笑った。(重松静馬『重松日記』)
八月七日の日記、僧侶の代わりに重松がお経を読むことになった場面である。
生き残った者の笑いには、生命の力が感じられる。
リュックサックの中から、古雑誌や征露丸、うちわや移植鏝、握り飯等を出して並べながら、用途の判らない移植鏝について尋ねると、どっと笑い、殊に婦人方は顔を赤らめて笑い崩れて、なかなか説明して聞かせる方がいない。(重松静馬『重松日記』)
八月十日の日記にも、女性たちが笑い崩れる場面があり、生きていく力強さが伝わってくる。
今日の会食の雰囲気は、親族や朋友などとの会食でも味わえない、温かい心の接触で、実に和やかなもので、戦時下とも思われなかった。(重松静馬『重松日記』)
実際に生き残った者でなければ書けない情景とは、あるいは、地獄の中で見た平和的な光景を言うのではないだろうか。
『重松日記』は『黒い雨』にはない魅力を持つ、日記文学だ。
つまり、『黒い雨』は『黒い雨』、誤解は誤解、『重松日記』は『重松日記』、ということである。
我々は、それぞれの作品と虚心に向き合えばよいのであって、原典と小説の優劣を競うために読み比べるのではない。
そもそも、『黒い雨』批判論には主観(私情)が多すぎる。
「じっと見る井伏氏は小男、朴訥で、癖のあるぽつんと少年のようなもの言いをする。不愉快」(豊田清史「知られざる井伏鱒二」)
あまりに私情が多すぎると、「井伏鱒二は不愉快な男だ」という主観自体が、『黒い雨』盗作疑惑をリードしたと受け止められても仕方がないだろう。
引用個所の指摘が、年々増えていくということも、客観的な検証を疎外する要因となった(『週刊金曜日(2002/04/05)』では「9割以上が引用だった」と、引用部分がさらに増殖している)。
井伏がどんな人物か、どれほどいい加減な作品を書いてきたか、はっきりさせてしまおう、と太宰はたくらんだ。(猪瀬直樹「ピカレスク 太宰治伝」)
太宰治と井伏鱒二と。
作家とは、死んでしまえば、どのような扱いを受けてもやむを得ない存在なのだろうか。
『黒い雨』盗作疑惑事件は、「文学とは何か?」ということを真剣に考えさせられる事件だった。
「井伏は『黒い雨』を刊行してから二十余年間、盗作、模索のことには一切触れず、新潮社から自分の全集が出たときに初めて、「この作品(『黒い雨』)は小説ではなくドキュメントである」と付記した。(略)このことは昨年大問題となった上高森古墳の捏造事件のいまわしいことと等しいと言えるのではないか」豊田清史は右のように書いているが、文壇には一般に知らぬ不可解な事実が多いようだ。(長篠康一郎「実証的研究のわが闘争(49)井伏鱒二『黒い雨』の真実」/『月刊カレント(H14/06)』所収)
「『黒い雨』はドキュメントである」という言葉は、もちろん、井伏鱒二一流のアフォリズムである。
しかし、そういった言葉の解釈も含めて、文学は、すべて読者が判断すべき責務を負っているものだ。
『黒い雨』と『重松日記』を読み比べたとき、その答えは、それぞれの読者が導き出せばいい。
『黒い雨』盗作疑惑は、『黒い雨』にとっても『重松日記』にとっても、互いに傷つけあうだけの不毛な論争だった。
それは、井伏鱒二も重松静馬も、決して望んでいたことではなかっただろう。
書名:重松日記
著者:重松静馬
発行:2001/05/25
出版社:筑摩書房