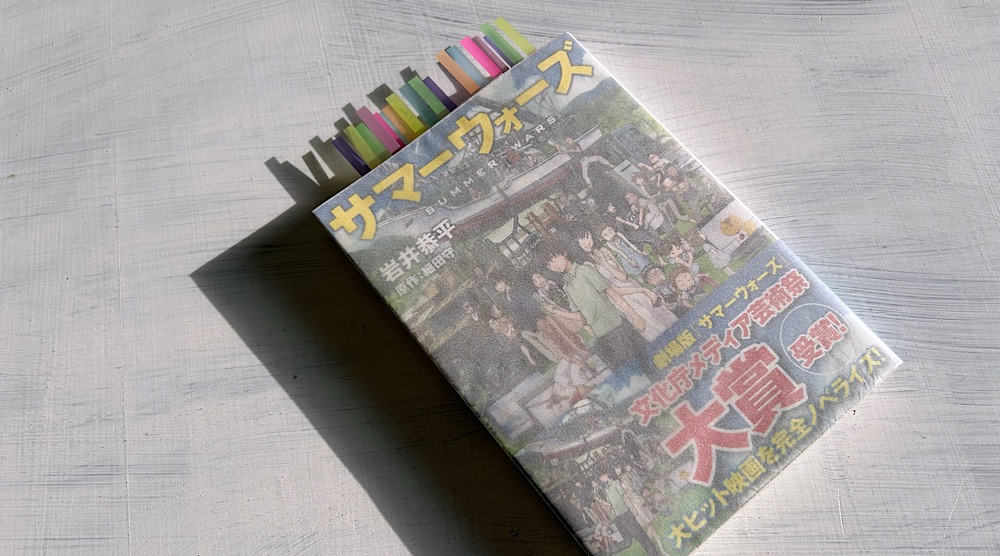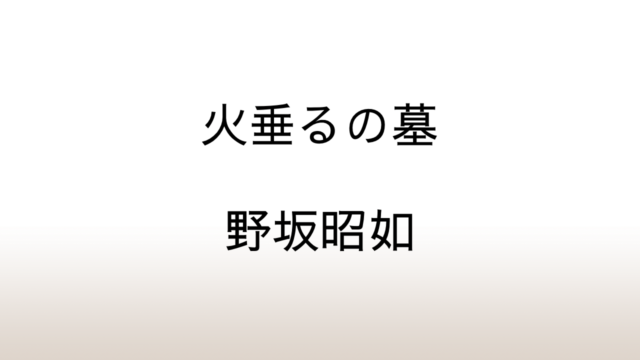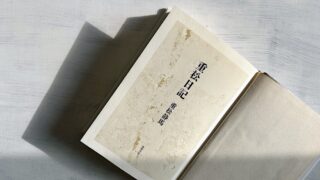岩井恭平「サマーウォーズ」読了。
本作「サマーウォーズ」は、2009年(平成21年)7月に刊行された長篇小説である。
細田守・原作の映画『サマーウォーズ』(2009)のノベライズ作品。
昭和時代に失われた「家族」の再興
『サマーウォーズ』のおもしろさは、パラダイムシフトのおもしろさである。
パラダイムシフトとは価値観の転換という意味で、既成の価値観を覆す刺激的な違和感こそが、この物語の醍醐味なのだ。
例えば、物語の舞台は、長野県上田市である。
上田駅は、長野駅から一つ前の駅にあたる。軽装の夏希と全身荷物だらけの健二が新幹線を降りると、駅のホームから大きなガスタンクが見えた。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
『サマーウォーズ』は、世界の平和を守る戦いの物語だ。
昔から、日本の平和を守るのは(地球の平和を守るのは)首都・東京の役割だとされてきた。
この物語では、首都・東京が活躍する場面はまったくない。
都会は、嫌いではない。目まぐるしく変わる日常に翻弄されるのも好きだし、賑やかで忙しいのも性に合っている。一人よりも大勢のほうが楽しいし、一生懸命な人たちに囲まれると血が騒ぐ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
東京の女子高生(篠原夏希)は、下級生男子(小磯健二)を連れて、曾祖母の住む上田市へと帰ってくる。
世界を混乱に巻きこんだAIとの戦いは、ここ(上田市)が主戦場だ。
それは、インターネットの急速な普及がもたらしたグローバル化による「地方の逆襲」を意味する。
日本の平和を(地球の平和を)守るのは、既に東京だけの役割ではなかったのだ。
陣内家は、室町時代から続く旧家である。
16代当主(陣内栄)の90歳の誕生日を祝うため、一族は、日本中から集まってくる。
こんなに大勢で食事をとるのは、いつ以来だろうか──。大勢の話し声が混じり合う食卓は、心地良かった。共働きで親戚との交流もほとんどなく、自宅で一人で夕食をとることが多い健二は、ひそかにこんな空間に憧れていたのだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
「共働きで親戚との交流もほとんどなく、自宅で一人で夕食をとることが多い健二」は、コミュニケーションの希薄な現代家族の象徴だ。
大家族・陣内家の末裔であるゲーム少年(佳主馬)は、生まれてくる妹を守るために戦う(キング・カズマVSラブマシーン)。
「小さい頃はオタク呼ばわり、大人になったら年甲斐もなく厚化粧だったわね」里香の弟である理一、直美の兄である太助が、うんうんと何度も頷く。「でも、家族だ。家族を守るためなら、いくらでも頑張れる」(岩井恭平「サマーウォーズ」)
それは、失われつつある家族の絆へのノスタルジーだったのかもしれない(「母さんを……、妹を……守れなかった……」)。
家族の絆は、やがて、社会の絆へと発展していく。
自分を見つめる彼らは皆、ナツキと同じだ。この広い世界中のどこにだって存在する人々。かけがえのない大切な人を守りたいと願う、ごく普通の家族たちだった。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
そもそも、侘助おじさんの開発したハッキングAI(ラブマシーン)は、失われた家族の絆を再現するためのものだった。
人との繋がりに憧れ、人に近いプログラムを創ろうとした。他の親戚よりも血の繋がりが薄い分を、金で補おうとした。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
しかし、人間ではないハッキングAI(ラブマシーン)に「愛」はない。
OZという、人と人どうしの新しいネットワークを絶とうとする存在。さらには人を破滅させ、家族という不変の繋がりを失わせようとする脅威。ラブマシーンが人々から奪おうとしているそれらは、10歳の頃から変わらず心細かった彼が心の底で欲していたものだったはずなのに。繋がりを欲する彼の不器用な愛(ラブ)が、ラブマシーンを狂わせてしまった──。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
ハッキングAI(ラブマシーン)との戦いは、侘助にとって、家族の愛情を取り戻すための戦いだった。
それは、自分を愛してくれた栄おばあちゃんへの愛情でもある(「大おばあちゃんの誕生日を知らなかったなんて、ウソ! だってこの端末のパスワードが大おばあちゃんの誕生日だったもの!」)。
──あたしたちは今日から家族になるんだ。そう言って歯を見せ、栄が笑った。家族。その言葉を聴いて、天の邪鬼だった彼は生まれてはじめて素直に栄の手を握り返した。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
一族の信頼篤い栄おばあちゃんは、陣内家というヒエラルキーの頂点に立つ当主だ。
古い家父長制ではくくることのできない、新しい大家族の構図がそこにはある。
戦時中や戦後を生き抜いてきた栄の人生は、まるで数々の戦場をくぐり抜ける武将のように勇ましかった。生きるだけで大変な時代を、栄は家族を守り抜き、こうして何の不安もなく食卓を囲めるまでに導いてくれたのだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
栄おばあちゃんに対するリスペクトは、戦後の日本を支えてきた古い世代へのリスペクトとして読むことができる。
OZの混乱を収めようと電話をかけまくる栄おばあちゃんは、この物語のもう一人の主人公なのだ。
「アンタなら、できる!」障子を開けようとした夏希の手が、ピタリと止まった。栄はまた別の人間に電話をかけ、力強い声で励まし続ける。「できる!」(岩井恭平「サマーウォーズ」)
それは、長い物語の最初のクライマックスでもあった(後半のクライマックスはナツキの花札)。
栄おばあちゃんから夏希へと受け継がれていく家族の絆が、そこに描かれている(「夏希……お前、ババアに似てきたな」)。
夏希が今、こうして田舎が好きで、親戚や家族という絆が何よりも大切だと思えるようになったのは、曾祖母のおかげだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
尊敬する栄おばあちゃんを安心させてあげたいという一心で、夏希は嘘までついて恋人(健二)を連れてきた。
家族をつくることが、陣内家にとって最大の喜びだったのだ(「ところで婿殿。二世のほうは、まだ予定なし?」)。
東京ではない地方都市で、女性を頂点とする大家族が活躍する物語。
本作『サマーウォーズ』にあるのは、昭和時代に失われてしまった「家族」の再興である。
かつて、家族の崩壊を描いた現代作家たちは、今、家族の再構築を描こうとしている。
侘助おじさんの孤独は、現代を生きる我々の孤独でもあった。
デジタル社会の潜在的な脅威
本作『サマーウォーズ』は、文化系時代の到来を描いた物語でもある。
ハッキングAIと戦うのは、数学オリンピック日本代表になりそこねた男子高校生(健二)だ(「僕だって……もうちょっとで日本代表になれたのに……」)。
ぼたぼたと鼻血を零しながら、健二は頭の中で計算を展開させ続ける。一瞬でも気を抜いたら、倒れてしまいそうだった。「がんばって、健二君!」夏希が叫んだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
ハッキングAI(ラブマシーン)との戦いで活躍するのは、自衛隊員でも警察官でも消防隊員でもなかった。
新しい戦争は、体育会系の人間ではなく、文化系の人間が戦う戦争だったのだ(「数学オリンピックで経験したシビアなタイム制限に比べたら──永遠に近い時間だ」)。
価値観の転換が、ここにもある。
本当は数学オリンピックで優勝したら、告白をするつもりだった。世界一になれば、きっと変われると思っていた。今の健二は世界一ではない。それでも今の健二は、以前の自分とは少しだけ違う気がした。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
本作『サマーウォーズ』は、主人公(健二)の成長物語である。
彼らは、いつだって夏休みに成長した。
夏休みは、少年たちを成長させてくれる季節だったからだ。
健二は振り返り、走ってきた道の先にある丘を見た。(略)美味しいご飯を食べ、敵との合戦で力を合わせ、勝利した数日間。この一夏の戦いを、彼は一生忘れることがないだろう。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
主人公(健二)を支えたのは、自分を信じてくれた栄おばあちゃんの言葉である。
猛烈な怒りが湧いた。これ以上、夏希を傷つけてしまうのが怖くて、夏希に拒否されることが怖くて、何もできない。健二は意気地なしのまま、何も変わっていない。だから、彼の手を恐る恐る動かしたのは、もらった勇気だ。──あんたなら、できるよ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
ヒーローが数学少年であるのと同じように、戦いの方法は「花札」という日本伝統の文化だった。
繰り返される刺激的な違和感。
「猪鹿蝶です」またナツキが、3枚の出来札を背負った。その勢いに圧されたように、ラブマシーンの輪郭が一瞬、乱れた。「こいっ!」ナツキは叫んだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
地方都市、大家族、そして、花札。
インターネットが牛耳る現代社会へのアンチテーゼ。
アナログな日本文化である花札が、最新技術の結果生まれたハッキングAIと戦う武器になるというパラドックス。
『サマーウォーズ』のおもしろさは、あらゆる逆転の発想というおもしろさなのだ。
そこに至ってようやく、ラブマシーンは事の真相を導き出した。OZを使っていない──。電子ネットワークなどという仮想現実空間ではなく、現実世界で人と人が接し、会話をして、力を合わせているのだ。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
『サマーウォーズ』が描いているのは、人間存在の再評価である。
デジタル万能主義は、ともすれば、人間という存在を見失ってしまいがちだ。
しかし、「AIは人間が創りだしたものだ」という事実を、忘れてはいけない。
「OZは世界中の人々が集い、楽しむことができる電子ネットワーク上の仮想世界です。アクセスはお手持ちのPC、携帯電話、TVなどから簡単に行えます」(岩井恭平「サマーウォーズ」)
1990年代以降の第三次産業革命がもたらしたデジタル社会は、人々の生活を急速に変えた(「さあ、あなたもOZでの快適な生活をはじめましょう」)。
一方で、新たなデジタル社会は、人間同士のリアルなコミュニケーションに代わって、ネット回線を通した非リアルなコミュニケーションの構築を進展させていく。
最新技術は、開発者の意思を超えて暴走した。
「だからっ! 俺はただの開発者だっての! プログラムを組むまでが仕事で、そのプログラムがどう使われようがどうしようもねえんだよ!」(岩井恭平「サマーウォーズ」)
歴史的に、戦争の陰には、科学者や技術者たちのたゆまぬ努力があった。
彼らの思惑を超えた悪意が、いつでも時代を変えてきたのだ。
さらに、科学技術の持つ潜在的な脅威が、『サマーウォーズ』でも露呈する。
「これ……。”あらわし” じゃないか?」佳主馬が言った。太助が唸る。「”あらわし” と原子力発電所が、どうして……あれ? あらわしって制御不能状態だってニュースで……」広間に沈黙が落ちた。(岩井恭平「サマーウォーズ」)
現代科学技術を象徴する存在である小惑星探査衛星「あらわし」(「はやぶさ」がモデル)や原子力発電所は、決してノーリスクの存在ではない。
「新しい社会は、新しいリスクをいくつも抱えこんでいる」という警鐘が、そこから聞こえてこないだろうか。
大切なことは、我々は、あらゆるリスクを想定しながら生きていかなければならない、ということだ。
栄おばあちゃんの遺言は、現代社会を生きる我々への遺言である。
「家族同士、手を離さぬように。もし辛い時や苦しい時があっても、いつもと変わらず、家族みんなそろってご飯を食べること。一番いけないのはお腹が空いていることと、一人でいることなんだから」(岩井恭平「サマーウォーズ」)
あの夏(2009年)の戦いから16年目の夏がやって来た。
当時、高校生だった夏希や健二は、今ごろ、どんな大人になっているのだろうか。
書名:サマーウォーズ
著者:岩井恭平
発行:2009/07/25
出版社:角川文庫