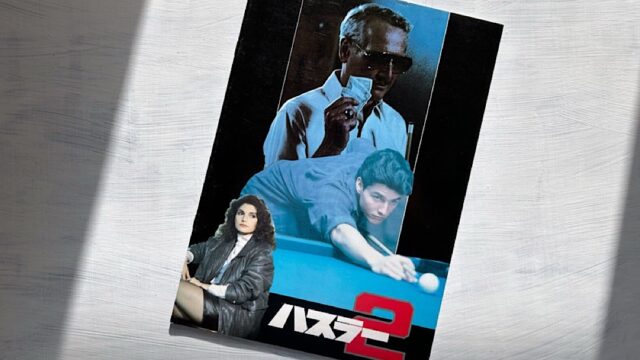『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』鑑賞。
本作『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』は、2022年(令和4年)4月にParamount+で公開された伝記ドラマである。
原題は「The Offer」。
この年は、映画『ゴッドファーザー』初公開から50周年のアニバーサリーイヤーだった。
『ゴッドファーザー』の舞台裏を描く
本作『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』は、1972年(昭和47年)に公開された映画『ゴッドファーザー』のメイキングドラマである。
『ゴッドファーザー』の舞台裏については、ハーラン・リーボの『ザ・ゴッドファーザー』(2001)というオフィシャルブックが既にある。
『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』では、名場面の舞台裏がストーリー仕立てで明かされていくので、映画『ゴッドファーザー』を観た人には、かなり興味深い内容となっている。
例えば、映画俳優(ジョニー・フォンテーン)を憎んでいる映画プロデューサー(ジャック・ウォルツ)のベッドに投げ込まれた馬の首は、本物の馬の首が使われていた。
胴体から切断された、名馬カートゥムの黒い絹のような頭が、どろどろした血の海の中に突っ立っていた。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
小道具担当の制作した模型(の馬の首)では、監督(フランシス・フォード・コッポラ)が納得しなかったらしい。
シチリア島でマイケルと結婚した女性(アポロニア)が殺される、自動車の爆発シーンも印象深い。
マイケルはアポロニアに向かって叫んでいた。「よせ! やめるんだ!」だが、その時アポロニアはイグニッションのスイッチを回しており、彼の叫び声はすさまじい炸裂音の中にかき消された。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
限られた予算の中で、自動車の爆破シーンは一度しか撮影することができない。
「うまく爆破しないのではないか」とスタッフが思った瞬間に、想定を超える爆発が起こり、建物の窓まで破壊してしまう。
名作には、想定外のドラマが付き物だ。
冒頭、ドン・ヴィトー・コルレオーネが、事務室のデスクに座っている場面。
原作に猫は登場していない(もちろん、脚本にも猫はいなかった)。
「しかし、あんたはどうして警察に行ったんだ? 初めから私のところに来ることもできたんだろうに」ボナッセラは、ドンの言葉をほとんど聞いていないみたいだった。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
猫は、ヴィトー・コルレオーネ役を演じるマーロン・ブランドが、撮影現場で拾ってきた野良猫だったが(つまりアドリブ)、コッポラ監督は、そのまま撮影を進める。
『ポケットモンスター』に登場するロケット団のボスがペルシアンを抱いているのも、マーロン・ブランドが野良猫を拾ってきたところから始まっているのだ。
妹(コニー)に暴力を振るった義弟(カルロ)を、長男(ソニー)がボコボコにするシーンは、演技ではなかった。
カルロ役のジャンニ・ルッソが、コニー役(タリア・シャイア)を本気で殴ったことに激怒したプロデューサーが、ソニー役(ジェームズ・カーン)に本気で暴れるよう指示したのだ。
ソニーは不明瞭な、怒りに詰まった声でののしりながら、すくみ上がったカルロを拳で殴りはじめた。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
コニー役のタリア・シャイアは、コッポラ監督の実妹だったから、妹が傷つけられたことに、兄としても激怒せずにいられなかったのだろう。
キャスティングについてのエピソードもある。
ヴィトー役(マーロン・ブランド)に出演をオファーしたのは、原作・脚本のマリオ・プーヅォだった。
『ゴッドファーザー』の原作と一緒に、オファーの手紙を受けとったマーロン・ブランドが興味を示したことで出演が決まったらしい。
ヴィトーの部下の殺し屋(ルカ・ブラージ)を演じたのは、本物のマフィアだった。
今、ブラージはドンの前に連れていかれ、緊張にすっかり身体をこわばらせていた。そして半分つかえながら、キザったらしい祝辞を述べ、さらに、ドンの最初の孫が男の子だったらどんなにいいだろうと言った。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
マフィア小説『ゴッドファーザー』の映画化にあたっては、本物のマフィアとのトラブルなどがあり、映画製作は簡単なことではなかった。
ルカは、その中で知り合ったマフィアの一人が演じることになる。
主役のマイケル・コルレオーネを演じたアル・パチーノは、当時、まだ無名の役者で、社内にはアル・パチーノの起用に反対する声も多かった。
マイケル・コルレオーネはドンの末の息子であり、父親の命令を拒否したただ一人の息子でもあった。彼の顔は、ほかの息子たちのようながっちりしたキューピッド形のそれではなく、まっ黒な髪もちぢれっけのないまっすぐな毛をしていた。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
歓迎されていない雰囲気を察したアル・パチーノは、別の映画への出演を決断するが、映画会社同士の交渉によって、アル・パチーノの『ゴッドファーザー』出演が決まる。
アル・パチーノとトレードされたのは、『ゴッドファーザー PART II』(1974)でヴィトー・コルレオーネの若き日を演じることになるロバート・デ・ニーロだった。
無名の俳優(アル・パチーノ)は、『ゴッドファーザー』(1972)によって映画スターとなり、日本では、榊原郁恵の『アル・パシーノ+アラン・ドロン<あなた』(1977)として登場することになる(関係ないか)。
コッポラ監督の制作意図が語られる場面もいい。
例えば、コルレオーネ家のキッチンは、小道具担当の制作したものではなく、上等の本物のキッチンが使用された。
低価格予算映画という使命を与えられた『ゴッドファーザー』には、手痛い出費だったが、そこにはコッポラ監督の強い思い入れがあった。
部下の一人が、スパゲティのボウルと、次にはフォークとワインをキッチンから運んできた。(略)ソニーとクレメンツァとテッシオはパンの皮でソースをぬぐい取りながらさかんにぱくついている。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
クレメンツァがマイケルに美味しいイタリア料理の作り方を伝授している場面は、彼らが「ファミリー」であることを印象付ける。
つまり、『ゴッドファーザー』は、マフィアの映画ではなく家族の物語であるという明らかなコンセプトが、何気ない場面によって描写されているわけだ。
シチリア島での撮影に固執したのも、監督のコッポラだった。
麻薬の売人(ソッロッツォ)とマクルスキー警部を殺害したマイケルは、シチリア島に身を隠しながら、ほとぼりが冷めるのを待つ。
シチリア島からニューヨークへ戻ったとき、マイケルは、ドン・ヴィトー・コルレオーネの後継者として再登場する。
だから、マイケルにとってシチリア島は、自身の再生を促す重要な舞台だったと言っていい。
彼はシシリー人の信じがたいほどの貧困ぶりから、まったくの不毛の地を想像していたのだ。ところが彼が目にしたものは、レモンの香りのする花々でおおわれた、豊潤そのもののような土地であった。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
コッポラ監督は、深いところまで『ゴッドファーザー』を考察していく。
作者であるマリオ・プーヅォ以上に、コッポラは『ゴッドファーザー』を理解していたのだ。
ジョニーはシナトラだったのか?
小説『ゴッドファーザー』において、映画スター(ジョニー・フォンテーン)は、あらゆる意味で、フランク・シナトラがモデルとなっていることを、強く示唆している。
ジョニーは彼らの英雄だった。彼らの昔の仲間でありながら、彼らにとっては夢にしか見ることのできない幾多の女性とベッドを共にすることができる、有名な歌手となり銀幕のスターとなったのだ。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
落ち目のジョニーが復活を賭ける映画は、フランク・シナトラの復活劇を支えた『地上より永遠に』(1953)を思い出させる。
小説を読んだシナトラが激怒したとしても不思議ではない。
シナトラから依頼を受けたマフィア(ジョゼフ・コロンボ)が、映画製作を妨害するあたりから、映画世界と現実世界との混乱が始まっていく。
小説『ゴッドファーザー』には、ジョニー・フォンテーンのエピソードがいくつかあるが、プロデューサーのアルバート・S・ラディ(ドラマの主役)は、マフィア(コロンボ)との話し合いによって、ジョニーの出演シーンを1か所だけに留める。
だから、小説では「第二部」で重要な役割を演じる友人(ニノ・バレンティ)も、映画では、冒頭のコニーの結婚式に登場するだけとなった。
フランク・シナトラと同じように、『パラマウント映画』もまた、落ち目の映画会社だった。
『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』は、パラマウントの復活劇を描いたビジネス・ドラマとして観ることもできる。
主人公は、ハリウッドの伝説的プロデューサー(ロバート・エヴァンス)と、『ゴッドファーザー』でアカデミー賞(作品賞)を授賞するプロデューサー(アルバート・S・ラディ)の二人だ。
彼らは、親会社(ガルフ&ウェスタン)のオーナー(チャールズ・ブルードーン)や幹部社員(バリー・ラピダス)から強いプレッシャーを受けながら、『ゴッドファーザー』の制作を進める。
落ち目のパラマウント売却を目論むガルフ&ウェスタンとパラマウントとの戦いは、まるで『課長 島耕作』を読んでいるかのようだ。
彼らは、家庭生活を犠牲にしてまで、映画制作に打ちこむ。
家族の物語である『ゴッドファーザー』を作りながら、自らの家庭生活は崩壊していくという痛烈なパラドックス。
彼らを支えていたのは、ただひたすらに映画制作への情熱だった。
パラマウントの企業売却を決定するはずの重役会議で、ロバート・エヴァンスが語った長いセリフは、パラマウント映画が培ってきた長い歴史そのものだった。
本作『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』は、単なるメイキングドラマではない。
それは、映画制作というビジネスに人生を賭けた男たちの、奇跡の物語だったのだ。
同時にそれは、男たちに振り回される女たちの物語でもあった。
全10回のドラマだから「メイキング・オブ・ゴッドファーザー」を中軸に、様々なエピソードが同時進行的に展開していく。
テーマが散漫になりそうなところで、かろうじて物語を支えているのは、やはり『ゴッドファーザー』という映画の魅力だったのだろう。
『ゴッドファーザー』と同じように『ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男』もまた、陰影に満ちた照明が織りなす光と影の演出によって、印象的な映像が作られていた。
日本映画にはない「暗さ」が、そこにはある。
その『暗さ』は、『ゴッドファーザー』とは何だったのか?、という根本的なメッセージを投げかけているかのようだ。
映画『ゴッドファーザー』は、光と影の物語だった。
父親であるヴィトー・コルレオーネの光と影を描き、息子であるマイケル・コルレオーネの光と影を描いた。
それは、つまり、イタリア系移民の光と影を描くことであり、ひいては、現代アメリカ社会の光と影を描くことでもある。
ボナッセラは、恐怖に顔を引きつらせながらこう叫んだ。「アメリカは私によくしてくれました。ですから私は善き市民となり、自分の娘もアメリカ人として育てたかったんです」(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
しかし、アメリカは、彼らを救ってはくれなかった。
アメリカにとって彼らは、常にマイノリティーであり続けたのだ。
コッポラ監督が撮影にこだわったシチリア島は、ドン・ヴィトー・コルレオーネの原点でもある。
この町の一万八千の住民は、一番近い山の斜面に穴をうがった住居、山から切り出した黒石で建てた貧しいあばら屋にひっそりと息を潜めていた。この町では昨年だけで、六十件を越す殺人事件があり、死の影がコルレオーネ全体をおおっているようだった。(マリオ・プーヅォ「ゴッドファーザー」一ノ瀬直二・訳)
華やかなマフィアの暮らしの陰には、イタリア系移民の苦悩があったように、アカデミー賞の陰にも、家庭崩壊という彼らの苦悩があった。
人生は、光と影の物語である。
彼らは、それをアメリカン・ドリームと呼んだ。
影のないところに、つまり、光は差さないということなのだろう。
書名:ゴッドファーザー
著者:マリオ・プーヅォ
訳者:一ノ瀬直二
発行:2005/11/15
出版社:早川書房