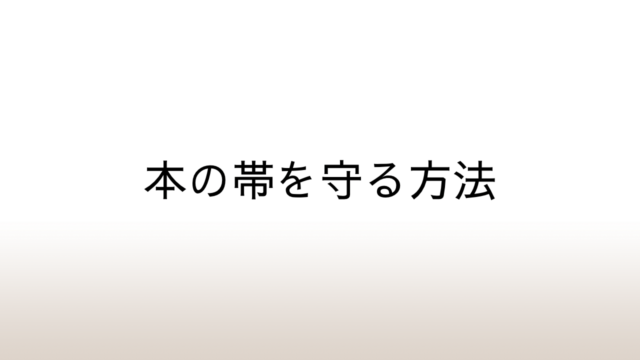J.D.サリンジャー『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』読了。
本作『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』は、2018年(平成30年)6月に刊行された、日本オリジナルの作品集である。
収録作品(原題)及び初出は次のとおり。
「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」
・Slight Rebelion off Madison
・1946年(昭和21年)12月『The New Yorker』
「ぼくはちょっとおかしい」
・I’m Crazy
・1945年(昭和20年)12月『Collier’s』
「最後の休暇の最後の日」
・The Last Day of the Furlough
・1944年(昭和19年)7月『The Saturday Evening Post』
「フランスにて」
・A Boy in France
・1945年(昭和20年)3月『The Saturday Evening Post』
「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる」
・This Sandwich Has No Mayonnaise
・1945年(昭和20年)10月『Esquire』
「他人」
・The Stranger
・1945年(昭和20年)12月『Collier’s』
「若者たち」
・The Young Folks
・1940年(昭和15年)3-4月『Story』
「ロイス・タゲットのロングデビュー」
・The Long Debut of Lois Taggett
・1942年(昭和17年)9-10月『Story』
「ハプワース16、1924年」
・Hapworth16,1924
・1965年(昭和40年)6月『The New Yorker』
本国アメリカでは読むことのできないサリンジャー作品
サリンジャーが生前に刊行した著作は、『ライ麦畑でつかまえて』『ナイン・ストーリーズ』『フラニーとゾーイー』『大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-』の4冊のみである。
このうち、いわゆる短篇小説集は『ナイン・ストーリーズ』だけだが、一方で、サリンジャーは、雑誌等に全部で30作の短編小説を発表している。

『ナイン・ストーリーズ』に収録された9作品以外の残り21作品は、単行本未収録(『ナイン・ストーリーズ』以前に発表された初期の作品)。
サリンジャーの死後、本国アメリカでは、オリジナル作品集の出版も認められていないから、この21作品を読むことはできないが、なぜか、日本では翻訳出版されてきた(『サリンジャー作品集』と『サリンジャー選集』)。
本書『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』には、残り21作品のうち、8篇の短編小説が収録されている。
さらに、サリンジャーが生前最後に発表した中篇小説「ハプワース16、1924年」は、本国アメリカでも、過去何度か出版の噂があったが、結局、現在まで出版されていない(日本語翻訳版は出版されているが)。
本書には、短篇小説8篇と中篇小説「ハプワース16、1924年」の、計9作品が収録されている。
本書収録作品を大きく分類すると、短篇小説8篇のうち6篇は、ホールデン・コールフィールドに関係する作品となっている(『ライ麦畑でつかまえて』の主人公の少年)。
特に「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」と「ぼくはちょっとおかしい」の2篇は、いずれ『ライ麦畑でつかまえて』にも登場するエピソードである。
6篇のうち残りの4篇は、サリンジャーの戦争体験を反映した作品で、本書中で最大の見せどころとなっている。
『ナイン・ストーリーズ』収録作品で言うと、「エズミに捧ぐ――愛と汚辱のうちに」に連なる作品群と言うことができるかもしれない。
残り2篇の短編は、デビュー当時の作品で、上流社会の若者たちの姿をシニカルに描いており。
戦争に行くまで、こうした上流社会の闇は、サリンジャーにとって一番の得意分野だった(ちょっと、フィッツジェラルドっぽい)。
本書中で唯一の中篇作品「ハプワース16、1924年」は、いわゆる「グラース・サーガ」(グラース家の物語)の作品で、作家となったバディが、長男シーモアの古い手紙を引用する構成となっている(シーモア・グラースは「バナナフィッシュにうってつけの日」で自殺する青年)。
サリンジャー最後の作品だが、内容が意味不明すぎるということで、当時、ジャーナリズムからは黙殺されたらしい。
グラース・サーガを読み解く上で、重要な作品であることに間違いはないのだけれど。
マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗
俗社会からの逃避を試みる高校生(ホールデン・モリシー・コールフィールド)の物語。
後に、長篇『ライ麦畑でつかまえて』の一部として使われた。
上流社会の若者が、ニューヨークからの脱出を夢見て、恋人(サリー・ヘイズ)に「マサチューセッツかヴァーモントか、そのへんに行かない?」と誘うが、あっけなく断られてしまう(当たり前だが)。
夜遅く、サリーの自宅へ「ツリーの飾りつけをしてあげる」と電話する場面は、ホールデンの「ささいな抵抗」が、失敗に終わったことを暗示している。
「サリー、イヴには、いって、ツリーの飾りつけをしてあげる。いいよね、どう?」「わかったから、もう寝て。どこからかけてるの? だれと飲んでるの?」(J.D.サリンジャー「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」金原瑞人・訳)
ラストシーンで、マディソン・アヴェニュー行きのバスを待っている場面も、束の間の「抵抗」を終えた若者が日常社会へ戻っていくことを示唆したものだ。
俗世間から抜け出せない若者の悲しい宿命を、コミカルに描いている(サリンジャーは「悲しい喜劇」と言った)。
サリンジャーにとっては、名門『ニューヨーカー』への掲載が決まった初めての作品だったが、折悪しく日米戦争が始まり、直前になって掲載が延期されてしまった(クリスマスの物語ということで、12月号への掲載が予定されていた)。
実際に発表されたのは、戦争が終わった翌年のホリデーシーズン、1946年(昭和21年)12月のことである。
サリンジャーの精神的自伝とも呼ばれた。
ぼくはちょっとおかしい
長篇『ライ麦畑でつかまえて』の素材となった短篇小説。
ホールデン・コールフィールドが、スペンサー先生を訪ねた後、自宅に戻ってフィービーと再会するシーンが描かれている。
セントラルパークの池のカモを気にしているのは、カモに自分自身を投影しているため(「池にはカモがいるけど、池が凍りついたら、いったいどこへいくんだろう」)。
『ライ麦畑』で読むよりも、メッセージがはっきりしている(『ライ麦畑』では、メッセージ性が巧妙に埋め込まれている)。
長いこと横になったまま起きていた。情けなくてしょうがない。自分でもよくわかっていた。正しいのはほかのみんなで、まちがっているのはぼくだ。(J.D.サリンジャー「ぼくはちょっとおかしい」金原瑞人・訳)
『ライ麦畑』に比べると、ホールデン・コールフィールドの開き直りが足りない。
作者(サリンジャー)が戦争を経験することによって、主人公(ホールデン・コールフィールド)も、新たな死生観を身に付けたものと思われる(『ライ麦畑』を深く掘ると、戦争に対するメッセージが浮かび上がる)。
妹(フィービー)への愛情は、大人になりきれない主人公の心を反映したもの(フィービーは子どもだけど、ぼくの本当の仲間だ)。
ほこりがついたオリーブを、ポケットにしまうあたり、ホールデンの優しさが示唆されている(幼い子どもたちのイノセントを守る姿勢)。
『ライ麦畑』を読み解く上で、とても参考になる作品(「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」と併せて)。
最後の休暇の最後の日
ヴィンセント・コールフィールドの親友(ジョン・F・グラッドウォラー・Jr、愛称ベイブ)が主人公の物語。
戦地への出発を控えた二人は「最後の休日」を満喫しているが、弟(ホールデン・コールフィールド)が戦場で行方不明になったことで、ヴィンセントは激しく動揺している。
「ベイブ、ホールデンはまだ二十歳にもなってなかった。来月、二十歳になる。いま、だれかを殺したくてしょうがない。じっとしていられないくらいだ。おかしいかい?」(J.D.サリンジャー「最後の休暇の最後の日」金原瑞人・訳)
第一次大戦での戦争体験を誇らしげに語る父親に対するベイブの言葉、「いま戦っている者も、これから戦う者も、戦いが終わったら、口をつぐみ、どんな形であれ、決して戦争のことを話してはならない」は、作者(サリンジャー)からの強いメッセージだ。
ベイブの妹(マティルダ、愛称マティ)は、戦争と対比されるイノセントの象徴。
この後も、一連の戦争物語では、イノセントな少女が、戦争に対するアンチテーゼの象徴として登場している。
サリンジャーの反戦メッセージが、ストレートに現れた作品である。
フランスにて
フランスの戦場にいるベイブの物語。
「爪が一枚はがれた」とあるのは、傷だらけのベイブの心を象徴している(サリンジャー作品では、「爪」が象徴的な役割を果たしている場合が多い)。
ベイブが所望する詩(ウィリアム・ブレイク「子羊」と、エミリー・ディキンソン「海図なし」)を読むと、作品のメッセージが理解できる(「子羊よ、神さまのおめぐみあれ」)。
ドイツ兵の掘った塹壕に体を落とし込むベイブは、身も心もズタボロだが、妹(マティ)かた届いた手紙を読んで救済される。
彼は穴のなかで手紙をそっと、よごれてぼろぼろになった封筒にもどし、封筒をシャツのポケットにもどした。それから穴のなかで少し体を起こして叫んだ。「おーい、イーヴズ! ここにいるからな!」(J.D.サリンジャー「フランスにて」金原瑞人・訳)
「おーい、イーヴズ! ここにいるからな!」の叫びは、ベイブの再生を暗示している。
名作「エズミに捧ぐ――愛と汚辱のうちに」を思い出させる構成だ(どちらも、少女からの手紙が、復活の可能性を示唆している)。
『サタデー・イヴニング・ポスト 1942年-1945年』に採録された。
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる
戦場で行方不明になった弟(ホールデン)を案じる兄の物語。
作品名「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる」は、トラックを題材とする詩のタイトルを考えているときに自然と浮かんできたもので、大切なものを失った喪失感を象徴している(しかも、無意識のうちに)。
新兵訓練基地に集まった兵隊たちのくだらない会話と、弟のことで頭がいっぱいの軍曹との対比が、全編を構成する。
少年はぬれてゆがんだ舟形略帽をななめにかぶり、中尉のほうをみて、雨のなかでじっと立っている。まるで命令されたかのようだ。幼いといっていい。おそらく十八歳くらいで、ホイッスルが鳴ってもうるさく騒ぎ続ける若い連中には見えない。(J.D.サリンジャー「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる」金原瑞人・訳)
少年兵には、行方不明になった弟(ホールデン)の姿が投影されていると読みたい(「ぼくはリストにサインしてるんです」)。
ラストシーンの「ホールデン、どこにいるんだ?」から始まるパラグラフは、痛々しいほどに切ない(「どこでもいいから出てきてくれ。きこえるか? 頼む、頼むから」)。
サリンジャーは、やはり、こうした戦争文学に優れた作品が多いと思う。
『ナイン・ストーリーズ』収録作品の頃には、戦争に対する憎悪を、ストーリーの奥底深く埋めて描くようになってしまったが(そして、その結果「意味不明」とか言われるようになった)。
『ナイン・ストーリーズ』が難解で理解できないという人は、サリンジャーの作品を、初期から順番に読んでいくと、意外と理解しやすいのではないだろうか。
他人
戦争から帰還したベイブの物語。
ベイブは妹(マティ)を連れて、戦死した親友(ヴィンセント・コールフィールド)の元カノ(ヘレン・ビーバーズ)を訪ねる。
ヴィンセントが死んだときの状況を、彼女に伝えるためだ(彼女は既に別の男性と結婚している人妻だ)。
ヴィンセントが彼女と結婚しなかったのは、幼い弟(ケネス・コールフィールド)の死が理由だったという(「わたしはヴィンセントを愛していた。でもヴィンセントは何も信じなかった。わかって、ベイブ」)。
嘘は絶対に、だめだ。ヴィンセントの彼女に、彼は死ぬ前、煙草を吸いたがったと思わせてはならない。彼は勇敢に微笑んだとか、最期に立派な言葉を口にしたと思わせてはならない。そんなことはなかったのだから。(J.D.サリンジャー「他人」金原瑞人・訳)
サリンジャーは、戦争を美化することを徹底的に拒絶する(「最も身近で、最も大きな嘘を撃ち落とせ」「死んだ仲間をがっかりさせるな。撃て! 撃て! さあ! 撃て!」)。
「なにもかも、どうしていいのかわからない。ここに来たって何もいいことなんかないのはわかってたのに、きてしまった。自分でもどこが悪いのかわからないんです。もどってきてからずっと」と混乱するベイブは、既に戦争PTSDの兆候を漂わせている(「自分でも、自分のことがわからなくて」)。
戦場から(他人だらけの)一般社会へと戻ってきたばかりのベイブは、平穏な光景になじむことができない(「まだ、いろんなことに慣れてないだけなんです」)。
「他人(The Stranger)」とは、ベイブ自身のことだったのだ(「よそ者」と訳した方が分かりやすい)。
ベイブの希望は唯一、愛しい妹(マティ)だけである。
最後の一文に、絶望の中に希望を見いだした青年の、復活への可能性を感じさせる(「それをみてベイブは思った。世界に、こんな美しいものがあるなんて」)。
表題作「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる」や「フランスにて」と併せて、本書中の注目作となっている。
若者たち
サリンジャーのデビュー作。
コロンビア大学で、ウイット・バーネットの講義(短篇小説の創作)を受講していたサリンジャーの作品が、バーネットが編集長を務める『ストーリー』に採用される場面は、映画『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』(2017)でも描かれている(この頃は、バーネットとサリンジャーの関係も良好だったのに)。
そのときの作品こそ、本作「若者たち」で、サリンジャーは21歳の誕生日を迎えたばかりだった(原稿料は25ドル)。
上流社会で生きる若者たちの陰の部分をシニカルに描いた作品で、どちらかといえば、フィッツジェラルドの作風に近い。
非モテの女の子と、非モテの男の子の、悲しいすれ違い。
「ねえ!」エドナは煙草の先で、大きな赤い椅子の肘掛けを軽くたたきながら声をかけた。「ねえ、ルシル! ボビー! ラジオ、もう少しましなのはやってないの? こんな曲で踊れるわけないでしょ?」(J.D.サリンジャー「若者たち」金原瑞人・訳)
しかし、彼女にダンスの相手はいない。
自尊心と虚栄心だけは高い女の子の寂しい心を、巧みにすくい上げている。
ロイス・タゲットのロングデビュー
デビュー作「若者たち」と同じく、ウイット・バーネットの『ストーリー』に掲載された。
上流社会の女性が、様々な過ちを重ねた後に、ようやく当たり前の人間性を獲得するという、これもまた、皮肉に満ちた作品だった。
やがて、ロイスはほんとうの意味で社会にデビューした。そして、だれもがそれに気づいたようだった。(J.D.サリンジャー「ロイス・タゲットのロングデビュー」金原瑞人・訳)
アーリー・サリンジャーを知る上で貴重な作品。
ハプワース16、1924年
サリンジャーが発表した最後の作品だが、本国アメリカでは書籍化されていない。
物語の語り手は、グラース家の次男(バディ・グラース)で、バディは、1948年に31歳で自殺した長男(シーモア・グラース)が7歳のときに書いた長い手紙を引用する。
つまり、物語のほとんどは、シーモアの手紙の全文である。
ちなみに、シーモア・グラースは、名作短篇「バナナフィッシュにうってつけの日」で自殺した青年(『ナイン・ストーリーズ』所収)。
そのとき、シーモアは、バディと一緒に、ハプワース湖のサマー・キャンプに参加していて、自宅にいる両親(ベシーとレス)、妹(ベアトリス、愛称ブーブー)、双子の弟(ウォルターとウェイカー)に宛てて、長い手紙を出していた。
キャンプ仲間たちとうまくコミュニケーションできない話から始まる手紙は、およそ7歳の少年が書いたとは思われないほど老成していて、魅力的な人妻に性的に欲情した話まで綴られている(「ミセス・ハッピーは、ぼくの欲望をかきたててやまない」)。
なぜ、そんなことが起こるかというと、彼(シーモア)は、前世の記憶を持った超人だからだ(しかも、家族の前世のことまで把握している)。
最近流行の転生譚だが、作者が「輪廻転生」の影響を強く受けていたことを感じさせる(「父さんは前世で二度、同じような問題に直面することを怠ったよね」)。
なお、原文では、両親を「レス」「ベシー」とファーストネーム(愛称)で呼んでいるところ、本書では「父さん」「母さん」と翻訳されている。
幼い子どもらしくないためという配慮によるものだが、本作「ハプワース16、1924年」そのものが、幼い子どもを超越した、輪廻転生を繰り返す超常的な力を持った男の物語なので、幼い子どもという視点にこだわる必要はない。
むしろ、7歳のシーモアは、父や母を越える存在として登場しているから、彼らに愛称で呼びかけたところで、まったく不自然ではない(というか、その方が必然)。
7歳のシーモアが、大人の女性の肉体に欲情するくだりは、彼が煩悩を払いきれないために輪廻転生を繰り返していることを示唆している(短篇「テディ」を思い出す)。
シーモアには予知能力もあって、家族の将来に対して、様々な示唆を与える(「間違いない! これまでいろんな未来を垣間みてきたけど、こんな、手放しで喜べる最高の光景はめったになかった」)。
一冊の本を20~30分で丸暗記してしまう記憶力や、肉体の痛みを精神的にコントロールする力も、シーモアの異常性を示すものだ。
家族は(もちろん両親も)シーモアの予言に逆らう余地さえなかっただろう。
とても、子どもから両親に宛てて書かれた手紙とは思われない文章が延々と続く。
圧巻は、後半を埋める、キャンプ場へ送ってほしい本のリクエスト(『アンナ・カレーニナ』『ドン・キホーテ』『ラジャ・ヨガ』『バクティ・ヨガ』、チャールズ・ディケンズ、ジョージ・エリオット、ジェイン・オースティン、ブロンテ姉妹、マルセル・プルースト、アーサー・コナン・ドイル、、、)。
シーモアを幼い子どもと考えてはいけない。
彼は、輪廻転生を繰り返す、人生経験豊かな修行者なのだ。
そこには、時代を越えて読み継がれるべき名作文学のリストがある。
著者(サリンジャー)のメッセージを、シーモアの言葉に転化したものだろうが、冗長を遥かに通り越して長い(それはそれで楽しいことは間違いないが)。
シーモアの独白を越えて、もはや、サリンジャー自身の独白となっているような印象さえ受ける。
注目したいのはアルフレッド・アードンナの『アレキサンダー』に関するシーモアの指摘。
ぼくはアレキサンダー大王も、その他のどうしようもない軍人もあまり好きじゃないけど、アルフレッド・アードンナはひどい。だって、さりげなく、不当な印象を読者に与えようとしているんだから。要するに、自分のほうがアレキサンドロス大王より優れているといわんばかりなんだ!(J.D.サリンジャー「ハプワース16、1924年」金原瑞人・訳)
「だって、さりげなく、不当な印象を読者に与えようとしているんだから」とあるのは、かつてサリンジャーの作品を評したジャーナリズムに対する批判だったのではないだろうか。
「シーモアの自殺の謎を解く鍵」が、この作品に隠れていると考える研究者もいる(「バナナフィッシュ」の深読み)。
名誉をかけていうけど、原因はなんであれ、ぼくたちはどちらかが死ぬときには、もうひとりが必ずその場にいるはずだ。僕の知る限り、間違いない。(J.D.サリンジャー「ハプワース16、1924年」金原瑞人・訳)
「バナナフィッシュにうってつけの日」で、シーモアは、眠っている妻の隣で拳銃自殺したことになっているが、そのとき、バディが、その部屋にいた可能性はあるのか?
シーモアが自殺したときのことを、バディは『フラニーとゾーイー』の中で回想している。
シーモアが自殺したのは、三年前のちょうど今日だ。遺体を引き取りに僕がフロリダへ行ったとき、どんなことがあったか、君に話したっけか? 五時間びっしり、僕は飛行機の上で薄馬鹿みたいに泣いていたんだ。(J.D.サリンジャー「フラニーとゾーイー」野崎孝・訳)
常識的に考えると、バディが、シーモアの自殺に立ち合った可能性はない。
しかし、シーモアが前世の記憶を有していたように(予知能力を有していたように)、常識を超える何らかの力が働いていたとしたなら?
グラース家では、何が起こっても不思議ではないという思いを、この「ハプワース16、1924年」は読者に与える。
サリンジャーにとって大切だったことは、ストーリーの論理性ではない。
むしろ、論理性を越える物語こそ、サリンジャーが重視したものだったのではないか(短篇「テディ」)。
本作「ハプワース16、1924年」は、明らかに論理性を超越した向こう側にある世界を描こうとしたものだが、一般的な文学観で、この作品を読み解くことは難しい。
隻手音声(片手の音を聴け)。
サリンジャーがたどり着いたひとつの境地が、この物語だったのかもしれない。
まとめ
本書『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』の読みどころは、やはり、一連の戦争物語である。
従軍体験以後、サリンジャーが書きたかったものは、悲惨な戦争に対する「NO」だ。
『ライ麦畑でつかまえて』や『ナイン・ストーリーズ』を、戦争文学として読む考え方は、現在では珍しくない。
本書収録作品を読むと、その意味が容易に分かるような気がする。
中篇「ハプワース16、1924年」は、かなり異質。
『ナイン・ストーリーズ』『フラニーとゾーイー』『大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-』と、一連のグラース・サーガを順番に読んできた方が、とっつきやすいかもしれない(バディに対する感情移入もできる)。
なお、本書の続編として、同じく金原瑞人の訳による『彼女の思い出/逆さまの森』がある。

書名:このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年
著者:J.D.サリンジャー
訳者:金原瑞人
発行:2018/06/30
出版社:新潮社