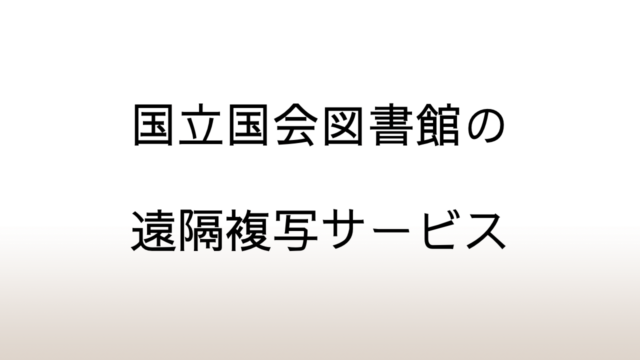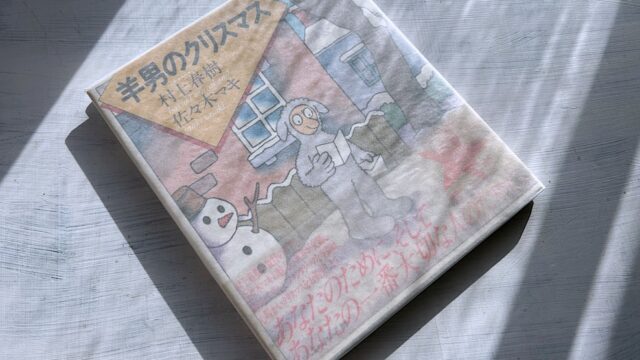村上春樹「とんがり焼の盛衰」読了。
本作「とんがり焼の盛衰」は、1983年(昭和58年)3月『トレフル』に発表された短篇小説である。
この年、著者は34歳だった。
作品集としては、1983年(昭和58年)9月に講談社から刊行された『カンガルー日和』に収録されている。
権威に群がる一般大衆の姿
本作「とんがり焼の盛衰」は、極めて象徴性に富んだ寓話だ。
著者本人の言葉を借りると「文壇(literary world)に対して抱いた印象をそのまま寓話化したもの」ということになるのだが、この作品が、国語の教科書に掲載された意味を考えるとき、<とんがり焼>を単に「文壇批判の物語」として解釈するだけでは、理解が不十分になってしまうだろう。
なぜなら「文壇批判」をテーマとする小説を、教科書に掲載することの必然性は、極めて低いと思われるからだ(そんな授業できないし)。
おそらく<とんがり焼>は、「文壇」という小さな世界に矮小化されない、もっと普遍的な象徴性を有している。
例えば、仮にこの作品を「文壇批判の物語」として読んだとき、<とんがり焼>は文学作品であり、<名菓とんがり焼・新製品募集>は、新人の作品を募集する文学賞のようなものということになる。
「ねえ、君はこれまでにとんがり焼って食べたことあった?」と僕は訊ねてみた。「あたりまえじゃない」と女の子は言った。「だって有名ですもの」「でもそんなに美味く……」と僕が言いかけたところで彼女が僕の足を蹴とばした。(村上春樹「とんがり焼の盛衰」)
とすると、<とんがり鴉>は、文学賞の選考委員として名を連ねている有名作家たち、あるいは「文壇」そのものということになるわけで、新作が認められるかどうかは、この<とんがり鴉>の意向によるところが大きい。
説明会に参加した主人公は、独創的で新しい<とんがり焼>を開発して、<名菓とんがり焼・新製品募集>に出品するが、この新しい<とんがり焼>の評価は社内でも分かれてしまうことになる。
真に新しいものが登場したとき、その評価は分かれることが普通かもしれないが、合否を決めるのは、結局のところ、選考委員たる<とんがり鴉>だという。
デビュー当時から、文壇のあり方に疑問を呈していた村上春樹らしい小説とも言えるが、そこに描かれているのは、果たして本当に「文壇」だけの姿だったのだろうか。
僕が思うのは、<とんがり焼>が「文壇」の象徴であるとするなら、この場合の「文壇」は、日本社会にはびこる、あらゆる「権威」の象徴でもあるのではないか、ということだ。
「権威」は、それを求める人たちに、この上ない価値を提供する一方で、関心のない人間にとっては、何の価値も持たないものでもある。
芸能界に興味のない人には「日本レコード大賞」は無価値に等しいものだし、ラーメンを食べない人にとっては、雑誌の「人気ラーメン店ランキング」なんて何の意味も持たない。
つまり、あらゆる権威とは、権威に追随する人があって初めて、権威として存在することができるということである。
「あなたってバカねえ」と少しあとで女の子がそっと耳うちした。「ここに来てとんがり焼の悪口なんか言ったら、とんがり鴉につかまって生きては帰れないんだから」(村上春樹「とんがり焼の盛衰」)
そう考えたとき、この物語で批判の対象となっているのは、単に文壇だけではないことが理解できる。
つまり、文壇という権威に追随する「一般大衆」こそが、この作品の本当の主人公なのだ。
芥川賞受賞作品というだけで、価値のある文学作品だと思い込み、ベストセラー作品だという理由だけを根拠に、大量の書籍を買い込む、この国の読書人たち。
歴史的に見たとき、その権威は、太平洋戦争を指揮した「日本政府」だったかもしれないし、1960年代の学生運動を牽引した「全学連」だったかもしれない。
そして、時代の権威は、すべて一般大衆の指示によって支えられてきたのである。
もちろん、「権威」しか拠り所のないところに発展はない。
この物語が指摘しているのは、こうしたシステムには未来がない(それが「盛衰」)ということなのだ。
本作「とんがり焼の盛衰」は、権威に追随する一般市民を含めた、この国のあらゆる伝統的なシステムに対する批判の小説だったのである。
周囲の評価に流されることなく、好きに生きていきたい
村上春樹が文壇を批判していることは確かだが、この物語の根底には、おそらく文壇以上の権威に対する痛烈な批判が、きっとある。
それは政治的な権威かもしれないし、社会的な権威であるかもしれない。
そうした様々な権威の象徴として<とんがり焼>があり、新しいものを受け入れがたい、日本の文化的風土があるのだろう。
むしろ、<とんがり鴉>を文壇関係者ではなく、一般市民として読んだ方が、この物語は理解しやすいかもしれない。
とんがり焼! とんがり焼! とんがり焼! と彼らは大声で叫んだ。その声が天井に反響して、耳の奥が痛くなるほどだった。「ほらね、本物のとんがり焼しか食べないんです」と得意そうに言った。「偽ものだと口もつけないんです」(村上春樹「とんがり焼の盛衰」)
伝統的で正統派の<とんがり焼>しか受け入れることのできない<とんがり鴉>の姿は、権威に盲従しがちな、この国の一般大衆の姿でもある(つまり「烏合の衆」だ)。
本作「とんがり焼の盛衰」は、そんな日本的な風土全般を広く批判した、極めて象徴性の高い寓話だったのである(「平安時代」とか「古今和歌集」とか伝統を誇る場面も、いかにも権威主義)。
そして、この作品で著者が最も伝えたかったこと、それは、周囲の評価に流されることなく、好きに生きていきていくことの尊さである。
僕は自分の食べたいものだけを作って、自分で食べる。鴉なんかお互いにつつきあって死んでしまえばいいんだ。(村上春樹「とんがり焼の盛衰」)
同調圧力に屈することなく、我が道を生きていく孤独な人間の物語。
そんなふうに読むと、この物語は、突然大きな普遍性を有してくるのではないだろうか。
作品名:とんがり焼の盛衰
著者:村上春樹
書名:カンガルー日和
発行:1986/10/15
出版社:講談社文庫