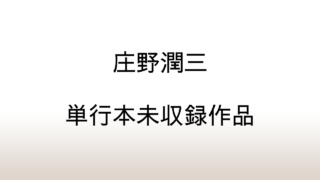吉本ばなな『キッチン』読了。
本作『キッチン』は、1988年(昭和63年)1月に福武書店から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は24歳だった。
吉本ばなな最初の作品集で、収録作品と初出は、次のとおり。
「キッチン」
1987年(昭和62年)11月『海燕』
1987年(昭和62年)第6回海燕新人文学賞受賞
「満月──キッチン2」
1988年(昭和63年)2月『海燕』
「ムーンライト・シャドウ」
大学の卒業制作
1987年(昭和62年)日本大学芸術学部長賞受賞
1988年(昭和63年)第16回泉鏡花文学賞受賞
菊池桃子が象徴するシティポップ世代の純文学「キッチン」
吉本ばななのデビュー作「キッチン」に、菊池桃子の「二人のNIGHT DIVE」という曲が出てくる。
私も洗いものを持って立ちあがった。カップを洗っていると、水音にまぎれて雄一が口ずさむうたが聞こえた。♪月明りの影/こわさぬように/岬のはずれにボートをとめた「あっそれ 知ってる。何だっけ。けっこう好き。誰のうただっけ」(吉本ばなな「キッチン」)
「二人のNIGHT DIVE」は、1984年(昭和59年)9月に発売された菊池桃子のデビューアルバム『OCEAN SIDE』に収録されている(作詞は秋元康)。
「杉山清貴&オメガトライブの妹分」として登場した菊池桃子は、1980年代、林哲司による「オメガサウンド」で、アイドルらしからぬ優れた楽曲を数多く残した。
近年のシティ・ポップ・ブームの中、菊池桃子も、再評価による再ブレイクを果たしたミュージシャンの一人と言っていい。
アルバム『OCEAN SIDE』は、チャート1位を獲得した名作ではあるものの、シングル発売されていない「二人のNIGHT DIVE」が、吉本ばななのデビュー作品に登場していることは興味深い。
平中悠一の提唱する「シティ・ポップと同時代的な文学=シティ・ポップ文学」の匂いが、この作品にも感じられるからだ。
1980年代は、常に「新しい時代の作家」が登場する時代だった。
少女漫画の影響を強く感じさせる吉本ばななも、「新しい時代の作家」と呼ばれた作家の一人だ。
「目がさめちゃって、腹へって、ラーメンでも作ろうかなあ……と思って……」夢の中とはうって変わって、現実の雄一は寝ぼけたブスな顔でぐしゃぐしゃそう言った。私は泣きはらしたブスな顔で、「作ってあげるから、すわってな。私のソファーに」と言った。(吉本ばなな「キッチン」)
若い世代の日常的な言葉を使った地の文章は、文学が日常生活とは疎遠なものではないことを、分かりやすく印象付ける。
80年代冒頭から始まっていた純文学のパラダイムシフトは、ここでも明らかだ。
作品における菊池桃子の登場も、若い世代の日常生活にとっては、何の違和感もなかったことなのかもしれない。
「ここが、特に好き」と私は2番のアタマのところをうたった。「とおくの──/とうだい──/まわるひかりが──/ふたりのよるには──/こもれびみたい──」はしゃいで、大声でくりかえして2人はうたった。(吉本ばなな「キッチン」)
主人公(桜井みかげ)は、たった一人の肉親である祖母を亡くして、天涯孤独な身の上となっていた。
デビュー作「キッチン」は、祖母を失った喪失感と向き合う若い女性の物語である。
主人公は、祖母と仲良しだったお客さん(田辺雄一)に誘われて、田辺家のマンションへ居候する。
雄一もまた、幼くして母を亡くしており、かつて父親だった母親(えり子)と二人で暮らしていた。
「この母が死んじゃった後、えり子さんは仕事をやめて、まだ小さなぼくを抱えて何をしようか考えて、女になることに決めたんだって。もう、だれも好きになりそうにないからってさ」(吉本ばなな「キッチン」)
元・男性の母親と、変わり者の青年との共同生活の中で、主人公は少しずつ喪失感を乗り越えていく。
考えてみると、母を失った雄一も、妻を失ったえり子さんも、やはり、喪失感と向き合いながら生き続けている人たちだった。
だから、この物語「キッチン」は、喪失感を抱えた三人の、克服の物語として読むことができる。
菊池桃子の「二人のNIGHT DIVE」は、喪失感を乗り越えようと生きる主人公と雄一にとって、青春のサウンド・トラックだったのだ。
親しい人の死と組み合わせるアイテムとして、菊池桃子は、いささかポップに過ぎるかもしれない。
しかし、肉親の喪失体験とシティ・ポップ(菊池桃子)とが、決して疎遠ではないことは、当時の若者世代が知っていた。
シティ・ポップは既に、若い世代の共通言語として機能していたからだ。
本作「キッチン」は、決して急進的な文学作品ではない。
親しい人間を失った喪失感というテーマは、文学においてオーソドックスなものだし、主人公の心のよりどころとして「台所(キッチン)」が引用されているところも、決して奇想天外なものではなかった。
夢のキッチン。私はいくつもいくつもそれをもつだろう。心の中で、あるいは実際に。あるいは旅先で。ひとりで、大ぜいで、ふたりきりで、私の生きるすべての場所で、きっとたくさんもつだろう。(吉本ばなな「キッチン」)
バスの中で一緒になった見知らぬ家族の会話を聞いて、主人公は涙を流す。
ガキ。私もまた疲れていたため思わず汚い言葉で思ってしまった。後悔は先に立たねえんだ。おばあちゃんにそんな口をきくなよ。(吉本ばなな「キッチン」)
思わずバスからエスケープして、薄暗い路地でわんわん泣いたとき、彼女は「厨房」の存在に癒される。
「厨房(台所)」は、彼女が失ったものの象徴だったからだ。
新しいキッチンを夢見るラストシーンは、主人公(桜井みかげ)の再生を予感させる。
台所と菊池桃子とおばあちゃんの死。
一見、異素材と思える組み合わせこそ、シティポップ世代の純文学だったのかもしれない。
80年代的ポップな太宰治だった「ムーンライト・シャドゥ」
「キッチン2」の副題が付いた2作目「満月」は、ストーカーに殺された田辺えり子の死を乗り越えようとする、主人公(桜井みかげ)と、元・同居人(田辺雄一)の物語である。
一作目「キッチン」に続き、二人は「親しい人間の死」という新たな喪失感と向き合わなければならない。
「ついにみなしごになってしまったよ」雄一が言った。「私なんて、2度目よ。自慢じゃないけど」私が笑ってそう言うと、ふいに雄一の瞳から涙がぽろぽろこぼれた。(吉本ばなな「満月」)
若い二人にとって重すぎる試練だが、ポップな地の文章が、物語が感情的に流れていくのをセーブしている。
「もっと、本質的に?」「そうそう。人間的にね」「あるの。絶対にあるわ」私はすぐさま言った。もしこれが「クイズ100人に聞きました」の会場だったら、あるあるの声が怒号のように響きわたっただろう。(吉本ばなな「満月」)
真剣な会話を、ジョークでかわす技術は、80年代の若い世代が好んで用いたコミュニケーション・スキルだ(「なーんちゃって」)。
重いテーマと軽い文章が、互いにバランスを取りながら、純文学という世界に共存している(「午後の光が射す調理室に立ちつくしたままで、私は、とほほほ、と思った」)。
もちろん、地の文章はすべてが軽すぎるというわけではなくて、要所要所で引き締めを意識したフレーズが投入される(「チン、とエレベーターが止まり、私の心が瞬間、真空になった」)。
遠く離れそうになった二人の距離を縮める役割を果たすものが、<真夜中のカツ丼>だったというプロットもいい。
なぜ、人はこんなにも選べないのか。虫ケラのように負けまくっても、ご飯を作って食べて眠る。愛する人はみんな死んでゆく。それでも生きてゆかなくてはいけない。(吉本ばなな「満月」)
主人公は(桜井みかげ)は、どこまでもまっすぐで、そして健康的だ。
激しい喪失感を抱えながら、安易に自己崩壊的な決着を選ぶことなく、ポジティブに人生を生きるということが、あるいは、1980年代という時代だったのかもしれない。
「どうして君とものを食うと、こんなにおいしいのかな」私は笑って、「食欲と性欲が同時に満たされるからじゃない?」と言った。「ちがう、ちがう、ちがう」大笑いしながら雄一が言った。「きっと、家族だからだよ」(吉本ばなな「満月」)
一作目「キッチン」では、菊池桃子が果たした役割を、本作「満月」では、真夜中のカツ丼が勤めている。
親しい人の死と真夜中のカツ丼と。
旺盛な食欲は、若い世代の生きる力を象徴するものだ。
健康的な80年代カップルの喪失と再生。
本作「満月」は、やはり「キッチン」とセットで読みたい青春小説だと思う。
最後の「ムーンライト・シャドゥ」は、著者(吉本ばなな)が22歳のとき、日本大学芸術学部文芸学科の卒業制作として提出した作品で、1987年(昭和62年)の芸術学部賞を受賞している。
簡単に言えば、80年代的ポップな太宰治という印象の作品だ。
後からなら大声でだって言える。神様のバカヤロウ。私は、私は等を死ぬほど愛していました。(吉本ばなな「ムーンライト・シャドゥ」)
本作「ムーンライト・シャドゥ」は、交通事故で恋人(等)を失った主人公(さつき)の喪失感をテーマとした短篇小説だ。
等(ひとし)の弟(柊)も、また、同じ事故で恋人(ゆうこさん)を失っていた。
柊の今着ているセーラー服は、ゆみこさんの形見だ。彼女が死んでから、私服の高校だというのに彼はそれを着て登校している。ゆみこさんは制服が好きだった。(吉本ばなな「ムーンライト・シャドゥ」)
男子高校生である柊(ひいらぎ)が着るセーラー服は、彼の喪失感を象徴するものだ。
デビュー作「キッチン」で、妻を失くした夫が女性になってしまったのと同じように(えり子さん)、恋人を亡くした青年の混乱もまた、性的な転換として描かれている。
謎の女性(うらら)も、また、恋人を亡くした喪失感を抱えていて、この物語は、彼らの救済のための物語として読むことができる。
この場面は泣きながら何度もリバースした場面だ。いや、思い出す度に涙が出てしまった。橋を渡り、追いかけていって行ってはだめだとつれ戻す夢も何度も、何度も見た。夢の中で等は、君がとめてくれたから死なずにすんだよ、と笑った。(吉本ばなな「ムーンライト・シャドゥ」)
本作「ムーンライト・シャドゥ」の本質は、たとえ幽霊でもいいから、死んでしまった人と、もう一度会いたいと願う、人間の悲しい祈りである。
100年に1回の「七夕現象」は、人間の悲しい祈りが生んだ少女漫画的な幻想だった。
少女漫画的幻想に救いを求めるという行為にこそ、80年代の若者たちは強い共感を抱いたのかもしれない。
「別れも死もつらい。でもそれが最後かと思えない程度の恋なんて、女にはヒマつぶしにもなんない」うららはドーナツをもぐもぐ食べながら世間話でもするようにそう言った。(吉本ばなな「ムーンライト・シャドゥ」)
作品タイトル「ムーンライト・シャドゥ」は、イギリスのマイク・オールドフィールド、1983年(昭和58年)のヒット曲「Moonlight Shadow」にインスパイアされたもの(歌はマギー・ライリーだった)。
「死んだ恋人に、いつか会えるかもしれない」という悲しい祈り。
その悲しい祈りを、本作「ムーンライト・シャドゥ」は、否定することなく、ポジティブに描いた。
本作『キッチン』収録作品に共通しているのは、喪失感と向き合う若者たちの、ひたむきなまでに前向きで健康的な姿である。
随所に1980年代の空気を感じるが、この空気感は、2024年の現代にまで繋がっているものだ。
懐かしいはずなのに、レトロスペクティブな感覚だけではない。
現代文学の源流が、あるいは、このあたりから生まれていたのだろうか。
書名:キッチン
著者:吉本ばなな
発行:1991/10/17
出版社:福武文庫