名作の舞台や作者ゆかりの土地を訪ねる文学紀行は、読書好きの人にとって憧れの旅行ではないだろうか。
殊に、自分の好きなものが海外文学の作品だとしたら、作品への理解を深めるためにも、旅行は、ひときわ有意義なものとなる。
著者(松本侑子)は、彼女の青春時代に愛読した海外文学を巡る旅に出た。
「今ほど海外旅行がさかんではなかった昭和に、心おどらせて読んだ物語の舞台は、今よりもはるかに遠い異国だった」「そのために憧れはますますふくらんでいった」「ずっと夢見てきた場所をめざす旅は、いつも私をこのうえなく幸福にした」などの言葉は、著者の文学作品に対する愛情を示すものだろう。
いくつになっても読書は尊くて楽しいものだが、青春時代に心を奪われた本の思い出を語る喜びは、本好きの人間にとってまさしく至福と言っていい。
著者にとって、それが、「赤毛のアン」「あしながおじさん」「はるかなるわがラスカル」などといった、海外の文学作品だった。
彼女は、子どもの頃の思い出を胸に、物語の舞台や作者ゆかりの土地を、大人になった彼女の目で見て回る。
幼き日の感動を呼び起こすこともあれば、大人だから理解できる新しい発見もあったことだろう。
ひとつひとつの作品に綴られたエッセイには、それぞれの物語に対する彼女の文学愛が溢れている。
美しいカラー写真が、物語の情景を鮮明に再現してくれる。
文学紀行の楽しさを教えてくれる一冊だ。
「はるかなるわがラスカル」の「よき時代の思い出」
作者のスターリング・ノースは十二歳の春にラスカルと別れた。その数年後、ポリオにかかり、いくらか体が不自由になった。ラスカルと暮らしたころのように川で泳ぎ、森を歩きまわり、自転車に乗り、カヌーをこぎ、スケートで疾走する、といった男の子らしい遊びは永久に失われてしまったのだ。(「はるかなるわがラスカル」)
スターリング・ノースの「はるかなるわがラスカル」は、二十世紀初めのアメリカの田舎の暮らしや中西部の湖水と森、野生の鳥や獣、魚、そして、そこで生きる少年の日々が活写された自然文学の傑作である。
ともに暮らした一年間の生活の中で、少年とラスカルとが互いに成長していく様子が、四季の移ろいも鮮やかに叙情豊かに綴られていくが、作者のスターリングにとって、ラスカルとともに生きた日々は、まぶしいくらいに健康だった少年時代への哀惜の物語でもあった。
「はるかなるわがラスカル」に付けられた「よき時代の思い出」なる副題には、そんな作者の切ない思いが偲ばれるようだ。
スターリングが少年時代にラスカルと暮らした家は今、スターリング・ノース協会が運営する記念館になっている。
「若きウェルテルの悩み」とゲーテの失恋体験
私は中学の時に初めて読んだ。ロッテの気持ちを考えない一方的なウェルテルのふるまいに興ざめするばかりで、失恋で命を絶つ心情が理解できなかった。恋をしたこともない十四歳には早すぎたのだろう。(「若きウェルテルの悩み」)
著者が「若きウェルテルの悩み」の文庫本を折に触れて開き、ウェルテルの青臭い懊悩にことごとく共感するようになったのは、片思いの恋にも自分自身にも悩みの多かった学生時代のことだ。
ウェルテルの書簡文を、著者は「友だちから恋の始まりの高揚、報われない悲しみ、未練を打ち明けられているようで」「幸せの意味を真剣に考える若い知性にも、二百年前の読者と同じように共感した」とある。
1774年に発行された「若きウェルテルの悩み」がベストセラーとなったとき、台頭し始めた市民階級の若者たちは、恋に煩悶しつつも、社会や宗教を思索しする知的でロマンチックな青年像に熱狂し、ウェルテルの青い燕尾服と黄色いチョッキが流行しただけでなく、ウェルテルと同じように自殺する若者が激増するまでの社会現象になったらしい。
ゲーテの失恋体験は、法律家見習いとして過ごしたヴェツラー時代のことだが、ヴェツラーは人口五万人のひっそりとした町で、かつては世界的に有名なライカカメラ社があった。
ゲーテの愛したシャルロッテ・ブッフの暮らした屋敷が、今も残されている。
文学紀行の旅は「初めてなのに懐かしい土地へと向かう、不思議な高揚感に満たされていた」と、著者は言う。
もしかすると、著者は、思い出の中にある物語の登場人物たちととももに、外国の街を旅していたのかもしれない。
書名:私の青春文学紀行
著者:松本侑子
発行:2008/7/25
出版社:新潮社「とんぼの本」

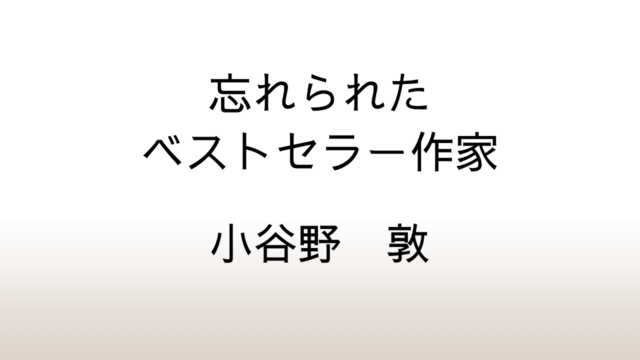




-150x150.jpg)









