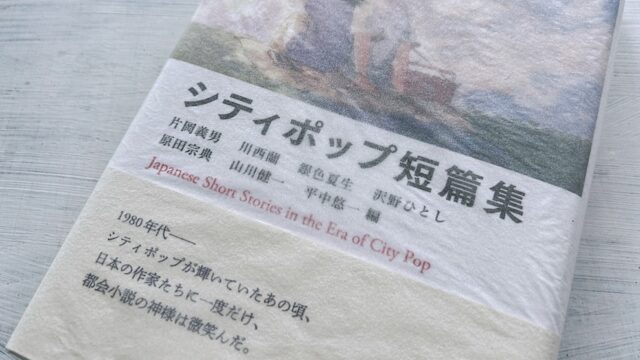佐多稲子「キャラメル工場から」読了。
本作「キャラメル工場から」は、昭和3年に発表されたプロレタリア文学の名作である。
キャラメル工場で働く若い女性たちの姿
佐多稲子が作家としてデビューしたのは昭和3年。
「プロレタリア芸術」に掲載された本作「キャラメル工場から」が処女作であった。
貧しい暮らしの中、家庭を支えるためにキャラメル工場で働いた経験が、そのまま作品の素材となっている。
主人公の<ひろ子>は13歳である。
「ひろ子もひとつこれへ行ってみるか」
仕事をしない父の指示によって、学校を辞めて、キャラメル工場へ働きに出かけることになった。
工場までは電車で四十分、徒歩だと2時間はかかる。
工場で得られる労賃は、電車賃を差し引くと、ほとんど間尺に合わないのだが、彼女の父は、そんなことを考えることさえできなかった。
ひろ子はこごえるよりも遅刻がおそろしかった。襟巻きに顔をうずめて、戦に行くような気持ちで歩いて行った。外は研ぎ立ての包丁のような夜明けの明るさだ。そしてきしむように寒い。橋の上では朴葉が何度かすべった。(佐多稲子「キャラメル工場から」)
工場では二十人ばかりの娘たちが、二列にならんだ台に向かい合わせに立ち、うつむきになって指先を一心に動かしている。
彼女たちは、みな、腹巻をして、父親のお古の股引を穿いて、工場の寒さをしのごうとしていた。
ひろ子は、トラホームでしょぼしょぼした目の娘と、女工頭の妹と、三人一組で働いていた。
みんな入ったばかりの新人たちである。
仕事中には、前日の成績として、優等者三人と劣等者三人の名前が貼りだされた。
他の娘たちが五缶こしらえるところ、ひろ子はどうしても二つ半しかできなかった。
終日、日の当たらない仕事室の窓からは、どぶ臭い川を隔てて、向う岸の家のごたごたした裏側が見えた。
昼になる頃、朝六時につめられた弁当は、アルミニウムの箱の中でぼろぼろに凍っていた。
キャラメルの仕事が途絶えると、化粧液の壜洗いをさせられた。
冷たい水の中に手を入れながら、ひろ子の鼻先からは涙が落ちてきた。
やがて、工場では日給制をやめて、一缶の賃金を数えるようになった。
多くの娘たちの賃金が下がり、それは、もちろんひろ子も同じだった。
「いっそ、もうどうかね、止めにしたら」
父がまた、何でもないように言い出した。
電車賃を差し引くと、いくばくも残らないことを、父は言っているらしかった。
ある日、郷里の学校の先生から手紙が届いた。
誰かからなんとか学資を出してもらうよう工面して—大したことでもないのだから、小学校だけは卒業するほうがよかろう—と、そんなことが書いてあった。
付せんがついてそれがチャンそば屋の彼女の所へ来た時—彼女はもう住み込みだった—それを破いて読みかけたが、それを掴んだままで便所にはいった。彼女はそれを読みかえした。暗くてはっきり読めなかった。暗い便所の中で用もたさず、しゃがみ腰になって彼女は泣いた。(佐多稲子「キャラメル工場から」)
学校へ通うことのできない辛さ
本作は、キャラメル工場で働く女性たちの姿をとらえたスケッチ的な短篇小説である。
特別のストーリーはないが、厳しい環境下での労働を強いられる若い女性たちの姿が、分かりやすい文章で、生々しいリアリティをもって描かれている。
ポイントは、キャラメル工場を辞めた後の、彼女の境遇だろう。
父親から「もう止した方がいい」と言われて、ホッとした彼女の様子が描かれた後で、場面は突然、故郷の学校の先生から手紙が届く場面へと変わる。
そのとき、彼女はもう、ラーメン屋に住み込みで働いているところで、到底学校に戻れる状況ではなかった。
キャラメル工場に通いながら、何度も「学校へ行って勉強したい」と願った彼女の願いは、もはや叶う見込みはない。
「大したことでもないのだから」という、手紙の文面が、ひたすらに彼女を泣かせる。
彼女が泣く場所は、ラーメン屋の便所だった。
「暗い便所の中で用もたさず、しゃがみ腰になって彼女は泣いた」という最後の一文が、彼女の境遇をまったく表しているかのようだ。
したたかな計算や、あざといストーリー展開がないからこそ、こうした作品は生きているのだと思う。
作品名:キャラメル工場から
書名:教科書で読む名作 セメント樽の中の手紙ほかプロレタリア文学
著者:佐多稲子
発行:2017/3/10
出版社:ちくま文庫
日本の近代文学の世界をもっと深く知りたい方へ
日本の近代文学の世界をもっと知りたい!という方に、おすすめの記事を用意しました。
日本の近代文学のおすすめ 50選!
夏目漱石や島崎藤村、志賀直哉、小林多喜二、谷崎潤一郎、太宰治など、有名どころの名作を集めてみました。
詳細な考察記事へのリンク付きなので、作品解釈に迷ったときの参考にもなりますよ!
▶ 日本近代文学の名作おすすめ50選|中高生・初心者でも楽しめる傑作を徹底解説