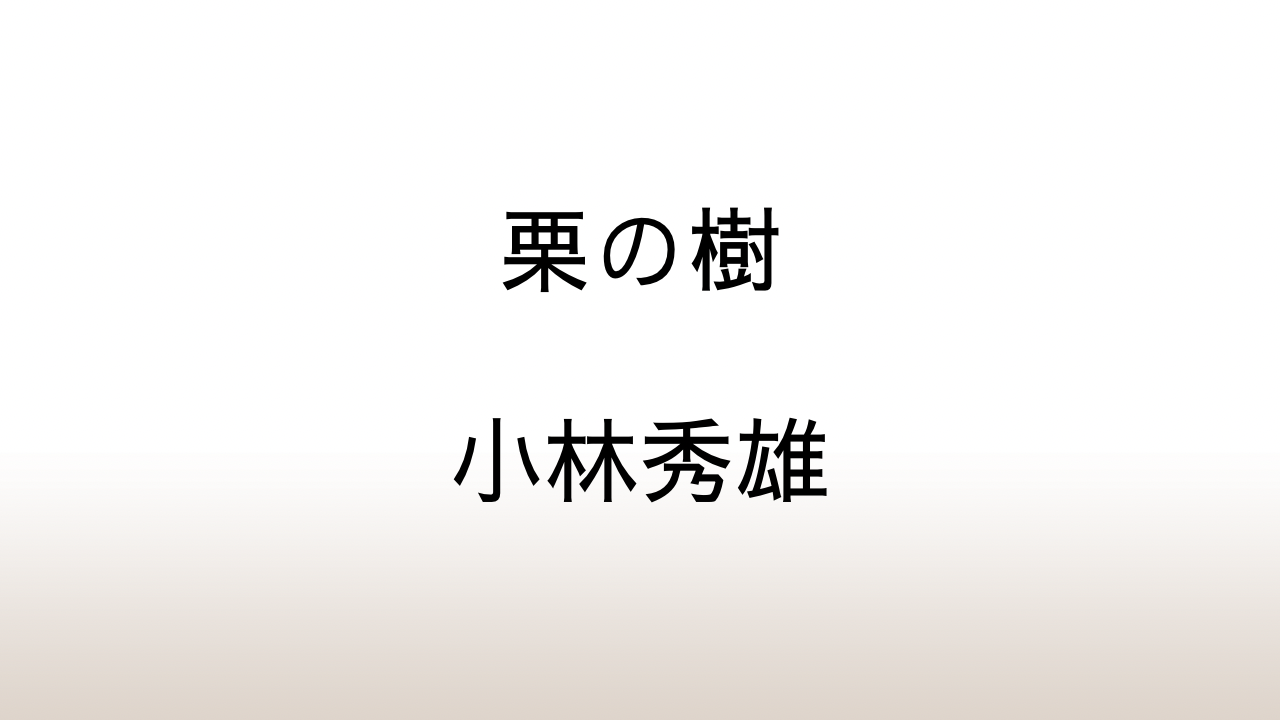小林秀雄「栗の樹」読了。
「珍品堂主人」の流れから、小林秀雄を読んでみる。
白洲正子や青山二郎との交流
白洲正子のエッセイに書かれている「真贋」という随筆も入っていた。
良寛の書を書けて得意になっていたら、良寛研究家の吉野秀雄がやってきて、この書が贋物だということが分かってしまった。
腹が立ったので、一文字助光の名刀で、縦横十文字にバラバラにしてしまう。
すっきりとしていい機嫌で飲み直すのだが、翌朝になって、切り刻むこともなかった、さっさと売れば良かったのだと後悔する。
くよくよしているところが、いかにも人間臭くていい。
呉須赤絵の見事な大皿を見つけて買ったことを、東京の青山二郎に話したところ、図柄や値段を聞いただけで「馬鹿」と言った。
無理に鎌倉まで連れ出して皿の実物を見せると、「思ったとおりの代物だ」と言って、「鑑定料に志那料理でもおごれ」と、横浜の南京町まで連れて行かれたという。
もっとも、この呉須赤絵、東京の「壺中居」という店へ持ち込むと、主人は箱を開けてちょいと覗いてから「これはいいですよ」と言って、つまらなそうに紐をかけたから、骨董は分からない。
小林秀雄も「青山さんが、どうしてあの時あんな間違いをしたか、今だにわからない」と綴っている。
近所に住んでいる瀬津さんという骨董屋で、彫三島の茶碗を見つけるが、値段が高すぎてとても手に出ない。
ところが、瀬津さんの方から、小林秀雄が持っている往生極楽院の千体仏の板画となら交換してもいいと言い出した。
半信半疑で物々交換をして、念願の彫三島を手に入れたその翌朝、瀬津さんが飛んできて「飛んだ失敗をしました」と言う。
小林秀雄は澄まして「そうだろう」と答えて、まんまと茶碗をせしめてしまったらしい。
井伏鱒二の「珍品堂主人」に登場する古印の話もある。
その中に古印に凝っているのがいて、或る時、麗水とある古色蒼然たる大きな焼印めいたものを見せ、奈良時代のものだという、麗水というのは朝鮮の麗水の事だという。麗水といえば確か百済の港だ、いや任那だったかな、まあどっちでもいい、ともかく大したものだ、と私は合槌を打ち、日韓交通の夢の跡をひねくり廻して興奮を覚えた。(小林秀雄「真贋」)
この麗水の古印は、やがて、友人の手を離れてゆくが、いつの間にやら「やっと取り戻した」と言って得意になっている。
ところが、この麗水を見た静岡県の醤油屋さんが「これなら家の倉庫に未だ三つや四つある筈だ」と話す展開は、まさしく『珍品堂主人』そのままである。
酒器にもこだわりを持った小林秀雄
骨董関係の随筆では、もうひとつ、「徳利と盃」もいい。
小林秀雄の酒好きは有名だから、当然、酒器にもこだわりを持っている。
徳利は俗に刷目と言われている朝鮮もので、下地に、何やらわけのわからぬ唐草風の鉄砂の絵附けが透けて見えるところが珍しいものだったが、これは鵠沼にいる焼き物好きの友人に譲ってしまった。
盃は唐津で、「唐津好きはやかましいことを言うが、私には、無地唐津と絵唐津で充分で、何処の窯のものかも知らない」という。
無地のものは、青山二郎が「掘出し物株式会社」なるものを空想していた当時に譲り受けたものである。
ところで、北鎌倉に目利きの爺さんがいて、庭に立派な陳列館を建てて収集品を飾っている。
ところが、この爺さん、酒の方はあまりイケる口ではないらしく、徳利と盃を見せろと言うと、唐津を三つ、堅手を一つ、見事な盃を四つ、炬燵の上にパラリと並べた。
一合はどうかと思われる小振りの、とろとろになった鶏竜山の徳利を出して来て、振って見せ、「わしには、これ一本で丁度だ」と笑った。店では見せない顔附きである。私が、黙って、盃を一つ一つ、ていねいに見ていると、彼は、独りごとのように言った。「五十年で、たったこれだけ。無いもんだ。いや、無いもんだ」(小林秀雄「徳利と盃」)
書名:栗の木
著者:小林秀雄
発行:1990/3/10
出版社:講談社文芸文庫