サリンジャー「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」読了。
本作は、1955年(昭和30年)11月『ザ・ニューヨーカー』に発表された中編小説である。
この年、著者は36歳だった。
ちなみに、この年、サリンジャーは、クレア・アリソン・ダグラスと結婚している。
作品集としては、1963年(昭和38年)1月にリトル・ブラウン社から刊行された『大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-』に収録されている。
日本では、1970年(昭和45年)4月、野崎孝の翻訳によって、河出書房新社から刊行された。
ちなみに、1955年(昭和30年)、サリンジャーは、二つの作品を発表している。「フラニー」(2月)と「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」(11月)だ。
家族の幸福を祈るグラース家の絆
本作「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」は、グラス家の長男<シーモア>の結婚式の日の様子を、次男<バディ>の目線から描いた中編小説である。
作品集『ナイン・ストーリーズ』中の「バナナフィッシュにうってつけの日」で、突然に自殺してしまう若者がシーモアだから、本作「大工よ」は、やがて「バナナフィッシュ」へとつながる物語として読むことができる。
そういう意味では、本作「大工よ」は、まるで『ナイン・ストーリーズ』に収録された作品の一つという感じがしないでもない(というか、『ナイン』との親和性を強く感じる)。
『ナイン・ストーリーズ』では断片的に登場していたグラス家の全体像が明確に示されているということも、本作の特徴の一つと言えるだろう。
作品タイトルの「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」は、妹のブー・ブーがバスルームの鏡に書き残していった詩の一節である。
「大工よ、屋根の梁を高く上げよ。エアリーズさながらに、丈高き男の子にまさりて高き花婿きたる。愛をこめて。先のパラダイス放送株式会社専属作家アーヴィング・サッフォより。汝の麗しきミュリエルと何卒、何卒、何卒おしあわせに。これは命令である。予は、このブロックに住むなんびとよりも上位にあるものなり」(サリンジャー「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」野崎孝・訳)
引用詩を要約すると「並の大男よりもずっと大きな花婿が来るので、屋根を高くして待っていなさい」ということになるが、これは、もちろん、シーモアを受け入れることになるミュリエルとその家族(特に母親)に対して向けられた言葉だろう。
シーモアは、一般の人間を超越した存在なのだから、シーモアと結婚する者も、それを受け入れるだけの大きな心を持たなければならない、という意味で。
結果として、ミュリエルもその家族も、シーモアを受け入れるだけの大きな心を持つことはできなかった(屋根の梁を高くすることはできなかった)ことは、既に「バナナフィッシュ」で書かれているとおりである。
ちなみに、1955年(昭和30年)、コーニッシュにあるサリンジャー邸では、増築工事が行われていた。大工をはじめとする職人たちは、サリンジャーの目前にいたのである。
偉大な花婿を歓迎する祝婚歌を引用しつつ、「汝の麗しきミュリエルと何卒、何卒、何卒おしあわせに。これは命令である」とあるのは、家族を代表してブー・ブーが示した強い祈りのようなものだ。
やがて、シーモアが自殺することを知っている読者は、「何卒、何卒、何卒おしあわせに」という言葉の重たさを感じないではいられない。
ブー・ブーはじめ、グラース家の人々もまた、シーモアの未来に対する不吉な予兆を、本能的に察知していたのかもしれない。
シーモアがミュリエルと結婚するのは1942年(昭和17年)5月のこと。その後、1948年(昭和23年)、妻ミュリエルと旅行滞在中だったフロリダで、ピストル自殺により死亡。30歳だった。
「バナナフィッシュにうってつけの日」とのつながり
本作の冒頭で、当時十七歳のシーモアが、生後十か月のフラニーに、「道教のある説話」を読み聞かせる場面が出てくる(このとき、バディは十五歳だった)。
それは、伯楽から紹介を受けた九方皐(きゅうほうこう)が、秦の穆公のために名馬を探してくる話だが、皐が「栗毛の牝馬」と言った、その馬は、実際には「漆黒の牡馬」だった。
当然、穆公は「馬の毛色はおろか、雌雄の別すらわきまえぬ男だ」と激怒するが、伯楽は動じることなく「皐の目に映っているのは魂の姿だ」と答える。
肝心かなめのものを掴むために、瑣細なありふれたことは忘れているのでございます。内面の特質に意を注ぐのあまり、外部の特徴を見失っているのでございます。見たいものを見、見たくないものは見ない。見なければならないものを見て、見るに及ばぬものは無視するのでございます。(サリンジャー「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」野崎孝・訳)
バディは、このエピソードを紹介した後で「この花婿が人生の舞台から永久に退場してからというもの、わたしには、彼の代りに馬を探しに遣わしたく思う者は一人として思い浮かべることすらできなくなった」と綴っている。
つまり、シーモアこそ「内面の特質に意を注ぐのあまり、外部の特徴を見失っている」人間であることを示唆しているのだが、この話は、シーモアが「人生の舞台から永久に退場」することになった物語「バナナフィッシュにうってつけの日」を思い出させる。
ピストル自殺する直前に、海辺で幼いシビルと戯れていたシーモアが、シビルの着ている水着の色を間違えてしまう場面である。
「きみのその水着、いい水着だね。ブルーの水着っていうの、こんなに好きなものないな」シビルは大きく目をみひらいて相手を見つめ、それから少し突き出た自分の腹に視線を落とすと「これは黄色」と、言った。(サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
あるいは、これは、シーモアが、もはや九方皐の境地にまで到達していることを示すエピソードだったのかもしれない。
いずれにせよ、本作「大工よ」が、「バナナフィッシュ」との密接な関連性の上に成り立っていることは明らかだろう。
紛れもなく「大工よ」は、「バナナフィッシュ」のプリクエル(前日譚)として読むべき物語なのだ。
バディの居心地の悪さは、グラス家の生きづらさ
本作「大工よ」において、物語の中心となっているのは、直前逃亡した花婿(シーモア)に取り残された結婚式の招待客たちの会話だが、ここで顕著になっているのは、一般社会とグラス家との大きな乖離(対立)である。
とりわけ文句の多い<介添夫人>は、一般社会の象徴だろう。
ただ一人、結婚式に参列した<わたし>(バディ)は、グラス家の代表として、非常識なシーモアに対する非難を一心に浴びることになるのだが、彼女の悪意に満ちた中傷は、グラス家の人々がこれまでも浴び続け、そして、これからも浴び続けていくだろう非難に他ならない。
好意的な四流批評家やコラムニストのうちで、ただの一人だって、シーモアの本当の姿を見てくれた者はいなかった。彼は詩人なんだ。本物の詩人なんだ。たとえ一行も詩を書かないにしても、その気になれば、耳の裏の形一つででも、パッと言いたいことを伝えることのできる男なんだ。(サリンジャー「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」野崎孝・訳)
世の中が、シーモアを異常者扱いするほどに、グラス家の(とりわけ兄弟の)結束は強くなっていく。
ここに、グラス家の幸福と孤独が描かれているような気がする。
シーモアは俗物を呪いながらも、俗物の象徴とも言うべき女性ミュリエルと結婚することにより、大いなる俗物を受け入れようとしている。
かつて、フラニーが「ズーイー」の中で<太っちょのオバサマ>を受け入れたように、シーモアもまた、ミュリエルという俗物を受け入れようとしていたのかもしれない。
切ないのは、たった一人で結婚式に参列し、介添夫人から散々に文句を言われる羽目になった、弟のバディである。
バディの居心地の悪さは、グラス家の生きづらさであり、バディの孤独は、グラス家の疎外感でもあっただろう。
バディの唯一の味方となったのが、背が低くて年老いた聾啞者(ミュリエルの大叔父)ただ一人だったことからも、グラス家が極めてマイノリティな存在として位置付けられていることが分かる。
シーモアと一般社会との乖離を考えたとき、やがて「バナナフィッシュにうってつけの日」で起こる悲劇の必然性も、何だか理解できるような気がする。
人生っていうのは、こういう短篇小説の積み重ねみたいなものなんじゃないだろうか。
作品名:大工よ、屋根の梁を高く上げよ
著者:J.D.サリンジャー
訳者:野崎孝
書名:大工よ、屋根の梁を高く上げよ/シーモア-序章-
発行:1970/04/15
出版社:河出書房新社



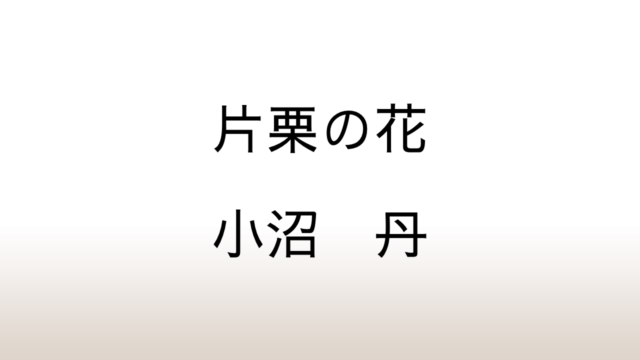
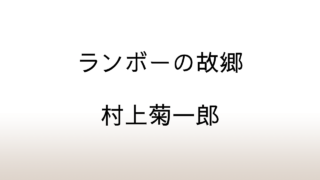

-150x150.jpg)









