「佐渡」は、学習研究社の「芥川賞作家シリーズ」から、昭和39年に刊行された。
本書には全部で13篇の作品が収録されているが、本書書き下ろし作品の「佐渡」を除いた12作品は、既刊の短編集からセレクトされた,自選の選集となっている。
その内訳は「舞踏」「会話」「恋文」は「愛撫」(昭和28年)から、「黒い牧師」「プールサイド情景」は「プールサイド情景」(昭和30年)から、「勝負」「机」「緩徐調」「バングローバーの旅」は「バングローバーの旅」(昭和32年)から、「蟹」「相客」は「静物」(昭和35年)から、「南部の客」は「道」(昭和37年)から、それぞれ選り抜かれた作品であり、庄野潤三の昭和30年代を理解する上で、十分な作品が収録されたベスト・セレクションとなっているが、本書で最も注目しなくてはならないのが、唯一の書き下ろし作品である「佐渡」だろう。
「佐渡」は、ラジオ番組に出演した「私」が、梅干と鰹節と豆腐について話をしたところ、思いがけず、聴者からの手紙を受け取り、「私」はその手紙の差出人が暮らす佐渡を訪れる、という話である。
もっとも、全体の構成は、前半のラジオ番組編と、後半の佐渡編に分かれていて、特に後半の佐渡編は、佐渡に向かうまでの話と佐渡に到着してからの話とで構成されているので、実際に「私」が佐渡に到着したときには、物語の幕が閉じつつあるという印象を受ける。
作品のジャンルとしては、形式的には、佐渡へ旅行した際の紀行文と言えるが、旅行の名前を借りながら、著者(庄野潤三)は「人生とはどういったものか」という人生観を描こうとしていたのではないだろうか。
決して派手な題材ではないけれど、人間としっかりと向き合おうとする作家の誠意を感じた。
「私」が旅をするに至った経過
行ってみて、手紙をくれたお爺さんがに会えればよし、会えなければそれでもいい。とも角、これまで考えたこともなかった佐渡という島と私との間に、幻の橋がかかった。それは、あると思えばある、無いと思えば無い、頼りない橋だけれども、ひとつ、この橋を渡ってみることにしてはどうか。(庄野潤三「佐渡」)
物語の前半は、ラジオ番組に出演した「私」が、「生活の味」というテーマの元に、梅干と鰹節と豆腐について話をする部分がほとんどだが、これは旅行と関係がないのではなく、「私」が佐渡へ旅行することとなったきっかけを描いている部分である。
「佐渡」は、ある意味で紀行小説的な作品だが、紀行そのものを描くというよりは、「私」が旅をするに至った経過までを含めて、というよりも、いっそ、旅行に至る経過に重点を置いて構築されていることが、大きな特徴だろう。
そして、梅干と鰹節と豆腐に関する話の中には、著者の人生観や家族観といったものが、決して大仰ではない形で綴られていて、読者の共感を呼ぶ部分だ。
佐渡旅行は、作家の家族観を描くための器
私は考えてみた。こういう顔の洗い方をする人は、誰からそれを学んだのか。おそらく子供の時分に彼の父親がこんなに音を立てて顔を洗っていたに違いない。(略)この子が大きくなって、親父になると、何時の間にやら、亡くなった父親にそっくりの口のきき方で、頑固なことを言い張るようになっている。ちゃんとそうなっている。(庄野潤三「佐渡」)
佐渡を旅しながら、「私」はいろいろな場面で、家族のことを思い出している。
旅を楽しんでいるというよりも、旅はあたかも昔を回想するための道具立てに過ぎないかのように、「私」は私自身の昔と家族のことを思い出してしまうのだ。
それは、ラジオに出て、梅干と鰹節と豆腐について話をしている時も同じだった。
だから、「佐渡」は紀行小説の面を持ちつつも、実は、家族小説の面をも持った小説である。
佐渡旅行は、作家の家族観を描くための器であるが、作家の家族観を引き出すための素晴らしい器になっている。
そして、佐渡の住人である「浦部怡斎」もまた、作家の人生観を描く上で欠くことのできない、重要な登場人物だった。
書名:佐渡
著者:庄野潤三
発行:1964/11/20
出版社:学習研究社



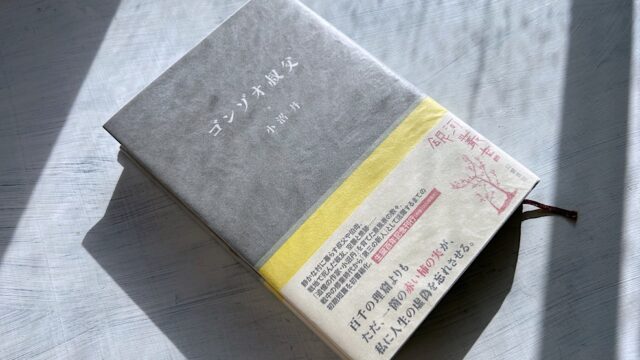


-150x150.jpg)









