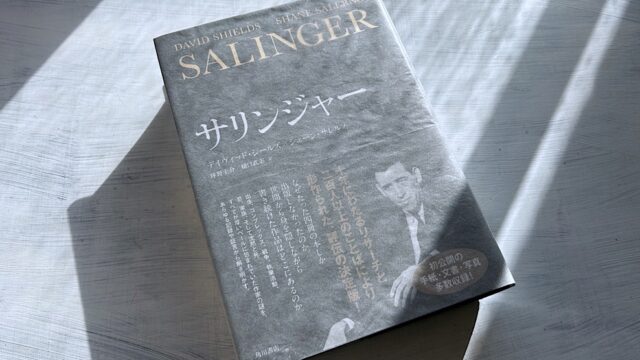夏目漱石の『三四郎』は、若者たちの迷いを描いた物語である。
本作「三四郎」は、1909年(明治42年)5月に春陽堂から刊行された長篇小説である。
この年、著者は42歳だった。
初出は、1908年(明治41年)9月1日から12月29日にかけて、『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』への連載。
なお、『三四郎』の直前まで、朝日新聞では、島崎藤村の自伝的青春小説『春』が連載されていた。
若者たちはなぜ迷うのか
福原麟太郎『夏目漱石』に「三四郎日和」という随筆がある。
あしたは秋分の日である。三四郎の大学の新学年の講義は、このあたりで始まったらしい。小説にそう書いてある。あの小説の季節は秋だ。(略)秋のあたたかな日射しが、すべてのものの上に、まぶしく、ぽかぽかと当っていて、空は青く澄んでいる。そういう日にあうと、今でも、きょうは三四郎日和だ、などという。(福原麟太郎「三四郎日和」)
夏目漱石の『三四郎』が出版されたとき、福原さんは15歳だった。
つまり、これから青春に入るという多感な時期に、リアルタイムで、この小説を読んだということになる。
少年の心を惹いたのは、もちろん、里見美禰子(みねこ)という名の、現代的かつ都会的な一人の女性だっただろう。
三四郎はいたずらに女の顔を眺めて黙っていた。すると女は急に真面目になった。「私そんなに生意気に見えますか」(夏目漱石「三四郎」)
美禰子の魅力にやられたのは、九州の田舎から出てきたばかりの三四郎だけではない。
明治を生きる多くの若者たちの中に、里見美禰子は新しい時代を象徴する女性像として、鮮烈に登場したのだった。
一般に『三四郎』は、主人公(小川三四郎)とヒロイン(里見美禰子)とのラブロマンスとして読まれることが多い。
ともに23歳の若者が、互いに惹かれつつ、最後には一緒になることができない、悲恋の物語である。
結婚が決まったとき、美禰子は三四郎に意味深な言葉をつぶやく。
女はややしばらく三四郎を眺めた後、聞兼るほどの嘆息をかすかに漏らした。やがて細い手を濃い眉の上に加えていった。「われはわが愆(とが)を知る。我が罪は常に我が前にあり」聞き取れない位な声であった。(夏目漱石「三四郎」)
名言の多い『三四郎』の中で、美禰子の漏らした「われはわが愆を知る。我が罪は常に我が前にあり」は、特に有名な一句だ。
もちろん、美禰子は、自分に対する三四郎の思いを知っていたのだろう。
いつか、三四郎が、親友(佐々木与次郎)と、こんな話をしていたことを思い出す。
「──君、女に惚れた事があるか」三四郎は即答が出来なかった。「女はおそろしいものだよ」と与次郎がいった。「恐ろしいものだ、僕も知っている」と三四郎もいった。(夏目漱石「三四郎」)
与次郎には隠れたラブロマンスがあるのだが、三四郎の頭の中にあったのは、里見美禰子のことだった。
サザーンの「Pity’s akin to love」の日本語訳について、与次郎は、こんな警句も吐いている。
与次郎はしばらく考えていたが、「少し無理ですがね、こういうなどうでしょう。可哀想だた惚れたって事よ」「いかん、いかん、下劣の極だ」と先生が忽ち苦い顔をした。(夏目漱石「三四郎」)
女性に対する関心と恐怖が、三四郎の中には共存している。
広田先生や与次郎は、美禰子を「乱暴な女」と呼んだ。
「あの女は落ち付いていて、乱暴だ」と広田がいった。「ええ乱暴です。イプセンの女のような所がある」「イプセンの女は露骨だが、あの女は心(しん)が乱暴だ。尤も乱暴といっても、普通の乱暴とは意味が違うがね」(夏目漱石「三四郎」)
美禰子の「乱暴」には、「生意気」という意味が込められている(いつか美禰子自身が、三四郎に問い質したように)。
それは、新しい時代に登場した新しい女性像に対する、男性たちの危機感だったかもしれない。
「イプセンの人物に似ているのは里見の御嬢さんばかりじゃない。今の一般の女性はみんな似ている。女性ばかりじゃない。苟くも新しい空気に触れた男はみんなイプセンの人物に似た所がある。ただ男も女もイプセンのように自由行動を取らないだけだ」(夏目漱石「三四郎」)
明治になって、日本は急速に西洋化を進めていたが、『三四郎』は、激動の時代に生きる若者たちを描いた物語である。
先生の説によると、こんなに古い燈台が、まだ残っている傍に、偕行社という新式の煉瓦作りが出来た。二つ並べて見ると実に馬鹿げている。けれども誰も気が付かない。平気でいる。これが日本の社会を代表しているんだという。(夏目漱石「三四郎」)
主人公の小川三四郎もまた、そんな時代の変わり目に悩まされつつ学ぶ、一人の青年だった(そして、おそらくはヒロインの里見美禰子も)。
「迷子の英訳を知っていらしって」三四郎は知るとも、知らぬともいい得ぬほどに、この問を予期していなかった。「教えてあげましょうか」「ええ」「迷える子(ストレイ・シープ)──解って?」(夏目漱石「三四郎」)
この後、美禰子は二度「ストレイ・シープ」という言葉を繰り返す(「立ち上がる時、小さな声で、独り言のように、「ストレイ・シープ」と長く引っ張っていった」/「「ストレイ・シープ」と美禰子が口のうちでいった」)。
のみならず、美禰子は、羊を絵を描いた絵葉書を、三四郎に送りつける。
机の上に絵葉書がある。小川を描いて、草をもじゃもじゃ生して、その縁に羊を二匹寝かして、その向う側に大きな男が洋杖(ステッキ)を持って立っている所を写したものである。男の顔が甚だ獰猛に出来ている。全く西洋の絵にある悪魔(デヴィル)を模したもので、念のため、傍にちゃんとデヴィルと仮名が振ってある。表は三四郎の宛名の下に、迷える子と小さく書いたばかりである。(夏目漱石「三四郎」)
この絵葉書が、美禰子に対する三四郎の思いを決定的なものにさせた。
そして、美禰子もまた、この絵葉書が、三四郎の心に与える影響を、きちんと理解していたのだろう。
一般に『三四郎』は、現代的な都会の女性(美禰子)に振り回される三四郎の童貞ぶりにフォーカスされることが多いが、振り回されていたのは、三四郎だけではなかったかもしれない。
注目の中で現代的な女性を演じる美禰子も、男たちの噂に振り回される存在だったし、そもそも、若者たちの導き役として登場する広田先生さえ、新しい時代に翻弄されて生きている(本人が意識するにしろ、意識しないにしろ)。
つまり、『三四郎』に登場する誰もが「ストレイ・シープ」なのであって、そこに、この物語の大きなテーマがある。
新しい時代の行方
三四郎は、自分の知らない新しい世界を見る青年だ。
女はその顔を凝っと眺めていた、が、やがて落付いた調子で、「あなたはよっぽど度胸のない方ですね」といって、にやりと笑った。(夏目漱石「三四郎」)
上京の途中で一緒になった若い女性に請われて、三四郎は、同じ部屋の同じ布団で一夜を明かすが、何もしなかった(つまり、セックスしなかった)三四郎を、翌朝、女は「あなたはよっぽど度胸のない方ですね」と笑う。
この経験は、童貞の三四郎に大きなトラウマとなって残る。
さらに、野々宮さんの部屋で留守番をしているときに、若い女性の自殺事件が起きる。
宵の口ではあるが、場所が場所だけにしんとしている。庭の先で虫の音がする。独りで坐っていると、淋しい秋の初である。その時遠い所で誰か、「ああああ、もう少しの間だ」という声がした。(夏目漱石「三四郎」)
汽車が通り過ぎた後に、三四郎は、若い女性の轢死体を見ることになるが、この経験も、三四郎には、ひどいトラウマとなった。
美しい美禰子と知り合いになるのは、この後のことで、三四郎は、まさに、新しい社会という荒海に揉まれていたと言える。
そして、23歳の三四郎が飛び込んだのは、東京帝国大学を中心とする知識人階級の世界だった。
二、三日前三四郎は美学の教師からグルーズの画を見せてもらった。その時美学の教師が、この人の画いた女の肖像は悉くヴォラプチュアスな表情に富んでいると説明した。ヴォラプチュアス!(夏目漱石「三四郎」)
「ヴォラプチュアス(官能的な・色っぽい)」という言葉から、三四郎は美禰子を連想する。
従来の日本女性とは異なるヒロイン像が、極めて美術的に描かれている。
野々宮さんの妹(よし子)と美禰子は、サッフォーの話で盛り上がる。
よし子は足を芝生の端まで出して、振り向きながら、「絶壁ね」と大袈裟な言葉を使った。「サッフォーでも飛び込みそうな所じゃありませんか」(夏目漱石「三四郎」)
サッフォー(サッポー)は、断崖から飛び降り自殺したレズビアンの詩人として知られている(サリンジャー『大工よ、屋根の梁を高く上げよ』(1955)は、サッフォーの詩をモチーフにした中編小説だった)。

若い女性たちの会話の中に、古代ギリシアの詩人の名前が違和感なく登場するのは、明治のインテリな世界を象徴している場面として読むことができる。
三四郎は、広田先生から『ハイドリオタフィア』という本を借りて読む。
「有難う。書物を返します」「ああ。──読んだの」「読んだけれどもよく解らんです。第一標題が解らんです」「『ハイドリオタフィア』」「何の事ですか」「何の事か僕にも分らない。とにかく希臘(ギリシア)語らしいね」(夏目漱石「三四郎」)
トーマス・ブラウンの『ハイドリオタフィア』は、『壺葬論』の日本語タイトルでも知られるが、この後、広田先生は、珍しく自分の打ち明け話を始める。
「僕がさっき昼寝をしている時、面白い夢を見た。それはね、僕が生涯にたった一遍逢った女に、突然夢の中で再会したという御話だが、その方が、新聞の記事より聞いていても愉快だよ」「ええ。どんな女ですか」「十二、三の奇麗な女だ。顔に黒子がある」三四郎は十二、三と聞いて少し失望した。「何時頃御逢いになったのですか」「二十年ばかり前」三四郎はまた驚いた。(夏目漱石「三四郎」)
広田先生の打ち明け話は、三四郎の失恋と対をなして、この長編小説のクライマックスとなっている。
「先生はそれで……」といったが急に痞えた。「それで?」「それで結婚をなさらないんですか」先生は笑い出した。「それほど浪漫的(ロマンチック)な人間じゃない。僕は君より遥に散文的に出来ている。「しかし、もしその女が来たら御貰いになったでしょう」「そうさね」と一度考えた上で、「貰ったろうね」といった。(夏目漱石「三四郎」)
広田先生は、独身の中年男性である。
先生が独身である理由は、三四郎の失恋の、すぐ隣にあるエピソードだ。
「そのために独身を余儀なくされたというと、僕がその女のために不具にされたと同じ事になる。けれども人間には生まれ付いて、結婚の出来ない不具もあるし、その外色々結婚のしにくい事情を持っている者がある」「そんなに結婚を妨げる事情が世の中に沢山あるでしょうか」(夏目漱石「三四郎」)
美禰子の結婚が決まったことで、三四郎は、心に大きな痛手を負っている。
それだからこそ、広田先生の結婚をしない事情にも踏み込んでしまったのだろう。
「その母がまた病気に罹って、いよいよ息を引き取るという、間際に、自分が死んだら誰某の世話になれという。子供が会った事もない、知りもしない人を指名する。理由を聞くと、母が何とも答えない。強いて聞くと実は誰某が御前の本当の御父(おとっさん)だと微かな声でいった」(夏目漱石「三四郎」)
広田先生は、不倫の子であり、そのために独身を通していたのだ(「その子が結婚に信仰を置かなくなるのは無論だろう」)。
広田先生の話を聞いて、三四郎はシェイクスピアの『ハムレット』を思い出す。
ハムレットがオフェリヤに向って、尼寺へ行け尼寺へ行けという所へ来た時、三四郎はふと広田先生のことを考え出した。──ハムレットのようなものに結婚が出来るか。(夏目漱石「三四郎」)
もしかすると、三四郎は、独身で生きる広田先生に、将来の自分の姿を重ねていたのかもしれない。

本作『三四郎』は、独身男性たちの物語だった。
三四郎と同じように、美禰子に振り回された野々宮さんも、その一人である。
野々宮さんは、招待状を引き千切って床の上に棄てた。やがて先生とともに外の画の評に取り掛る。与次郎だけが三四郎の傍へ来た。「どうだ森の女は」(夏目漱石「三四郎」)
物語は、原口さんの描いた美禰子の肖像画を、四人の男たちが眺めている場面で終わる。
野々宮さんが棄てたものは、美禰子から届いた結婚式の招待状である。
三四郎は「森の女という題が悪い」と吐き捨てて、口の内で「ストレイ・シープ、ストレイ・シープ」と繰り返した。
四人のインテリな男たちも、また、ストレイ・シープだったのだろう。
仕事に迷い、女に迷い、社会に迷う。
それが、明治という新しい時代だったのかもしれない。
かつて美禰子と一所に秋の空を見た事もあった。所は広田先生の二階であった。田端の小川の縁に坐った事もあった。その時も一人ではなかった。迷羊(ストレイ・シープ)。迷羊(ストレイ・シープ)。雲が羊の形をしている。(夏目漱石「三四郎」)
三四郎は、この新しい時代を、これから生きていく青年である。
おそらく、知識人階級の人々は、新しい日本の行方に戸惑っていたのだ。
「しかしこれから日本も段々発展するでしょう」と弁護した。すると、かの男は、すましたもので、「滅びるね」といった。(夏目漱石「三四郎」)
福原麟太郎は、この一節を引いて「日本は40年後に滅びた」と指摘している(太平洋戦争への参戦と敗戦のこと)。
古い時代と新しい時代とが葛藤する中、若者たちは、さらなる新しい時代を生み出すべく苦悩していた。
三四郎の失恋も、また、新しい時代の形成過程を物語るエピソードの一つだったのかもしれない。
書名:三四郎
著者:夏目漱石
発行:1938/05/15
出版社:岩波文庫