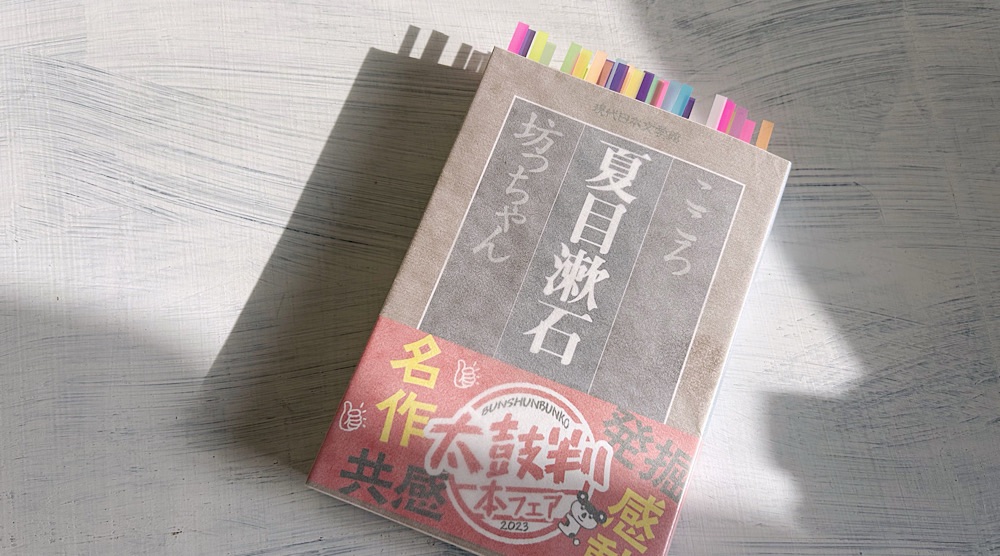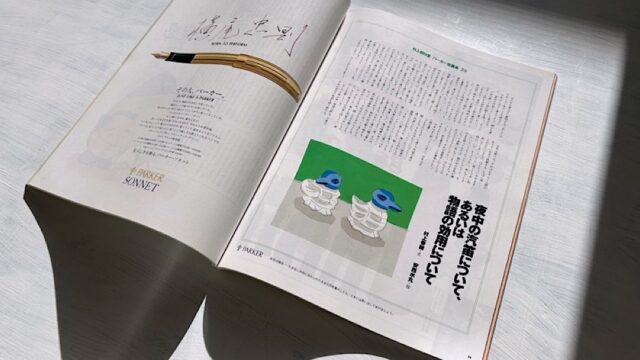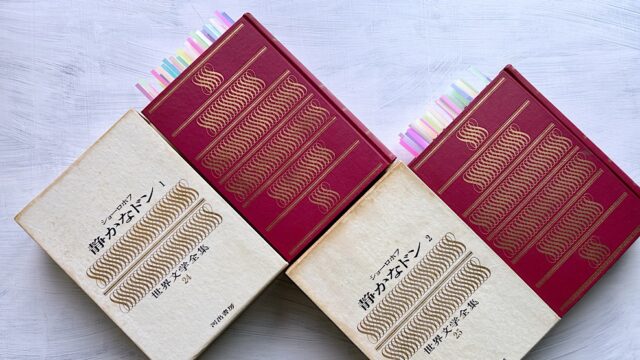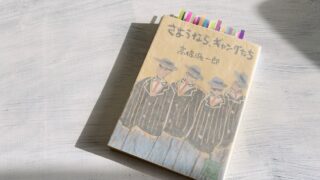夏目漱石「坊っちゃん」読了。
本作「坊っちゃん」は、1907年(明治40年)1月に春陽堂から刊行された作品集『鶉籠(ウズラカゴ)』に収録された短篇小説である。
この年、著者は40歳だった。
初出は、1906年(明治39年)4月『ホトトギス』(第九巻第七号・附録)。
坊っちゃんは敗北のヒーローだった
本作「坊っちゃん」は、東京理科大学を卒業したエリート青年が、四国の高校教師として赴任したものの、教員集団や生徒のいじめに遭い、逆切れして暴力事件を起こした末に、結局は職を辞してしまうという、ひとつの転職物語である。
江戸っ子らしい「べらんめえ」の語り口調は威勢が良く、正義のヒーローが悪者をやっつける勧善懲悪の物語として伝えられているが(一種の英雄伝説)、現実の主人公(坊っちゃん)は決して幸福なヒーローではない。
帰りがけに、君なんでもかんでも三時過ぎまで学校にいさせるのは愚だぜと山嵐に訴えたら、山嵐はそうさアハゝゝゝと笑ったが、あとから真面目になって、君あまり学校の不平を言うと、いかんぜ。言うなら僕だけに話せ、随分妙な人もいるからなと忠告がましいことを言った。(夏目漱石「坊っちゃん」)
まっすぐで正義感の強い主人公(坊っちゃん)に、世の中はあまりにも窮屈で生きにくいところだった。
この「生きにくい世の中」を、主人公は持ち前の根性とパワーでもって強行突破しようとしている。
箆棒(べらぼう)め、先生だって、出来ないのは当り前だ。出来ないのを出来ないというのに不思議があるもんか。そんなものが出来るくらいなら四十円でこんな田舎へくるもんかと控所へ帰って来た。(夏目漱石「坊っちゃん」)
もちろん、世の中は、根性とパワーだけで突破できるほど簡単ではない。
初めて経験する大人社会で、東京生まれのエリート青年は、厳しい試練を与えられる。
翌日なんの気もなく教場へはいると、黒板一杯ぐらいな大きな字で、天麩羅先生とかいてある。おれの顔を見てみんなわあと笑った。おれは馬鹿々々しいから、天麩羅を食っちゃ可笑しいかと聞いた。すると生徒の一人が、しかし四杯は過ぎるぞな、もし、と言った。(夏目漱石「坊っちゃん」)
生徒が愚劣なら、大人たちもやはり愚劣である。
「そのマドンナが不たしかなんですかい」「そのマドンナさんが不たしかなマドンナさんでな、もし」「厄介だね。渾名の付いてる女にゃ昔からろくなものはいませんからね」(夏目漱石「坊っちゃん」)
同僚・吉川先生(うらなり君)の恋人(マドンナ)を寝取ったのは、上司の教頭(赤シャツ)だった。
赤シャツは人事権を発動して、目障りの部下(うらなり君)を遠くの学校へ飛ばしてしまう。
インチキな学校は、もちろん、社会の縮図そのものだ。
食いたい団子の食えないのは情けない。しかし自分の許嫁が他人に心を移したのは、なお情けないだろう。(略)本当に人間ほどあてにならないものはない。あの顔を見ると、どうしたって、そんな不人情なことをしそうには思えないんだが──(夏目漱石「坊っちゃん」)
日常の不満が溜まっているところに、この不倫事件があったものだから、主人公(坊っちゃん)は、いよいよ我慢できない。
人があやまったり詫びたりするのを、真面目に受けて勘弁するのは正直過ぎる馬鹿と言うんだろう。あやまるのも仮りにあやまるので、勘弁するのも仮りに勘弁するのだと思ってれば差し支えない。もし本当にあやまらせる気なら、本当に後悔するまで叩きつけなくてはいけない。(夏目漱石「坊っちゃん」)
主人公は、親友(山嵐)と共謀して、教頭(赤シャツ)と美術教師(野だ)に私的制裁(リンチ)を加える。
「無法で沢山だ」とまたぽかりと撲る。「貴様のような奸物はなぐらなくっちゃ、答えないんだ」とぽかぽかなぐる。おれも同時に野だをさんざんに擲き据えた。(夏目漱石「坊っちゃん」)
暴行事件の主犯たる主人公(坊っちゃん)と山嵐は、懲戒処分を待つ間もなく、逃げるように四国を離れた。
悪者をやっつけたヒーローとしての達成感は、そこにはない。
むしろ、あるのは、敗れて去る者の敗北感だけである。
つまり、主人公(坊っちゃん)は、学校という敵に立ち向かいながら敗れ去る、敗北のヒーローだったのだ。
世の中に正直が勝たないで、ほかに勝つものがあるか、考えてみろ。今夜中に勝てなければ、あした勝つ。あした勝てなければ、あさって勝つ。(夏目漱石「坊っちゃん」)
正義感の強い主人公は、常に孤独だった。
教員集団にも生徒集団にも馴染むことができず、同じように異分子であった同僚(山嵐)としか、本音をもって話し合うことができない。
そこは、根性とパワーだけで強行突破できるほど、生やさしい世界ではなかったのだ。
読者が主人公(坊っちゃん)に共感するのは、物語に現実感がないからである。
人は誰も、「赤シャツ」や「野だ」になることはできても、「坊っちゃん」になることはできない。
仮に「坊っちゃん」になることができたなら、それは、社会的に抹殺されることを意味している。
なることができない存在だからこそ、読者は「坊っちゃん」を爽快な冒険小説として読むことができるのだ。
主人公のやったことは、結局は「ちゃぶ台返し」に過ぎない。
不遇の同僚(うらなり君)の転勤を阻止することもできず、浮気な美女(マドンナ)を取り戻すこともできず、赤シャツ一派に牛耳られた学校を改革することさえもできない。
彼は、ただ暴れて、仕事を辞めて、逃げるように去っていくだけだ。
その後ある人の周旋で街鉄の技手になった。月給は二十五円で、家賃は六円だ。(夏目漱石「坊っちゃん」)
月給四十円をもらっていた大卒エリート青年は、月給二十五円で路面電車(現在の都電)の技術者として再出発する。
本作「坊っちゃん」は、いわば、主人公(坊っちゃん)の転職物語だった。
若き日の挫折体験と再出発に至る経緯が、そこには語られているのである。
インチキな学校に対するアンチテーゼとしての「清」という存在
殺伐とした学校生活を、ハートウォーミングな物語として支えているのは、下女「清(きよ)」の存在である。
母が死んでから清はいよいよおれを可愛がった。時々は小供心になぜあんなに可愛がるのかと不審に思った。つまらない、廃せばいいのにと思った。気の毒だと思った。(夏目漱石「坊っちゃん」)
孤独な主人公が孤独に見えないのは、背景に「清」の存在があったからだ。
それから清はおれがうちでも持って独立したら、一所になる気でいた。どうか置いて下さいと何遍も繰り返して頼んだ。おれも何だかうちが持てるような気がして、うん置いてやると返事だけはしておいた。(夏目漱石「坊っちゃん」)
主人公(坊っちゃん)と老婆(清)との関係は、ひとつの恋愛物語(ラブ・ロマンス)として読むことができる。
作家(庄野潤三)は、英文学者(福原麟太郎)との対談の中で、「清」の存在意義に触れた。
あのばあやさんというのがひじょうに大きな役割を果たしていますね。ばあやさんというものに対する一種の恋愛といえばおかしいですけれども、ばあやさんを慕っている気持、あれが『坊っちゃん』の底を脈々と流れていまして、もしあれがなければ、ただのこっけいな小説、威勢のいい小説ということになったと思いますが、たえずばあやさんが出てきて、かわいそうな環境におかれた主人公に対してどういうわけか知らないけれども、同情してひとりで応援するということから、これは何かやはり人間と人間との世の中での触れ合いの不思議さ、あわれな心細いもの、そういうものを象徴しているようで、それがやはり漱石自身の生い立ちの暗さとか不仕合せとか、そういうものに根ざしているのじゃないかという気がしたんです。(福原麟太郎・庄野潤三「日本の文壇と英文学─夏目漱石をめぐって」/福原麟太郎『夏目漱石』)
清に対する主人公(坊っちゃん)の信頼は、ある意味で、宗教的な性格さえ帯びている(あるいは、それを「信仰」とでも呼ぶべきような)。
清はおれの事を欲がなくって、真直な気性だと云って、ほめるが、ほめられるおれよりも、ほめる本人の方が立派な人間だ。何だか清に逢いたくなった。(夏目漱石「坊っちゃん」)
二人をつないでいるのは、打算のない無垢の愛だ。
この物語の中で、清は、打算だらけのインチキな学校に対するアンチテーゼとしての役割を果たしている。
つまり、主人公(坊っちゃん)を中心として、「赤シャツ」と「清」という対立構造が、この作品のバランスを保っているということだ。
赤シャツがホホホホと笑ったのは、おれの単純なのを笑ったのだ。単純や真率が笑われる世の中じゃ仕様がない。清はこんな時に決して笑った事はない。大いに感心して聞いたもんだ。清の方が赤シャツよりよっぽど上等だ。(夏目漱石「坊っちゃん」)
もちろん、まっすぐな「清方式」だけで、世の中を生きていくことは難しい。
インチキな社会を経験したからこそ、主人公は「清」の持っているイノセントな価値を再認識することができたのだ。
おれには到底やり切れない。それを思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない身分もない婆さんだが、人間としてはすこぶる尊い。今まではあんなに世話になって別段ありがたいとも思わなかったが、こうして、一人で遠国へ来てみると、始めてあの親切がわかる。(夏目漱石「坊っちゃん」)
本作『坊っちゃん』は、主人公の清に対する愛情を再評価するための物語だったとして読むこともできる。
そういう意味で、坊っちゃんと清との心の交流は、ひとつのラブ・ロマンスの構図をなしていると言っていい。
宿のお婆さんが「主人公に嫁あり」と誤解するのも当たり前だ。
「しかし先生はもう、お嫁がおありなさるに極きまっとらい。私はちゃんと、もう、睨ねらんどるぞなもし」「へえ、活眼だね。どうして、睨らんどるんですか」「どうしててて。東京から便りはないか、便りはないかてて、毎日便りを待ち焦がれておいでるじゃないかなもし」(夏目漱石「坊っちゃん」)
ここに、主人公(坊っちゃん)の強さがある。
主人公の正義は、愛する清に裏打ちされた正義だったのだ。
どうしても早く東京へ帰って清といっしょになるに限る。こんな田舎に居るのは堕落しに来ているようなものだ。新聞配達をしたって、ここまで堕落するよりはましだ。(夏目漱石「坊っちゃん」)
冒険の旅に出たヒーローが、故郷で自分の帰りを待っている恋人の愛に気付いて、故郷へ戻るという構図が、この物語にはある。
まして、主人公(坊っちゃん)は、戦いに敗れて帰ってくる悲劇のヒーローである。
ヒーローの傷ついた心を慰めるのは、ヒロイン以外にない。
清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが気の毒な事に今年の二月肺炎に罹って死んでしまった。死ぬ前日おれを呼んで坊っちゃん後生だから清が死んだら、坊っちゃんのお寺へ埋うめて下さい。お墓のなかで坊っちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと云った。だから清の墓は小日向の養源寺にある。(夏目漱石「坊っちゃん」)
主人公(坊っちゃん)とヒロイン(清)とは、お互いに支え合う存在だった。
裏切ることを知らない二人の信頼関係は、学校に象徴される「不確かな世の中」を、真っ向から否定するものでもある。
あるいは、それは「幻想」だったのだろうか。
しかし、そのような「幻想」を信じているからこそ、我々は、この「不確かな世の中」を生きていくことができるのではないだろうか。
本作「坊っちゃん」の真の主人公は、もしかすると、天使のような「清」だったのかもしれない。
作品名:坊っちゃん
著者:夏目漱石
書名:こころ 坊っちゃん
発行:1996/03/10
出版社:文春文庫