川本三郎「村上春樹論集成」読了。
著者の川本三郎さんは1944年(昭和19年)生まれで、1949年(昭和24年)生まれの村上春樹より5歳ほど年上ではあるが、ほぼ同世代と言っていい。
川本さんは、村上春樹の経営するジャズ喫茶「ピーター・キャット」を訪れたのは、店が中央線の国分寺駅南口のビルの地下にあった1970年代半ば頃のことで、「ユリイカ」編集長の小野好恵さんに案内されたのが最初だった。
やがて、店は千駄ヶ谷のビルの2階へと移り、大きな窓のある明るいジャズ喫茶へと変身した後、ペーパーバックばかり読んでいた無口なマスターは、1979年(昭和54年)、「風の歌を聴け」という小説で群像新人賞を受賞した。
村上春樹のデビュー作について、川本さんは「素敵に面白かった」「朝起きたてに洒落たうぇすと・コーストふうのジャズをきいたみたいに気分がよかった」「夏のまっさかり、スタン・ゲッツやゲイリー・バートンでも聞きながらビールのびんをシュッと一本抜きたい気分だ」と絶賛している。
カート・ボネガットの影響が色濃く感じられる作風に、ボネガット・ファンの一人でもあった川本さんは、「同じようなボネガット育ちがいるのだなあ」と、強く共感したらしい。
次作『1973年のピンボール』(1980年)も、川本さんは「主人公たちの繰り返される単調な翻訳という、まったく生活臭のない生活ぶりに魅かれてしまってこの小説を読んだ」「そういう抽象的な生活が実に魅力的なものに思えてならない」と肯定的に評した。
さらに、次の『羊をめぐる冒険』についても、「村上春樹の『羊をめぐる冒険』に感動した」「最近読んだ小説のなかではいちばん好きなものだ」と大絶賛しているが、殊に「俺は俺の弱さが好きなんだよ」という鼠の台詞は、70年安保闘争での挫折体験を共有する世代として、非常に激しい共感を寄せている。
以降、川本さんの中で「俺は俺の弱さが好きなんだよ」という言葉は、村上春樹を論ずるときに繰り返し引用される、象徴的なフレーズとなった。
物語の主題となっている「羊」について、川本さんは、1960年代末期から70年代初頭にかけて、若い世代から絶対的な支持を受けた「革命思想」「自己破壊」という「観念」ではないかと考察している。
行き場をなくした日本の革命思想が、連合赤軍の中に封印されて山中で消えていったように、「羊」は北海道の山中で鼠の生命とともに消えていく。
その「弱さ」こそが、あの時代を経験した人々だけが共有しうる世代的共感ということなのだろうか。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)を、川本さんは、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』になぞらえながら、「村上春樹だけに描ける現代の”個室”に読者を誘ってくれる淡く、感動的な作品である」と評した。
この頃、川本さんにとって村上春樹は、50年代のサリンジャーや60年代のヴォネガット、現代のジョン・アーヴィングなどとと並ぶ「カルト・ライター」として認識されていたらしい。
カルト・ライターとは、上の世代の評価は低くても、同時代の、同世代の、若い世代の読者には圧倒的に支持される作家のことで、カルトには「信仰」とか「熱狂」といった意味があるのだけれど、カルト・ライターであり、マイナー・ポエットであることにこそ、川本さんは村上春樹の存在意義を見出していたのかもしれない。
『ノルウェイの森』(1987年)が登場したとき、川本さんは「これまでともすれば風俗的興味でのみ語られることの多かった六十年代が、ようやくそこで生きてきた当の世代によって内在的に語られるようになってきたのはいいことだと思う」と綴った。
あまりに1960年代への回帰志向が強すぎたために、川本さんの書評も、作品以上に1960年代という時代へと向きすぎている(つまり、それが『ノルウェイの森』という小説だった)。
『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)の発表後、川本さんは「この空っぽの世界のなかで」という村上春樹論の中で、1980年代の(つまりは、デビューから現在までの)村上春樹を総括している。
それは、少なくとも、この時点までの村上春樹作品は、ひとつの文脈の中で語ることができたということなのだろう(今にして振り返ってみると、ということになるのだけれど)。
「村上春樹は空虚と闘っている作家である」「村上春樹の作品が読者を感動させるのはその表面的な言葉の戯れ、都市的モノの羅列・カタログ作り、気の利いたアフォリズムのためではなく彼が頑固なまでにいまここにあることの空しさを語り続けているからだ」と、川本さんは書いている。
「みんな、なるべく息をするんじゃない。残りの空気が少ないんだ」という「ニューヨーク炭鉱の悲劇」という短編小説の最後の一行に象徴されるような時代観こそ、1960年代を生きてきた者たちにだけ伝わるメッセージだったのかもしれない。
『ねじまき鳥クロニクル』(1994-1995年)以降、川本さんの村上春樹評は、方向性を見失っていくが、実は、川本さんが方向性を見失ったというよりも、村上春樹の進む方向性が変わっただけだった。
『アンダーグラウンド』(1997年)には、「なぜ突然、村上さんが「社会派」になったのかという違和感がのびりついて離れなかった」と、困惑ぶりを隠さない。
『海辺のカフカ』(2002年)が出たときにも、「個々の話は面白いのだが全体につながっていかない」「この小説には、中心になる核がない」と戸惑いが先行し、かつて得られたような共感は、二度とは戻ってこなかった。
かつて、1960年代を生きた人たちが、「自己破壊」という「観念」を失ったのと同じような喪失体験を、1980年代の村上春樹を愛した人たちも経験したと言えるだろうか。
書名:村上春樹論集成
著者:川本三郎
発行:2006/5/27
出版社:若草書房





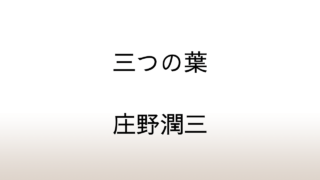
-150x150.jpg)









