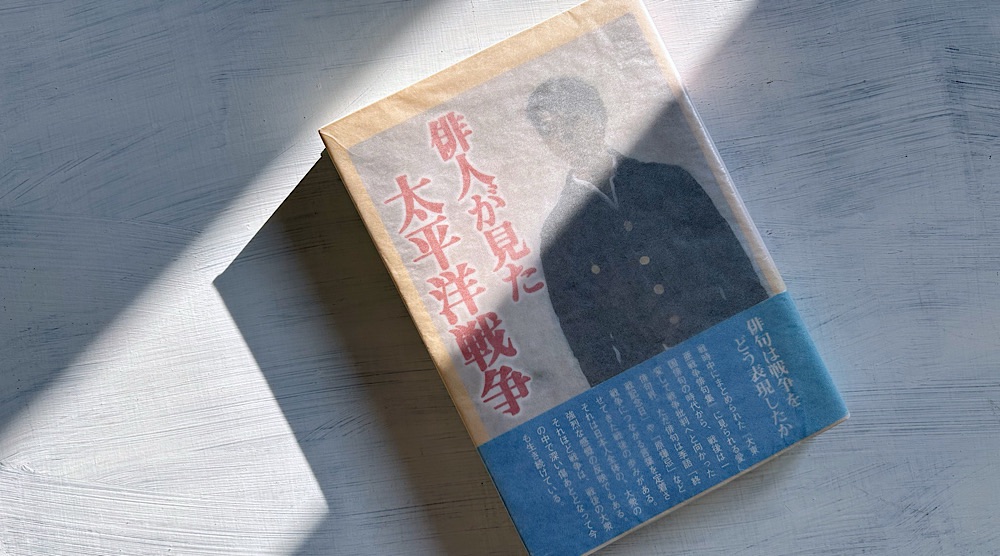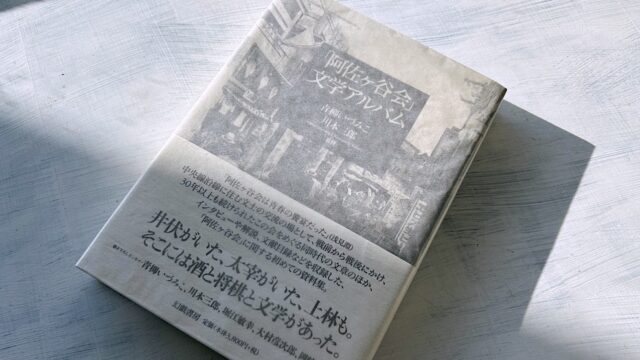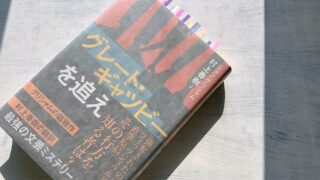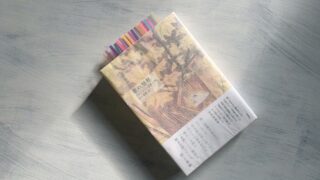『俳人が見た太平洋戦争』読了。
本作『俳人が見た太平洋戦争』は、2003年(平成15年)8月に北溟社から刊行されたルポルタージュである。
構成(目次)は次のとおり。
・誰かものいへ-日本人は戦争をどう俳句で表現したか(大牧広)
・戦争を詠んだ名句(成井恵子)
・広島からヒロシマへ-中国新聞に見る戦時下の俳句(吉原文音)
・【新資料】大東亜戦争俳句集(河野南畦編)
・俳句と原爆(河野南畦)
・「天皇俳句」の詠法(谷山花猿)
・まぼろしの<京大俳句>終刊号の周辺-俳壇特高弾圧篇(杉本雷造)
・私の戦争と平和(氷室樹)
・あの日を追う(射場柏葉)
・現代俳人が詠んだ「戦争」の俳句
・私の戦争体験
・太平洋戦争下の暮らしの年表(編集部編)
戦意高揚を詠む
戦時中の俳句は、戦意高揚のためのツールだった。
俳壇の中核を担う俳人の多くが、日本国民の戦意を高揚するための俳句を詠んでいる。
戦告ぐ船は飛雪をひた進む 橋本多佳子
開戦を詠んだ橋本多佳子の作品は「ひた進む」の一語に、戦争に臨む国民の覚悟が表現されている。
1941年(昭和16年)12月8日、米英との戦争に勝利を信じた国民も少なくなかった。
そのためか、戦時中というのに浮かれた句も多い。
戦勝の春やローマに遊びたし 山口青邨
開戦で明けた1942年(昭和17年)の正月、日本は「戦勝の春」で盛り上がっていた。
戦勝の春を飾って、無敵皇軍が綽々の余裕を誇る大東亜戦争下、初の陸軍始観兵式は、1月8日かしこくも大元帥陛下の親臨を仰ぎ奉り、代々木練兵場においていと厳かに挙行されました。(1942年「NHKニュース」より)
「ローマに遊びたし」のローマは、もちろん、ムッソリーニ政権下にある同盟国イタリアの首都だ。
呑気と言えば呑気だが、開戦当時、多くの日本国民は、アメリカやイギリスと戦争をして勝つことができると、本気で信じていたらしい。
冬霧にぬれてぞ祈る勝たせたまへ 水原秋桜子
「ぬれてぞ祈る勝たせたまへ」には、(神がかり的とも言うべき)日本人らしい精神性が現れている。
日本人の戦争は、いつだって精神的な戦争だったのだ。
秋桜子には「シンガポール陥ちぬ春雪の敷く夜なり」という、シンガポール陥落を祝福する作品もある。
国の秋測り知られぬ力あり 高浜虚子
「測り知られぬ力あり」も、いかにも根性論的な作品である。
米英には物量では勝てなくても、気持ちの上では負けていなかったということか。
蚤殺すにも渾身の力以て 山口誓子
当時の日本人にとって、大国・米英は「蚤」だった。
敗戦を経た現代から考えると、ただただ滑稽でしかないが、当時は、本気だったのだろう。
いくさして富士美しき国の春 富安風生
富安風生の「いくさして」は、いかにも薄っぺらで、安物の額縁に入った絵画を思わせる。
しかし、このように分かりやすい作品が、当時の人々の心には響いたのかもしれない。
日本人の「大和魂」は、「富士」や「桜」に託して詠われることが多かった。
変わったところでは、神話を引用した句がある。
ポケットに日本書紀あり紀元節 上野青逸
日本書紀は、日本の伝統を理論武装する上で、重要なアイテムだったのだろう。
日本は神国なれや朝桜 小野房子
「日本は神国なれや」になると、これは俳句ではなくて、単なるスローガンである。
門松やわが日本は神の国 鈴木松月
「わが日本は神の国」も同様で、このような戦意高揚のスローガン的な俳句が、戦時中は大量生産されていたのだ(ある意味で、これはこれで興味深いが)。
ただし、「現人神」である天皇を詠むことは許されなかった。
太平洋戦争当時、天皇陛下を俳句に詠むことは、およそ庶民にとって畏れ多い行為だったのだ。
天よりの玉の御声ぞ冬霞 小野蕪子
「天よりの玉の御声」とは、すなわち、天皇陛下の御言葉(玉音)を意味する。
天皇陛下を句に詠むための技巧が、そこにあったと言うべきか。
小野蕪子は、戦意を昂揚するための作品を多く残した。
それだけではなく、およそ戦争に後ろ向きな俳人たちを次々と告発していった。
「私は和歌や俳句の小詩形のかげに隠れている変な分子がありはしないかということを恐れています。俳句の雑誌をみてすらドウかと思ふ議論や作品に接します。これら不純分子を征伐するのもいいと思います」谷山花猿「『天皇俳句』の詠法」)
戦争にネガティブな姿勢を示す俳人たちへの政治的な弾圧は、このような戦意高揚の陰で進められていった。
厭戦と反戦
俳人に対する政治的弾圧として有名な事件に「京大俳句事件」(新興俳句弾圧事件)がある。
当時の俳壇は、大政翼賛会の下部組織である「日本俳句作家協会」が中心となっていた。
俳壇ではこの年の十二月、同じ国策協力の趣旨の下に、高浜虚子、富安風生、渡辺水巴、小野蕪子、水原秋桜子、荻原井泉水、中塚一碧楼らを発起人とし、虚子を会長とする「日本俳句作家協会」が結成し、愈々 ”人間” より ”国家” が重視され、”人間” は ”国” の奉仕としてその存在が認められる空虚な ”愛国吟詠” 時代に突入してゆくのであった。(杉本雷造「まぼろしの<京大俳句>終刊号の周辺-俳壇特高弾圧篇」)
国策にそぐわない俳句を作る人々は、当然、国家による弾圧の対象となる。
「京大俳句事件」では、多くの俳人たちが、特高警察によって検挙され、厳しいペナルティを受けた。
それは、必ずしも政治的思想とは関係のない次元だった。
例えば「無季俳句は伝統否定であるが故に共産主義である」のような論理で、多くの俳人たちが告発されていったのだ。
反戦の態度を示すことができない人々は、沈黙をもって抗議するしかなかった。
加藤楸邨の戦前の作品に、有名な句がある。
蟇誰かものいへ声かぎり 加藤楸邨
それは、既に、自由に発言することが難しくなってきた時代だったことを示している。
俳人は、俳句というツールを巧みに操って、時代と向き合っていった。
戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺白泉
廊下の奥には、立入禁止の部屋がある。
戦争は、もはや、戦場だけではなく、生活の中にあったのだ。
この句では、戦争というものの核心は、戦場などではなく、都会にある立派な建物のなか、市民の生活の場の近くにあることを示唆している。(略)軍の組織が拡大し、自分の所属している建物だけでは不足していたことが、当時の実態であった。(大牧広「誰かものいへ-日本人は戦争をどう俳句で表現したか」)
軍人が詠んだ俳句には、もっとストレートに戦争がある。
寒夜二時重傷兵の目あいてをる 長谷川素逝
戦争を詠むということは、つまり、死を詠むということでもあった(特に、太平洋戦争末期においては)。
勿忘草わかものの墓標ばかりなり 石田波郷
石田波郷「勿忘草」には、「松山帰省」の前書きがある。
若者の墓標が林のようにある。知っている名前もあるにちがいない。そのほとんどが、出征し戦死した男性の変り果てた姿である。(大牧広「誰かものいへ-日本人は戦争をどう俳句で表現したか」)
銃後の生活にも俳句があった。
冷めた味噌汁に今朝も最後の便りをよむ 波止影夫
戦争の俳句とは、感情を詠むものではない。
戦争そのものを詠むものだったからだ。
生活の中に戦争があるということの重たさを、現代の我々は読むことができる。
そして、戦争は、戦後になってまでも続いた。
決死隊となりしが生きて米を磨ぐ 秋元不死男
「決死隊」とは、神風特攻隊で知られる特別攻撃隊のことを指す。
自分の命を捨てる覚悟をもって、入隊したのであったが、神の加護によって命を失うことなく終戦を向かえた。そして、戦後の日常の生活を営みつつある。(大牧広「誰かものいへ-日本人は戦争をどう俳句で表現したか」)
生きて米を磨いでいることの違和感。
死と向き合った戦場と戦後の日常という二つの世界の距離が、どれほど遠いものだったか。
焼け跡の都会を生きる人々は、むしろ、終戦直後にこそ戦争を感じていたかもしれない。
焼跡に遺る三和土や手毬つく 中村草田男
焼け跡の三和土は、焦土となった日本そのものを象徴するものとして読んでいい。
無心に手毬をつく少女の姿に、生きていくことの決意がある。
いくたびか哭きて炎天さめゆけり 山口誓子
かつて、米英を「蚤」と詠んだ山口誓子の自宅も、1945年(昭和20年)6月の大阪空襲で焼けた。
炎天の焦土に慟哭した国民は少なくなかったはずだ。
忍従の唇に汗しほからし 富安風生
敗戦を耐え忍ぶ富安風生「忍従の」は、「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」と読んだ昭和天皇の「終戦の詔書」 を連想させる。
加藤楸邨は、一本の鶏頭に終戦の日の日本を詠んだ。
一本の鶏頭燃えて戦終る 加藤楸邨
加藤楸邨も、1945年(昭和20年)5月の東京空襲で罹災した。
「病臥中の弟を背負い、妻子と共に火中を彷徨した」とある(射場柏葉「あの日を追う」)。
1945年(昭和20年)5月の東京空襲で芝三田の自宅を焼かれた久保田万太郎は、戦後の一時期、鎌倉文士となった。
何もかもあっけらかんと西日中 久保田万太郎
「何もかもあっけらかんと」に、すべてを失った日本の脱力感を感じる。
なんだったんだ、この戦争というやつは? とでも、言いたかったのかもしれない。
カチカチと義足の歩幅八・一五 秋元不死男
「義足の歩幅八・一五」の「はち・いち・ご」というリズムが、義足の歩幅を巧みに表している。
8月15日の迎え方には、様々な思いがあったということだろう。
敵というもの今は無し秋の月 高浜虚子
敗戦の秋の虚無感を「敵というもの今は無し」から読むことができる。
娘星野立子の句日記には、「父は終戦の日、ラジオの前に端座して、陛下の御言葉を深く頷きながら聞いていた」と記されている。(射場柏葉「あの日を追う」)
終戦の年、72歳だった高浜虚子には「秋蝉も泣き蓑虫も泣くのみぞ」の句もある(一億号泣を詠んだ作品)。
庶民にとって「戦後」とは、戦争の終わりではなかったかもしれない。
葬も了へてなほ靴音を待つ秋夜 飯田蛇笏
蛇笏の長男・三男の戦死は、戦後の1947年(昭和22年)になって伝えられたという。
次男は既に昭和十八年に病没。四男龍太は否応なしに飯田家を継ぐべく、土着定住の心を固めねばならなかった。それはやがて長兄の二人の遺児と嫂の面倒を見ることとなった。(射場柏葉「あの日を追う」)
被災地・広島を詠んだ作品にも名句が多い。
広島や卵食う時口ひらく 西東三鬼
西東三鬼の「広島や」には、季語がない故の不気味さがある。
ゆで卵は「人間の皮膚がズルリと向けた街」を象徴するものだ。
原爆の投下された広島、一年前には、自分が腰かけている石は火になり、大量の人が死に、生き残った者は、この石の前をぞろりぞろり、腕から皮膚をたれさげて、火傷の身をひきずっていたのだ。いま、そこで自分は、生きて茹で卵を食っている。皮を剥がした卵の感覚が、原爆にさらされた人間の群につながる。(大牧広「誰かものいへ-日本人は戦争をどう俳句で表現したか」)
わずか十七文字の言葉が伝えるものの大きさが、そこにはある。
本書を読んで思うことは、戦争というものは、やはり一面からだけでは語ることができない、ということだ。
「あとがき」に、中曽根康弘首相の俳句が紹介されている。
私はかつて元総理大臣の中曽根康弘氏の句集を編集していて、氏の戦地での体験を詠んだ句「戦友(とも)を焼く鉄板かつぐ夏の浜」に感銘を受けた。(「俳人が見た太平洋戦争」あとがき)
「青年将校」と呼ばれ、強固な親米政権を作りあげた政治家の原点が、そこになかっただろうか。
本書『俳人が見た太平洋戦争』は、多くの示唆に富んだ文芸ルポルタージュである。
もしも、足りないものがあるとしたら、それは、戦争で死んでいった若者たちの俳句(つまり、辞世の句)と、戦災孤児を含む罹災者を詠んだ俳句である。
私は戦争末期から戦後へストリートチルドレンだった。喧嘩、ウソつき、カッパライの毎日を生きた。(中野一灯「焼け跡族は強し」)
巻末の「私の戦争体験」には、かつて戦災孤児だった人の体験談も収録されている。
もちろん、罹災者に俳句を詠む精神的な余裕など、どこにもなかっただろう。
生き延びてこその文芸、命あってこその俳句である。
もしかすると、それは、見えないところにこそ戦争の真実があった、ということを意味しているのかもしれない。
書名:俳人が見た太平洋戦争
編者:北溟者編集部
発行:2003/08/15
出版社:北溟社