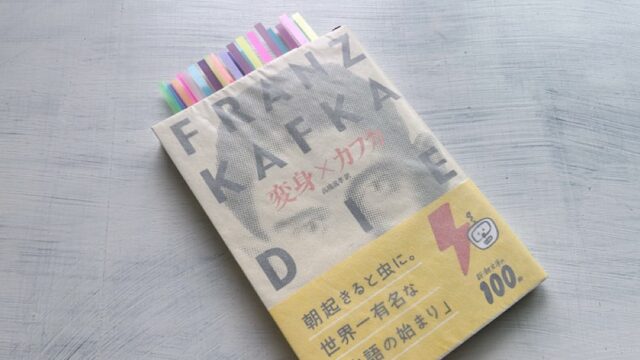松原惇子『クロワッサン症候群』読了。
本作『クロワッサン症候群』は、1988年(昭和63年)11月に文藝春秋から刊行された。
この年、著者は41歳だった。
バブル時代の『ハートに火をつけて』
1989年(平成元年)4月13日から6月29日までフジテレビ系(木曜劇場枠)で放送された、浅野ゆう子主演のトレンディドラマ『ハートに火をつけて』は、「クロワッサン症候群」の女たちを描いたドラマでもあった。
「クロワッサン症候群」とは、若い頃は「自立した女」を目指して、結婚なんかせずに一人で生きていこうと考えていたものの、30歳前後になって「やはり結婚しなくてはならない」と焦り始める女性たちのことを意味する言葉だ。
1988年(昭和63年)に本作『クロワッサン症候群』が出版されたことで大きな話題となり、流行語にもなった。
田代春(浅野ゆう子)、浅井悦子(田中美佐子)、本城亜矢(かとうかずこ)の3人は、いずれも30歳で、仕事にも情熱を燃やすキャリアウーマンだが、悦子と亜矢の二人は「結婚したい」と焦り始めている。
結婚願望を持つ彼女たちは、内田恵(鈴木保奈美)の結婚(と離婚)をきっかけに知り合った島田祐二(柳葉敏郎)や矢沢国太郎(布施博)、西尾信行(三浦洋一)の男性3人と恋愛関係を展開させていく。
いわゆる『男女7人夏物語』型のトレンディドラマだ。
もともと仕事仲間で、男女の関係を意識したことのなかった春と祐二は、春が西尾から、祐二が亜矢から猛烈なアタックを受けたことで、互いに男女であることを意識し始める。
「男女の間で友情は成立するか?」をテーマにしたドラマだったが、彼らの恋愛劇の下敷きとなっているのが「クロワッサン症候群」だった。
亜矢とセックスしたことで、祐二は春を好きだという自分の本心に気付き、祐二に告白されたことで、春も祐二を好きだったということに気付く(つまり、ハートに火がついた)。
西尾と祐二の間で揺れ動く春の涙は、恋愛がそのまま結婚へと結びつく大人の恋愛を意味している。
軽はずみに結婚して新婚旅行中に離婚を決意する恵(鈴木保奈美)の若い恋愛とは、重みが異なっているのだ。
おそらく、30歳という年齢は、人生の転換期にあったのだろう。
1989年(平成元年)の平均結婚年齢(初婚)は、男性28.5歳、女性25.8歳で、女性の結婚適齢期は26歳前後だったことがわかる。
25歳を過ぎると「売れ残りのクリスマスケーキ」と言われた時代だった(クリスマスケーキは12月24日までが売れ時なので)。
最新(2023年)データでは、男性31.1歳、女性29.7歳と、平均結婚年齢(初婚)は依然として上昇傾向にある。
平成初期の時代、「女性の時代」と言われながらも結婚は、女性にとってやはり大きなテーマだった。
毎回、春(浅野ゆう子)が自室で独り言を言う場面があって、カメラ目線で「悪かったわね、30歳で」と怖い顔をした。
秘蔵のカラオケセットで、夜中に独りでカラオケを唄うという設定も、一人暮らしの寂しさを象徴している(1970年代のニューミュージック系の音楽が多かった)。
最後に春が秘密のカラオケを祐二に聴かせる場面は、二人の友情を決定づける象徴的な場面となっていた。
バブル時代のトレンディドラマだから、ドロドロの三角関係が絡み合っても、あくまで爽やかに描かれているが、「30歳の独身女性」という言葉は、彼女たちの心理に極めて重たい影響を与えている(特に後半はシリアスな展開が続く)。
祐二は既に亜矢と肉体関係まであったし、春は西尾と婚約していた。
その二人が、互いのパートナーを裏切ってまで、一緒になることができるのか(『男女7人秋物語』では、二人とも互いのパートナーを裏切って元のさやに納まる)。
と言って、心の中で互いを想い続けたまま、別の人と一緒になってもいいのか。
結局、二人は恋愛関係よりも友情を選ぶことになるのだが、彼らがその後どうなったのかという答えは明かされない。
人生の結論は、30歳くらいで出すことができるようなものではないからだ。
仮に、彼らが友情を優先して別の異性と結婚した場合、夏目漱石『それから』(1910)のような問題が、将来的に出てくる可能性はある。
『それから』は、好きだった女性を友人に譲っておきながら、後に自分の元へ取り戻してしまう男の物語だが、別の男性の妻帯者となった女性を奪い返す行為は、倫理的にも許されない。
結局、彼ら夫婦は社会から追放されて、やがて『門』(1911)に描かれる夫婦として再登場する。

つまり、トレンディドラマ『ハートに火をつけて』に描かれている男女の愛憎劇は、明治時代から続く伝統的なテーマだったということだろう。
『ハートに火をつけて』は、浅野温子・浅野ゆう子W主演『抱きしめたい!』(1988)に続くバブリーなトレンディドラマだったが、『抱きしめたい!』ほどの話題作とはならなかった。

『クロワッサン症候群』のブームに乗った脚本だったが、「焦る30歳独身女」という設定が、あまりにもリアル過ぎたかもしれない。
「新しい女の生き方」を雑誌に学んだ女たち
『クロワッサン症候群』の「クロワッサン」とは、雑誌『クロワッサン』のこと。
一九七七年四月、クロワッサンは平凡出版社(現在のマガジンハウス)から創刊された。(略)クロワッサンの創刊を皮切りに続々と女性誌が創刊された。五月、集英社より『MORE』創刊、婦人生活社より『ノラ』創刊、そして主婦と生活社より『アルル』創刊。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
第一次女性誌創刊ブームは、団塊の世代によって構成された「ニューファミリー」をターゲットに盛り上がったが、旧態依然の誌面が支持を受けることはなく、各誌とも苦戦を強いられた。
その中で、エリカ・ジョングの自伝的小説『飛ぶのが怖い』(1976)が日本でもベストセラーとなり、「翔んでる女」が流行語となる。
「女性の自立」に注目した『クロワッサン』は、1978年(昭和53年)8月「結婚しない女」の特集を組んだ。
「結婚した女はみじめか離婚しているわ」「16年間、少なくとも夫と2千回セックスしたわ。私は名門出の高級娼婦にすぎなかった」<クロワッサン 七八年八月一〇号>(松原惇子「クロワッサン症候群」)
ライバル誌『MORE』も、1978年(昭和53年)5月「女のターニングポイント」を企画、自立した女たちの生き方が、女性誌の大きなテーマとなっていく。
一九七〇年代後半から、八〇年前半にかけての、我が国の女性誌がうちあげた、シングル讃歌は、相当強力なものだった。その中核をなしたのが、女性なら一度は手にしたと思われる『クロワッサン』である。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
『クロワッサン』と『MORE』の成功に続けとばかりに、1980年(昭和55年)、再び女性誌創刊ラッシュが訪れた。
一九八〇年四月に婦人画報社からファッションを中心とした女性誌『25ans(ヴァンサンカン)』が創刊。五月、アメリカのハースト・マガジン社の発行する女性誌『コスモポリタン』と提携した『コスモポリタン日本版』が集英社より創刊。講談社から『ミス・ヒーロー』、文化出版局から「ツディ」、いずれも二十代の女性に焦点をあてた生活情報誌である。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
どの雑誌もターゲットは、二十代のオシャレなシングルウーマンだった。
各女性誌は、「自立する女」「結婚しない女」をテーマに快進撃を続ける。
1980年(昭和55年)は「新しい女の生き方」が華開いた、メモリアルな年だったと言っていい。
そして、この時代に結婚適齢期の20代だった若い女性たちが、後に「クロワッサン症候群」と呼ばれることになる。
クロワッサンが当時女たちに与えた影響力は、はかりしれないものがあった。その女性誌の影響をモロにうけて、未だに独身を続けている女たちを、私は『クロワッサン症候群』と名づけた。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
1978年(昭和53年)から1981年(昭和56年)まで、女性誌はこぞって「新しい女の生き方」を発信した。
女性誌の影響を受けた若い女性たちは、「自立した女」であることを意識し、「結婚しない女」として生きていくことを決意する。
もはや、女が三十すぎて独身でいることは、恥ずかしくも卑下することでもない時代なのである。(略)彼女たちは、結婚できないのではなく、結婚していないだけのこと。キャリアを持ち、オシャレをし、海外旅行に行き、自由を謳歌している。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
しかし、1980年(昭和55年)前後の「自立した女性」ブームから7~8年が経過して、時代は改めて変わりつつあった。
「自立した女性」は、既に新しい時代のテーマではなかったのだ。
そう。一九八八年の今、シングルは一見、市民権を獲得したかのように見える。しかし、本当にそうだろうか?(松原惇子「クロワッサン症候群」)
1980年代後半、著者は、適齢期に結婚しなかったことを後悔する、多くの女性たちへ取材することになる。
その集大成が、本作『クロワッサン症候群』だった。
本来なら、結婚してふつうの生活をしているはずの女たちが、雑誌によってあおられ、仕事をもつことがステキに見え、その結果、三十すぎても独身生活を余儀なくされているという、なしくずし独身が都会に案外多いのではないだろうか。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
1989年(平成元年)のトレンディドラマ『ハートに火をつけて』が描いているものは、まさしく、この「クロワッサン症候群」の女性たちである。
もちろん、本書には、現代の価値観とは相容れない指摘も多い。
「結婚してふつうの生活をしているはず」とあるのは、「女性の幸せは結婚である」という旧い価値観に基づくものだし、そもそも「結婚=専業主婦」という発想も、現代には通用しない論理展開だ。
1986年(昭和63年)に男女雇用機会均等法が施行された後も、既婚女性が働き続けるという発想は、まだ稀だった。
キャリアウーマンも結婚と同時に退職する「寿退社」が、(当時としては)当たり前の感覚だったのだ。
「仕事か? 結婚か?」という二者択一の思考回路は、1980年代後半にあってはやむを得なかったかもしれない。
桐島洋子や向田邦子を擁して「女の生き方」を発信し続けてきた『クロワッサン』も、80年代後半には、すっかりと路線を変更して、幸福な主婦の生活を応援する雑誌となっていた。
クロワッサンは変わった。雑誌はもともとそういう性格のものなのである。変わるのだ。(松原惇子「クロワッサン症候群」)
取り残されたのは、1980年(昭和55年)前後に20代だった(一部の)女性たちだけだ。
『ハートに火をつけて』の春や亜矢や悦子たちのように、結婚を焦る独身女性たちの存在がクローズアップされた。
1980年代のトレンディドラマは時代を反映している。
というか、時代を反映しているからこそ「トレンディドラマ」なのだ。
時代背景を理解していないと、ドラマそのものが理解できないことにもなりかねない。
逆に言うと、トレンディドラマは、当時の時代性を知る上で、貴重な教材とも言える。
ゴージャスなライフスタイルのバックボーンとなっているものを読み解くことが、トレンディドラマを正しく理解するポイントである。
『ハートに火をつけて』と『クロワッサン症候群』。
どちらも既に時代遅れのものとなってしまったけれど、時代遅れのものだからこそ、そこにはリアルな1980年代後半という時代性がある。
あれから36年。
『ハートに火をつけて』の女性たちは、どのような人生を過ごしてきたのだろうか(そして、島田祐二も)。
書名:クロワッサン症候群
著者:松原惇子
発行:1988/11/15
出版社:文藝春秋