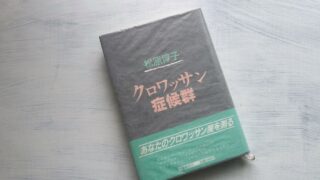光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』には、クマに関するエピソードが2篇ある。
コミックス第6巻所収「第58話/クマが出た!」と、コミックス第7巻所収「第67話/北海道の熊(オヤジ)」である。
麦ちゃんの奥山村のツキノワグマ
光瀬龍・原作『ロン先生の虫眼鏡』は、1970年代後半のナチュラリストにとって、貴重な教科書だった(少なくとも、当時、少年だった者にとっては)。
実際、『ロン先生の虫眼鏡』を読んで、動物や昆虫の世界に興味を持ったという例も少なくない。
光瀬龍・原作、加藤唯史・作画の『ロン先生の虫眼鏡』は、1977年(昭和52年)から『週刊少年チャンピオン』に連載された少年漫画である。
1979年(昭和54年)4月からは『月刊少年チャンピオン』へ移籍し、連載は1981年(昭和56年)まで続いた。
当時の『週刊少年チャンピオン』と言えば、『がきデカ』『ふたりと5人』『マカロニほうれん荘』などのナンセンス・ギャグ漫画が主力で、真面目な教養漫画とも言える『ロン先生の虫眼鏡』は、かなり異色の作品だった。
なにしろ、コミックスには「大自然ロマンコミックス」とある。
高度経済成長時代に発達した文明社会の中、自然科学に対する少年たちの関心も高まっていたのかもしれない。
『ロン先生の虫眼鏡』では、クマに関するエピソードが2篇ある。
コミックス第6巻所収「第58話/クマが出た!」と、コミックス第7巻所収「第67話/北海道の熊(オヤジ)」である。
当時は、山間地域においてクマ被害が多発しており、社会的なニーズに応えた作品として読むことができる。
コミックス第6巻に収録されている「第58話/クマが出た!」は、ツキノワグマの物語である。
麦ちゃんの住んでいる仙人郷のある奥山村では、最近、クマ被害に悩まされていた。
村が用意した鉄砲隊も、現役を引退した元・猟師の百姓ばかりで、銃の手入れも満足に整っていない。
困った村長は、ロン先生に救援を求めた。
「クマはあの山から来るんですよ」「あの山の南側の山腹には、少なくとも五頭のツキノワグマがすんでると思われます」「その中の一頭が年を取っていて、冬眠前の食いだめが十分にできなくて人里を襲ったんでしょうな」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
「ツキノワグマとヒグマとはどう違うの?」という洋子ちゃんの質問に答えて、ロン先生はツキノワグマについての解説を始める。
「ヒグマは北海道、ツキノワグマは本州以南にすむクマだよ」「一般にはツキノワグマのほうがヒグマに比べて小さいが、それでも体重四百クログラムに達するものがあるね」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
ツキノワグマは、必ずしも小さな動物ではない。
「ツキノワグマは全身真っ黒だが、首に三日月形の白い模様があるのが特徴だ」「ヒグマは全身赤っぽい褐色だがね」「ツキノワグマはヒグマほどではないが、やはり猛獣で、大変危険な動物だよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
「山でクマに出会ったら、どうすりゃいいのかね?」と尋ねたのは、駐在所のお巡りさんだ。
「クマはとても気が小さいんだ。臆病なんだよ」「だから、突然、人間に出会うと怖くてたまらないから、わけもわからず飛びかかってくるんだ」「カンを叩くとか、大声を出すとか、クマに人間が通るぞということを、あらかじめ教えてやれば、クマはさっさと逃げてしまって、絶対に人間の前に姿を現さないよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
「クマに人間が通るぞということを、あらかじめ教えてやれば、クマはさっさと逃げてしまって、絶対に人間の前に姿を現さないよ」とあるが、現代のクマは「人慣れ」しているとも言われる。
人慣れしたクマは、人間の存在を知っていて、あえて近寄ってくる場合もあるらしい。
村長は「死んだふりをすればいいというね」と、昔ながらの言い伝えを持ち出した。
「それというのも、自分に害意がないものとして安心するからなんだ」「実際、これで50パーセント助かってるんだよ」「じゃ、残りの50パーセントはだめか……」「それもツキノワグマの場合であって、ヒグマの場合はまるでだめだと言われているよ」「ヒグマは気が荒いから、そんなことでは安心しないんだね」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
現在では、クマに対して「死んだふり作戦」は、あまり有効ではないかもしれない。
もっとも、クマの襲撃から逃げ切ることは簡単ではない。
「木に登ったらどうなんだろう?」「クマは木登りは上手だし、水泳もうまい。走るのも人間よりずっと速いという万能選手だから、クマに追いかけられたらかなわんね」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
当時、ロン先生の解説を読んで、クマという動物の「素晴らしさ」を学んだような気がする。
特に「万能選手」という言葉が印象的だった。
クマに襲われたら、逃げ切ることは難しいのだ。
「クマは上手に後ろ足でパッと立ち上がることができるし、両手で人間を胸に抱えこんで、かみついたり、腕で強烈なパンチを食らわせたりすることができる」「前進後進も自由だ」「見かけからは想像もつかず、動作が活発だからね」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
本来、クマは草食動物である。
主食は木の実や新芽で、クロスズメバチの巣を掘り返して、ミツを舐めたり、ハチの子を食ったりしても、他の動物を襲って食ったりはしない。
「じゃ、どうしてこの村に来るんですか?」「トウモロコシや干し柿が吊るしてあったり、干してあったりすると、我慢できなくなるんだ」「それで、人間の家の中に、そのようなものがあるというのを知ったクマが、家の中へ入ってくることもあるんだ」「そして、人間を見てカッとなるんだよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
ロン先生が提案したのは、電気柵の設置だった。
「イノシシを防ぐのと同じように、集落の周りに裸電線を引いて、弱い電流を流したらいいだろう」「念のために、各家の周囲にも作って、夜の間だけでも流したらどうかね」「動物は、人間よりもずっと電気ショックに敏感だから、一度ピリッとくると、もう二度と近づかないよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第58話/クマが出た!」)
本話は、ロン先生の解説が中心で、洋子ちゃんや元太くんが活躍する場面は、ほとんどない。
せっかくの奥山村なのに、麦ちゃんの登場場面が少ないのも残念。
風邪で寝こんでいる元太くんを置き去りにして、麦ちゃんと洋子ちゃんは、麦ちゃんが住む仙人郷へ行ってしまう。
麦ちゃんは連載第1話「チャタテムシ」から登場していて、実は(レギュラーメンバーの)洋子ちゃんよりも歴史の古いキャラクターだったのだ。
書名:ロン先生の虫眼鏡(第6巻)
著者:光瀬龍・原作、加藤唯史・作画
発行:1979/07/20
出版社:秋田書店
ヒグマの恐怖に耐えて生きる北海道民
コミックス第7巻に収録されている「第67話/北海道の熊(オヤジ)」は、『ロン先生の虫眼鏡』では貴重な「北海道回」である。
ヒグマ被害に悩む「北海牧場」からの要請を受けて、ロン先生は(元太くんと洋子ちゃんを連れて)北海道へ渡る。
「町役場や森林組合では、どんな対策を立てているのかね?」「それが、まだこれといった決め手がないんだ」「このごろは専業猟師はうんと少なくなったし、アマチュアのハンターは、クマなどという大物は撃ったことがなくてね」「クマ対策の自警団も、積極的な手が打てないというのが現状なんだよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
北海道の農家や牧場にとって、ヒグマの出没は死活問題である。
「たとえば、大正14年12月、天塩山地の三毛別に近い三渓村という村で七人が殺され、三人が重傷を負うという大惨事が起きた」「これは北海道のヒグマの被害の中で、最大の悲劇だね」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
三毛別のヒグマ事件は、吉村昭の長篇小説『羆嵐』(1977)に詳しい。

「昭和34年には殺されたヒツジが六百三十八頭、牛 三十四頭、馬 四十頭、ヤギ 十四頭にも達している」「昭和40年には、馬・牛・ヒツジを合わせて九百五十八頭も死んでいる」「人間の被害の方は、この百年間に七十六人も死んでいる」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
ヒグマ被害は、決して開拓時代の昔話ではない。
「ことに山地では、ヒグマに対する警戒なしで生活がなり立たんほどだよ」「それにヒグマは、今のところ、ほとんど数が減っていない」「オオカミやエゾシカなどは開拓が進むにつれて急速に消えてしまったのに、ヒグマだけは開拓によって滅ぼされなかった唯一の動物だよ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
住宅化が進んだ現代にあってさえ、ヒグマは住宅街へと出没してくるのだ。
ヒグマは、北海道民の暮らしに、大きな影響を与えている。
「北海道からヒグマがいなくなれば、一番いいんだろうね」「ヒグマが滅びてはかわいそうだ……と言う人もいるけど、この気持ちは、その恐怖に耐えて生活するんでなければ分からないことです」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
かつて開拓者たちは、北海道のヒグマを「オヤジ」と呼んだ。
近年は、こうした愛称も廃れてしまったようだ。
「自然破壊だの、やみくもな開拓のせいだなどと言う人もいるが、昔からたくさんの人々が、北海道の原始林や草原で働いてきた」「そこで言われる開拓とは、住宅地を作るとか、観光施設を作るなどというのとは違うんだ」「木を伐り、畑を耕し、自然と一体となって堂々とやってきたのだ」「この人たちにとって、ヒグマはまさに悪魔だ」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
このときのロン先生の「そこで言われる開拓とは、住宅地を作るとか、観光施設を作るなどというのとは違うんだ」というひと言は、少年の心に深く刻みこまれた。
「木を伐り、畑を耕し、自然と一体となって堂々とやってきたのだ」は、北海道開拓を象徴する言葉と言っていい。
北海道開拓の現実については、戦後開拓者たちの悲惨な様子を描いた、開高健『ロビンソンの末裔』(1960)を読むと、よく理解できる。

この話の中でロン先生は、クマ除けの超音波装置を開発する。
「いや、こいつが意外に役立ったよ」「超音波のような高い音を出すんだが、クマがいやがる音というのがあってね。実験するつもりで持ってきたんだよ」「そいつはいいや! 先生、それを牧場の周囲に取りつけましょう!」(光瀬龍・原作、加藤唯史・作画『ロン先生の虫眼鏡』/「第67話/北海道の熊(オヤジ)」)
ロン先生の開発したクマ除けの超音波装置だが、現代まで実用化されてはいないようである。
この物語では、元太くんが二度に渡ってヒグマの襲撃を受けた。
やんちゃでおっちょこちょいの少年の面目躍如といったところだが、最後には「ヒグマ恐怖症」にかかってしまうというオチもいい。
初出は、1979年(昭和54年)4月2日『週刊少年チャンピオン(NO.14)』で、雄大な北海道の大自然に対する都会人の憧れが反映された物語だった。
ちなみに、この時期、北海道出身のフォーク歌手(松山千春)は、『空を飛ぶ鳥のように 野を駈ける風のように』を発表している(1979年5月)。
アルバム・ジャケットは、北海道十勝管内の足寄町で撮影されたもの。
それは、北海道が、まだまだ北海道らしい時代だったのかもしれない。
書名:ロン先生の虫眼鏡(第7巻)
著者:光瀬龍・原作、加藤唯史・作画
発行:1979/09/05
出版社:秋田書店