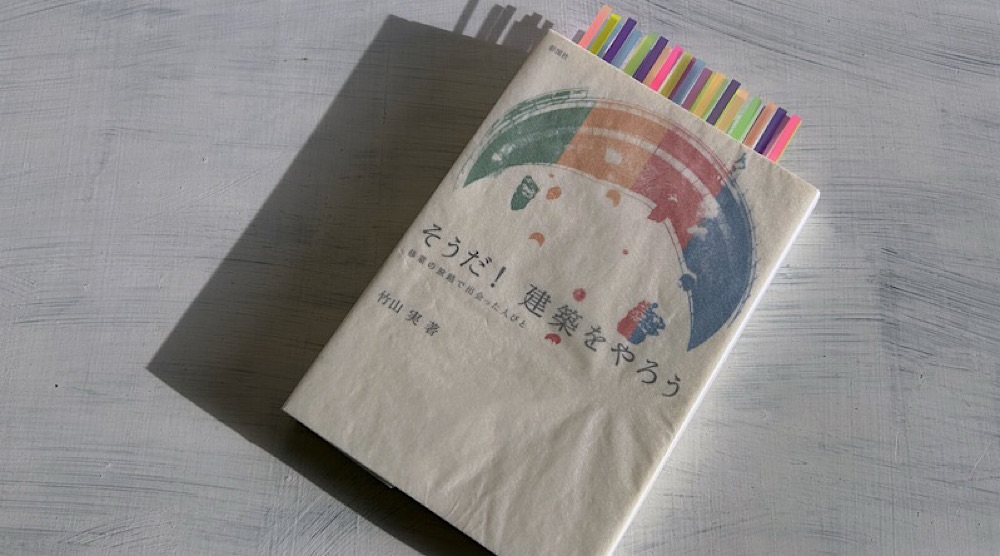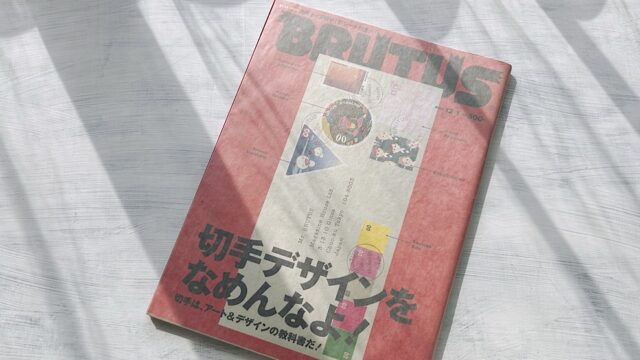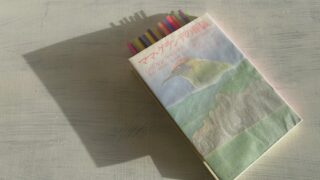竹山実「そうだ! 建築をやろう」読了。
本作「そうだ! 建築をやろう」は、2003年(平成15年)11月に彰国社から刊行された自叙伝である。
この年、著者は69歳だった。
戦前戦後の札幌の思い出
本作『そうだ! 建築をやろう』は、札幌出身の建築家(竹山実)の自叙伝である。
もっとも、半生記を回顧したものというよりは、建築家として独立する30歳までに出会った人々の回想が中心だが。
副題に「修行の旅路で出会った人びと」とあるのも、建築家・竹山実が誕生するまでの経過を描いた回想録と考えていい。
とりわけ、札幌時代の思い出については、本作『そうだ! 建築をやろう』に詳しい。
竹山実の思い出は、そのまま、札幌の歴史へと繋がるものだ。
僕の生家は、札幌の市街地に位置していた。この街の市街地を南北に貫く運河と東西を縦断する電車通りのちょうど交差点だったから、そこはいわばこの北の都市の座標の中心部に当たっていた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
「この街の市街地を南北に貫く運河」とあるのは創成川のことで、「東西を縦断する電車通り」とあるのは、現在の国道36号線のこと。
現在、札幌の市電は、「すすきの」から北へ向かって「西4丁目」へとつながっているが、全盛期には、「すすきの」から豊平川を越えて「豊平駅前」まで市電が走っていた(「豊平線」)。
「豊平駅前」とは定山渓鉄道線の発着駅の名前で、「すすきの」から「豊平駅前」まで市電で移動し、ここで定山渓鉄道に乗り換えるという交通ルートが、かつてはあったのだ。
タボの家とわが家を隔てている運河は、僕の生まれたころには既に創成川と呼ばれていた。僕が子供のころは、この川沿いに美しいアカシアの樹が何本も植えられた並木路もあった。しかも、川の両岸には芝生の公園もあって人の賑わいが絶えなかった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
竹山実は1934年(昭和9年)生まれなので、11歳で終戦を迎えている。
建築家の少年時代となると、それは、戦前・昭和初期の札幌を意味していたのだろう。
自宅の前を創成川が流れ、隣の道を市電が走っていた。
この軌道を走る電車がときどき横転したりした。僕が見ただけでも二度あった。僕の家の側に倒れて怪我人が出たこともあった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
昭和初期の美しい思い出は、やがて、戦時中の思い出へと変化していく。
最も強烈な印象として残ったのは、強制疎開である。
ガキ大将たちの家々も次から次へと壊されていった。ケンカしても負けを知らないタローの家も犠牲者だった。仏壇屋を営む親の慌てぶりを見て、息子のタローは初めて涙を見せた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
国道36号線は当時から、千歳の空港や室蘭の軍港に通じ、小樽の港へと直結していた。
米軍の焼夷弾による攻撃から火災を回避しようと、市街地を二分するこの街路に防火帯が計画された。
国道の幅員を倍にするため、北側の建物が一律に削られることになった。
国道36号線の幅員が広いのは、戦争中の強制疎開が原因となっている。
戦争直後、この街路に沿って解体された跡地に、こんどは、ほんのわずかしか奥行きをもたない珍妙な家々が立ち並んだ。それは樺太からの引揚者家族を収容するための仮設住居だった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
終戦後、戦地からの復員兵だけではなく、本州からの疎開者や外地からの引揚者が大量に札幌へ集まり、札幌の人口は爆発的に増加した。
当然、住宅難が社会的な問題となった。
作者(竹山実)の父親も、シベリア抑留地の収容所で暮らしていたらしい。
父が引揚げ船で無事に舞鶴港に帰ったのは、召集されてから八年ぶりだった。やがて、汽車を乗り継ぎ札幌の駅前に降り立った父は、迎えに集まった知り合いを一カ所に集め、演台を用意させた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
シベリア帰りの復員兵が、共産主義に洗脳されていたという話は珍しくない。
戦争が、また、彼の人生をも狂わせてしまったのだろう。
その頃、日本は教育改革のまっただ中で、作者も教育制度改革の影響を直接的に受けた世代だった。
中学校を卒業して、札幌第一高校(現在の札幌南高校)へ入学した作者は、高校二年からは札幌東高校へ通うことになる。
高校に通う学生を全員集めて、アッというまに東西南北の区域に分割したこの出来事は、地元ではよく、牌を混ぜて四つの場に分けるマージャンにたとえられた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
そのため、竹山実は、札幌南高校と札幌東高校、二つの同窓会に所属していたという。
札幌第一高校では、中山周三に国語を学んだ。
いちばん印象深く、いまなお記憶に残る教師のひとりは、中山周三という名の国語の先生だった。(略)この先生は歌人で、釈迢空(折口信夫)の教えを受けたと聞いていたが、そのせいか、彼が紹介した正岡子規やアララギ派の数々の短歌は、いまでも記憶しているものがあるほどだ。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
驚くべきことだが、高校時代の竹山実は文学青年だった。
漢字の書取りの勝抜き戦でも、常に上位に位置していた。
たしか、いまは作家に転じた渡辺淳一の横綱は安定していて、いくら頑張っても僕はせいぜい大関止まりだった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
札幌南高校には、文学青年が多かったらしい。
同じ高校に通っていた同期の者のなかにも、後年文筆で身を立て、直木賞を受賞してベストセラーを出し、多額納税者に名を連ねるほどの流行作家になったり、あるいはSF小説でユニークな作品を世に送るようになった同級生もいる。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
「直木賞を受賞してベストセラーを出し、多額納税者に名を連ねるほどの流行作家になった」とあるのは、先述の渡辺淳一である。
渡辺淳一の高校時代については、自伝的長篇『阿寒に果つ』(1973)に詳しい。

「SF小説でユニークな作品を世に送るようになった同級生」は、『白き日旅立てば不死』で有名な札幌在住のSF作家(荒巻義雄)のこと。
詩人の更科源蔵とも交流があった。
アイヌ研究家で知られる更科源蔵に同行してニセコの山を登ったこともあった。この詩人は大変な物知りで、山小屋のランプを囲んで夜遅くまで彼の話に聞き入ったこともあった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
つまり、高校時代の竹山実は、文学と深い関わりを持ちながら暮らしていたということなのだろう。
戦後の闇市では、英文タイプライターを手に入れている。
終戦直後には、この狸小路の東端に闇市が集まった。(略)そのころ中学生になっていた僕は、頻繁にここに足を運んだ。なかでも駐留軍から放出されるさまざまな物資に目を奪われた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
CIEの英文論文コンテストで最優秀賞を受賞した作品は、このときのタイプライターによって書かれたものだ。
周囲の誰もが、竹山実は、やがて文学の道を歩むのだろうと考えていた。
ちょうどそのころ、僕が読んでいた作家のひとりにハンス・カロッサがいた。『幼年時代』『美しき惑いの年』などの作品では、その写実的でしかも映像的な描写が、たまらなく僕の想像力を刺激した。『医師ギオン』でこの作者が医者であることを知らされ、その誠実でヒューマンな姿勢にますます感銘を受けた。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
ハンス・カロッサの影響を受けた作者は、医学を選ぶか、文学を選ぶかで迷った。
早稲田大学の文学部に願書を出すため上京したとき、建築学科で見た学生の作品に興味をそそられた(「それが意外に文学的だと、僕には感じられた」)。
それが「文学的だ」という理由で、竹山実は(早稲田大学の)建築学科も受験することになる。
北大と早稲田の二つの大学から選んだ三つの志望学科(医学、文学、建築)の入学試験が慌ただしく終わり、その結果を待つことになった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
入学試験の結果は、すべて合格で、作者(竹山実)は、籤(くじ)を作って進学先を決めた。
入学手続きの締切りが直前に迫ったある日の朝の食卓で、僕は今日こそ最終決定をすると家族のみんなに宣言をして食卓に籤をつくった。自分の箸を一本取り出し、目をつぶってそれを片手の指先で垂直に立て、それが自然に倒れる方に志望を託した。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
そのときに出た答えが「建築」だったことは言うまでもない。
早稲田大学で作者は建築を学び、やがて、世界的に有名な建築家へと成長していく。
ここに描かれているのは、建築家・竹山実が誕生するまでの前史を綴った物語だったのだ。
創成川に面した竹山実の生家
建築家・竹山実の生家は、現在も当時と同じ場所にある。
札幌市中央区南5条東1丁目の北西角にある「竹山食品工業」がそれだ。
同社は、1889年(明治22年)に、創業者の竹山岩吉氏が札幌二条市場近くに海産商「竹山商店」を創業したのがルーツ。1927年(昭和2年)に2代目が佃煮製造を開始、1937年(昭和12年)に現在地に移転、「竹山佃煮工場」に改称した。1949年(昭和24年)に3代目が「竹山食品工業」を設立、現在に至っている。(「創業135年、札幌の老舗佃煮メーカー竹山食品工業が自主廃業へ」/『リアルエコノミー』2023年2月24日)
札幌市内で135年の歴史を有する竹山食品工業が廃業したのは、2023年(令和5年)のこと。
「極上ちりめん」「白じゃこ」「栗きんとん」「黒豆」「花そぼろ」「桜でんぶ」など、人気商品を多く扱っていたが、佃煮の主原料となる魚類の調達難に続き、2020年(令和2年)からのコロナ禍で佃煮市場が急速に縮小し、売り上げも減少していたという。
2022年4月には、1940年代後半から営業してきた「竹山佃煮 札幌三越店」を閉店して経営合理化を進めてきた。しかし、原材料価格の高騰やエネルギー価格の上昇が響き、早期の事業停止が最良と判断、自主廃業することにした。(「創業135年、札幌の老舗佃煮メーカー竹山食品工業が自主廃業へ」/『リアルエコノミー』2023年2月24日)
自主廃業したものの、かつての工場や自宅は、当時のままだ。
独特の外観で、現在も角地に立つアルミパネルの住宅は、建築家・竹山実の作品である。
一九七二年、冬季オリンピックが札幌で開催されるのを機に、そのころはまだ元気だった父が、老朽化した家の外壁だけでも修復したいと思い立った。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
なにしろ、国道36号線に面した自宅である。
多くの観光客の来道を見据えて、竹山家の改装計画は始まったが、母屋があまりに古すぎた。
僕の最終提案は、いまの家をぜんぜんいじらずにそのままにして、その上に新しい「化粧」を被せるという案だった。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
国道36号線と創成川に向いた二面の外壁だけを、アメリカ製のアルミパネルで覆ってしまえば、古い家が見えることはない。
外部をアルミの化粧パネルで覆った結果、この古い木造家屋は外装が一変して見違えるように生まれ変わった。海産物問屋のイメージを青と白のストライプのパターンに漂わせてむかしの面影を残そうとしたが、近所の人はアッというまにまったく新しい建物が出来たと信じきって、みんな驚いたようだ。(竹山実「そうだ! 建築をやろう」)
現在も、竹山実が少年期を過ごした実家は、青と白のアルミ・パネルに包まれて、角地に立っている。
それは、1970年代初頭にあって、ずいぶんと近未来的な建築物に見えたことだろう(現在でさえ、かなり異質な印象を与える)。
アルミパネルの隙間からは、当時のままの古民家をチラ見することができる。
札幌軟石のうだつに刻まれた「海産商」の文字も歴史を感じさせる。
国道36号線に面して、昔のままの工場が並んでいる。
目の前の国道は、戦争末期の強制疎開によって道路が拡幅された道だ。
自宅の西側には、創成通りのアンダーパスを挟んで、今も創成川が流れている。
かつて、札幌まつりには、この河畔に露店が並んだことは、竹山実の回想にも綴られているとおりだ。
本作『そうだ! 建築をやろう』は、建築家・竹山実の回想録であると同時に、札幌の歴史を振り返った貴重な記録としても読むことができる。
いや、札幌市民は、むしろ、この回想録を、札幌の過去を振り返るためのガイドブックとして読むべきではないだろうか。
そこには、昭和初期に少年期を過ごし、太平洋戦争の中で思春期を迎え、終戦直後の混乱に青春時代を送った一人の若者の、懐かしい思い出がある。
そして、国道36号線と創成川に面して建つ、青と白のストライプのアルミパネルの家は、そこで竹山実が生まれ育ったことを示す、記念碑的な建築物なのだ。
書名:そうだ! 建築をやろう
著者:竹山実
発行:2003/11/10
出版社:彰国社