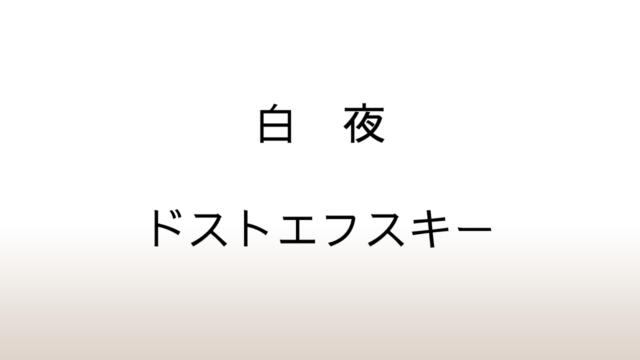ジョージ・オーウェル「パリ・ロンドン放浪記」読了。
物語は「パリ、コックドール街、午前七時」から始まる。
時代は1929年(昭和4年)で、コックドール街はポーランド人やアラブ人、イタリア人などが滞留する安宿が密集する、典型的なパリのスラム街だった。
ジョージの暮らしているホテルは、暗い、ガタビシした五階建ての安普請で、木の板で仕切った四十の部屋があったが、どの部屋も狭く、芯から汚れていて、壁の割れ目を隠すために重ねて貼られたピンクの壁紙の隙間には無数の南京虫が住みついていた。
客は浮浪者ばかりで、ほとんどは外国人、靴直しや煉瓦職人、石工、土工、学生、娼婦、ゴミ拾いなど、様々な商売の人間が荷物一つ持たずに現れては一週間滞在して、また姿を消していく、そんなホテルだったらしい。
この街でジョージは、老婆の家の地下で暮らす若い女性を金で犯し、仲間のボリスと二人で職を探し求め、豪華なホテルで「皿洗い」として働きながら、ホテルのレストランにあって「皿洗い」がどれだけ惨めで侮蔑的な存在であるかということを知る。
やがて、新規開店するレストランへ移った後も、ジョージは厨房の「皿洗い」として働き、最後に「皿洗いは奴隷である」という結論を得てパリを去り、故郷のイギリスへと帰国する。
物語の後半はロンドンのスラム街での暮らしぶりで、友人に紹介された仕事が始まるまでの間、ジョージは浮浪者として生活しなければならない。
地元の浮浪者と仲良くなったジョージは「スパイク」と呼ばれる浮浪者臨時収容所へ行き、マーガリンを塗った楔形の半ポンドのパンと、砂糖抜きなので苦いココアの食事を食べるが、「スキリー」(缶に湯を入れて、底にひでえオートミールがちょこっとへえってる奴よ、とアイルランド人の老人は説明した)をよこすスパイクは最低だと聞いていたから、これだけの食事でも、あるいは多少はまとまなものだったのかもしれない。
浴室の光景はあきれるほど不愉快で、五十人の汚い男が素っ裸になって狭い部屋で押し合いへしあいしており、二つの浴槽にロールタオルも二枚だけ、不潔な足の悪臭ときては死ぬまで忘れられないものなのに、たくさんの人間が、既に他人が足を洗った水を使わなければならない。
ベッドのない寝室で横になると、隣で寝ている男の息が顔にかかり、裸足の足が始終触れるくらいに密着して、寝返りを打てば必ずぶつかるほど。
真夜中に隣の男が同性愛的な行為をしかけてきたが、失業して妻に逃げられた男たちは、女性とのつながりがまったくなくなってしまうため、長く浮浪者をやっている者の間で同性愛は極めて普通のことらしかった。
バディという相棒を得て、ロンドンでの浮浪者としての暮らしは、いずれジョージが仕事にありつくまで続くが、『パリ・ロンドン放浪記』では、貧民窟とも呼ばれる細民街の様子が、浮浪者たる著者の目を持って克明に描かれている。
ジョージは、ジャック・ロンドンのルポタージュ『どん底の人びと』を既に読んでいて、最下層で生きる人々に強い関心を持っていたから、ある意味では意図的に貧困生活を体験したらしいが、浮浪者になりすましてスラム街に潜入取材したジャック・ロンドンとは異なり、ジョージは実際に貧しくて金がなかったから、現実的に最下層の人間となり浮浪者として生活した。
ジャックの『どん底の人びと』が研究書のような第三者性(上から目線のようにも思える)をもって書かれているのに対して、ジョージの『パリ・ロンドン放浪記』が貧民街の人々に対する親しみや愛情をさえも感じさせるのは、一時的とは言え、ジョージが真正の浮浪者であったためかもしれない。
パリではボリス、ロンドンではバディという愛すべき相棒を始め、スラム街で生きる人々の描写はリアルで生々しく、キャラクターがしっかりととらえられている。
貧民街を舞台に貧困層の人間を描いた物語として、十分に読み応えのある作品だと思った。
書名:パリ・ロンドン放浪記
著者:ジョージ・オーウェル
訳者:小野寺健
発行:1989/4/17
出版社:岩波文庫