吉野弘「くらしとことば」読了。
吉野弘は詩人である。
「夕焼け」という作品が広く知られている。
固くなってうつむいて/娘はどこまで行ったろう。/やさしい心の持主は/いつでもどこでも/われにもあらず受難者となる。/何故って/やさしい心の持主は/他人のつらさを自分のつらさのように/感じるから。/やさしい心に責められながら/娘はどこまでゆけるだろう。/下唇を噛んで/つらい気持ちで/美しい夕焼けも見ないで。(吉野弘「夕焼け」)
あるとき著者は、この「夕焼け」という作品に対する批評の中に「夢焼け」という言葉を見つけた。
「日焼け」や「雪焼け」や「酒焼け」という言葉はあるけれど、「夢焼け」という言葉はない。
印刷所のミス、誤植である。
ところが、著者(吉野弘)は、この「夢焼け」という不思議な言葉に魅かれた。
心の隅に燃えている炎、誰にもいわずに、こっそり育てている望み、その炎に焼かれながら、みすみす老いてゆく淋しさ—そんな人生の横顔がこの言葉にはある。
そして、著者は本当に「夢焼け」という題名の詩を書いた。
「あるとき、どこかの文選工が活字を拾い違え/私の詩の表題「夕焼け」を/「夢焼け」と誤植したから」というフレーズで始まる作品だった。
誤植に怒るのではなく、そこから新しい作品を生み出していく豊かな発想力と、何より言葉に対する敏感な詩人の感性を伝えるエピソードだと思う。
もうひとつ。
金魚鉢で金魚を飼ったけれど、一匹を残してみんな死んだ。
金魚鉢の大きさとして、金魚一匹が生きるのにちょうど良い広さだったのだろう。
同じころ、著者は仲間たちと一緒に会社を興した。
不景気の嵐が吹き荒れていた1964年(昭和39年)のことである。
コマーシャル関係のデザインの会社で、最年長という理由で著者が社長を務めた。
一匹狼みたいな連中の集まりで、この会社は長くは続かないだろうと、著者は感じ始める。
会社としての収入もなく、社長業の数か月は給料も出なかったらしい。
結局、会社は創立からたった六か月で解散した。
金魚が金魚鉢の中で、たった一匹しか生きられなかったように、仲間たちもまた、それぞれの金魚鉢の中でしか生きることができなかったのだと、著者は思う。
さらに、もうひとつ。
「スキャンダル」という音の中の「キャンダル」は「キャンドル」に似ていると、著者は言う。
キャンドルは「人の世の闇を照らし出す」ものだから、スキャンダルに通じる性質がある。
人は多分、ある大きな闇の中に生き、自分自身も闇をかかえてくらしている。
その闇をしみじみと見せてくれるのが、他人の、スキャンダルという名のキャンドルなのだ。
もちろん、自分の中にもスキャンダルは潜んでいる。
それを自分で明るみにさらす力がないから、他人のスキャンダルの明かりを借りて、自分の中の闇を眺めているのにすぎない。
そういう繊細な話を、著者は優しくて朴訥な言葉でしみじみと語りかけてくれる。
決して鋭いのでもなければ切り刻むのでもない。
本当は誰よりも鋭敏な感性で人間と向き合っているのに、著者はただひたすらに誠実であろうとしている。
そんなエッセイの数々は、「雪の日に」という一篇の詩を思い出させた。
「雪はひとたび ふりはじめると/あとからあとから ふりつづく/雪の汚れを かくすため」というフレーズを含んだ、あの「雪の日に」だ。
愚直なまでに人間的であろうとした「吉野弘」という詩人の生き様を見るような言葉の連なり。
雪がはげしく ふりつづける/雪はおのれを どうしたら/欺かないで生きられるだろう/ それが もはや/みずからの手に負えなくなってしまったかのように/雪ははげしく ふりつづける(吉野弘「雪の日に」)
エッセイを読んでいるうちに、次は詩集を読みたくなった。
吉野弘の文章には、そんな魅力がある。
書名:くらしとことば
著者:吉野弘
発行:2015/8/10
出版社:河出文庫


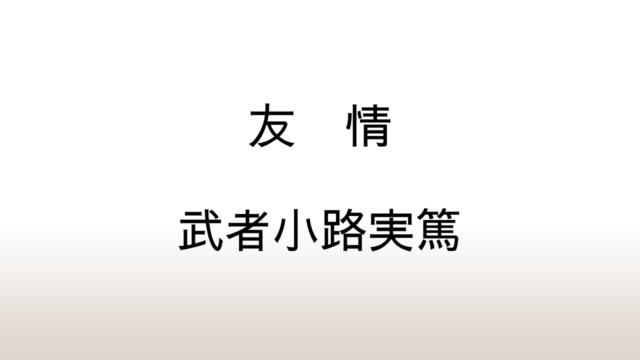



-150x150.jpg)









