庄野潤三「けい子ちゃんのゆかた」読了。
はじめに、あとがきから。
「文學界」に連載して文藝春秋から昨年四月に本になった『メジロの来る庭』に続いて「波」に連載した「けい子ちゃんのゆかた」が完結して新潮社から本になる。『貝がらと海の音』(新潮社)に始まり、夫婦の晩年をテーマにして続けて来た連作の十作目に当る。十年続いたことになると思えばうれしい。子供がみな結婚して「山の上」のわが家に二人きり残された夫婦が、いったいどんなことをよろこび、どんなことを楽しみにして生きているかを描く私の仕事は、休みなしに続いてゆく。(庄野潤三「けい子ちゃんのゆかた」)
庄野文学の晩年の代表作とも言うべき「夫婦の晩年シリーズ」の連作は、本作『けい子ちゃんのゆかた』で10作目となった。
特別の物語ではない、日常生活を淡々と綴る作品が10年続いたということになり、10年続いたということは、一定数の読者の支持があったということに他ならない。
改めて「すごい」と思う。
連作シリーズとは言え、10年の間に、作品の印象が少しずつ変わってきたことは言うまでもない。
次男のところの孫娘であるフーちゃんが小さかった頃は、作品中にも頻繁に登場して、祖父母の楽しみを朗らかに描く場面が多かったし、次男のところで飼っている「犬のジップ」や「うさぎのミミリー」を預かったりして、物語に起伏の変化を与えていた。
本作では、夫婦が高齢となったためか、ペットを預かることもなくなり、孫が遊びに訪れる場面も少なくなった。
題名ともなっている「けい子ちゃん」の浴衣をお直しするエピソードは、本作全体の中では貴重なものであって、むしろ、昔の作品の回想と、庭の野鳥に関する記述が多くを占めるようになっている。
例えば、九度山の柿を送ってくれていた「相谷さん」が亡くなったとき、庄野さんは「九度山とはご縁がある」といって、初期の代表作「静物」を執筆した頃のことについて長く回想している。
「群像」で意欲のある作家にまとまった枚数の作品を書かせて「一挙掲載」といって載せる企画をしたとき、庄野さんもエントリーをして、兄の勧めで九度山の旅館に籠って執筆活動に取り組んだという話である。
ところが、何を書くか決まっていない庄野さんは、その静かな旅館で何も書くことができなかった。
「四、五日粘って、私はこの九度山の宿をあとにして、東京石神井公園のわが家へ帰った。そんなことがあった。私はあきらめないでこの仕事にくらいつき、やっと中篇の小説を一つ書き上げて、『群像』にわたすことが出来た。これが『静物』であった。」
「「釣堀へ行こうよ」と男の子にせがまれ、「釣れるかもしれない」と女の子がいうので、重い腰を上げて子供と一しょに近くの釣堀へ出かける父親であるが、金魚が一尾かかったのに気をよくして引き上げる話から始まるのが、苦労した末に出来上った『静物』という作品であった」
「これを題名とした本がその年の新潮社文学賞を受賞したこともなつかしい思い出になった」と、庄野さんは当時を振り返っている。
人生の締めくくりの時期に入りつつあることが、作品を構成するひとつひとつのエピソードから感じられるような気がした。
高校1年生になったフーちゃん
シリーズ第1作目から、中心的なキャラクターとなっている孫娘のフーちゃんは、本作では高校1年生として登場している。
高校生ともなると、幼い頃のように頻繁に祖父母の家を訪れたりはしない。
庄野さんは、妻が小さなひな人形を飾る様子を眺めながら、幼いフーちゃんが祖父母の家を訪ねては、楽しく遊んでいった日々を懐かしく回想している。
シリーズを開始した頃の作品で描かれているエピソードが、既に懐かしい思い出となっているのだから、子どもの成長は早いし、10年間という時の流れも重い。
だからこそ、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」には、子ども時代のアルバムをめくる楽しさが感じられるのだろう。
書名:けい子ちゃんのゆかた
著者:庄野潤三
発行:2005/4/30
出版社:新潮社



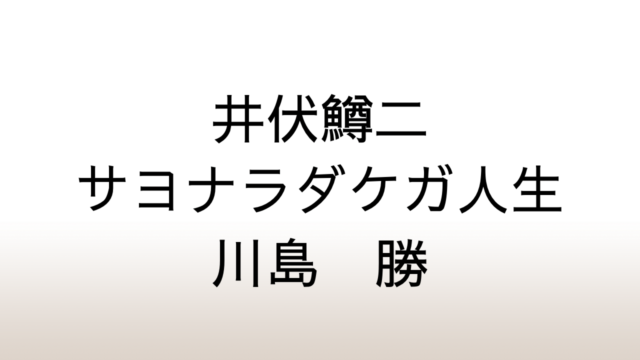

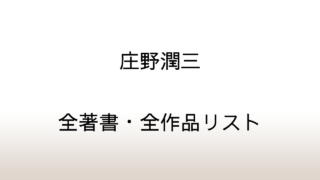
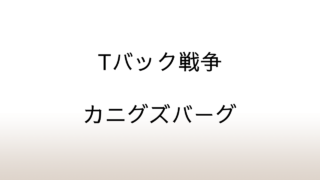
-150x150.jpg)









