井伏鱒二「珍品堂主人」読了。
本作「珍品堂主人」は、1959年(昭和34年)1月から9月まで『中央公論』に連載された長編小説である。
この年、著者は61歳だった。
単行本は、1959年(昭和34年)10月に中央公論社から刊行されている。
人生は駆け引きの連続だということ
「珍品堂主人」は手元にもあるが、中公文庫の増補新版は、本作のほか、「珍品堂主人について」「能登半島」という井伏さんの骨董エッセイ、さらに巻末には白洲正子のエッセイ「珍品堂主人 秦秀雄」が収録されている豪華版だということだったので、改めて買い直した。
ついでに言うと、「この本を読んで—『珍品堂主人』」という河上徹太郎と井伏さんとの書簡形式のあとがきも楽しい。
「珍品堂主人」は、ある意味において、井伏鱒二の代表作とも言える長編小説である。
骨董屋が料亭を始めるものの、金持ちと女に翻弄されて店から追い出されてしまう。
見栄張りで強情なところのある不器用な中年男の生き様は、確かに映画としても楽しめそうなストーリー展開だが、この作品の魅力は、そうしたストーリー展開そのものよりも、主人公の加納夏麿が関わる多くの人間たちとの駆け引きの綾にある。
料亭を始めるにあたって相談を持ちかけた出資者との駆け引き、料亭の相談役として入りこんで来た茶の湯の女師匠との駆け引き、さらには、骨董を売り買いしながらぼろ儲けを狙っている骨董仲間たちとの駆け引きなど、この小説を読んでいると、人生とはまさしく駆け引きのことなんだと気づかされる。
その駆け引きの綾が、「蘭々女はもう珍品堂の生活に深く立ち入っている存在でした。たとえば鰻の尻尾が籠の目を探り当てるように、するりと細い隙間から入って来たのです」などというような、絶妙の表現で描かれていくところに、この小説の醍醐味があると言えるだろう。
さあ、嬉しくってたまらない。掘出しだ、掘出しだ。
さらに、もうひとつ、この小説の魅力、あるいは最大の醍醐味ということを語れば、それは、骨董の魅力に憑かれた男の描写である。
例えば、飲み屋の女を浅草まで連れ出したとき、珍品堂は古道具屋のショウウィンドウで掘出物を見つける。
地下鉄に乗ろうと思って虎の門に来ると、古道具屋があるのでショウウィンドウをちょっと覗きました。すると一尺四方くらいな赤い毛氈を敷いて、下げ燈篭を一つ置いてある。鉄の打物だけれども、六角型で火屋の窓が古建築の蔀戸みたいな造りになっている。実に見事だ。震いつきたいほどでした。全財産を投じても買おうと思いました。胸が動悸をうちはじめていました。(井伏鱒二「珍品堂主人」)
骨董好きが掘出物を見つけた瞬間の感動がリアルに伝わってくる。
あるいは、蘭々女に一杯食わされて、新薬師寺の本尊そっくりの顔をしている白鳳仏を手に入れた場面。
さあ、嬉しくってたまらない。掘出しだ、掘出しだ。家に帰って仏像を床の間に安置すると、一つびっくりさせてやれとばかりに、骨董仲間の来宮に電話をかけたところが留守でした。では、さっそく唐津のおあずけで稼いでやれと、小石川の八重山のところへその徳利を持ちこむと、これは贋だから買いたくないと云うのです。(井伏鱒二「珍品堂主人」)
レアなアイテムを手に入れて、「さあ、嬉しくってたまらない。掘出しだ、掘出しだ」と踊るように家へ帰ってくる様子が目に見えるようである。
さらに、一緒に手に入れたおあずけ徳利を骨董仲間に売りつけようとしたところ、「これは贋だから買いたくない」と、早速、仲間同士の駆け引きが始まって、物語が脈を打ち続けていく。
男にとって骨董は女と同じようなもの
せっかく大きくした料亭を追い出されたとき、出資者の九谷さんは、鎌倉時代の瀬戸瓶子を送って寄こす。
箱の紐を解いて蓋をあけ、肩に丸みのある瓶子を取出すときには喉がごくりと鳴りました。大型の口で厚手ではあるが至って姿が上品です。肩付そっくりに肩が張っていて、総体に薄黄色いところへもって来て柿色に釉薬が濃く流れている。それを逆さにすると、ばらばらと穴あき銭がこぼれ出た。その一枚一枚は、嘗て珍品堂が歯ブラシで土を摺り落して手塩にかけておいたものであった。古銭愛好家の模造した穴あき銭ではないのです。(井伏鱒二「珍品堂主人」)
実は、この瀬戸瓶子は、かつて珍品堂が九谷さんに譲ったもので、「初め珍品堂が売り惜しみをして、さんざん九谷さんに口説かれてから手放すことにしたもの」であった。
「今、こうしてその箱を見ると、惜しみながら別れた可愛い女に再会したような気持でした」というようなところにも、骨董に対する珍品堂の愛情が感じられる。
ところで、かつて珍品堂に「骨董は女と同じだ。変なものを掴むようでなくっちゃ、自分の鑑識眼の発展はあり得ない。骨董にも女にも、相場があるようで相場がないものだ。持つ人の人格が相場である」と言ったのは、骨董仲間の来宮竜平だが、この来宮のモデルは小林秀雄だということが、巻末にある白洲正子のエッセイに書かれている。
こんなところにも、この小説の醍醐味があるのかもしれない。
書名:珍品堂主人
著者:井伏鱒二
発行:2018/1/25
出版社:中公文庫


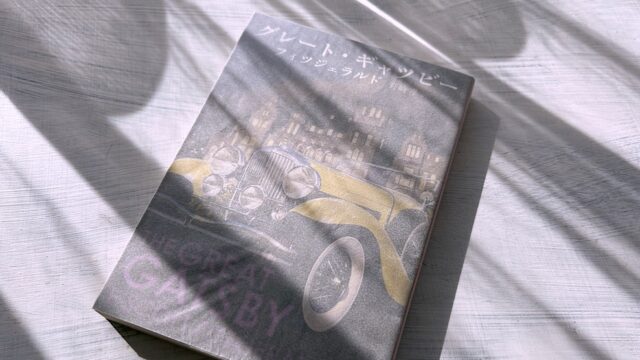




-150x150.jpg)









