庄野潤三「野菜の包み」読了。
本作「野菜の包み」は、昭和45年4月号の「群像」に発表された短篇小説である。
作品集では『小えびの群れ』(1970、新潮社)に収録された。
五人家族の愉快な日常風景のスケッチをベースにした作品。
「台所の隅に立てかけてあるハトロン紙の細長い包みが、「ぐらり」という感じで揺れた」という書き出しがいい。
「ハトロン紙の細長い包み」は、「いましがた妻が買って来て、そこへ立てかけた野菜の包み」なのだが、続いて「彼」(庄野さんのことだろう)は、ぐらりと揺れた野菜の包みの陰に、一匹のねずみを発見する。
咄嗟にねずみの逃げ道を塞がなければならないと考えた彼は、「ねずみ」と聞いただけで怖気づいている妻に指示を出す。
ここで、物語は「ハメルンの笛吹き」という童話の話になる。
「ハメルンの笛吹き」は、いったいどんな曲を吹いて、町中のねずみを誘い出したのだろう。彼の家にも笛はあることはある。中学二年の下の男の子が、音楽の授業で使っているのがある。もしかりに「ハメルンの笛吹き」の吹いた曲というのが分かっていて、それが幸いなことに練習次第では吹けないことはない曲であるなら、子供に覚えさせたらいいだろう。(庄野潤三「野菜の包み」)
しかし、下の男の子が笛の練習をしていると、途中できっとつかえる。
最初からやり直しては、何度も行きつ戻りつする。
それが夜ふけということもあってか、その笛の曲は、どれもみなはかなく聞こえた。
「あれでは、『ハメルンの笛吹き』の吹いた曲が分かって、中学生にも吹ける程度の曲であったにしても、無理だろう」と、彼は考える。
次に、物語は「ねずみ捕りの男」という絵の話へと続いていく。
それは、十七世紀のオランダの画家の展覧会を観に行った時のことで、数多く集められた銅版画の中に、一軒の家の前にねずみ捕りの男とその子供が立っていて、家の人に話しかけているところを描いたものがあった。
こうしてねずみを捕りながら、この親子は農家から農家へとまわっているのだろう。世の中にはさまざまな職業がある。いったいどうして習い覚えたわざか知らないが、彼はねずみという生きものを相手にこの世を生きている。田舎道を先に籠のついた変な棒を持った男と子供が並んで歩いているところを見かけたら、それはねずみ捕りの親子である。(庄野潤三「野菜の包み」)
これは、おそらく、レンブラントの『ねずみ捕り屋』を観た時の回想だろう。
 レンブラント『ネズミ捕り屋』アムステルダム国立美術館
レンブラント『ネズミ捕り屋』アムステルダム国立美術館「或いは、川岸につながれた小舟の中に、この二人が昼寝をしている姿を見ることがあるかも知れない」と、彼が想像を膨らませていく場面がいい。
そして、物語は、さらに、彼が小さな頃に読んだ、ドイツの漫画の本へとつながっていく。
たったの一匹だけれども、それはなかなか手ごわい相手であった
それは、外国へ行っていた父が、子どもたちへのお土産に買って来てくれたものだったが、「おそらく兄弟の中でこの本をいちばんよく読んだのは、彼ではないだろうか」と、彼は、当時を振り返っている。
最後に物語は、台所に置いた野菜の包みの陰にねずみが出て、彼と妻がねずみの逃げ道を塞ごうとしている場面へと戻ってくる。
下の男の子が小学六年の時、「三匹のねずみ」という唱歌を習った。外国の民謡で、輪唱に向いた曲である。「ねーずーみ三びーき」という歌詞で始まる。次に、おんなじ節で、「はーやいな、はーやいな」と云うから、いったいどこか知らないがそこいらの地面をねずみが競争するみたいに走りまわっているのかと思ったら、そのあとは、少し早口になって、「百姓のかみさん くわをふり上げては ねずみの尾をちょんと 切ります」となる。(庄野潤三「野菜の包み」)
「愉快な気分にならずには居られないような曲」を思い出しながら、彼は、自分が台所に閉じこめたのは、「ねずみ、三匹」ではなく、たったの一匹だということを考えた。
たったの一匹だけれども、それはなかなか手ごわい相手であることは、過去の経験から、彼にも妻にも分かっていることなのだった。
その後、ねずみがどうなったのか。
それは書かれていないので分からない。
書名:小えびの群れ
著者:庄野潤三
発行:1970/10/20
出版社:新潮社



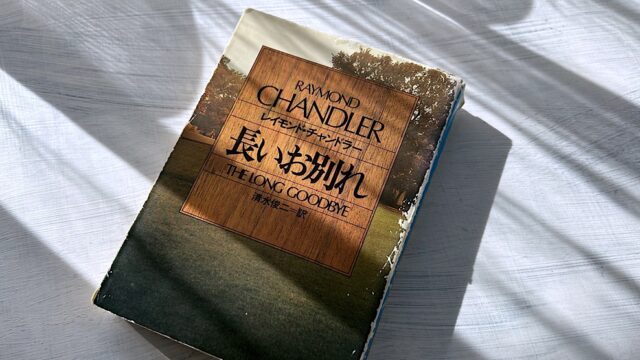



-150x150.jpg)









