井伏鱒二「黒い雨」読了。
本作「黒い雨」は、1965年(昭和40年)1月から1966年(昭和41年)9月まで『新潮』に連載された長編小説である。
連載開始時、著者は67歳だった。
なお、連載開始当初の表題は「姪の結婚」だったが、途中から「黒い雨」に変更された。
単行本は、1966年(昭和41年)10月に新潮社から刊行されている。
原爆投下直後の被爆地に降った黒い雨
「黒い雨」は、言わずと知れた、日本の原爆文学の最高峰に位置する作品であり、戦争文学としても、第一級の作品である。
「黒い雨」というのは、原爆投下直後の被爆地に降った雨のことで、「黒い雨訴訟」などのように、その言葉は現在も生き続けている。
主人公の閑間重松は、同居する姪の矢須子の結婚問題のことで思い悩んでいた。
縁談のたびに、矢須子が原爆病患者だという話が持ち上がって、うまく進んでいた話も必ず破談になってしまうのだ。
これが最後かもしれないという良い話が持ち込まれたとき、閑間重松は矢須子が被爆者ではないということを実証するため、原爆が投下された当時に書かれた矢須子の日記を公表することを決意する。
被爆の事実のないことが明らかになれば、矢須子が原爆病患者であるという噂も、科学的に証明することができるだろう。
さらに、重松は、矢須子の日記と重ね合わせるように、被爆者である自身の日記や、妻をはじめとする関係者の手記を織り交ぜながら、広島に投下された原子爆弾による被害の実情を、庶民の視点から再現しようとする。
この小説のほとんどは、矢須子や重松、その他関係者の日記あるいは手記によって構成されており、小説というよりも、むしろドキュメンタリーの手法に近い。
午前十時ごろではなかったかと思う。雷鳴を轟かせる黒雲が市街の方から押し寄せて、降って来るのは万年筆ぐらいな太さの棒のような雨であった。真夏だというのに、ぞくぞくするほど寒かった。雨はすぐ止んだ。私は放心状態になっていたらしい。夕立が降りだしたのはトラックに乗っていたときからではなかったかと思ったりした。私の知覚はずいぶん性能が下落していたに違いない。黒い夕立は私の知覚をはぐらかすように、さっと来てさっと去った。だまされたような雨であった。(井伏鱒二「黒い雨」)
この「黒い夕立」こそが、放射能を含んだ「黒い雨」であるが、日記を読んでいる重松は、そんなことを知らないから、矢須子は被爆していないものとばかり信じ込んでいる。
間もなく、矢須子は原爆病の症状を発症し、たちまち重体となってしまう。
それは、軽度の原爆病患者であった重松よりも、ずっと重症で、急激な悪化であった。
事実に裏打ちされたエピソード
「黒い雨」は、ひとつの戦争日記である。
厳密に言えば、戦争日記の姿を借りた小説作品なのだが、庶民の視点で多くの小説を書いて来た井伏さんらしい作品となっている。
それは、戦争の肯定でも、戦争の否定でもない。
戦争という歴史に翻弄されながら激しく生き続ける庶民の姿が、そこにはあるだけだ。
僕は耳をすましてその人たちの声を聞いた。それによると国道沿いの人家では、どの家でも雨戸を締めて避難者の立入りを避けている。可部線の三滝駅の手前の或る雑貨屋では、いつの間にか避難民の女が入って来て押入の中で死んでいた。雑貨屋の主人が引きずり出すと、纏っている着物はその家の娘の夏の晴着であった。(井伏鱒二「黒い」)
雑貨屋の主人が着物を剝ぎ取ると、女の焼死体は腰巻もパンツも履いていなかった。
若い女性だったから、水や食べ物を探すよりも、裸体を隠すことに一生懸命だったらしい。
「黒い雨」では、被爆当時の庶民のエピソードが、そのような手記の形を借りて、次から次へと登場してくる。
紛れもない事実に裏打ちされたエピソードだから、「戦争反対」などというスローガンよりも、ずっと心奥深くまで響いてくるものがあるのだろう。
被爆した人間の悲しみと、避難者たちに関わり合おうとはしない人間の悲しみ。
その双方が描かれているところが、この小説の持つ大きな説得力の根拠だと思った。
書名:黒い雨
著者:井伏鱒二
発行:1970/6/25
出版社:新潮文庫

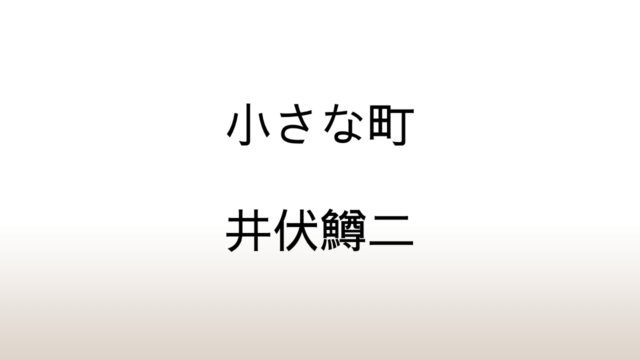
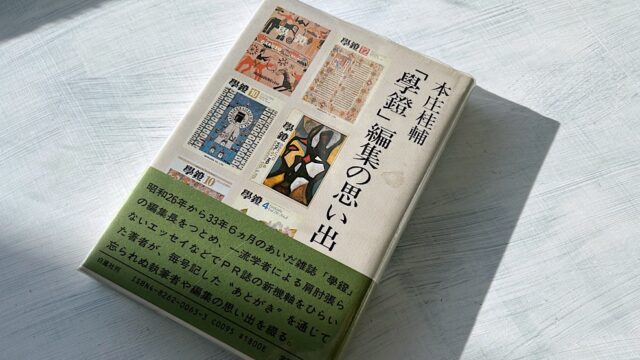



-150x150.jpg)








