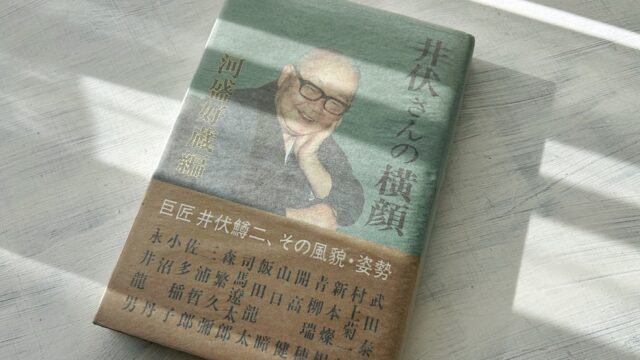村上春樹「パン屋襲撃」読了。
この作品は、1981年の「早稲田文学」に発表された短篇小説である。
単行本としては『夢で会いましょう』(糸井重里との共著)に「パン」というタイトルに改題されて収録された。
なお、今回は『村上春樹全作品 1979〜1989(第8巻)』に収録された「パン屋襲撃」を読んだものである。
パン屋の提案は「ワグナーを好きになること」
腹を空かせた二人の男たちがいる。
彼らはもうまる二日水しか飲んでいなくて、一度だけひまわりの葉っぱを食べてみたものの、もう一度食べたいという風には思えない。
思い余った二人は、包丁を持ってパン屋に出かけた。
パン屋は商店街の中央にあって、布団屋と文房具屋に挟まれている。
パン屋の主人は、頭の禿げた、五十過ぎの共産党員だった。
共産党員のパン屋を襲うことに興奮した彼らは、ヒットラー・ユーゲント的な感動さえ覚えながら店へと押し入る。
店内では、だらしない買物袋を提げたオバサンが、どのパンを買おうか悩んでいる。
最初に彼女は揚げパンとメロンパンをトレイに乗せるが、しばらく考えた末にメロンパンを棚へと戻し、また少し考えてからクロワッサンをふたつ、トレイに乗せた。
なかなか店内から出ていかないオバサンに、<僕の相棒>は苛立つが、<僕>は彼女が買物を終えて出ていくのを、辛抱強く待っている。
やがて、オバサンの買い物が終わり、彼らは「とても腹が減っているんです」と、主人に打ち明ける。
「そんなに腹が減っているんならパンを食べればいい」主人は言った。「でも金がないんです」「さっき聞いた」と主人は退屈そうに言った。「金はいらないから好きなだけ食べりゃいい」(村上春樹「パン屋襲撃」)
しかし、他人の恵みを受けるわけにはいかない彼らは、店主の提案を拒絶する。
次に、店主は「じゃあこうしよう。君たちは好きにパンを食べていい。そのかわりワシは君たちを呪ってやる」と言い出すが、僕の相棒は「俺は嫌だね。呪われたくなんかない」と、この提案も受け入れることはできない。
結局、店主は、二人がワグナーを好きではない、ということを確かめてから、「ワグナーを好きになってくれたら、パンを好きなだけ食べさせてあげよう」と、交換条件を持ちかける。
二人はワグナーを好きになり、パン屋と一緒に『トリスタンとイゾルデ』を聴きながら、お腹いっぱいにパンを食べて、満ち足りた気分になる。
ワグナーによってパン屋に取り込まれた若者たち
この物語のポイントは、空腹の若者たちがパンを食べるために、パン屋の提案を受け入れて、好きでもないワグナーを好きになるという部分にある。
共産党員であるパン屋の主人の提案を受け入れることは「共産党を受け入れる」というメタファーであり、ワグナーを好きになるということは「ナチズムを受け入れる」というメタファーでもある。
おそらく、村上春樹は、政治的な偏りを払拭するために、あえて「ワグナーファンの共産党員」という、相反する思想をひとつに抱えたキャラクターを作り出したものだろう。
大切なことは、共産党かナチズムかという二択ではなく、空腹を満たすために、二人の若者が自分たちの心をパン屋に譲り渡したという事実である。
おそらく、二人の若者が自分たち(の生き方)を守るためには、「ワグナーファンの共産党員」を殺してしまうという選択肢しかなかったはずだ(彼らはそのつもりで包丁を持参していた)。
しかし、彼らは、パン屋の主人の呪いを恐れ、最終的に「ワグナーを好きになる」ことを選択する。
その結果、彼らはお腹いっぱいパンを食べることができて、満ち足りた気分で岐路に着くことができるのだ。
しかし、彼らの行為は「パンを食べるためにワグナーを受け入れる」ものであり、そこに読者は、何がしかの割り切れない気持ちを抱くことになる。
彼らは、貧困故に好きでもない「ワグナー(ナチズム)」や「共産党」を受け入れざるを得ないからだ。
この割り切れなさは、やがて、後日譚である「パン屋再襲撃」へと繋がっていくものだろう。
同じ物語を林芙美子が書いたら、もっと直接的で重たいものになるに違いないが、村上春樹はポップ・カルチャーの立場から、多少の諧謔味を感じさせつつ、貧困を描いているのだと感じた。
ところで、作品の冒頭で「神もマルクスもジョン・レノンも、みんな死んだ」という文章が出てくる。
この作品が発表される前年の1980年12月に、ジョン・レノンは暗殺されているのだが、もしも、ジョン・レノンだったら、果たして、パン屋の提案を受け入れてワグナーを好きになっているだろうか。
人間、主義や思想だけで食べていくことはできないということは、確かに事実だとしても。
作品名:パン屋襲撃
書名:村上春樹全作品 1979〜1989(第8巻)
発行:1991/7/22
出版社:講談社