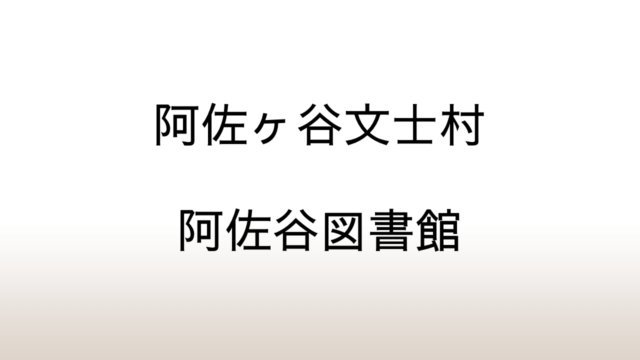永井龍男「胡桃割り」読了。
本作「胡桃割り」は、1948年(昭和23年)の「学生」に発表された短篇小説である。
胡桃割り思い出す父親の姿
それは、戦争は始まっていたが、日曜日には、まだ六大学野球を観ることのできた時分のこと。
友人と野球場を訪れていた<私>は、千駄ヶ谷で絵描きをしている中学時代の友だちを訪ねる。
食後に、彼はブランデーと一緒に胡桃を出して、それを古風な飾りのついた胡桃割りに挟んで割った。
「虚子の句に “秋もはや熱き紅茶とビスケット” というのがあるが、食後の胡桃とは、相変わらず洒落たもんだ」と友人が言うと、絵描きは「洒落ているということもないが、—じつは、今日は親父の命日でね」と言った。
親父の命日にまつわる胡桃割りの物語—。
<僕(絵描き)>が小学六年生で、中学へ入るための予習が毎日続いている頃、母の病態は、もうかなり悪くなっていた。
日光へ遠足に行く前々日、母にもしものことがあったら、遠足には行けないかもしれないと、姉が言った。
<僕>はふてくされて、父の書斎へ無断で入りこむ。
卓の上には胡桃を盛った皿があり、<僕>はナット・クラッカーで胡桃を割ろうとするが、胡桃の固い殻を割ることはできない。
かんしゃくを起こした<僕>は、ナット・クラッカーを叩きつけて、胡桃の皿を割ってしまう。
やがて、<僕>は中学に進んで間もなく、母は亡くなり、姉にも縁談が起こった。
姉が結婚してしまうと、この家は父と弟の二人になってしまう。
心配した姉は、<桂おばさん(死んだ母の遠縁に当たる未亡人)>に、家へ来てもらってはどうかと、<僕>に提案する。
ドキンとした。みんな、自分を可愛がってくれる人は行ってしまって、お体裁に、代わりの人を置いてゆこうとしている。—そんな気もした。「僕、嫌だ」(永井龍男「胡桃割り」)
姉は淋しそうに、そのまま黙り込んでしまった。
やがて、時が経ち、母の一周忌が来た。
久しぶりに、父の書斎で、親子三人が卓を囲んだ。
姉は間もなく結婚して、この家を出てゆく。
父は、会社の仕事に一区切り付けようと思う、というようなことを言った。
やけに老けて見える父の顔。
どうしたはずみか、桂さんのおもかげが、その時僕の眼に浮んできた。僕はちょっとあわてた。そして困って、胡桃を一つ摘むと、クラッカーに挟んで片手で握りしめた。すると、カチンと、快い音がして、胡桃は二つに綺麗に割れた。(永井龍男「胡桃割り」)
「お父さん。僕、桂さんに家へ来てもらいたいんだけど、、、」と、<僕>は言った。
胡桃は<僕>自身の殻を可視化したもの
胡桃は、もちろん、<僕>自身の象徴である。
幼い<僕>に胡桃を割ることはできないが、成長した<僕>は胡桃を割ることができた。
胡桃は<僕>自身の殻であり、その殻を割ったのは<僕>自身である。
シンプルなストーリーだが、心地良い風に吹かれているような、爽やかな気持ちになることができた。
旧制中学(現在の高校)に入ったばかりの<僕>は、少年と大人との端境期で生きている。
大人へのステップはいくつもあるに違いないが、そのひとつの象徴を可視化したものが、胡桃割りだったに過ぎない。
単調な少年成長譚に変化を付けるため、このエピソードを、主人公の古い友人である<絵描き>に語らせているところもいい。
導入の大学野球の光景から、奥さんの手料理、そしてブランデーと胡桃割りへと進んでいく流れも、ちょっとしたドラマを観ているようで楽しめる。
短編小説でドラマを仕立てるというのは、こういうことなのだろう。
作品名:胡桃割り
著者:永井龍男
書名:教科書名短篇 少年時代
発行:2016/4/25
出版社:中央公論社(中公文庫)

(2026/03/09 17:58:44時点 楽天市場調べ-詳細)