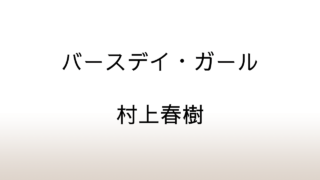安部公房「箱男」読了。
本作「箱男」は、1973年(昭和48年)3月に新潮社から刊行された書き下ろし長編小説である。
この年、著者は49歳だった。
この作品を構造的に理解することに意味はない
何度読んでもおもしろいけど、何度読んでも意味不明。
それが、本作『箱男』という長篇小説である。
実際『箱男』は、なんとも中毒性の強い作品だ。
ろくにストーリーも理解できないのに(ろくにストーリーを理解できないからこそか)、全部読み終えた後で、また最初に戻って読み始めてしまう(読まずにはいられない)。
ストーリーが難解なのは、複数の筋書きが、そうとは分からない形で、いくつも組み合わせられているからで、そのことに気がつくと、この作品を構造的に理解することに意味はないんだということが分かる(理解できないんだから)。
箱から出るかわりに、世界を箱の中に閉じ込めてやる。いまこそ世界が眼を閉じてしまうべきなのだ。きっと思い通りになってくれるだろう。(安部公房「箱男」)
構造的に破綻しているのに読んで楽しい、というのが『箱男』である。
場面展開の繋がりは曖昧で、何となく繋がっているような気持ちで読み進めて、結局は大筋さえ理解できていないという結論。
そして、再び始まる物語(最初から読み返す)――。
この作品を読ませる原動力となっているのは、<箱男>という不気味な概念である。
箱男的世界における新しい発見
<箱男>は、ダンボール箱を被った都市徘徊者(いわゆる浮浪者)である。
他者から見られることを拒絶する箱男は、箱の隙間から社会を覗くことによって自己の充足感を満たしている。
箱男が象徴するものは、管理社会からの逃避だ。
どこにも登録されない存在である箱男は、管理社会にコミットすることのできない存在でもある。
君だって、目撃したことくらいはあるに違いない。しかしそれを認めたくない気持も同じくらいよく分かる。見て見ぬふりは、何も君だけとは限らないのだ。(安部公房「箱男」)
社会の底辺でさえないという点において、箱男は乞食や浮浪者とも違う。
ダンボール箱によって匿名性を確保した箱男は、傍観者としての立場から社会を観察しているだけだ。
「匿名の存在」という点で、箱男はインターネットのSNSにおける発言者にも似ているが、実際のところ箱男は、自分から社会へコミットすることはないので、SNS上の繋がりと同じではない。
あえて言えば、ネット掲示板において、匿名の発言をひたすら覗き続けているだけの「ROM(Read Only Member)」に近いかもしれない。
ダンボールの隙間を通して見る社会は均一化されていて、既存の価値観をすべて無効にしてしまう。
ところが、箱の窓を額縁にして覗いたとたん、すっかり様子が違ってしまう。風景のあらゆる細部が、均質になり、同格の意味をおびてくる。(安部公房「箱男」)
箱男的視点で世の中を見れば、これまで見えていなかったもの(価値がないと信じていたもの)が、随分と見えてくるに違いない。
箱男的世界が中毒性を有する理由の一つが、ここにある。
小説「箱男」はどこにも辿りつかないけれど、箱男的世界は、新しい発見の可能性を示唆してくれる。
どらえもん「石ころぼうし」と岡林信康『俺ら いちぬけた』
「箱男」の存在は、『ドラえもん』に出てくる「石ころぼうし」(1974、コミック第4巻)を思い出させる。
被ることによって、道端に転がっている石ころのように、社会から無関心な存在となってしまう帽子。
「石ころぼうし」の象徴も匿名性だが、のび太は、社会から認知されないことに恐怖を覚える。
管理社会にあっては、社会(例えば住民票など)に登録されていないことほど恐ろしいことはない。
のび太が脅えたのは、社会から断絶されてしまうこと(社会から見捨てられてしまうこと)の恐怖である。
一方の「箱男」(1973)は、自らの意思で社会からドロップアウトし、傍観者として生きていくことに生存の道を見いだす。
そこに、小市民・のび太と箱男との違いが明確にあるが、社会から匿名の存在になるという点で、石ころぼうしも箱男も、同じ機能を有していると言える。
1970年安保闘争の後の時代、人々の関心は「無関心な存在(匿名性)」へと転換しつつあったのだろうか。
1971年(昭和46年)には、岡林信康が『岡林信康アルバム第3集 俺ら いちぬけた』を発売している(♪死にたくないから町を出るんだ~)。
70年安保闘争の後の虚無感の中で、「市民社会からの逃避」は、一般市民に与えられたひとつのテーマだったのかもしれない。
「箱男」の面白さは小説的欠陥の中にある
本作「箱男」を筋書きで追っていったとき、「箱男の記録ノートを書いているのは誰か?」という問題で行き詰まる。
ノートを書いているのは、箱男のようであり、贋箱男のようでもあり、作者本人(!)であるようにも読めるからだ。
「そう、ぼくが書いているのかもしれない。ぼくのことを想像しながら書いている君を想像しながら、ぼくが書きつづけているのかもしれない」「なんのために?」「箱男を告発するために、その実在を印象づけようとしているのかな」(安部公房「箱男」)
「誰がノートを書いているのか」という謎は、この物語の大きなテーマにもなっているのだが、メタフィクション的構造と入れ子構造とが複雑に重ね合わせられた上に、論理的な矛盾も孕んでいるから、事実解明をすることは容易ではない(というか無理)。
小説として重大な欠陥があるようにも思えながら、「箱男」の面白さはその小説的欠陥の中にある、というあたりが、そもそも矛盾。
というか、地の文章の他に、モノクロのスナップ写真(!)や新聞記事、供述書、詩などがコラージュ作品のように組み合わされている『箱男』という作品を、通常の小説のように読み解くことは不可能だろう(そして、文学好きは、なぜかここに惹かれる)。
全体を追いかけ続けていると、メビウスの輪のように際限がないが、作品を構成しているエピソードや、一つ一つの文章を読み砕く快感が凄い。
なにしろ、ツッコミどころ満載なので、こればかりは、実際に読んでみないと分からない。
ちなみに、<箱男>は29歳の若者で、見習看護婦の女の子に恋をして、3年間も暮らし続けた段ボール箱を、危うく手放してしまいそうになる。
そこに、看護婦の雇い主である<贋箱男>が現れて、箱男と贋箱男は、どちらが本物の箱男かを争うことになるのだが、さらに、小説の作者が入りこんできて、何がなんだか分からなくなるというのが、大雑把なストーリー。
本物と偽物というのは、この物語の大きなテーマだ。
作品名:箱男
著者:安部公房
発行:2005/5/25
出版社:新潮文庫






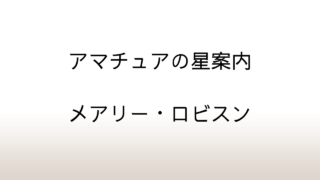
-150x150.jpg)