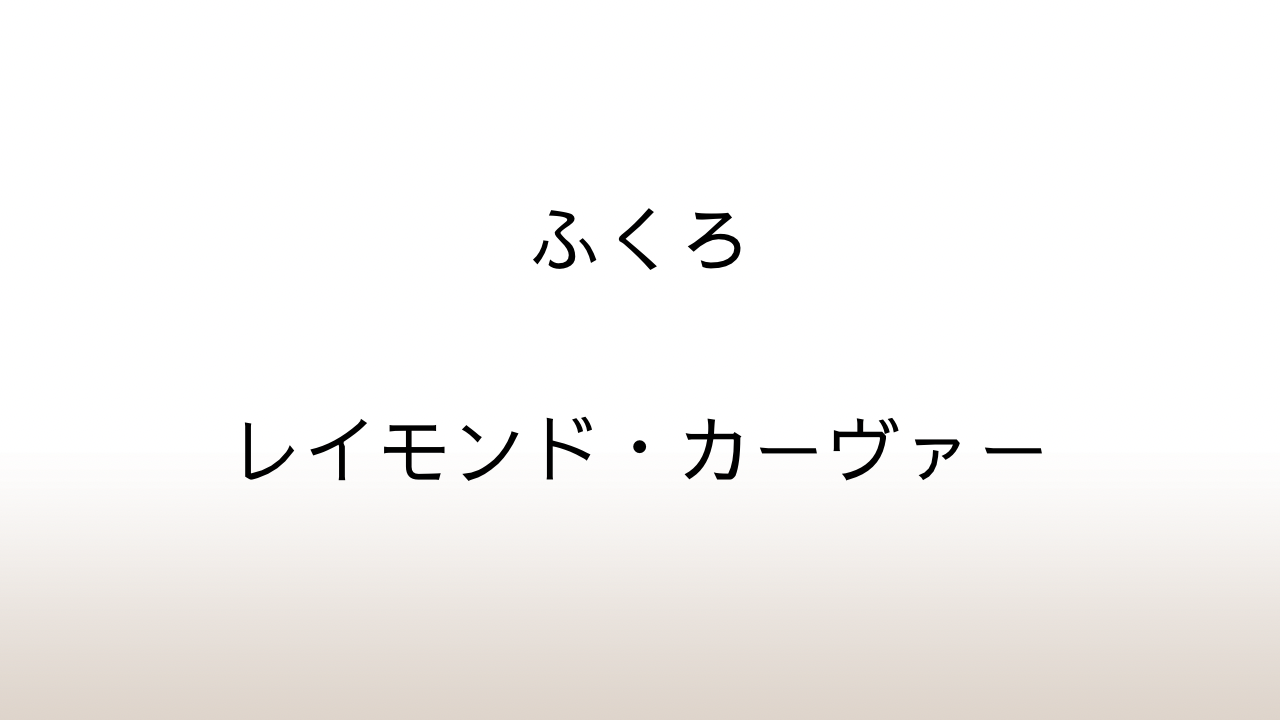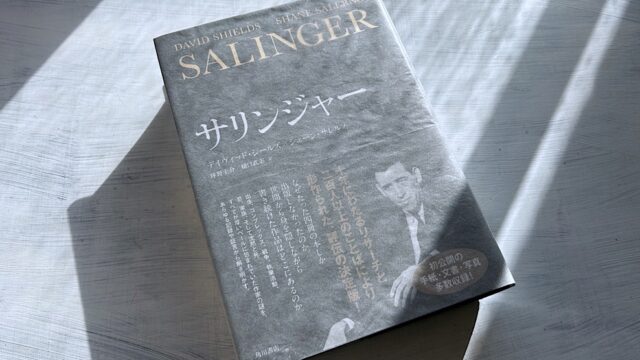レイモンド・カーヴァー「ふくろ」読了。
本作「ふくろ」は、1974年(昭和49年)の冬に発表された短篇小説である。
この年、著者は36歳だった。
原題は「Sacks」。
作品集としては、1981年(昭和56年)4月にクノップフ社から刊行された『愛について語るときに我々の語ること』に収録されている。
日本では、1990年(平成2年)に晶文社から刊行されたアンソロジー『アメリカ小説をどうぞ』(片岡義男編集)に、松本淳の翻訳で収録されている。
離婚して別れた父親との再会の物語
本作「ふくろ」は、1983年(昭和58年)5月『海』に、村上春樹の翻訳で発表された「菓子袋」と同じ短篇小説である。
村上春樹訳の「菓子袋」は、レイモンド・カーヴァーの作品集『愛について語るときに我々の語ること』に収録されていて、現在では、この作品は「菓子袋」という邦題で定着している(Wikiも「菓子袋」)。
当然、村上春樹訳で紹介すべきところなんだけど、今回『アメリカ小説をどうぞ』を読んで、松本淳訳も面白かったので、あえて「ふくろ」について書くことにした。
原タイトルは「Sacks」だから、普通に「袋」なんだけれど、小説の作品名としてはイメージが湧きにくいかもしれない。
この「袋」は、物語の語り手である<レス>が、久しぶりに再会する<父親>から貰った「白い菓子袋」のことである。
「メアリも子供も元気か?」父は言った。「みんな元気だよ」私は言ったが、事実というわけではない。父は白い菓子袋を開けた。(レイモンド・カーヴァー「ふくろ」訳・松本淳)
父親と会うのが久しぶりだった理由は、父が、彼の妻(レスの母)と離婚していたからである。
しかも、父親の浮気が離婚の原因だったためか、父親に対するレスの態度は、どこか冷たい。
この物語は、空港のラウンジで、離婚の原因となった父親の浮気のことを、レスが一方的に聴かされている場面を描いたものである。
「あのとき死んじまえばよかったと思ったもんだ」父は言った。頑丈な腕をグラスの両側に投げ出して。「あんたには教育がある。レス、公正な判断ができるだろう」(レイモンド・カーヴァー「ふくろ」訳・松本淳)
おそらく、父は、彼の言い分を理解してほしかったのだ。
同じ男である息子のレスに、自分の気持ちを理解してほしかったのだ。
本作「ふくろ」は、そんな父と子の再会の物語である。
生々しい家庭崩壊の現場
この物語のクライマックスは、浮気の現場を目撃したサリーの夫が、メチャクチャになってしまう場面である。
「要するにだ、あの男が滅茶苦茶になってしまったんだ。そうなんだよ。床にひれふして泣いた。彼女はキッチンだ。泣いて。ひざまずいて神に祈った。男に聞こえる激しい声で」父は続けて何か言おうとした。(レイモンド・カーヴァー「ふくろ」訳・松本淳)
浮気の代償の重さを、父はサリー夫婦の取り乱しぶりに見たのではないだろうか。
自分の離婚以上に生々しい家庭崩壊の現場に、父は立ち合ったのかもしれない。
しかし、それ以上、父は何かを言うことはなかった。
やがて、フライトの時間が来て、レスは父と別れる。
私は父と握手した。それ以来、父には会っていない。シカゴへの途上、私は父のくれた袋をカウンターに忘れて来たことに気がついた。べつにかまわない。キャンディーにしろアーモンドロカにしろ、メアリにはどうでもいいものだ。(レイモンド・カーヴァー「ふくろ」訳・松本淳)
父が持参した「菓子袋」は、息子に歩み寄る父の気持ちの象徴だったのだろう。
その父の気持ちに、レスは寄り添うことができなかった。
置き忘れた菓子袋は、どこにも行き場のなかったレスの気持ちの象徴である。
ところで、ラウンジのカウンターには、二人の男と腕を絡ませて笑っている女がいて、レスは、父親の話より、むしろ、そっちの女に気を取られているようだ。
もしかすると、レスもまた、父親と同じように、嫁ではない他の女と浮気をしているのではないだろうか。
あるいは、レスの嫁が、他の男と浮気をしているとか。
いずれにしても、父の話は、レスにとって関心のない物語ではなかった。
むしろ、まともに聴くに堪えない生々しい話だったのだ。
そして、父の会話の端々からほのめかされる母親の不貞の可能性。
「だれにでも間違いはあるさ」──。
その言葉は、もしかすると、父親にだけ向けられたものではなかったのかもしれない。
作品名:ふくろ
著者:レイモンド・カーヴァー
訳者:松本淳
書名:アメリカ小説をどうぞ
編者:片岡義男
発行:1990/6/30
出版社:晶文社