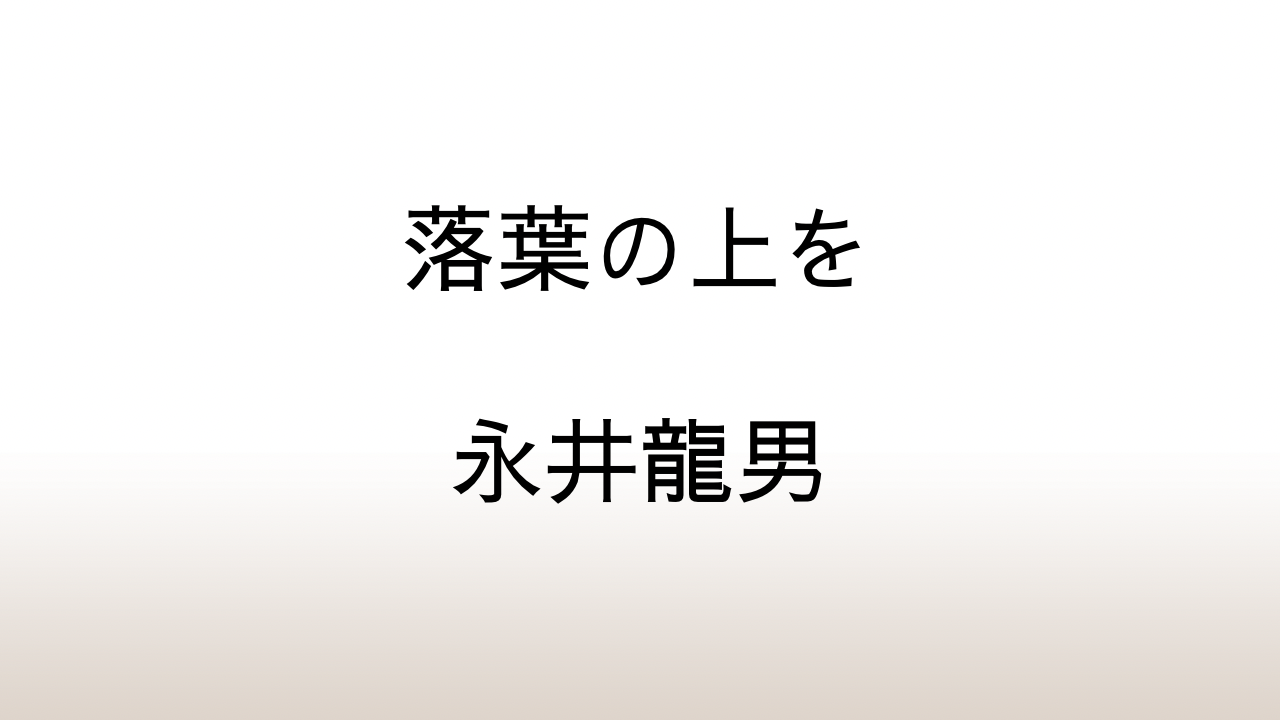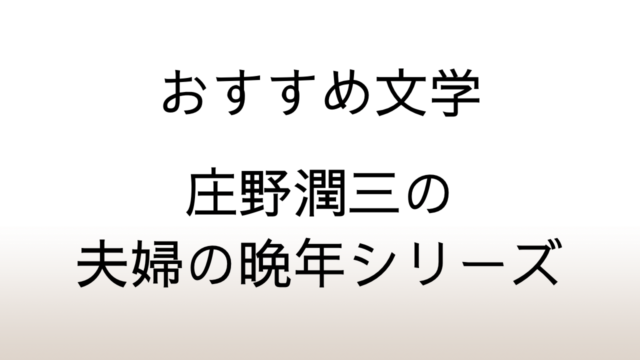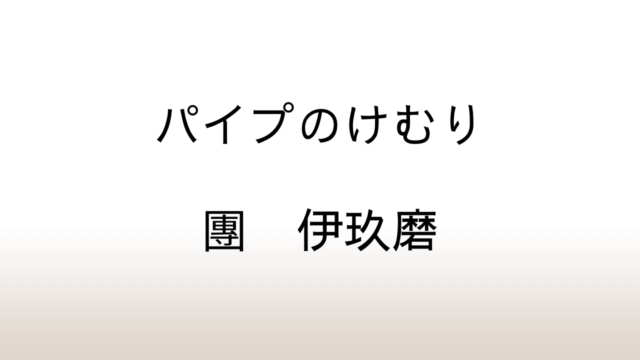永井龍男「落葉の上を」読了。
本作「落葉の上を」は、1987年(昭和62年)7月に朝日新聞社から刊行された随筆集である。
この年、著者は83歳だった(1990年に86歳で逝去)。
永井龍男の短篇小説を読む味わい
永井龍男の随筆を、最近の言葉で表現すると「エモい」ということになるのではないだろうか。
老齢の鎌倉文士の随筆に「エモい」はおかしいかもしれないが、感覚に訴える微妙な質感が、永井龍男作品の特徴だと思われる。
それは、特別に情緒的な表現ではなく、特別に感傷的な言葉ではない。
例えば、「豆をまく」という作品に、次のような一文がある。
「大学生おほかた貧し雁帰る」と、中村草田男の句が遺っているが、貧しいのは大学生ばかりではなかった。(永井龍男「豆をまく」)
草田男の俳句を引用しながら、「貧しいのは大学生ばかりではなかった」と自分たちの暮らしを振り返るところに、読者は深い共感を覚える。
これは、別に、俳句のエッセイでも、中村草田男についてのエッセイでもないのだ。
「階段」は、鎌倉文学館のTさんへの追悼文だが、「この世を離れた人を思うにつけ、この世に残った者の頼りなさが、身にしみて感じられる」「合掌を終え、私は四十五日間の眠りというものをしきりに考え続けた」など、印象的なフレーズが多い。
磨き込まれた文章というよりも、感覚的に湧いて出た文章という感じがする。
自分を「小作家」と称する、その感覚が、随筆作品の中にも反映されているのかもしれない。
「……まあ、この子がお嫁に行くんですものね、あたしたちが年を取るのも」眼鏡をかけた伯母が、丹念にスナップを見比べて、それから一枚一枚伯父の前に送ってよこす。「結婚式は結婚式だよ。写真をよくごらん。世の中は年寄りが多すぎる。それが、祝儀不祝儀にかこつけて集まりたがる。少しは、おれを見習ったらどうだ」(永井龍男「春の星」)
「結婚式は結婚式だよ。写真をよくごらん。世の中は年寄りが多すぎる」などという会話文には、永井龍男の短篇小説を読む味わいが、そのままある。
だから、永井龍男という作家は、随筆までおもしろいのだろう。
老齢の鎌倉文士の身辺雑記に漂う1980年代
鎌倉文士仲間である今日出海への追悼文「百日紅」はいい。
「あの頃はよかった。二人ともよく勉強したね」「酒が高くて、茶ばかり呑んでな」五年たち、十年たって顔を合せる度に、どちらからとなくそんな述懐が挨拶代りに口を出た。(永井龍男「百日紅」)
若い頃からの友人と一緒に年を取る。
年齢を重ねることの情感が、この随筆にはある。
入院中小康を得た折りには、奥さんに自己の葬儀通夜などについてそれとなく指示を与え「おれの居ないおれの通夜は、さびしいもんだろうな」と微笑したという。(永井龍男「百日紅」)
「おれの居ないおれの通夜は、さびしいもんだろうな」という、今日出海のつぶやきの切なさ。
また、別のところでは、入院中に「これはパパの大好きなアイスクリームよ」と娘が勧めたとき、「うん、おれが生きていた間はなあ」と、今日出海は微笑したとある。
ある意味で、今日出海らしい言葉を、永井龍男が巧みにすくい上げているということかもしれない。
ところで、「赤飯」という作品は、野球に関する著者の思い出を綴った随筆だが、ちょうど日本シリーズの季節だったらしい(一連の随筆は朝日新聞に連載されていた)。
それは、1985年(昭和60年)の日本シリーズのことで、阪神タイガーズと西武ライオンズが日本一を争っていた。
五時のニュースで、バースが三点ホームランしたことを知る。少し雲はあったが、第二戦も申し分ない日曜日であった。(永井龍男「赤飯」)
老齢の鎌倉文士の身辺雑記。
それが、本書『落葉の上を』に通底する大きなテーマで、さりげなく1980年代後半の空気が感じられるところも楽しいと思った。
書名:落葉の上を
著者:永井龍男
発行:1987/7/25
出版社:朝日新聞社