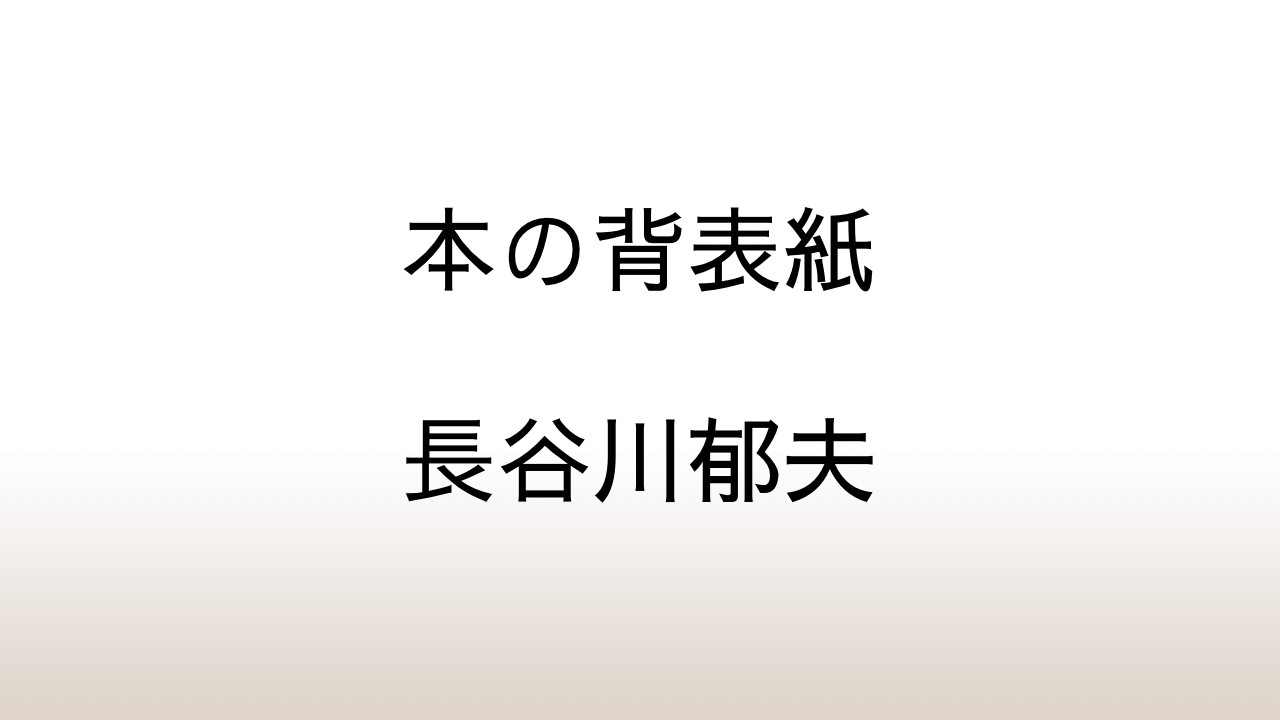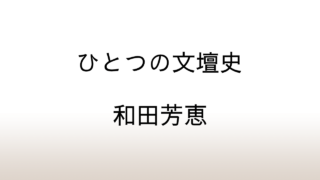長谷川郁夫「本の背表紙」読了。
本作「本の背表紙」は、2004年(平成16年)6月から2007年(平成19年)5月まで『静岡新聞』読書面に連載されたエッセイ集である。
連載開始の年、著者は57歳だった。
単行本は、2007年(平成19年)12月に河出書房新社から刊行されている。
季節感に重点を置いた文芸評
著者の長谷川郁夫は、1972年(昭和47年)に小沢書店を創立した人である。
編集者として、多くの作家と交流を重ね、その思い出を本書に綴った。
本書の「おわりに」で、著者は「現代文学のなかに季節感が消えてゆくのを残念に思う」と綴っている。
合理主義という、科学技術信奉のオプティミズムは、文学から季節を奪った。暮しのなかから陰翳が、つまりは心の宿る場所が喪われたと観察される。生活の実際面が明るくなったぶん、文学は曇ったのだといえるかも知れない。(長谷川郁夫「本の背表紙」)
著者は、本書で「季節感」に重点を置いた文芸評を展開している。
春夏秋冬で章が構成され、各随筆のタイトルが季語になっているのも、季節感にこだわって文芸作品と向き合ったことの証だろう。
登場する作品や作家は、とりわけ著者と交流の深かった人か、あるいは、著者の関心の高かった人たちだと思われる。
例えば、「夏の章」に、永井龍男の「青梅雨」がある。
東京生まれの小説家には、芥川龍之介以来、技巧派が多く、難解な短篇を書く。久保田万太郎など俳諧趣味、芝居好きも共通した特徴。省略という技法に凝り、また、粋で自然な流れの会話体を身上とする。永井氏は、石川淳とともに江戸っ子作家の最終走者だった。(長谷川郁夫「青梅雨─永井龍男」)
永井龍男は「冬の章」でも「山茶花」「十三夜」「蜜柑」と、何度も繰り返し登場する作家だ。
「東京・神田猿楽町に生まれ育った永井さんには、頑固な職人といった印象があった」「短篇小説の名手とされたのは、そこに完璧を目指す職人気質が感じられたからだろう」と、編集者の目から観た、客観的な作家論が続く。
今日の小説家としては珍しく、永井さんは生活上の行動半径が狭い人であったといえる。その小説・随筆の多くは身辺日常のこと、限られた交友関係をもととしたものだった。しかし、その確かな眼は、鎌倉の路地裏にも四季の移り変わりを見逃すことはなかった。(長谷川郁夫「山茶花─永井龍男」)
永井龍男の作品が多く登場するのは、永井龍男が季節感にこだわった作品を、多く提供してきたということなのかもしれない。
小沢書店から『小沼丹作品集』を出している小沼丹についての回想もいくつかある。
おそらく、小沼さんの追懐は、明治学院の中学に通うハイカラ少年時代の日々へと遡っていたことだろう。そう思うと、私の記憶の底から、小沼さんが酔って唄うエノケン・ソングの数々が聞こえて来る。たしか、「一杯のコーヒーから」などという歌もあった筈だ。(長谷川郁夫「珈琲挽き─小沼丹」)
随筆「珈琲挽き」から、小沼丹の懐かしい回想へと展開していく構成は、読んでいて心地良い。
そして、編集者の作家を観察する眼は確かなものだったと、感心させられる場面が多かった。
小沼さんの随筆に小鳥の話が多いことから、書くことが思い浮かばないまま、書斎の窓から庭先を眺めているのでしょう、などと憎まれ口を叩いて叱られたものだが、じつは、この庭先が小沼さんの「小宇宙(ミクロコスモス)」だった。その意味は、自らの文学世界を限定して、ささやかな幸福を描くことに徹したところにある。(長谷川郁夫「目白─小沼丹」)
小さいながら一つの世界(小宇宙)を極めることが、小沼文学の真髄だったのかもしれない。
ちなみに、小沼丹は「鰻屋─小沼丹・庄野潤三」でも、盟友・庄野さんとともに登場していて、これも楽しい話となっている。
亡くなった作家を偲ぶ追悼文
年齢的なこともあるのかもしれないが、本書では亡くなった作家を偲ぶ追悼的な文章が多い。
飯田龍太さんが亡くなった。一度も会ったことがないのに、寂しく思うのは、井伏鱒二の読者としてこの俳人に親しみを感じていたからだ。堀口大学さんが晩年、甲州にはじめて飯田家を訪ねた秋の一日のエピソードもあった。(長谷川郁夫「春霞─飯田龍太」)
「ヴィーナス─堀口大学」では、<新詩社以来の終生の友・佐藤春夫を喪った>堀口大学の悲しみを綴っている。
堀口さんは葬儀委員長として、「また会う日あらば必ずまず告げん友に逝かれる友の嘆きを」などという挽歌五首を霊前に捧げた。(長谷川郁夫「ヴィーナス─堀口大学」)
「友に逝かれる友の嘆きを」というフレーズに、堀口大学の嘆きが凝縮されている。
とりわけ親交の深かった吉田健一は「健一忌─吉田健一」で登場。
健一忌などという語は、歳時記にはない。しかし、八月三日には、できれば明るい午後のうちから、ギネスを傍らに、吉田さんの時間に浸りたい。(長谷川郁夫「健一忌─吉田健一」)
酒をこよなく愛した吉田健一にふさわしい随筆だと思う。
酒の話では「中秋名月─井伏鱒二」もいい。
いうまでもなく、詩作は井伏さんの余技である。遊びの精神から生まれたもの。引用の二篇は、日本酒讃歌であり、友を恋うる歌であった。酒は友を呼ぶ。井伏さんは、まことに男ごころの機微を知る人だった。(長谷川郁夫「中秋名月─井伏鱒二」)
「われら万障繰りあわせ/よしの屋で独り酒をのむ」(逸題)と「コノサカヅキヲ受ケテクレ/ドウゾナミナミツガシテオクレ/ハナニアラシノタトヘモアルゾ/「サヨナラ」ダケガ人生ダ」(勧酒)は、まさに日本酒讃歌と呼ばれるにふさわしい作品だった。
井伏鱒二に関しては、小沼丹の口利きで色紙をもらったときの思い出を綴った「凧─井伏鱒二・草野心平」も良い話である。
編集者の目から作家観に共感
本書では、編集者の目から見た作家観についても、参考になる文章が多い。
例えば、「葉桜─幸田文」では「文さんの作品の底には、いつも隅田川の水が流れている」と、幸田文の文学を短い言葉で表現する。
開高健は「動物精気を感じさせる文学」で、井伏文学は「自然のなかでの人間の愚かさを、愛情ある眼差しで描き続けたもの」、田中小実昌の小説には「自由人の体臭が感じられる」のであり、それが「いわゆる全共闘世代に支持された最大の理由といえるだろう」と分析する。
作品解説も鋭くて、安部公房「砂の女」で描かれる「自由」は、「ベルリンの壁の崩壊以前の語として生きている」のであり、「共同体の連帯意識は、組織を指す政治的な喩えだろう」と読み解く。
立原正秋の「罌粟の花」に出てくる「白い花」は「戦後的虚無の象徴」、後藤明生の「吉野夫人」は「追分という場所の記憶の古層をめぐる作品だった」と考察する。
「どの土地にも、そこに根差した記憶(物語)がある」「それを掘り起こすのも文学(言葉)の力だろう」という文学観にも共感できる。
つまり、本書『本の背表紙』には、共感できるフレーズが非常に多かった、ということだ。
特に強く共感できたものに、福原麟太郎について触れた「手毬─水上勉・福原麟太郎」がある。
その後「チャールズ・ラム伝」を読み、「われ愚人を愛す」「本棚の前の椅子」などの随筆集を古本屋で蒐めて、一通り揃えてしまうほどに愛読した。そこから私は、この国の文学のなかに、豊かな大人の文章の世界があることを教えられた。健康な文学。それを日だまりの匂いのする文学といってもよい。(長谷川郁夫「手毬─水上勉・福原麟太郎」)
もうひとつ、井伏鱒二を語った「尊魚堂主人─井伏鱒二」も外してはいけない。
井伏さんの絶筆は、著作目録に従えば、「心の森林浴」。「開高健全集」の推薦文だった。この言葉は元来は開高健が使ったものの引用だが、井伏さんの文業をあらわすにも相応しい語と思う。屈託ある日、井伏さんの文章に触れると、こころ和む気がするのである。(長谷川郁夫「尊魚堂主人─井伏鱒二」)
文芸のプロだから当たり前なんだろうけれど、すべてのページに日本文学に対する深い愛情と洞察が感じられる。
こんな教養を持った大人になりたいと、改めて思った。
つまり、自分は、教養ある大人が好きなんだな。
裏を返すと、自分は教養のない大人が好きじゃないんだな。
今更ながらに納得。
書名:本の背表紙
著者:長谷川郁夫
発行:2007/12/25
出版社:河出書房新社