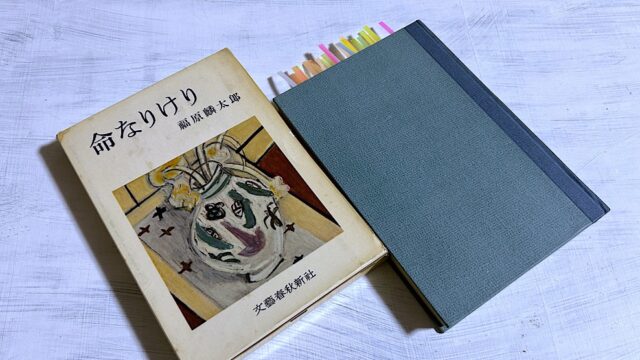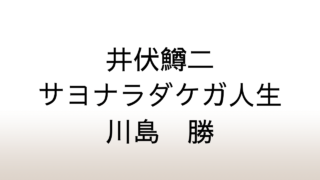庄野潤三「自分の羽根」読了。
本作「自分の羽根」は、1968年(昭和43年)2月に講談社から刊行された随筆集である。
この年、著者は47歳だった。
庄野潤三という作家の源流
最初に「あとがき」を読む。
私は短い文章を読むのが好きで、短ければ短いほど気に入るという性質がある。それで、この本にも出来るだけ枚数の短いものを拾い上げるようにした。おが屑みたいなものがまじっているが、お許し頂きたい。(庄野潤三「自分の羽根」あとがき)
「おが屑」というところに、庄野さんらしさがある。
そして、本書を読み終えた後で、この第一随筆集の性格が、ほぼ「あとがき」に集約されていたことが分かる。
同じように、庄野潤三という作家の全仕事を理解した上で、この随筆集を読むと、ここに庄野潤三という作家の源流があることを、間違いなく見出すことができる。
その象徴が「私は自分の経験したことだけを書きたい」と宣言している表題作「自分の羽根」だ。
つまり私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい。私の羽根でないものは、打たない。私にとって何でもないことは、他の人にとって大事であろうと、世間で重要視されることであろうと、私にはどうでもいいことである。人は人、私は私という自覚を常にはっきりと持ちたい。(庄野潤三「自分の羽根」)
そして、庄野さんは、作家として、生涯自分の前に飛んで来た羽根だけを打ち続けた。
恐ろしい意志だと思う。
ガンビア時代の友人、散髪屋ジムから届いたクリスマス・カードの話もいい。
「潤三、ケニオンのフットボール・チームは第一戦に勝った。それから残りの試合に全部負け、最後にハイラムにも勝った。今年はなかなかいいチームだった」これを見ると、一回でも二回でも勝つと大変いいチームということになる。他の人が聞いたらおかしいだろうが、私はジムのような考え方が本当は好きである。(庄野潤三「散髪屋ジム」)
病気見舞いに春らしい花をいっぱい持っていこうと考える「病気見舞い」も庄野さんらしい一篇だ。
「いっぱい包んで下さい」私はそう云ったが、主婦が赤やピンクのを一本ずつ抜き出して、「このくらいですか?」「いや、もっと」と云ってるうちに、主婦がこれでいくらですというのを聞いて、あわてて、「いや。そのくらいで結構です」と止めた。どっさりとは言えない数で、まことに残念であったが、春を知らせる花がそんなに安い値段でないというのはいいことだ。(庄野潤三「病気見舞い」)
「春を知らせる花がそんなに安い値段でないというのはいいことだ」という文章に、庄野さんの人生観がある。
そういう意味で、この随筆集では、庄野さんの人生観を明確に読むことができる。
なにしろ、「多分こういう感情は現代向きではないかも知れないが、それならそれで私は自分が現代向きでないことの方を喜ぶのだ」(「弟の手紙」)のような一文にさえ、生き方に対する強いこだわりが感じられるくらいだ。
サラリーマンを辞めて、独立したばかりの作家としては、むしろ強い姿勢を持たなければ、人生に勝てなかったということなのかもしれない。
何故やめたか? それにはどう答えればいいだろうか。(略)会社員である自分と作家である自分を毎日の生活の中で均衡をもたせて行くための無理が、とうとう堪えられなくなったからだ。それは、体力的にもむろんそうであったが、何よりも精神的に強い苦痛となった。(庄野潤三「憂しと見し世ぞ」)
思うに、この頃の庄野さんは、相当に張り詰めた精神状態を保ち続けていたのだろう。
些細な一文に、攻撃的とさえ感じられるくらいの鋭さを見つけることがある。
あるいは、それは、庄野潤三という作家の若さであったかもしれない。
私は小説が書けないときに、「死せる魂」を取り出して、どこでもいい、チチコフが馭者セリファンと三頭の馬とともにどこかの地主のいる村めがけて馬車で駆けているところを開いて読んでみる。そうすると、気持がほぐれて来て、「何もくよくよすることはない」と考える。(庄野潤三「ゴーゴリ」)
ゴーゴリ「死せる魂」の翻訳は、おそらく横田瑞穂だろう。

「生牡蠣」の中に、横田瑞穂と小沼丹の名前が登場している。
もう四年も前のことになるが、私たち三人は、毎週一回、きまった日に顔を合せて、よくビールを飲みながら呑気なおしゃべりをして、時間を過したものであった。そういう一年があった。(庄野潤三「生牡蠣」)
近年、横田瑞穂宛てに献呈された署名本が、売りに出たことがある。
庄野潤三や小沼丹の書いたものもあり、いたたまれない気持ちになって、僕はそのうちの何冊かを買った。
なにしろ、この「生牡蠣」が書かれた時からでさえ、50年以上の時が経っているのだ。
庄野さん流に言えば「チェーホフの小説に、「何事も神様のみ心でさあ」という馭者が出て来る」(「無精な旅人」)ということになる。
すべてを受け入れるところから、庄野さんの文学は始まっていたのだろう。
石神井公園から生田の山へ
東京で庄野さんは、最初、石神井公園に住んだ。
「静物」の舞台となった釣り堀のある街である。
私は石神井に八年間いたが、この釣堀に入って自分で釣ってみたのは二回だけであった。一回目は釣れたが、二度目は一尾もかからなかった。(庄野潤三「石神井公園──文学の東京」
生田へ引っ越す前には、一時的に借家住まいをしている。
去年の十二月に私たちはそれまで七年暮していた石神井の家を引き払って、駅にもう少し近いところにある借家に移った。新しい家が出来るまでの僅かな間の仮り住居であった。(庄野潤三「豆腐屋のお父さん」)
いよいよ、生田の山が登場するようになると、庄野文学の本格的な幕開けだという気がする。
始めは道路より少しでも高いところへ建てたいと思っていたが、こんな山の上に住むようになるとは思わなかった。人は高台というかも知れないが、私は頑固に山と思っている。(庄野潤三「フクロウの声」)
青柳瑞穂の家で骨董品を見せてもらったのも、この頃のことだろう。
もうとっくに夜になっていた。さっきからピアノのいい音色が聞えてきたが、それも終った。小学校四年生のお孫さんが練習していたのである。ピアノが止むと、ふくろうの声だけが庭にひびいた。(庄野潤三「青柳邸訪問記」)
ピアノを弾いていた「小学校四年生のお孫さん」は、『阿佐ケ谷アタリデ大ザケノンダ』の著者でもある、ピアニスト・青柳いずみこだ。
阿佐ヶ谷あたりで飲み明かした頃の話は「わたしの酒歴」に登場する。
阿佐ヶ谷にも知っている飲屋が一軒しかないわけではなくて、駅の踏切を中心として、夜更けの人気のない道を、この店からあの店へ、またあの店からこの店へと歩いて行くこともある。そんなとき、一緒に歩いている誰かが、空を見上げて、「何だか夜明けのような気がする」とつぶやき、ついでにここが東京の阿佐ヶ谷でなくて、イタリアのどこかの田舎町をほっつき歩いていることにしてはどうだろうと考えた。(庄野潤三「わたしの酒歴」)
当然、先頭にいたのは、井伏鱒二だったに違いない。
「地震・雷・風」は、「井伏さんと一緒にお酒を飲んでいる時、「あ、今云われたことは、よく覚えておこう」と思うことがある」という一文から始まる。
もちろん実際には、そんなことは不可能なのだが、そのくらい井伏さんの話は面白かったということらしい。
井伏さんの話は、聞いているその場で面白いと思ったら、あとは忘れた方がいいのかも知れない。話を聞くことが出来たのがそもそも幸運なのだから(私は実際、何度もそう思った)、もうそれでよい。(庄野潤三「地震・雷・風」)
こんなところにも、庄野流の人生哲学がある。
鮮明な生き方が、ただし、押しつけがましくはないところこそ、そもそも、庄野さんの生き方だったのかもしれない。
最後に、自分の一番好きな随筆をひとつ。
「豆腐屋はばかがやるもんだっていうが」とある時、彼は私にいった。「ばかだってできないや」根気がいる仕事なので、ばかならやれるものではない。そういう意味である。私はその言葉を聞いて笑った。豆腐屋の息子も一緒になって笑った。(庄野潤三「豆腐屋」)
まるで短篇小説のような味わいが、庄野さんの随筆にはある。
短い作品だからこそ、伝わるものもあるような気がする。
そう思ったとき、最初に読んだ「あとがき」のことを思い出した。
庄野さんの作品は「おが屑」にこそ注目しなければならないのかもしれない。
書名:自分の羽根
著者:庄野潤三
発行:1968/02/20
出版社:講談社