杉野健太郎「アメリカ文学と映画」読了。
本書「アメリカ文学と映画」は、アメリカ文学の<映画へのアダプテーション>に関する批評実践をまとめた論集である。
映画と原作との違いを指摘しながら、改変の意味や効果を探る
本書で採りあげられている文学作品は、アメリカ文学におけるキャノン(代表的作品)ばかりで、ホーソーン『緋文字』、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』、スタインベック『怒りの葡萄』、テネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電車』、チャンドラー『長いお別れ』、カポーティ『冷血』など、有名作品の名前が並ぶ。
ところで、映画にとって、文学作品が重要な素材であることは間違いないが、映画は時に原作(文学作品)を裏切ることがある。
「映画は、オリジナル(原作)に忠実でなければならない」といった固定観念が、映画のオリジナリティを批判することになるのだ。
しかし、文学作品の映画化を「アダプテーション(翻訳=置き換え)」として捉えたとき、映画は原作から解き放されて、独自のオリジナルティを有することになる。
「原作を解釈し、メディアを越えて行う翻訳(置き換え)」こそを映画化と考えれば、映画が原作に忠実である理由は必要ないからだ。
本書は、「原作に忠実か否か」といった議論をすることなく、映画と原作との違いを指摘しながら、改変の意味や効果を探るという部分に論点が置かれている。
例えば、本書で責任編集を務めた杉野健太郎は、レオナルド・ディカプリオ主演による、バズ・ラーマン監督の『華麗なるギャツビー』(2013)について、ギャツビーの死後のストーリーを、あえて、ニックとギャツビーの関係だけに絞ることによって、この作品のテーマの明確化に寄与していると指摘している。
[ニックとギャツビーとの関係は]ギャツビーとデイジーとの関係よりも大切な関係だ。この映画は、不道徳でごみのような人間であるとみなが打ち捨てるような人間が今まで出会ったなかで最も希望に満ちた人間であり、こんな人物とは二度と出会うことはないだろうというニックの理解に関するものなのだ。ニックがその物語を書いたギャツビーという名の男が実際になぜグレートかを理解する物語なのだ。(ブルーレイ特典映像「バズ・ラーマン監督によるイントロダクション」)
ラーマン監督の『華麗なるギャツビー』では、物語の語り手であるニックと恋人ジョーダンとの恋愛関係は、ほとんど省略されているが、それは、ギャツビーとニックとの友情関係こそが、この物語のテーマであり、その他の要素は可能な限り排除されているためだと、著者は考察しているのである。
映画のラストシーンで、ニックが、自らが書いた物語『ギャツビー』の表紙タイトルに「偉大なる」という文字を追加するのは、この作品は「ギャツビーがなぜ偉大な人物なのか」ということを描いた物語であるからだろう。
また、トルーマン・カポーティの『冷血』を扱った映画には、リチャード・ブルックス監督の『冷血』(1967)と、ベネット・ミラー監督の『カポーティ』(2005)がある。
村上龍の『1969』に登場する映画が『冷血』。高校生がデートで観る映画としては、あまりふさわしい作品ではなかった。
ここで、2本の映画が証明しているのは、トルーマン・カポーティという小説家の「ペンによる暴力性」だと、本稿著者の越智博美は指摘している。
このように2本の映画を通して見たときに、ノンフィクション・ノヴェルとしての『冷血』は、「ノヴェル」という用語の裏に、きわめて暴力的な、ペンによるアダプテーション作業を潜ませていたということが、遡及的に露わになる。そしてその暴力性こそ、作家本人に名声を与えもすれば、彼の心を苛むものでもあったのだ。(越智博美「そのまなざしを受けとめるのは誰なのか」)
こうした論考を読むと、文学作品の映画化は、文学作品を単純にビジュアル化するものではなく、文字列を映像に置き換えながら、原作者の内面に切り込んでいく作用を持ったものであるということが分かる。
映画と原作との違いを通して、文学作品をより深く理解する
ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』(1973)は、レイモンド・チャンドラーの原作を完全に越えた映画作品だった。
エリオット・グールドのフィリップ・マーロウ像は、かつてハンフリー・ボガートが演じたマーロウ像を完璧に破壊しているし、何より原作『長いお別れ』で、マーロウは、久しぶりに再会した親友テリー・レノックスを撃ち殺したりしない。
原作を読んだ後で、この映画を観た人はパニックになるし、先にボガートの『三つ数えろ』(1946)を観ていた人は、アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』に裏切られたと感じるだろう。
しかし、本稿著者の諏訪部浩一は、「そもそも『ロング・グッドバイ』が、同時代における「観客の期待」を裏切ることを目的(の少なくとも一つ)として撮られた映画」だと指摘する。
そして、アルトマン監督の狙いを考察しながら、原作の『長いお別れ』に登場するフィリップ・マーロウの変化に切り込んでいく。
この出口のないトートロジーは、この小説のマーロウを、前期作品よりもはるかに内省的にする(語り口も、「マーロウ」的な皮肉な比喩が減り、より直接的で「シリアス」な言葉が目立つ)。『長いお別れ』の彼は、ハードボイルド的な規範に基づいて行動するというより、その「規範」自体に、あるいはそれを抱えた自分自身に拘泥していると言ってもいい──(諏訪部浩一「裏切りの物語」)
アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』は、とんでもない映画だが、彼が、なぜ、そのような映画を撮ったのか?ということを考えることにより、我々はチャンドラーの『長いお別れ』と、一層親密になることができるのかもしれない。
このように、原作と映画との相違点を考察する作業は、実は、文学作品をより深く理解するための作業ともなっている。
そういう意味で、本書は映画論でもあり、文学論でもあるのだ。
書名:アメリカ文学と映画
編集:杉野健太郎
発行:2019/10/30
出版社:三修社

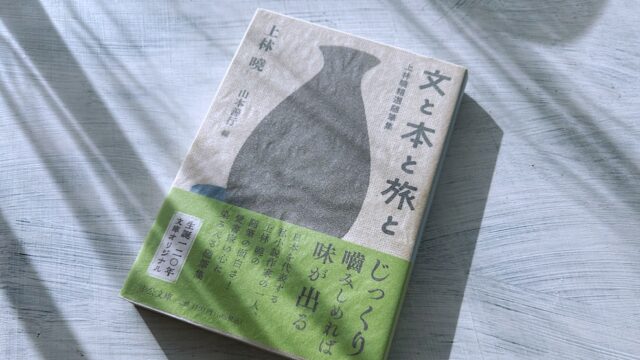
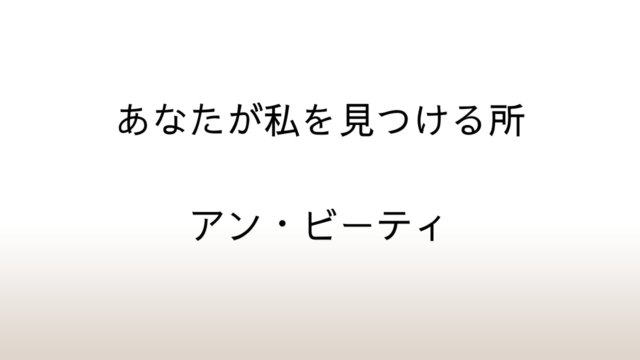



-150x150.jpg)









