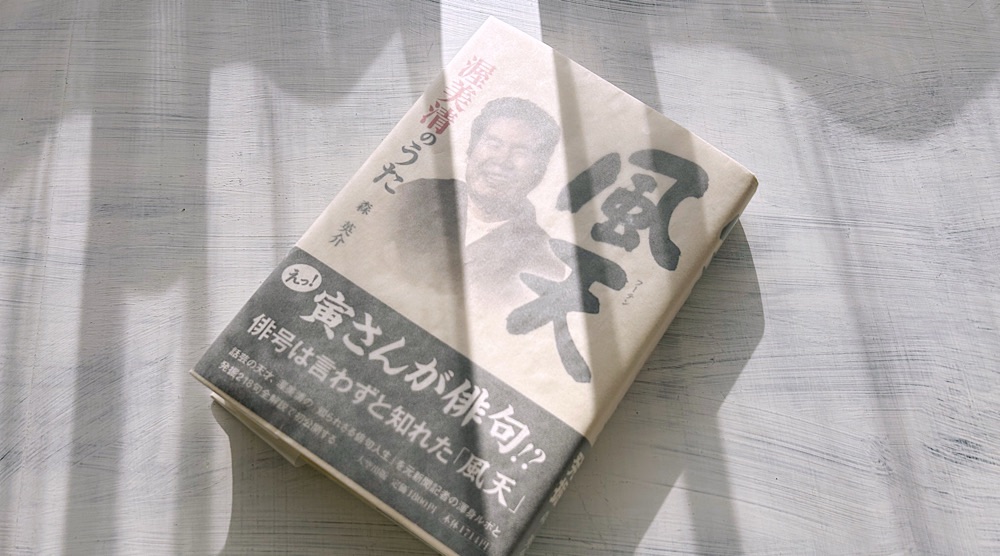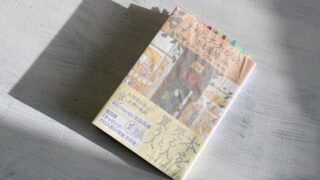森英介『風天 渥美清のうた』読了。
本作『風天 渥美清のうた』は、2008年(平成20年)7月に大空出版から刊行されたルポルタージュである。
人生を旅に重ねた男の粋な演出
フーテンの寅さんこと渥美清は、俳句を趣味としていた。
俳号は「風天(フーテン)」。
森英介編『渥美清句集 赤とんぼ』(2009)には、彼の死後に発掘された俳句223句が収録されている。
もっとも、渥美清は、俳句結社で活動していたわけでなく、作品披露は、彼が参加する(素人集団の)句会に限られていた。
森英介『風天 渥美清のうた』(2008)は、渥美清が参加した句会を訪ねて、風天の作品を発掘する過程をまとめたルポルタージュとして読むことができる。
渥美清が、初めて俳句を作ったのは、雑誌『話の特集』編集長(矢崎泰久)主催の「話の特集句会」である。
記録によると渥美清が「話の特集句会」に初めて参加したのは一九七三年三月。「男はつらいよ」シリーズで最も人気の高かった浅丘ルリ子扮するリリーが初めて登場した第十一作「寅次郎忘れな草」が公開された年である。(森英介「風天 渥美清のうた」)
イラストレーター(灘本唯人)は、渥美清が参加した句会の様子を回想している。
「渥美さんが『話の特集句会』に『新人の渥美です』と名乗って初めて来た日のことをよく覚えています。この会は世話役が当番制で、当番になるとみんなより早く会場に来て、鉛筆をそろえたり紙を用意したりしなければならない。私と渥美さんは当番が一緒になって話しているうちに仲よくなった」(灘本唯人/森英介「風天 渥美清のうた」より)
お酒を飲まないことで知られる渥美清だったが、「話の句会特集」では、飲み会にも参加していたらしい。
「渥美さんはウチの句会では俳句が終ったあと仲間と一緒にビールを飲んで楽しそうでした。業種が違う気やすさからか、午前一時ごろまで話し込んで盛り上がっていました。(略)そのあと渥美さんは一切お酒を飲まないと聞きましたがどうしても信じられませんでした」(灘本唯人/森英介「風天 渥美清のうた」より)
イラストレーター(和田誠)も、「話の特集句会」発足メンバーの一人だった。
渥美清さんは寅さんシリーズたけなわの数年間、メンバーでした。俳号は「風天」。「フーテンの寅」のフーテンですが、漢字にすると風情がありますね。映画の中で寅さんがしみじみとつぶやくシーンのように、俳句の作風も何気ない言葉の中に観察力の鋭さを見せたり、ちょっとした侘しさを漂わせたりしてとてもいいんです。(和田誠「五・七・五交遊録」)
和田誠は、自ら句集を編むほど、俳句に熱心だった。
「話の特集句会」の歴史については、矢崎泰久『句々快々「話の特集句会」交遊録』に詳しい。
渥美清さんが参加されたのは、一九七四年の初句会からで、尻込みする渥美さんを永六輔さんが口説き落して連れてきた。(略)「俳号は<風天>でよろしいでしょうか。何しろ生まれて初めて俳句というものを作るので、よろしくご指導下さい」と、まこと謙虚に頭を下げた姿は忘れられない。(矢崎泰久『句々快々「話の特集句会」交遊録』)
『渥美清句集 赤とんぼ』には、1973年(昭和48年)3月の話の特集句会に参加した際の作品が冒頭に収録されている。
うつり香のひみつ知ってる春の闇
さくら幸せにナッテオクレヨ寅次郎
「さくら幸せにナッテオクレヨ寅次郎」は、いかにもフーテンの寅さんらしい挨拶句である。
渥美清の参加は、「話の特集句会」にも大きな影響を与えたらしい。
なにしろ浅井さんに至っては、すぐに弟子入りしてしまい、俳号も<愼平>から<風太>に変えた。挙句に<風天>が去った時に、<風太>も話の特集句会から去って行った。(矢崎泰久『句々快々「話の特集句会」交遊録』)
渥美風天の作品に感動したカメラマン(浅井慎平)は、俳号を「風太」に変えて、渥美風天に弟子入りすると宣言したとか。
「話の特集句会」で生まれた作品から、いくつか拾ってみる。
エーアイスおせんにキャラの我が青春
ステテコ女物サンダルのひとパチンコよく入る
さばつまんで扇風機の音やくざ者
テレビ消しひとりだった大みそか
鍋もっておでん屋までの月明り
青春時代の回想句には、切ない情感が漂う。
千鳥波すれすれにどこへゆく
いつも何か探しているようだナひばり
土筆これからどうするひとりぽつんと
秋の野犬ぽつんと日暮れて
風天俳句の特徴のひとつが、小さな動植物に自己投影された心境俳句である。
「千鳥」も「ひばり」も「土筆」も「野犬」も、いずれも風天自身に向けられた言葉だ。
「土筆これからどうするひとりぽつんと」のように、自分の将来を占うような作品は、殊にに、風天俳句らしい。
コスモスひょろりふたおやもういない
天皇が好きで死んだバーちゃん字が読めず
夢で会うふるさとの人みな若く
短い俳句作品の中に、作者の半生が詠われている。
「夢で会うふるさとの人みな若く」は、(時間的にも距離的にも)遠い故郷に向けて詠まれた作品だろう。
山吹キイロひまわりキイロたくわんキイロで生きるたのしさ
行く年しかたないねていよう
初句会今年もやるぞ!ヤケッパチ
捨て身の中に生きる道を探す作者の姿がある。
「行く年しかたないねていよう」には、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」に通じる諦めの境地を感じる。
いま腹切ったのに陽炎ほろほろ
夜釣り忘れた詩(うた)くちずさんでる
経済市況のラジオ暑中見舞土間に一枚
写生句というよりは人事句で、作者の生き様が、そのまま俳句作品として反映されているところに、風天俳句の魅力がある。
しっかり自分と向き合わなければ、生まれてくることのない作品だっただろう。
句会ごとに作品が収録されている『渥美清句集 赤とんぼ』で、「話の特集句会」の次に登場するのは、「トリの会」だ。
「話の特集句会」のメンバーの一人だったイラストレーターの灘本唯人があるとき、気の合った仲間を集めて独自の句会を始めた。麻雀好きのメンバーばかりだったから「トリの会」と称した。(森英介「風天 渥美清のうた」)
「トリの会」時代の作品は、イラストレーター(和田誠)がメモしていたものだ(「私自身のメモの中に『トリの会』での風天句が新たに九句見つかったよ」)。
ずいぶん待ってバスと落葉いっしょに
小春日や柴又までの渡し船
映画『男はつらいよ』にも、寅さんが「矢切の渡し」に乗って登場する場面がある。
「ずいぶん待ってバスと落葉いっしょに」は、1974年(昭和49年)11月の作品。
旅暮らしの寅さんをイメージさせる俳句は、人生を旅に重ねた男の粋な演出だったのかもしれない。
俳人・渥美清の辞世の句
寅さん(風天)の俳句が、初めて公になったのは、雑誌『AERA(アエラ)』1996年(平成8年)8月19・26日号「追悼渥美清さん 裸の心みせた寅さんの45句」で、続いて、『月刊俳句朝日』1996年(平成8年)10月号に「渥美清さん逝く 絶唱・フーテンの寅さん俳句45句 繊細な感受性とサービス精神」が掲載された。
いずれも、「アエラ句会」で渥美風天が披露した作品を公開したものである。
渥美風天が初めて姿を現したのは、翌平成三年十月八日、関口芭蕉庵で開かれた第四回句会だった。その年のアエラ新年号の表紙モデルを依頼した際、くだんの句会に話が及び、一緒にいかがですかと誘った。誘いはしたが、本当に来るとは誰も思っていなかった。(森英介「風天 渥美清のうた」)
「話の特集句会」から「アエラ句会」へと活動の場を移して、渥美風天は俳句を作り続けた。
フーテンの寅さんと風天は、個性を全く異にしていた。寡黙。みんながビールを飲みながら、がやがややっている隣室の隅の暗がりで、一人壁に向かって想を練っている。鬼気さえ感じられた。(森英介「風天 渥美清のうた」)
「アエラ句会」で、渥美清は、フーテンの寅さんではなかったらしい。
自分が有名人、芸能人として振る舞う、またそう扱われるのが嫌いだというのはすぐ分かった。句会が終わると、最寄りの居酒屋に練り出すことになっていたが、風天はそれに加わらず、文字通り風のごとく、みごとに姿を消した。(森英介「風天 渥美清のうた」)
自己紹介は、いつも「アエラで会計をやっております渥美と申します」だった。
アエラ句会に10回参加した渥美風天は、計45句を残した。
赤とんぼじっとしたまま明日どうする
年賀だけでしのぶちいママのいる場末
お遍路が一列に行く虹の中
「赤とんぼじっとしたまま明日どうする」は、句集『赤とんぼ』の由来となった作品。
我が身の将来を占う自己投影の作品だ。
『カラー版新日本大歳時記(春の巻)』に掲載された「お遍路が一列に行く虹の中」は、1994年(平成6年)6月6日、アエラ句会最後の日に作られた。
脚本家(早坂暁)は、この作品の背景について触れている。
<お遍路が一列に行く虹の中>ができた「現場」は、代表作の一つのNHKドラマ「花へんろ・風の昭和日記」だったというのである。(森英介「風天 渥美清のうた」)
渥美清がナレーションを担当した『花へんろ・風の昭和日記』(1985)は、NHKオンデマンドで視聴することができる。
お遍路に興味を持っていた渥美清は、『男はつらいよ』でも、お遍路を採り入れたいと考えていた。
森英介『風天 渥美清のうた』に、山田洋次監督のインタビューがある。
「実は四十九作目を作るならその渥美さんのこだわりもヒントにあって、高知を舞台にして『寅次郎花へんろ』という作品を撮る考えでした。お遍路の旅に寅さんがつきあっているうちに美しい女性に会う物語です」(山田洋次/森英介「風天 渥美清のうた」より)
幻となった第49作『寅次郎花へんろ』のマドンナは田中裕子、ゲストは西田敏行の予定だったという。
村の子がくれた林檎ひとつ旅いそぐ
あと少しなのに本閉じる花冷え
一っ杯目のために飲んでるビールかな
「村の子がくれた林檎ひとつ旅いそぐ」は、まさに映画のワンシーンを十七文字に変換したものだ。
もしかすると、渥美風天にとっては、俳句も映画も、同じ人生の一幕だったのかもしれない。
『花へんろ・風の昭和日記』と同じころ、渥美清は、尾崎放哉の役にも関心を持っていたという。
「渥美ちゃんが『吉村昭の小説《海も暮れきる》を読んだ、この尾崎放哉の役をやりたい』と言ってきた。いつも僕がけしかけていたが、彼の方から『これがやりたい』と言ってきたのは初めてだった。(早坂暁/森英介「風天 渥美清のうた」より)
吉村昭『海も暮れきる』は、NHKでドラマ化の話が進み、渥美清と早坂暁は、香川県小豆島までシナリオハンティングに出かけているが、結局、この計画は実現しなかった。
尾崎放哉や種田山頭火といった漂泊の俳人に、渥美清は惹かれていたのだろう。
渥美風天が最後に参加した句会は、「トリの会」の後継とも言える「たまご句会」だった。
「たまご句会」の記録は一九九三年三月六日から一九九六年三月二十八日までの十回分。渥美が亡くなったのは一九九六年八月四日だから最後の句会は亡くなるわずか五ヵ月前ということになる。(森英介「風天 渥美清のうた」)
たまご句会の記録は、やはり、イラストレーター(和田誠)が入手してきたものだ(全部で29句あった)。
だーれもいない虫籠のなかのきゅうり
1994年(平成6年)9月に作られた「だーれもいない虫籠のなかのきゅうり」は、辞世の句としても読むことができる。
『男はつらいよ 拝啓車寅次郎様』が公開された、この年、肝臓がんが肺にまで転移していた渥美清は、医師から「映画出演はもう不可能」とまで言われていたという。
「だーれもいない虫籠のなかのきゅうり」は、渥美風天自身の姿でもあったはずだ。
「話の特集句会」で渥美清と一緒だった小沢昭一は、『俳句で綴る変哲半生記』(2012)で、渥美風天を懐かしく回想している。
この会には以前、渥美清さんも加わっておりまして、彼の句は好きで、また彼も、よく私の句を採ってくれたこと、懐かしく思い出します。(小沢昭一「俳句で綴る変哲半生記」)
森英介『風天 渥美清のうた』には、小沢昭一のインタビューも収録されている。
「よけいなこと、大きなお世話だろうけど、俳句を使って渥美清論をやろうというのは、ナンというか砂上の楼閣みたいなもの。寅次郎は出てきても渥美清は出てこないと思いますよ」(小沢昭一/森英介「風天 渥美清のうた」より)
車寅次郎と渥美清。
その二人を、俳人(風天)は俳句として描いた。
しかし、その男たちの向こう側には、もう一人の男がいた。
俳優(渥美清)の本名(田所康雄)である。
「ウーン、”入れ子” というのかな、車寅次郎の中に渥美清が入っていて、その中に風天がいて、さらにその中に田所康雄がいて……。そのいちばん中の田所康雄が抜け出して亡くなってしまった。でも、周りは残ってる。映画の観客や俳句を詠む人にとってはいつまでも生きている。それが渥美さんの生き方だったんじゃないかな」(山田洋次/森英介「風天 渥美清のうた」より)
人間(田所康雄)は、俳優(渥美清)のままで死んだ。
「フーテンの寅さん」という映画主人公と、「風天」という俳人による俳句だけを遺して。
現在、我々は「渥美風天」という俳人の残した俳句を詠みながら、かつて銀幕の中で活躍した「渥美清」という映画スターを懐かしく偲んでいる。
あるいは、それが「田所康雄」という一人の男が演じ続けてきた人生の芝居だったとしても、我々にとって、それは、人生の真実に他ならないのだ。
書名:風天(フーテン)渥美清のうた
著者:森英介
発行:2008/07/10
出版社:大空出版