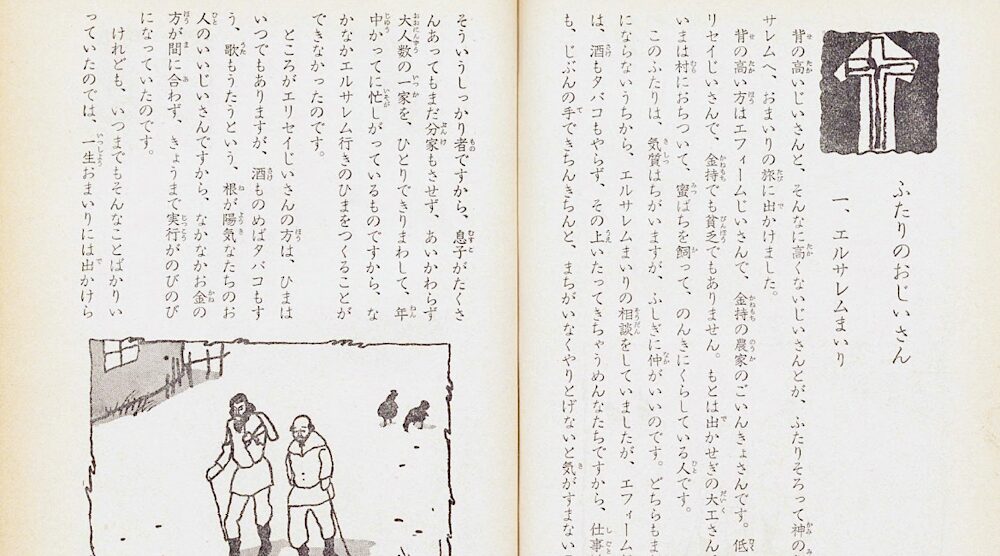庄野潤三「エイヴォン記」読了。
本作『エイヴォン記』は、1989年(平成元年)8月に講談社から刊行された長篇随筆である。
初出は、1988年(昭和63年)8月~1989年(平成元年)7月『群像』で、連載開始の年、著者は67歳だった。
いわゆる『フーちゃん三部作』最初の作品である。

フーちゃん(2歳)の華やかなデビュー
本作『エイヴォン記』は、庄野さんの読書体験を綴った長篇随筆である。
さらに、二歳になる孫娘(庄野文子、愛称フーちゃん)や、園芸の好きなご近所さん(清水さん)との交流が、読書体験と呼応する形で組み込まれている。
フーちゃんが、初めて登場するのは、連載2回目の「ベージンの野」。
こんなふうにして私は「エイヴォン記」の二回目に「猟人日記」より「ベージンの野」を取り上げて一しょに読んでみようという心づもりが出来たのだが、「ベージンの野」に登場するロシアの田舎の子供たち──フェーヂャとかパヴルーシャ、イリューシャ、コースチャ、いちばん年下のワーニャの話をするより前に、私と妻の夫婦が二人きりで暮しているところへ、ときどき現れる小さな女の子(それは私どもの孫娘なのだが)のことを紹介しておきたい。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ベージンの野」)
連載最初の回で触れられていないということは、フーちゃんの登場は、あるいは計画的なものではなかったのかもしれない。
「エイヴォン記」の二回目が雑誌に載る少し前に、満二歳の誕生日を迎えたばかりなのだ。私たちの家から歩いて五分くらいのところの大家さんの家作に住んでいる次男の長女で、孫のなかでただ一人の女の子である。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ベージンの野」)
庄野さんの孫としては、長女(夏子)夫妻のところの子どもたちが、既に作品中へ登場しているが、女の子の孫は、フーちゃんが初めてだった。
初めての孫娘は、後期庄野文学の中で、非常に大きな存在となっていく(『エイヴォン記』が始まったときは、もちろん、誰も知らなかっただろうが)。
或る日。夕方、図書室のベッドで本を読んでいたら、文子が買物の帰りの母親と一緒に来た。図書室とは、長男と次男が結婚するまで寝起きしていた部屋で、新しく壁際に本棚を作って、書斎から本を移したので、図書室と呼ぶようになった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ベージンの野」)
中期庄野文学のファンには懐かしいエピソードが出てくる。
ちなみに、長男(龍也)と次男(和也)は、かつて『明夫と良二』シリーズの主人公だった兄弟で、長女(和子)とともに、五人家族の物語を賑やかに盛り上げた功労者でもある。
フーちゃんは、妻の部屋(かつて長女が勉強部屋と寝室にしていた小さな部屋)にある、机の椅子に座らせてもらう。
ついでにいうと、この勉強机は、長女が小学校へ入学したときに買ったのだが、気に入って、新しいのに買い換えようといっても承知せずにずっと使っていたものだ。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ベージンの野」)
長女の机の話は、『夕べの雲』(1965)に出ている。
「これはやっぱり新しいのを買った方がいいな。もうだいぶ窮屈そうだ」大浦がそういうと、晴子は、「いいよ、大丈夫よ、これで」「まあ、高校へ入ったときまで辛抱するか」「いいよ、いいよ。この方が貫禄があっていいよ」(庄野潤三『夕べの雲』)
『夕べの雲』から24年。
幼い日の長女が座った机に、今、孫娘のフーちゃんが座っているというところに、世代交代と時代の流れが反映されている。
次男に聞いてみると、この前、休みの日にフーちゃんを連れて、駅の向うの山の上の小学校へ行った。そこは次男が通った小学校である。校庭で遊んでいたら、授業が終って、生徒がいっぱい出て来たので、フーちゃんはよろこんだ。(庄野潤三『エイヴォン記』より「蛇使い」)
小学校も、また、世代交代を示すひとつの象徴だろう。
庄野家の子どもたちが通った小学校は、川崎市立生田小学校で、「山の上の家(庄野さんの自宅)」からは、山道を下りて、駅を越えて、向こう側の山道を上ったところにある。
ちなみに、いずれフーちゃんが通うのは、西生田小学校だった(次男一家は読売ランド前へ引っ越していった)。
二歳になったばかりの頃のフーちゃんは、かなり個性的な女の子だったらしい。
次の日、昼前のいつもの散歩の時間に、道を歩き出しながら、妻は、「昨日はフーちゃん、荒れましたね」といった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「エイヴォンの川岸」)
フーちゃんは、言葉で表現することが苦手だったから、感情の揺れを把握することが難しかったのかもしれない。
次男の話。ここへ来るとき、道ばたで拾った枯枝を一本、手に持って歩いていた。坂道の下まで来たら、文子が溝を指して、その枯枝をここへポイしろという。物をいわない子だから、身ぶりで知らせた。(庄野潤三『エイヴォン記』より「精進祭前夜」)
『エイヴォン記』のフーちゃんは、とにかく「物をいわない子」だった。
妻は、フーちゃんを抱き上げた。フーちゃんは、開き戸のところの風船を見つけて、「わあ、風船だァ」といって、よろこんだ。そこまで聞いた私は、「フーちゃん、日本語を話すのか」あまり物をいわない子が、そんなことをいったから、驚いた。(庄野潤三『エイヴォン記』より「蛇使い」)
「わあ、風船だァ」という言葉で驚くくらい、フーちゃんは、寡黙な女の子だったのだろう(「フーちゃん、日本語を話すのか」が楽しい)。
図書室で縫いぐるみの人形の「クマさん」や「ウサギさん」を九度山の柿の箱の「バス」に乗せて押して遊んでいたら、ミサヲちゃんが次男が「クマのプーさん」のディズニィの三十分のヴィデオを買って来たことを話した。すると、フーちゃんが、「かんがえる。かんがえる」といった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふたりのおじいさん」)
妻が「カンガとルゥ?」と訊ねるあたり、イギリス文学を読み込んでいることが分かる(カンガとルゥは、A・A・ミルン『クマのプーさん』に登場するカンガルーの子ども)。
「やあ、こんちは、カンガ」「こんにちは、プーさん」「ぼくのとぶのを見てごらん!」ルーは、キイキイ声でこういったかと思うと、また穴のなかへおちました。(A.A.ミルン「クマのプーさん」石井桃子・訳)
ディズニーのアニメは、庄野家の子どもたちも、幼いころに観ていたもので(『夕べの雲』に『ディズニィ・ランド』の「コヨーテ腹ぺこ物語」が出てくる)、井伏鱒二と仲の良かった石井桃子・訳の『クマのプーさん』も、夫婦で愛読していたらしいから、フーちゃんとプーさんに関するエピソードは充実している。
長靴を履いたフーちゃんは、「あんちゃん(あつ子ちゃん)とこんちゃん(妻)とお母さんとでちゅっちゅ、見に行こう」という。大家さんの庭にせきせいいんこの籠が吊してあるのを見に行こうというのである。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふたりのおじいさん」)
連載後半に入ると、フーちゃんの言葉が増えている。
台所で妻がメロンの皮をむいて、包丁を入れて、皿に乗せていたときのことだ。フーちゃんは待ち切れなくて、お皿のメロンに手を出そうとした。「あとで、みんなと一しょにね」といって私が止めると、一呼吸おいて、「ばァか」といった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「少年パタシュ」)
庄野さんは「物をいわないフーちゃんが、いった。日に日に賢くなる」と、目を見張っている。
本作『エイヴォン記』では、フーちゃんと庄野さん(著者)を取り巻く関係者も、数多く登場する。
四十一歳の誕生日(極秘事項ナリ)の翌日のお昼にあんな心のこもったお昼御飯を作って頂き、そして素晴らしい贈り物を頂いて、心もおなかも、お土産ぎっしりの縞のバッグもふくらませて帰宅しました。(庄野潤三『エイヴォン記』より「精進祭前夜」)
『インド綿の服』(1988)では主役だった長女(夏子)の手紙が、『エイヴォン記』では要所要所で登場する。
南足柄の長女から宅急便が届いた。アップルパイ、家で飼っているちゃぼの卵、胡麻せんべい、近所の親しい方から貰ったてんぐさ、海苔、無事退院した工芸家の宗廣先生からの「あしがら織」のネクタイとテーブル掛けなどいっぱい入っている。(庄野潤三『エイヴォン記』より「少年パタシュ」)
「長女の宅急便」も「アップルパイ」も、後期庄野文学ではおなじみとなっている小道具だろう。
随筆集『誕生日のラムケーキ』(1991)には、「長女の宅急便」というエッセイも収録されている。
夕方、小田原へ行った帰りのミサヲちゃんとフーちゃんが寄った。ミサヲちゃんは結婚するまで研究生として紬の染織を教わっていた南足柄市の工芸家の宗廣力三先生が腎臓を悪くして小田原の病院に入院したことを聞いたその翌日にお見舞いに行ったのであった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふたりのおじいさん」)
ミサヲちゃんと次男(和也)の結婚式は、1985年(昭和60年)10月で、その翌月(11月)、庄野さんは脳内出血で緊急入院をするのだが、次男(和也)とミサヲちゃんをつないだのも、南足柄市に住む長女(夏子)だった。
長女の家のすぐ下に染織工芸家の宗近拓三さんのお宅があり、全国各地から染織の勉強に来た研究生の若い娘さんが何人かいる。その中でひとり栃木県から来ていた娘さんが仕事の合間にときどき長女のところへ遊びに来ていた。(庄野潤三『インド綿の服』より「足柄山の春」)
長女は、「のんびりした、大らかな気質の娘さんで、この人ならカズヤどん(と長女は下の弟のことを呼んでいる)と合いそうだ」と考えたらしい。
次男夫妻のところに長女(フーちゃん)が生まれるのは、1986年(昭和61年)7月で、このあたりの経過については、庄野さんの闘病記『世をへだてて』(1987)でも読むことができる。
つまり、庄野文学のアイドル(フーちゃん)は、『エイヴォン記』で突然デビューしたわけではなく、『インド綿の服』や『世をへだてて』などの先行作品で、既に予兆を見せ始めていたということなのだろう。
この後、フーちゃんは、三部作(『エイヴォン記』『鉛筆印のトレーナー』『さくらんぼジャム』)をはじめとして、十年に及ぶ大作「夫婦の晩年シリーズ」においても、庄野文学のアイドルとして活躍し続けることになる(最後の『星に願いを』では女子高生だった)。

清水さんの薔薇
本作『エイヴォン記』の「エイヴォン」とは薔薇の名前である。
八月のはじめであった。夕方、暗くなりかける頃、図書室の窓際のベッドで本を読み、まどろみかけていたら、妻が、「清水さん、エイヴォンを下さった」と知らせに来た。(庄野潤三『エイヴォン記』より「クラシーヴァヤ・メーチのカシヤン」)
清水さんは、フーちゃんとともに、本作『エイヴォン記』を支える大きな柱の一つとなっている、近所の主婦だ(団地の四階に住んでいる)。
四日目になると、書斎の上の花生けのエイヴォンの蕾が開いて、大きくなった。花生けの口から出ている葉のかたちがいい。花を下さったとき、清水さんは妻に、「咲きませんでしょう」といったけれども、咲いた。立派なエイヴォンである。(庄野潤三『エイヴォン記』より「精進祭前夜」)
庄野さんは、清水さんから頂いたエイヴォンがよほど、気に入ったらしい。
エイヴォンの薔薇は、全編を通して繰り返し、登場している。
「エイヴォン? エイヴォンといえばイギリスの田舎を流れている川の名前だ。ほら、『トム・ブラウンの学校生活』のなかで、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るが、あの川の名がエイヴォンだよ」(庄野潤三『エイヴォン記』より「ブッチの子守歌」)
連載最初の回で、清水さんのエイヴォンを採り上げた庄野さんは、このエイヴォンの薔薇を、物語を盛り上げるためのアクセントとして随所で用いるばかりか、『エイヴォン記』という書名にまで引用した。
最終回の稿を書き上げた頃、清水さんが一番咲きの薔薇を揃えて届けてくれた。その花束と別に、蕾のふくらんだエイヴォンを一本、渡してくれた。妻は早速、そのエイヴォンを書斎の机の上の花生けに活けた。私はその前に坐った。「間に合せて咲いてくれて、有難う」といいたかった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふるさと」)
清水さんのエイヴォンから始まった物語は、清水さんのエイヴォンで終わる。
清水さんの薔薇は、やはり、フーちゃんとともに『エイヴォン記』を支える、大きな柱だったのだ。
もっとも、清水さんが持ってきてくれるのは、薔薇の花に限ったことではない。
あるときは、ライラックの花を持ってきてくれたこともあった。
妻が、「ライラックがかったローズは、エリザベス女王のお好きな色です」という。八年ほど前に「エリア随筆」の作者チャールズ・ラムのことを書くためにロンドンを訪れたとき、ハロッズ百貨店で南足柄の長女とあつ子ちゃんのためにカーディガンを買った。選んだのはライラックがかった、くすんだローズの色であったが、店員のおばあさんが、「クィーンのお好きな色です」といったというのである。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふるさと」)
「八年ほど前に「エリア随筆」の作者チャールズ・ラムのことを書くためにロンドンを訪れたとき」のことは、『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(1984)に詳しい。

ライラックの花の向こう側に、家族の思い出がある。
二人が話している間、フーちゃんはバケツの中のチューリップを見ていた。「フーちゃん、チューリップ上げようか」と清水さんがいった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふるさと」)
フーちゃんと清水さんの会話は、庄野文学を通して貴重なレア・シーンである。
二人の主役が、長篇随筆の最後の章になって初めて、同じ舞台に立ったのだ。
「特別のドラマは起こらない」と言いながら、『エイヴォン記』は、意外と見せ場の多い物語である。
庄野潤三の読書体験
フーちゃん、清水さんと、『エイヴォン記』の柱を紹介したが、本書の中心的な柱となっているのは、庄野さんの若き日の読書体験である。
かつて、愛読した文学作品を、毎回ひとつ紹介する。
それが、本作『エイヴォン記』の、最も基本的なコンセプトだった。
例えば、初回タイトル「ブッチの子守歌」は、デイモン・ラニアンの作品集『ブロードウェイの天使』に収録された短篇小説である。
デイモン・ラニアンは、戦後に亡くなった私の父の好きな作家であった。戦争が終った翌年くらいであったか、父が、「デイモン・ラニアンというのは面白い」と何度か私にいった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ブッチの子守歌」)
1985年(昭和60年)3月、庄野さんは、宝塚歌劇団月組の『ガイズ&ドールズ』を観に行っているが、これは、デイモン・ラニアンの短篇「ミス・サラ・ブラウンのロマンス」を原作としたブロードウェイ・ミュージカルだった。
宝塚月組の『ガイズ&ドールズ』を観たその日に、私たち(というのは私と妻だが)と一緒にこのミュージカルを見物した友人のS君が、銀座の書店の本棚で新潮文庫の『ブロードウェイの天使』を見つけて買い求めた。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ブッチの子守歌」)
その三日後、成城学園の本屋で『ブロードウェイの天使』(加島祥造・訳)を見つけた庄野夫人が、この文庫本を買って帰り、庄野さんは、「私は父が亡くなってから三十五年たって、やっとのことで父が好きだったデイモン・ラニアンを読んだ」と綴っている(友人のS君とあるのは、作家の阪田寛夫)。
現在、新潮文庫『ブロードウェイの天使』は入手困難だが、2024年(令和6年)5月に、同じく新潮文庫から、田口俊樹・訳の『ガイズ&ドールズ』が出版された。

本作『エイヴォン記』で紹介されている「ブッチの子守歌」は、「ブッチは赤子の世話をする」という邦題で収録されているものを読むことができる。
デイモン・ラニアンと同じアメリカの作家では、ドロシー・キャンフィールドの「情熱」が紹介されている。
西川正身編『アメリカ短篇集』(市民文庫)という一冊の文庫本がある。表紙がちぎれかかったのを、セロ・テープで貼りつけて補修してある。奥附を見ると、昭和二十八年四月十五日初版発行となっている。(庄野潤三『エイヴォン記』より「情熱」)
市民文庫は河出書房の発行で、他に『ロシヤ短篇集』(神西清編)や『フランス短篇集』(鈴木信太郎編)、『ドイツ短篇集』(相良守峯編)、『イギリス短篇集』(福原麟太郎編)があった。
いま、この広告の目次内容を見ると、どうしてほかの国のも買っておかなかったんだろうと悔まれる。せめて福原さんの編集による『イギリス短篇集』くらいは、買っておくべきであった。目次のなかに私の好きなハックスリーの「半休日」が入っているではないか。(庄野潤三『エイヴォン記』より「情熱」)
敬愛する福原麟太郎の訳だから、庄野さんとしては、本当に残念だったのではないだろうか。
市民文庫『アメリカ短篇集』は、現在、もちろん入手困難で、ドロシー・キャンフィールドの作品も、児童文学『リンゴの丘のベッツィ』が、唯一邦訳で手に入る作品らしい。
レアな作品が多く登場するのも、『エイヴォン記』の醍醐味のひとつだ。
シャーウッド・アンダースンの短篇「卵」(吉田甲子太郎・訳)も、『アメリカ短篇集』に収録されている作品である。
プロット(筋)というものをことさらに排したアンダスンで、「卵」もそういう特色を持った小説だから、筋を追いながら紹介するということが出来ない。部分で成り立っているような小説であり、ちょっとした一行にも作者は意味を持たせている。(庄野潤三『エイヴォン記』より「卵」)
シャーウッド・アンダーソンは『ワインズバーグ・オハイオ』で有名な人気作家で、本作「卵」も、過去、何度か邦訳されているが、現在、入手可能なものはないようだ。
「プロットを排除した小説」というところで、庄野さんにも響くものがあったのかもしれない。
『懐しきオハイオ』にも、シャーウッド・アンダースンの「卵」が登場している。
私は前に読んだシャーウッド・アンダースンの「卵」という短篇を思い出して訊いてみた。「変なかたちをした雛は生れないか?」「ときどき、ある」(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「送別会」)
アンダースンさんの養鶏場を見学しながら、庄野さんは、シャーウッド・アンダースンの小説のことを思い出したらしい。
アメリカ文学以上に多いのは、ロシア文学である。
例えば、若き日の庄野さんが愛読した作家として知られている作家にチェーホフがいる。
今回は、『チェーホフ著作集』第四巻(中村白葉訳・三学書房)から、「少年たち」という短篇を紹介したい。この『チェーホフ著作集』は、戦争中の昭和十八年五月一日、第一回配本の「桜の園」(ほかに「かもめ」「伯父ワーニャ」「三人姉妹」)をもって刊行を始めたものだが、出版事情が悪くなったために、昭和十九年九月二十五日発行の「三年」(ほか「アリアードナ」など中短篇六篇を収める)の第六回配本を最後に刊行を中止した。(庄野潤三『エイヴォン記』より「少年たち」)
この『チェーホフ著作集』を、復員して高校教師となった庄野さんは、戦後間もないころに、大阪阿倍野の古本屋で手に入れたという(刊行済みの計六冊のみだったが)。
半端の『チェーホフ著作集』ではあったが、これを古本屋で買って、抱えて帰ったときは嬉しかった。(略)戦争が終った翌々年の夏、私は『チェーホフ著作集』の六冊を机の上に積み上げて、ひと夏をチェーホフを読んで過そうと決心したことを思い出す。(庄野潤三『エイヴォン記』より「少年たち」)
三学書房の『チェーホフ著作集』のエピソードは、庄野さんの作品では散見されるものであり、まさに「ルーツ・オブ・庄野文学」のひとつと言えるものだろう。
「精進祭前夜」も、同じく『チェーホフ著作集』からの選定である。
戦争が終った翌々年の夏(その年の秋にはじめての赤ん坊の長女が生れた)、机の上にこの『チェーホフ著作集』六冊を積み上げて、チェーホフを読んで過した。(略)このとき読んだチェーホフの短篇小説のなかでいちばん気に入ったのが、これから紹介する「精進祭前夜」であった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「精進祭前夜」)
中村白葉・訳のチェーホフは、戦後日本におけるチェーホフのスタンダードとして、かつては多くの文学全集で読むことができたが、最近はさすがに入手が難しくなってしまった(現代性のあるチェーホフは新訳も多い)。
同じくロシア文学のツルゲーネフ「ベージンの野」は、岩波文庫『猟人日記』(佐々木彰・訳)に収録されている。
「猟人日記」の(上)には、全部で十四篇収められているが、私の好きな「ベージンの野」は、こちらの方に入っている。(略)私はどんな話なのか覚えていなかったけれども、読み返してみて、「ベージンの野」をはじめて読んだとき、気に入ったことを思い出した。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ベージンの野」)
ツルゲーネフ『猟人日記』からは、もう一遍、「クラシーヴァヤ・メーチのカシヤン」が紹介されている。
私は(下)を読み、もう一度(上)に引返してあれこれ読み返してみるうちに、『猟人日記』からもう一篇、読んでみるとすれば、「おれの名前はカシヤンで、蚤というのがそのあだ名……」と森の中でカシヤンが自作の歌らしいものを歌い出す場面の出て来る「クラシーヴァヤ・メーチのカシヤン」がいいだろうかと考えるようになった。(庄野潤三『エイヴォン記』より「クラシーヴァヤ・メーチのカシヤン」)
岩波文庫『猟人日記』は、現在、残念ながら入手困難で、『猟人日記』は、現代人にとって親しみやすい小説とはなっていないのが現実だろう。
もう一篇、ロシア文学として、『トルストイ童話集』収録の「ふたりのおじいさん」がある。
昭和五十三年に七十七歳で亡くなった十和田さんは、私の敬愛する作家であった。(略)十和田さんは話好きで、話の上手な方であった。私よりも二十一歳、年上であった。この『トルストイ童話』も、扉の裏の頁に十和田さんの署名入りで贈って下さった。三十年前のことだ。(庄野潤三『エイヴォン記』より「ふたりのおじいさん」)
十和田操の『トルストイ童話』は、「学年別童話集・小学五年生」として、1959年(昭和34年)に東光出版社から刊行されたもので、既に入手困難な書籍である(当たり前か)。
そもそも、十和田操の著作そのものが、レアな時代となってしまった。
ちなみに、1970年(昭和45年)に冬樹社から刊行された『十和田操作品集』の覚書は、庄野潤三が執筆している。
https://gentle-land.com/towada-misao-oboegaki/
庄野さんの敬愛する作家の翻訳として、佐藤春夫の『志那文学選』がある。
今回は戦前の昭和十五年七月に新日本少年少女文庫のなかの一冊として刊行された佐藤春夫編『志那文学選』(新潮社)から「蛇使い」を読んでみることにしたい。(略)その頃、私は佐藤春夫の本を集めていたので、少年少女のために編まれたこの本をよろこんで買ったような気がする。(庄野潤三『エイヴォン記』より「蛇使い」)
「その頃」とあるのは、九州の大学に入学して、福岡の町で下宿生活をしていた頃のことで、当時の生活は自伝的長篇『前途』に詳しい。
晩、九時ごろ、小高が僕の預っていた江嶋さんの贈り物のお菓子を食べに来た。僕にも食えと云うので、僕も食べた。春夫の本、持っているのを全部見せてくれと云うので、積んであった中から出した。小高はひとつひとつみて、「ええの、持っとるなあ」と何度も云った。(庄野潤三『前途』)
「小高」は、大学で一緒だった島尾敏雄のことで、二人は、競い合うように、佐藤春夫の著作を買っていたらしい。
本作『エイヴォン記』の最後に収録されている魯迅「ふるさと」も、佐藤春夫の翻訳によるもので、『志那文学選』に収録されていた。
国語の教科書にも掲載されている「ふるさと」は、多くの日本人にとって馴染み深い中国文学のひとつだろう。
『エイヴォン記』のタイトルと関わりが深いのは、トマス・ヒューズ『トム・ブラウンの学校生活』だろう。
エイヴォンという名を耳にして、先ず最初に思い浮べるべきものは、シェイクスピアの生れたストラッドフォード・アポン・エイヴォン、あるいはストラッドフォード・オン・エイヴォンであるかもしれない。私もそれを考えないわけではなかったが、シェイクスピアよりも先にトム・ブラウンの名を持ち出したのは、慈愛深い両親の膝もとを離れてラグビー校に入学したトム少年が英国独特のパブリック・スクールの寮の生活のなかでどのように成長して行ったかを振り返る物語の方が親しみが深く、妻にも一読を勧めた覚えがあるからだろう。(庄野潤三『エイヴォン記』より「エイヴォンの川岸」)
『エイヴォン記』と『トム・ブラウンの学校生活』との関わりは、庄野さんにとって印象深いものであったらしく、その後の作品の中で、繰り返し語られていくことになる。
最初のころ、清水さんが畑のばらを届けて下さる度に、妻はばらの名前をお訊きした。パパメイヤとかジュリアというのをよく頂いた。一度、赤い、いい色をしたばらが入っていた。妻が訊くと、「エイヴォン」と清水さんは言った。これを聞いて、私は、「エイヴォン? エイヴォンといえば、英国の田舎を流れている川だ。『トム・ブラウンの学校生活』のなかに、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るだろう。あの川がエイヴォンだ」といい、花もいいし、名前もいいので、エイヴォンが気に入り、ふだんは花生けを置かない書斎の机の上に花生けを置いて、妻にそのエイヴォンを活けてもらったという話は、前に書いたことがある。(庄野潤三『鳥の水浴び』)
2000年(平成12年)に刊行された『鳥の水浴び』にも、『エイヴォン記』の思い出が綴られている。
丁度そのころ文芸誌に連載の随筆をたのまれて、何を書くか、まだ決まっていなかった。私は先ず清水さんからばらのエイヴォンを届けて頂いたことを書き、連載の随筆の題を「エイヴォン記」とした。そうして、そのころはまだ「山の下」の家作にいて、買物の帰りにミサヲちゃんに連れられて、山の上の私たちの家へよく来るようになった、丁度、満二歳になったばかりの孫娘のフーちゃんをその連載の第一回に登場させた。(庄野潤三『鳥の水浴び』)
連載の第一回は、デイモン・ラニアン『ブッチの子守唄』だが、『ブッチの子守唄』にフーちゃんは登場していない。
『エイヴォン記』におけるフーちゃんの初登場は、連載二回目の『ベージンの野』なのだ。
いずれにしろ、後々まで繰り返し語られるほど、『エイヴォン記』は、庄野さんにとって大切な作品となったということだろう。
そこには、もちろん、満二歳のフーちゃんが、庄野文学で華々しくデビューしたという付加価値があることは間違いない。
最後に、唯一のフランス文学である「少年パタシュ」について。
今回は堀口大学『毛虫の舞踏会』からトリスタン・ドレエム作「少年パタシュ」を紹介したい。『毛虫の舞踏会』は、戦争中の昭和十八年二月、札幌青磁社から刊行されたフランス装の、表紙の下の方にかたつむりの絵のカットが入った本で、私の持っているのは、奥付を見ると、戦後の昭和二十一年八月十五日発行の第三刷、となっている。定価金三十円。(庄野潤三『エイヴォン記』より「少年パタシュ」)
この『毛虫の舞踏会』については、古い随筆がある。
「少年パタシュ」は中でも好きな作品であるが、トリスタン・ドレエムという著者の名は初めてお目にかかるもので、今もって「一八八九年・ロ・エ・ガロンヌ県マルマンドに生る。蝸牛とパイプの詩人として知らる」という短い紹介以外には、何も知らない。(庄野潤三「毛虫の舞踏会」随筆集『自分の羽根』所収)
トリスタン・ドレームの『パタシュ』シリーズは、絵本として日本でも人気があるらしい。
さて、本作『エイヴォン記』では、様々な国の文学作品が紹介されているが、すべての作品に共通しているのは、幼い子どもか、男のお年寄り(つまり、おじいさん)が登場する作品だということだろう。
これは、庄野さん(おじいさん)とフーちゃん(孫娘)との関係を踏まえた選書であることは明らかで、一見、交わりようなく見える読書体験とフーちゃんのエピソードとの共通項を、著者は巧みにすくいあげている。
さらに、古い文学作品と孫娘フーちゃんとをつなぐ潤滑油となっているのが、清水さんの薔薇で、この三つの要素が絶妙なバランスを保ちながら組み込まれているところに、本作『エイヴォン記』最大の特徴があると言っていい。
『エイヴォン記』の中で、庄野さんは、古い文学作品のあらすじ(というか梗概)を紹介しているが、底本と当たってみると、必ずしも正確な引用ではないことが分かる。
そこには、現代の読者に、古い文学作品の魅力を伝えたいという著者の意向が含まれているのであり、庄野さんの『エイヴォン記』を読むことで、我々は、現代社会から忘れられた古い外国文学の魅力に触れることができるのだ。
本作『エイヴォン記』は、気軽に読み終えることのできる長篇エッセイだが、その奥底は、おそろしく深い。
なぜなら、ここに紹介されている原著に当たるだけで、かなりのエネルギーを費やすし、庄野家の人々に関するエピソードを把握しようと思ったら、さらに膨大なエネルギーを必要とするからである(それは、庄野文学を制覇することと、ほぼ等しい)。
僕が『エイヴォン記』という作品を、繰り返し愛読しているのは、本書が持つ底知れぬ深さに惹かれているからなのではないだろうか。
できれば、こういう作品を、もっとたくさん読みたかったなあ。
書名:エイヴォン記
著者:庄野潤三
発行:2020/02/18
出版社:小学館「P+D BOOKS」