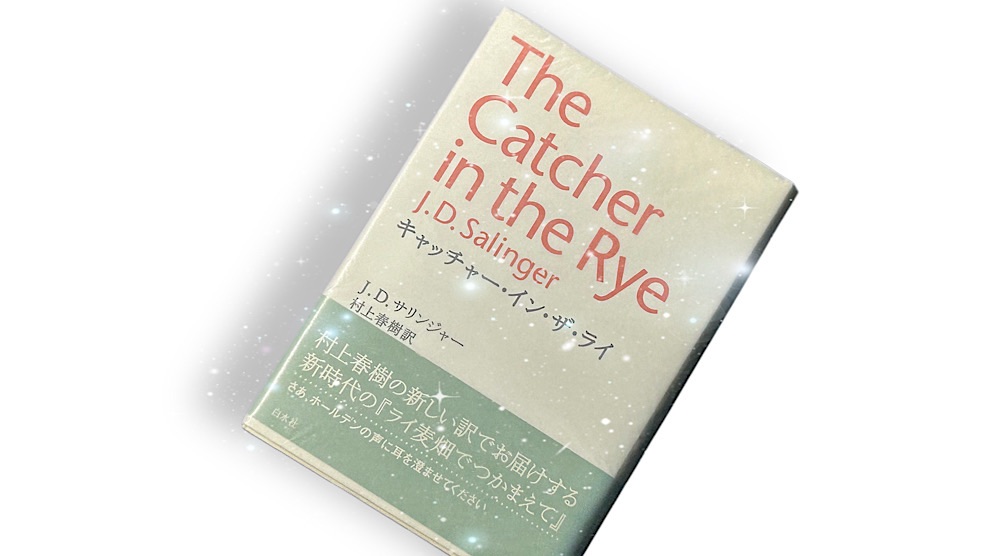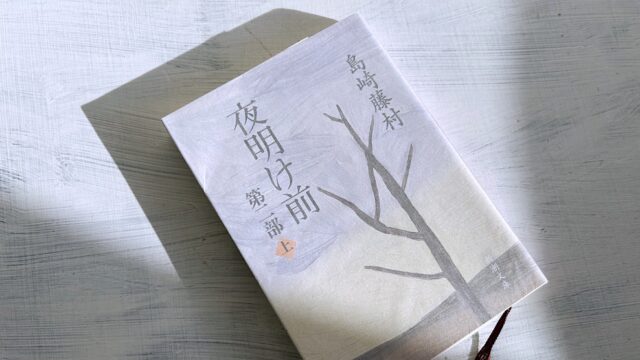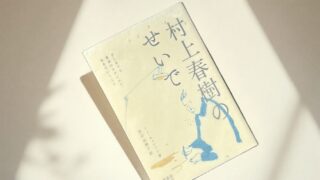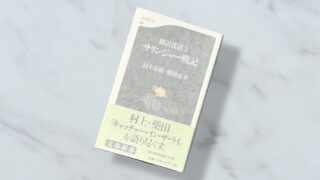J.D.サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は、変わり続ける世の中で生きていくことの難しさを描き出している。
主人公のホールデン・コールフィールドは、なぜ、それほどまでに「生きにくい」と感じていたのだろうか?
ホールデン・コールフィールドの「生きにくさ」は、現在を生きる我々の「生きにくさ」でもあったかもしれない。
ホールデン・コールフィールドの疎外感はどこから来るのか
この世界的に有名な物語を、アリーの視点から読み直したら、どうなるだろうか?
アリーは、主人公(ホールデン・コールフィールド)の死んだ弟だ。
弟はもうこの世にはいない。うちの一家がメインの別荘にいるときに、白血病で死んじゃったからだ。一九四六年の七月十八日のことだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
主人公(ホールデン・コールフィールド)は、物語全体を通して、死んだ弟(アリー)に対する異常なまでの愛情を見せている。
なぜなら、主人公(ホールデン)は、死んだ弟(アリー)自身だったからだ。
「アリー的キャッチャー」の世界にあって、ホールデンは「生きていたかもしれない」アリーの化身である。
もしアリーが白血病で死ななかったとしたなら、彼(アリー)はどのように成長していったのだろうか?
そのひとつの仮説がホールデン・コールフィールドであり、兄(DB)である。
主人公(ホールデン・コールフィールド)は、16歳になったアリーの姿だ(「僕は当時十六歳で、今では十七歳なんだけれど」)。
ルームメイト(ストラドレイター)に殴られたホールデンは、ニューヨークの夜へ飛び出していく。
ストラドレイターとの喧嘩の原因は、死んだ弟(アリー)の形見である野球のミットだった。
弟のアリーは左利き野手用のミットを持っていた。つまり弟は左利きだったんだよ。でもそれが描写に向いているというのは、彼がその指の部分や、腹の部分やら、とにかくいたるところに詩を書き込んでいたからなんだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
ホールデンは、寮生活にまで、死んだ弟の形見であるミットを持ち歩いていた。
詩の書きこまれたミットは、もちろん、死んだアリーの象徴である。
弟が死んだ夜、僕はガレージで寝て、そこの窓ガラスをこともあろうに全部こぶしで割っちまったんだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
そのとき、ホールデンは13歳で、アリーは11歳だった(「アリーは二つ年下だったんだけど」)
アリーのミットについて書かれた(ホールデンに代筆してもらった)「描写的な作文」を読んで、ストラドレイターは激怒する。
「いい加減にしろよな」彼はものすごく気を悪くしていた。かなり怒り狂っていた。「なんでお前はいつもこう、とんちんかんなことばっかりやるんだよ」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
もちろん、ホールデンはストラドレイターを許すことができない。
詩の書きこまれたミットは、アリー自身(ホールデン自身)だったからだ。
自分自身の存在を否定されたからこそ(否定されたと受け止めたからこそ)、ホールデンは(勝てるはずのない)無謀な喧嘩を仕掛けていかなければならなかった。
ストラドレイターが、ホールデンの幼なじみ(ジェーン・ギャラガー)とデートしたことも、ホールデンの怒りの原因となっている。
家族をべつにすれば、ジェーンは僕がアリーの野球ミットを見せたただ一人の相手だった。詩をいっぱい書きつけた例のミットをさ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
アリーのミットは、ホールデンの内面の奥底深い場所に潜む、本当の彼自身である。
それほど大切なミットを見せるくらい、ホールデンにとって、ジェーンは特別な存在だったのだ。
そのジェーン・ギャラガーが、ストラドレイターと(夜の自動車の中で)「性的な関係に及んだかもしれない」と想像することは、ホールデンにとって、この上もない苦痛だったに違いない。
もちろん、ホールデンはジェーンを信じていた。
エド・バンキーの罰当たりな車にストラドレイターと一緒に座っているジェーンを思い浮かべるたびに、あやうく気が狂いそうになった。彼女がストラドレイターのやつになんて一塁ベースを踏ませないはずだってことはわかっていたんだけど、それでもなおかつ平静ではいられなかった。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
「アリーのミット」からの連想が「一塁ベースを踏ませないはずだ」という表現へとつながっていくところがいい。
変わり続けることへの恐怖
本作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』では、この手の「細部のディテール」における細工がすごい。
細部のディテールを読み飛ばしてしまったら、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読む意味なんて、まったく失われてしまうだろうと思われるくらいに。
ちょっとした脱線(に見えるようなエピソード)にも、作者からのメッセージがある(「話のポイントからはずれない人は好きです。でもね、そのポイントにしがみつく人はそんなに好きじゃないんだな」)。
何度も登場する「赤いハンティング帽子」や「セントラルパークのアヒル」が意味しているものは何か?
その細部を読みこんでいくことが、つまり、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』という小説を読みこむということなのだ(これが楽しい)。
エドモント・ホテルで、若い売春婦(サニー)を(セックスもしないで)追い帰した直後に思い出したのは、死んだアリーのことだった。
アリーがそれを聞きつけて、自分も一緒に行きたいって言い出した。それは駄目だよと僕は言った。お前はまだ小さいんだからってさ。だから、すごく落ち込んだときなんかに、僕はずっとこう言い続けるわけだ。「オーケー。うちに帰って自転車を取ってこいよ、ボビーのうちの前で会おうぜ。さあ、急いで」ってさ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
世の中の「インチキ」な面を発見するたびに、ホールデンは傷ついていく(「だから十ドルなんだよ、チーフ。そう言ったじゃないか」)。
アリーの分身たるホールデンは、常にアリーと(内面の自分自身と)対話を続けていた。
この物語は、ホールデンとアリーによる自己対話の物語である。
アリーは、まだ生き続けていたのだ(ホールデンとして、ホールデンの心の深いところで)。
ニューヨークの街を徘徊しながらも、ホールデンが考えているのは死んだアリーのことだった。
クリスマス気分あふれる五番街で、彼は「自分がこのまま消えてしまうのではないか」といった恐怖にとらわれる。
それから僕はあることをやり始めた。四つ角に行くたびに、自分が弟のアリーと話をしているって思いこむことにしたんだ。僕は言った、「アリー、僕を消したりしないでくれよな。アリー、僕を消したりしないでくれ。アリー、僕を消したりしないでくれ。頼むぜ、アリー」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
あるいは、アリーは、時間の流れを象徴する存在だったのかもしれない。
変わっていくことを、世の中が変わり続けていくことを、ホールデンは何よりも恐れていたからだ。
「僕にはもうこの通りを向こう側まで渡りきることができないんじゃないかっていう気がしたんだよ」と、常に「死」を意識しているホールデンは、まさしく死んだアリー自身である。
両親に会うかもしれないという危険を冒してまで、ホールデンが自宅へ戻ってフィービーと会うのも、やはり「死」への恐怖からだった。
もし僕が肺炎をこじらせて死んじゃったら、フィービーはどんなふうに感じるだろうって想像してみた。(略)もし実際にそんなことになったら、たぶんフィービーはすごくがっかりしちゃうはずだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
変わり続けていく世の中では、誰が、いつ死んでもおかしくない。
この物語が、当時の退役軍人からも強く支持されたという背景には「いつ死んでもおかしくない」という恐怖への共感があったのではないだろうか。
「生きにくさ」が意味するもの
死んだ自分自身への思いは、博物館のミイラとして再現される。
「ミイラ? ミイラってどういうものなの」と僕は一人の子どもに尋ねた。「ほら、ミイラだよ。死んじまったやつだよ。トゥーンに埋められたやつ」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
ミイラの話は、物語の冒頭で、スペンサー先生との会話の中にも登場していた(「で、君は自由選択の記述問題で、自らエジプト人について書くことを選んだ」)。
物語の細部が、あちこちでリンクしているということも、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の特徴と言っていい。
もちろん、「死んだ人間が生きている」ということは現実的にあり得なかった。
妹(フィービー)が、そのことを指摘している。
「アリーは死んでるんだよ。自分でいつもそう言ってるじゃない! もし誰かが死んでしまって、天国にいるとしたら、それはもうじっさいには──」「死んでるってことはわかってるよ! 僕がそのことを知らないとでも思っているのか? それでもまだ僕はあいつのことが好きなんだ。それがいけないかい?」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
10歳のフィービーもまた、生きているアリーの化身である(「フィービーはもう十歳で、昔のようなおちびじゃない」)。
主人公(ホールデン)にとって、妹(フィービー)は、やはり特別の存在だった(アリーと同じように)。
君にフィービーを会わせたい。フィービーくらい可愛くって頭のいい小さな女の子って、君はこれまでの人生を通して目にしたことがないはずだ。ほんとに頭がいいんだよ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
フィービー(10歳のアリー)は、ホールデン(16歳のアリー)が苦しんでいることに傷ついている。
それは、もしかしたら生きていたかもしれないアリーが感じていただろう痛みだったのだ。
なにしろ、「アリーが生きていたかもしれない世界」は、アリーにとって(あるいはホールデンにとって)、あまりにも生きにくい世の中だった。
この「生きにくさ」は、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』という世界観の大きなテーマとなっている。
アリーの「もうひとつの人生」を象徴するエピソードとして、ジェームズ・キャッスルの自殺を忘れることはできない。
もう死んでいて、血やら歯やらがあたりに飛び散っていた。みんな遠巻きにしているだけだった。彼は僕が貸したタートルネックのセーターを着ていた。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
白血病で死んだアリー、飛び降り自殺したジェームズ、ニューヨークの街で傷つきながら生きているホールデン。
それらは、すべて、たった一人の人間の物語だったかもしれない。
つまり、そこは、どうあっても生きていくには厳しい(厳しすぎる)世の中だったのだ(特にアリーのように純粋な少年にとっては)。
彼らが生き延びるためには、兄(DB)のように生きていくしかなかった。
DBってのは僕の兄さんなんだけど(略)。ところが今じゃ、ハリウッドに移って、せっせと身売りみたいなことをしている。そうだよ、僕の兄のDBがだよ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
『秘密の金魚』のようにイノセントな小説を書いていたDBが、俗社会の象徴ともいえる「ハリウッド」で、俗社会の象徴である「映画」の仕事をしている。
それは、アリーやフィービーの否定であると同時に、彼らが生き延びていくための、ひとつの仮説だったのだ。
「身体を売って生きている」という点では、売春婦(サリー)も、小説家(DB)も同類だった(ここで二人がリンクしている)。
それが世の中を生きていくための選択肢だというなら、世の中は、あまりにも残酷で悲しい。
物語全体に通底しているのは、インチキな世の中を生きていくことの(つまり成長していくことの)悲しみである。
本作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読むときは、コールフィールド家の四人の子どもたちに注目する必要があるだろう(あくまでひとつの方法論として)。
実を言えば、僕は家族の中でただ一人出来が悪いんだ。兄のDBは作家をしているし、死んじゃった弟のアリーは前にも言ったように神童みたいなものだった。出来が悪いのは僕だけ。でも君はなんといってもフィービーに会わなくちゃいけない。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
彼らは、すべて、ひとつの人格から置き換えられた架空のキャラクターである。
死んでしまったアリー、生きているアリーとしてのフィービー、成長する過程で壁にぶつかっているホールデン、そして、生きにくさという壁を乗り越えた(つまり大人になった)DB。
DBだけが仮名(イニシャル)になっているのは、彼が、既に「向こう側」の人間になってしまったこと(インチキな世の中で生きる大人になってしまったこと)を示唆している。
もちろん、DBにとってさえ、生きていくことは簡単ではなかった。
兄のDBはなにしろ四年間も軍隊に入っていた。戦場にも行った。Dデイにも敵前上陸もした。でも彼は戦争よりも軍隊のほうをより憎んでいたと僕は真剣に思うんだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
DBの「軍隊に対する憎悪」は、学校生活や寄宿舎生活におけるホールデンの怒りとして再現されている(つまり、軍隊と学校がリンクしているのだ)。
戦争を乗り越えて、DBは生き続けている。
「DBはクリスマスには帰ってくるのかな?」と僕はきいた。「帰ってくるかもしれないし、こないかもしれないってお母さんは言ってた。成り行き次第なんですって。ハリウッドに残って、アナポリスを舞台にした映画のために脚本を書かなくちゃならないかもしれないんだって」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
彼らにできることは、生きている今を、ただ受け入れることだった。
フィービーがぐるぐる回り続けているのを見ているとさ、なんだかやみくもに幸福な気持ちになってきたんだよ。あやうく大声をあげて泣き出してしまうところだった。僕はもう掛け値なしにハッピーな気分だったんだよ。嘘いつわりなくね。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
回転木馬に乗って回り続けている間、フィービーは「永遠の10歳」である。
あの博物館と同じように、そこは時間という概念を越えた、永遠の空間だった(「この博物館のいちばんいいところは、なんといってもみんながそこにじっと留まっているということだ」)。
音楽は『おおマリー!』だった。五十年くらい前、僕がまだ小さな子どもだったときにも、まったく同じ音楽がかかっていたんだぜ。それが回転木馬の素敵なところなんだよ。いつだって同じ音楽がかかっているところがさ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
もちろん、永遠というものが存在しないことを、我々は既に知っている。
だからこそ、この物語『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は切ないのだ。
作品タイトルとなっている「ライ麦畑の捕まえる人」は、アリーであり、ホールデンである。
「つまりさ、よく前を見ないで崖の方に走っていく子どもなんかがいたら、どっからともなく現れて、その子をさっとキャッチするんだ。そういうのを朝から晩までずっとやっている。ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
そして、「ライ麦畑のキャッチャー」につまえてほしいと願っているのも、また、アリーであり、ホールデンだった。
死にたくなかったアリーと、死にたくはないというホールデンの叫び。
彼らの悲痛なSOSこそが、つまり、本作『ライ麦畑のキャッチャー』という物語が伝えている、重要なメッセージだったのだ。
17歳まで生き延びたホールデンに残された道は、ハリウッドで活躍する作家(DB)しかない。
あるいは、社会からドロップアウトして隠遁生活を送るか?(「で、どういうことかというとさ、僕らはその車で明日の朝、マサチューセッツとかバーモントとか、そういうあたりに行くのさ」)。
作者(サリンジャー)が選んだのは、まさかの隠遁生活だった(彼自身が「秘密の金魚」となってしまったのだ)。

果たして、物語の主人公(ホールデン・コールフィールド)は、この生きにくい世の中を生き抜いていくことができたのだろうか?
DBはほかのみんなほど悪質じゃない。でも僕にいっぱい質問を浴びせかけるという点では同じようなもんだ。この前の土曜日、彼は今脚本を書いている新作映画に出演するイギリス人の女の子を連れて、車でここに来た。彼女はかなりつんつんしてたけど、なにしろ美人ではあったね。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)
生きていくことの難しさ。
その難しさを乗り越えてまで生きていく価値が、この世の中にはあるのか?
そんな疑問を、この物語からは読みとることができる。
自分自身と向き合うために
村上春樹・訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』に登場する主人公(ホールデン・コールフィールド)は、野崎孝・訳『ライ麦畑でつかまえて』に登場するアグレッシブなホールデンに比べると、ずっと冷静で内省的だ。
彼は、むしろ、哲学者のように、人生と(つまり、自分自身と)向き合っている。
野崎孝の『ライ麦畑でつかまえて』(1964)が、激動の1960年代を象徴する物語だったとしたら、村上春樹の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(2003)は、「失われた30年」を象徴するゼロ年代の物語だったのかもしれない。
橋本福夫による初の邦訳『危険な年齢』(1952)は、もちろん、荒廃した戦後社会を象徴する物語だったのだろう。
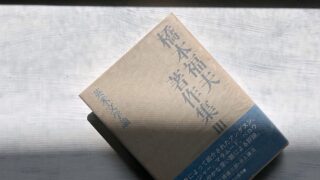
いつの時代にもホールデン・コールフィールドがいて、世の中に悩み、傷つき、苦しみながら生きていたのだ。
まるで、現代を生きる僕たちと同じように。
書名:キャッチャー・イン・ザ・ライ
著者:J.D.サリンジャー
訳者:村上春樹
発行:2003/04/20
出版社:白水社