中城ふみ子「乳房喪失」読了。
本書「乳房喪失」は、1954年(昭和29年)に刊行された、中城ふみ子の処女歌集である。
乳房を切除した女性の心情を詠う
中城ふみ子の『乳房喪失』は、その斬新なタイトルで記憶に残る歌集である。
乳がんの治療のために、乳房を切除した女性の心情を詠った作品が中心だが、本書に収録された短歌は、もちろん、乳房に関するものばかりではない。
夫との離婚、東京での暮らし、新しい恋、そして闘病生活と、この歌集には、昭和20年代に青春時代を送った若き女性の人生が描かれている。
いささか、天邪鬼な見方になるが、僕は、乳房喪失を詠ったものよりは、そこに至るまでの日々の暮らしの中に興味を覚えた。
衿のサイズ十五吋の咽喉佛ある夜は近き夫の記憶よ(中城ふみ子「乳房喪失」)
別れた夫を思う夜もあった。
愛想を尽かして別れた男性であっただろうに。
埃ふくガードの下の靴みがき目あげて田舎ものわれを見透す(中城ふみ子「乳房喪失」)
上京中の暮らしを詠んだものには、良い作品が多い。
プラタナス黄ばみ吹かるる街にしてギヴアンドテイクの恋ばかりみる(中城ふみ子「乳房喪失」)
都会志向の強い、若い女性らしさが、十七文字の中から伝わってくる。
もっとも、等身大の日常生活を詠ったものに、昭和20年代の日本が見えることも確か。
火元の女を呪詛する声も直きに止み明日は小さきバラツクが建たむ(中城ふみ子「乳房喪失」)
そういう意味では、朝鮮人部落を題材にした一連の作品も忘れがたい。
唐黍畑荒せしわれら童にて切なさもありし朝鮮部落(中城ふみ子「乳房喪失」)
個人的に言って、恋愛歌は、あまり好きではないが、次の作品などはいい。
自画像を抱えて猫背に帰りゆくきみの独身なお続くべく(中城ふみ子「乳房喪失」)
ページをめくりながら好きな短歌を探す楽しさが、一冊の歌集にはある。
傷だらけの20代を短歌で詠う
「あとがき」を読んでみる。
生きている中に自分の像を建てる様な用心ぶかさは愚かなことかも知れない。だが将来、母を批判せずには置かぬであろう子供たちの目に偽りのない母の像を結ばせたい希いが、ここ四年ほどの未熟な作品をまとめさせる要因になった。(中城ふみ子「乳房喪失」)
1954年(昭和29年)の夏に亡くなったとき、中城ふみ子は31歳だった。
「どの頁をひらいても母の悲鳴のようなものが聴こえるならば」と、ふみ子は綴っている。
ふみ子の20代は、傷だらけの20代だったのかもしれない。
ただ、そうした「悲鳴のような20代」が、『乳房喪失』に収録された素晴らしい作品群を生み出したことも、また事実であろう。
私小説作家が、肉を切り、血を流しながら小説を書いたように、ふみ子の短歌にも、彼女の肉や血の匂いを嗅ぎ取ることができる。
そのようなリアリティこそが、『乳房喪失』という歌集の本質なのではないだろうか。
先入観なしに本書と向き合えば、「淫乱な女流歌人」などという偏った評価は生じるはずがない。
屯せる駐留兵のまえ足鳴らし通りすぎ何の腹癒せとする(中城ふみ子「乳房喪失」)
進駐軍の前を通り過ぎるとき、足を踏み鳴らすふみ子の苛立ち。
そんな些細なところに、僕は中城ふみ子という歌人の魅力を感じるような気がした。
書名:乳房喪失
著者:中城ふみ子
発行:1954/8/25(重版)
出版社:作品社
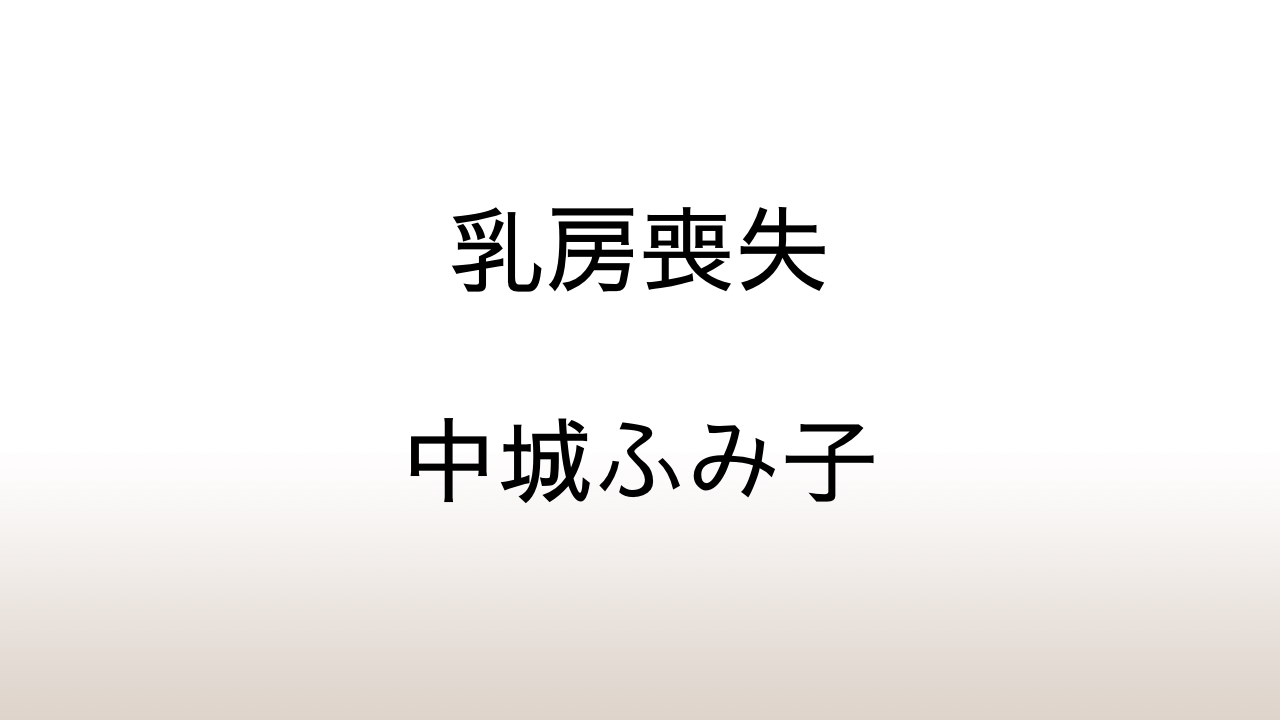


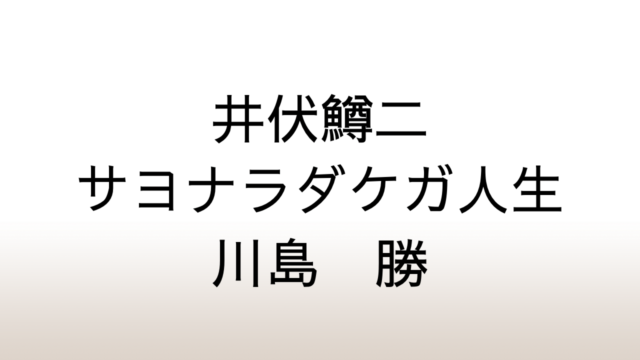
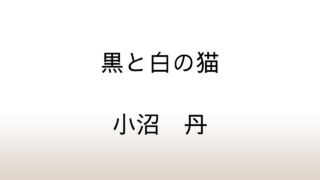
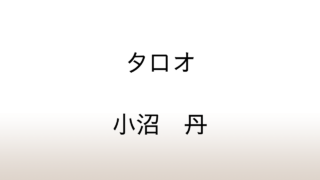
-150x150.jpg)









