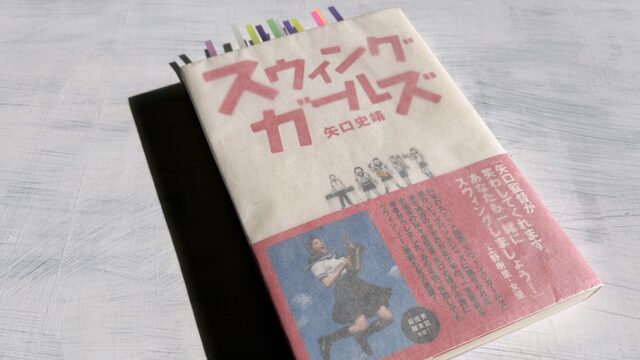島崎藤村「千曲川のスケッチ」読了。
本作「千曲川のスケッチ」は、1911年(明治44年)6月から9月まで『中学世界』に連載された長編随筆である。
この年、著者は39歳だった。
単行本は、1912年(大正元年)12月に佐久良書房から刊行されている。
四季の移り変わりの中で、小諸の自然と人を描く
本作「千曲川のスケッチ」は、1899年(明治32年)から1905年(明治38年)まで暮らした長野県小諸市の様子を綴った小諸滞在記である。
ここで藤村は、小諸の自然と人々とを四季の移り変わりを背景に、詩情たっぷりに描いている。
西の空はと見ると、山の端は黄色に光り、急に焦茶色と変り、沈んだ日の反射も最後の輝きを野面(のら)に投げた。働いている三人の女の頬冠り、曲めた腰、皆な一時に光った。男の子の鼻の先まで光った。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
一群のスケッチは、藤村が小諸に赴任した翌年の明治33年頃から書き始められたものらしいが、それは、藤村が韻文から散文へと作家スタイルを変える過渡期でもあった。
時々きらっと光るように詩的な表現の現れるところが、本作「千曲川のスケッチ」の魅力と言えるだろう。
また、『中学世界』という少年誌に発表された本作は、旧知の少年に宛てて書かれた体裁を採っているため、文章も平易で分かりやすい。
旧制中学は、現在の中学一年生から高校二年生までの子どもたちが在籍していたから、ほぼ中高生向きの読み物だったと言っていい。
つまり、中高生の関心を惹くよう、題材にも注意が払われているということである。
例えば「学生の死」では、十八歳で病死した教え子のことが綴られている。
士族地の墓地まで、私は生徒達と一緒に見送りに行った。松の多い静な小山の上にOの遺骸が埋められた。墓地でも讃美歌が歌われた。そこの石塔の側、ここの松の下には、Oと同級生の生徒が腰掛けたり佇立んだりして、この光景を眺めていた。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
信州の田舎町で死んだ、耶蘇教の少年。
日本の中の異国情緒を、当時の中高生たちは感じていたのではないだろうか。
明治小諸の貴重な記録文学
藤村は、小諸の自然に大きな関心を寄せているが、個人的には、小諸の習俗や人々の様子にいいものが多いと思った。
「巡礼の歌」は、冬のある日に見た、乳飲み子を背負った女の巡礼の話。
こうして山の上に来ている自分等のことを思うと、灰色の脚絆に古足袋を穿いた、旅窶れのした女の乞食姿にも、心を引かれる。巡礼は鈴を振って、哀れげな声で御詠歌を歌った。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
同じように下層社会の人々を描いた「一ぜんめし」もいい。
そこは下層の労働者、馬方、近在の小百姓なぞが、酒を温めて貰うところだ。こういう暗い屋根の下も、煤けた壁も、汚れた人々の顔も、それほど私には苦にならなくなった。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
この一膳飯屋「揚羽屋」が看板を張り替えるとき、常連だった藤村は、看板の文字を書くように頼まれたらしい。
食べ物の話でいうと、同僚教員と山小屋に泊まった「深山の燈影」も楽しい。
同僚教員は、山小屋の番人夫婦とも懇意で、持参した牛肉で鍋を作ってもらうが、二人は食べきれないほどの夕飯を食べる。
三杯ほど肉の汁をかえて、私も盛んな食欲を満たした。私達二人は帯をゆるめるやら、洋服のズボンをゆるめるやらした。「さア、おかえなすって──山へ来て御飯(おまんま)がまずいなんて仰る方はありませんよ」(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
満腹だと言っているのに、番人の細君は、同僚教員の茶碗に飯をいっぱい盛ってしまう。
「ひどいひどい──ひどくやられた」と言って、同僚教員が「チ、それじゃ、やるか、どうも一ぱい食った──ええ、香の物でやれ」などと言って、みんなを笑わせるあたりは、藤村の楽しい小諸時代を象徴しているのではないだろうか。
本作「千曲川のスケッチ」は、明治小諸の貴重な記録文学だが、最後の「奥書」には、島崎藤村という作家の、明治文学に寄せる思いが綴られている。
旧いものを毀そうとするのは無駄な骨折だ。ほんとうに自分等が新しくなることが出来れば、旧いものは既に毀れている。これが仙台以来のわたしの信条であった。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)
自分の青年時代と重ね合わせながら、藤村は明治二十年代の文学を懐かしく思い出している。
こういう文章にも、感傷的らしい藤村の文学の一端があるのだと思った。
そして、現代の我々にとって、この「奥付」は、明治二十年代から三十年代の文学を知る上で、非常に楽しく、分りやすいものだ。
書名:千曲川のスケッチ
著者:島崎藤村
発行:2004/06/05 改版
出版社:新潮文庫