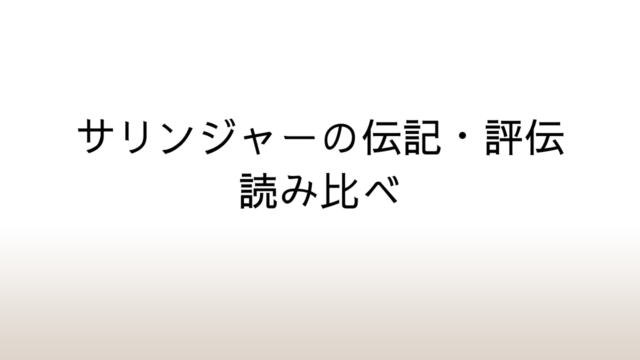村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」読了。
本作「ダンス・ダンス・ダンス」は、1988年(昭和63年)10月に講談社から刊行された長編小説である。
この年、著者は39歳だった。
ストーリーにコミットする洋楽や小説
村上春樹の長編小説の中で、最も多く繰り返し読んだ作品は、デビュー作『風の歌を聴け』(1979)だ。

爽やかな夏の青春小説である『風の歌を聴け』は、毎年、夏が近くなるたびに読み返すくらい好きだった(ページ数が少なくて、文章があっさりしているところもいい)。
読み終えた後で、最も深く感心してしまう作品といえば、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)である。

二つの物語がパラレルに進行する構成も凄いし、テーマの持つ重みは、いかにも純文学らしくていい。
しかし、読んで楽しい作品となると、本作『ダンス・ダンス・ダンス』以上のものはないだろう。
決して短くはないのに、あまりに面白くて、大抵の場合、あっという間に読み終えてしまう。
それでは、『ダンス・ダンス・ダンス』の、どこがそんなにおもしろいのか?
まず、主人公の軽妙なモノローグがいい。
本作『ダンス・ダンス・ダンス』は、孤独を抱えた34歳のバツイチ男性が、社会との繋がりを求めてジタバタする物語だが、彼のモノローグは都会的で、実に洗練されている(そして、ふざけている)。
漁師はセブン・スターを吸い、文学はショート・ホープを吸った。二人ともチェーン・スモーキングに近かった。彼らは「ブルータス」なんか読まないのだ。全然トレンディーじゃない人たちなのだ。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「漁師」も「文学」も、主人公を連行した赤坂署の刑事のあだ名だ(主人公が勝手に付けた)。
レイモンド・チャンドラーの『さらば愛しき女よ』(1940)で、フィリップ・マーロウが、大男の警官を「ヘミングウェイ」と呼んだのと同じようなものだろう。

「六法全書を持ってきてその法律のあるところを見せてくれと言おうと思ったが」とあるのも、レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(1953)へのオマージュらしい。
私はゆっくり立ち上がって、本棚からカリフォルニア州刑法をひき出して、デイトンにつきつけた。「ぼくが質問に答えなければならないと書いてあるところを教えてくれないか」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」清水俊二・訳)
主人公のキャラクターには、私立探偵(フィリップ・マーロウ)が多分に反映されているのだ。

本作『ダンス・ダンス・ダンス』は、主人公が、行方不明となった恋人(キキ)を探す(あるいは、メイを殺した犯人を探す)、ひとつのミステリー小説(あるいは探偵小説)として読むことができる(「わかった、執事が犯人だ」)。
「これはむずかしいぜ、ワトソン君」と僕はテーブルの上の灰皿に向かって言った。もちろん灰皿は何も答えなかった。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
主人公の軽妙なジョークは、会話文の中で一層と生き生きとする。
13歳のガールフレンド(ユキ)に、主人公は「ねえ、今度ディズニーランドに行ってみないか?」と誘いかける(この春、東京ディズニーランドがオープンしたばかりだった)。
「あんなところ行きたくなんかないわよ」と彼女は顔をしかめて言った。「ああいうの嫌いなの」「ああいうソフトでやわでわざとらしくて子供向きで商業主義的でミッキーマウス的なところは嫌なんだね?」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
高度資本主義社会の象徴であるディズニーランドを、主人公はディスっているのだが、実際、主人公(34歳)とユキ(13歳)との会話は、ストーリー上で重要な意味を持っている場合が多い。
一緒に旅行したハワイで、ユキは、初めてのお酒(ピナ・コラーダ)を飲む。
「おいしい」と彼女は言った。「動議支持」と僕は言った。「おいしいに二票」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
続けて二人は、「ユキと友だちになりたい」と言った母親(アメ)について話し合う。
「人と人が友達になるというのはすごく難しいことだと思うわ」「賛成」と僕は言った。「難しいに二票」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
学生運動の時代を引きずった主人公の古い価値観が示されているが、このあたりは、村上春樹節炸裂というか、とにかく、楽しんで好き勝手なことを書いている作者の姿が眼に浮かぶようでおかしい。
『ダンス・ダンス・ダンス』は、著者がリラックスして、伸び伸びと執筆していることが、分かりやすく伝わってくる小説なのだ。
だから、村上春樹を好きとか嫌いとかいう議論は、意外と、この作品で分かれるのかもしれない(「ついていけない」という人も多いだろうから)。
「山羊のメイ」と彼女は繰り返した。「あなたの名前は?」「熊のプー」と僕は言った。「童話みたい」と彼女は言った。「最高。山羊のメイと熊のプー」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
娼婦(メイ)のイノセントな可能性を引き出すのに、この会話は、激しく効果的に機能しているが、村上春樹という小説家の魅力は、こうしたところにあるのではないだろうか(優れた比喩力)。
かつて、主人公から「お姫様」と呼ばれたことで傷付いていたユキは、「ねえ、私のこと二度とお姫さまって呼ばないでね」とつぶやく。
「呼ばない」と僕は言った。「ちゃんと約束するよ。ボーイ・ジョージとデュラン・デュランに誓って約束する。二度と呼ばない」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
ジョークとシリアスのバランスが絶妙に取れている。
そして、ボーイ・ジョージ(カルチャー・クラブ)とデュラン・デュランに代表される無数のカルチャー・アイテムは、物語を立体的なものに仕立て上げる効果を発揮している。
この物語は、深い喪失感を抱えた中年男性の自分探しの小説でもある。
レイ・チャールズの「ボーン・トゥー・ルーズ」だった。それは哀しい曲だった。「僕は生まれてからずっと失い続けてきたよ」とレイ・チャールズが歌っていた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「そして僕は今君を失おうとしている」と歌うレイ・チャールズの喪失感は、主人公自身の喪失感でもあった。
この物語に登場する無数のカルチャー・アイテム(洋楽や映画や小説)は、単にオシャレな装飾としてではなく、物語に意味付けをするための重要な役割を担っている。
両親の愛情を求めてユキが泣いたとき、カーステレオから流れていたのは、ブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」だった。
ブルース・スプリングスティーンが「ハングリー・ハート」を歌った。良い歌だ。世界もまだ捨てたものではない。ディスク・ジョッキーもこれは良い歌だと言った。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「飢えた心」は、両親の愛情に飢えて泣くユキの心に、ダイレクトにコミットしていると読んでいい。
あるいは、ドルフィン・ホテルの一室で、憧れのユミヨシさんと過ごしているときに流れたマントヴァーニ・オーケストラ。
主人公は、ユミヨシさんの好きなブラディー・マリー(Bloody Mary)を作って、二人で乾杯する。
背景音楽が必要だったので、枕元の有線放送のスイッチを入れ、チャンネルを「ポピュラー音楽」というのにあわせた。マントヴァーニ・オーケストラが「魅惑の宵」を麗々しく奏でていた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「魅惑の宵」は、ブラッディ・メリー(Bloody Mary)という女性が登場するミュージカル『南太平洋』の楽曲である。
つまり、特別の説明はないものの、そこに登場するカルチャー・アイテムが、物語のストーリーにさりげなくコミットメントしているのだ。
音楽以外も同じで、象徴的なところで言うと、主人公が、二人の刑事から取り調べを受ける場面だろう(「漁師」と「文学」)。
「それで、一人で夕食食べてから、ずっと本を読んでたの?」と漁師が質問した。「まず皿を片付けて、それから本を読んだ」「どんな本?」「信じないかもしれないけど、カフカの『審判』」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
カフカの『審判』は、二人の警官に不当逮捕される物語だから、主人公は、わざわざ「信じないかもしれないけど」と前置きしているのだが、カフカを読んでいない二人の刑事には、たとえそれが痛烈な皮肉だったとしても通じることはない。
『ダンス・ダンス・ダンス』を読んでいて、音楽や小説が登場すると、一つ一つその意味を探ってしまう。
意味がないようでいて、しっかりと隠された意味を持っているのが、村上春樹の小説の楽しいところなのだ(まるで宝探しゲームみたいに)。
もう四月だ。四月の始め。トルーマン・カポーティの文章のように繊細で、うつろいやすく、傷つきやすく、そして美しい四月のはじめの日々。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
この物語では、大人の中のイノセント性が重要なポイントとなっているから、「傷つきやすい四月」という表現も、ストーリーにリンクしていると考えることができる。
たぶん運が悪いだけだ、と僕は結論を下した。そして新聞を読んでしまうと、フォークナーの「響きと怒り」の文庫本をバッグから出して読んだ。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
貴族の一家が没落して悲劇的な死を迎える『響きと怒り』は、やがて訪れる五反田君の死を暗示していたのだろうか。
意味がないまでも、深い共感を覚える文章表現は多い。
そうこうするうちにエリオットの詩とカウント・ベイシーの演奏で有名な四月がやってきた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「エリオットの詩」とあるのは、「四月は最も残酷な月」というフレーズから始まるT・S・エリオットの『荒地』だし、「カウント・ベイシーの演奏」とあるのは、「パリの四月」を意味している。
読んでいて、こんなに「楽しい」小説というのも珍しいと思う。
「何ということもなく気持ちの良い春の宵」に、主人公がゆっくり読んだという「佐藤春夫の短編」は、いったいどんな作品だったのだろうか。
いずれにしても、カルチャー・アイテムのイメージが、そのまま、物語のイメージを創造する効果は大きい。
1983年(昭和58年)4月に主人公が読んでいる87部署シリーズの新刊は『凍った街』(エド・マクベイン)。
牧村拓の従順な下僕として登場する「書生のフライデー」は、ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』に登場する召使いの名前(フライデー)に由来している。

「羊男」と「いるかホテル」は主人公の自己核だった
本作『ダンス・ダンス・ダンス』は、喪失感を抱えた男の自己再生の物語である。
物語の設定は、『羊をめぐる冒険』(1982)と同じものとなっている。
『ダンス・ダンス・ダンス』は『風の歌を聴け』と『1973年のピンボール』と『羊をめぐる冒険』という三部作の延長線上にあるものである。というよりも、もう少しはっきり限定して言えば『羊をめぐる冒険』の続編と言った方がいいかもしれない。(村上春樹「羊男の物語を求めて」)
つまり、『羊をめぐる冒険』で突然姿を消してしまったガールフレンドを探すために、当時、彼女と二人で泊まった「いるかホテル(札幌市内にある)」を訪ねるというのが、この物語の始まりとなっている。

主人公が、彼女(キキ)を探そうと思ったのは(四年半も経っているのに)、積み重ねられた深い喪失感を解消したいと考えたからだ。
僕はこう感じるのだ。彼女はいるかホテルという状況を通して僕を呼んでいる、と。そう、彼女は今また再び僕を求めているのだ。そして僕はいるかホテルにもう一度含まれることによってのみ、彼女ともう一度巡り合えるのだ。そしておそらく彼女がそこで僕の為に涙を流しているのだ。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
夢の中では細長い形に歪められている「いるかホテル」は、主人公自身の心の中だ(潜在意識。主人公も「問いかけるまでもなく、答えは始めからわかっている。ここは僕の人生なのだ」と言っている)。
羊男に動かされている主人公は「僕が僕自身についていったい何を知っているのだろう?」と、自問自答を繰り返す(しかし、「でーたフソク、カイトウフノウ」)。
だから、キキを探す旅は、主人公自身を探す、自分探しの旅でもある。
もう一度「羊男」に会うことによって(自己核を見つけることによって)、主人公は、自分自身を取り戻し、深い喪失感から解放されることを望んでいたのだろう。
主人公の自分探しの旅は、現代性と過去性という大きな対比の構造の中で進められるが、その象徴として登場するのが、旧式の「いるかホテル」と、最新の「ドルフィン・ホテル」である。
古い価値観(踏み込んで言えば1970年前後の学生運動の時代の)を捨てきれない主人公は、高度文明社会と自分自身との折り合いをうまく付けることができない、現代社会のはみ出し者だった。
牧村拓(ユキの父親で作家)からは「考え方のシステムがどうこうなんて時代じゃない」と指摘され、漁師(赤坂署の刑事)からは「なあ、今は一九七〇年じゃないんだよ」と突き放されているのも、主人公の旧式な価値観を表したものだろう。
旧式な「いるかホテル」の管理人とも言うべき「羊男」は、主人公自身の意識の核と言える(もう一人の自分、生身の自分、本当の自分)。
村上春樹の小説では、潜在意識下の自分(もう一人の自分)と会話する場面が、頻繁に登場するが、「もう一人の自分」の存在は、特別に珍しいものではない。
スポーツ競技では、本来の実力を出せない場合に「自分を見失っている」と表現することがあるし(あるいは「こんなの、私じゃない」みたいな)、本来の力を発揮したときには「自分を取り戻した」というような表現を使う。
意を沿わない命令に従うとき、我々は「自分を殺して」仕事に取り組むわけで、人は、いつでも、「本当の自分」の存在を、自分自身の中に意識しているものなのだ。
だから、古い「いるかホテル」に迷い込んだ主人公が「羊男」と会話をする場面は、主人公自身との「心の対話」として読んでいい。
何処にも行けないままに年をとりつつある自分は、誰をも真剣に愛せないまま、何を求めればいいのか分からなくなってしまった。
「ねえ、僕はもう一度やり直してみたい」と打ち明ける主人公に、羊男は「踊るんだよ」とアドバイスする。
「でも踊るしかないんだよ」と羊男は続けた。「それもとびっきり上手く踊るんだ。みんなが感心するくらいに」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
結局のところ、人生がダンスのようなものだとしたら、音楽の鳴っている間、人は踊り続けるしかない。
少なくとも、それが、1980年代を生きる大人の、人生哲学だったのだ。
不器用な主人公と対照的に、現代社会の申し子として登場するのが、中学校時代の同級生「五反田君」である。
「いろんな可能性があった」と五反田君はグラスを顔の上にあげて天井のライトにすかせて見ながら言った。「なろうと思えば医者にだってなれた(略)目の前にカードがずらっと並んでた」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「カードなんて見たこともなかった」とつぶやく主人公の言葉を、五反田君は冗談だと思ってにっこり笑うが、トレンディ俳優として活躍する五反田君も、外側からは想像も付かないような「心の闇」を、自分自身の中に抱えている(それは「現代社会の闇」でもある)。
結局、主人公の指摘に答える形ですべてを告白した後(シェーキーズ)、五反田君は自殺するが、現代社会のメタファーたる五反田君の死を受け入れることで、主人公は、大きな喪失感から解放されたと言える(過去性が現代性に勝った)。
五反田君は「ある種の自己破壊本能だろう」と自己分析しているが、主人公と同じ学生運動の時代を生きた五反田君も、やはり、自分の中の現代性と過去性との一致に困難を抱えていたのだ。
「時々ひどく疲れるんだ、そういうのに」と五反田君は言った。「すごく疲れる。頭痛がする。本当の自分というものがわからなくなる。どれが自分自身でどれがペルソナかがね」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
現代性と過去性という大きな対比構造の中で、現実とイメージとの対比という問題を抱えて、人は現代社会を生きている(「あの子はお伽噺を信じすぎたんだ」)。
おそらく、死んだ「鼠」の延長線上にあると思われる五反田君は、主人公自身の姿でもある。
僕は泣きたかった。でも泣くことさえできなかった。そう、五反田君は僕自身なのだ。そして僕は僕自身の一部を失おうとしているのだ。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
ひどく突き詰めて言えば、『ダンス・ダンス・ダンス』は、主人公と五反田君との戦いの物語である。
それは、主人公にとって「自分との戦い」でもあった。
激変する社会の中で、自分の価値観が無意味に思えてきたとき、人は強い疎外感を覚える(特に、自分の価値観が旧時代のものであるとき)。
心の闇を告白して五反田君が死んだとき、主人公は、自分の価値観に自信を取り戻すことができたのだろう(つまり、五反田君の死は、主人公にとってカタルシスとしての機能を果たした)。
可能性はあるのだ、と僕は思った。そしてそう思った瞬間に何かが終わったような気がした。とても微妙に、そして決定的に、その何かは終わってしまったのだ。何かとはいったい何だ?(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
その主人公の戦いを隣でサポートしてくれていたのが、不登校の霊感少女(ユキ)である。
13歳のユキは、大人とも少女とも区別の難しい女性として登場する。
髪を上できゅっとまとめて色の濃いサングラスをかけ、小さなビキニに身を包んでビーチに寝転んでいると、ユキは年齢がよくわからなくなった。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
酒を飲み(ピナ・コラーダ)、煙草を吸う(ヴァージニア・スリム)ユキは、疑似的な大人の女性として描かれるが、13歳の女子中学生であるが故に、主人公とセックスすることはできない(つまり、肉体的に繋がる必要がない)。
彼女もまた、現代社会を受け容れることのできないアウトローであり、主人公との間に強い共感性を抱くことになる(局部的に激しい共感性は、ユキの大きな特徴となっている)。
死んだディック・ノース(片腕の詩人)に冷たい態度を取ったことを後悔するユキに、主人公は「そういう考え方は本当に下らないと僕は思う」と言って、冷たく突き放す。
「でもそれはとても難しいことみたいに思えるけれど」と彼女は言った。「難しいことだよ、とても」と僕は言った。「でもやってみる価値はある。ボーイ・ジョージみたいな唄の下手なオカマの肥満児でもスターになれたんだ。努力がすべてだ」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
ジョークとシリアスのバランスを取りながら、主人公は、13歳のユキと真剣に向き合っている。
五反田君の死を乗り越えて、主人公がユミヨシさんの元へと戻っていったとき、ユキもまた、自分の居場所を見つけて、現実世界へと戻っていった(「私、家庭教師につくことにしたの」)。
つまり、主人公の自分探しの旅は、13歳のユキにとっても、自己再生の物語となっていたのである(五反田君の死によって浄化された結果という言い方もできる)。
主人公と五反田君の物語と、主人公とユキの物語という二つのストーリーが、終盤でドッキングして、すべての事件を解決に導くという小説的な構造は、やはり、レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』に対するオマージュだったのかもしれない。
ハワイのオフィス・ビルの一室で見た白骨は、主人公自身の成長だ(浄化の軌跡)。
「あれはいったい何を意味していたんだろう? 六体の白骨」「あなた自身よ」とキキは言った。「ここはあなたの部屋なんだもの、ここにあるのはみんなあなた自身なのよ。何もかも」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
「私はあなた自身の投影に過ぎないのよ」と、キキは言った。
「あなたが泣けないもののために私たちが泣くのよ」とも。
著者・村上春樹は、「自作を語る」の中で、羊男といるかホテルが主人公の自己核であることを明らかにしている。
『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公の「僕」が、ことあるごとに、いわば宿命的に、羊男とドルフィン・ホテルというデフォルメされた自己核に引き戻されていくように、作家としての僕もいつも何かの節目にさしかかるたびに、宿命的に羊男という存在に、そして羊男の住んでいる場所に、引き寄せられていった。(村上春樹「羊男の物語を求めて」)
思うに、人は誰しも、自分の中に、羊男を住まわせている。
そして、人生に迷ったときに、人は、自分の中の羊男と会話をしているのだ(おそらくは無意識のうちに)。
自己対話の物語ということでは『1973年のピンボール』や『羊をめぐる冒険』と同様の作品と言うことができるが、物語としてのスケールは、これまで以上に壮大で複雑なものとなった。
おそらく『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という作品が、「鼠三部作」を、より熟成させた結果なのだろう。
札幌のドルフィン・ホテルでユミヨシさんと結ばれる場面は、主人公の再生を具象化したものである。
主人公と一緒に「壁」を抜けたユミヨシさんは、しっかりと主人公の心にコミットすることができたのだ。
ポイントは、彼女の持っているイノセンス性である。
ユミヨシさんと深く結ばれた後で、主人公は眠っている女を抱きながら、そっと一人で泣いた。
時々声を出さずに泣いた。僕は失われたもののために泣き、まだ失われていないもののために泣いた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
主人公が泣き終わったとき、静かに夜が明ける。
再生。
やがて、朝が訪れて「ユミヨシさん、朝だ」と囁く主人公の言葉は、主人公の再生を明確に描き出している。
もしも、村上春樹の作品を一つだけ選ぶとしたら、僕は、やはり『ダンス・ダンス・ダンス』を選んでしまうような気がする。
ジョークとシリアスのバランス。
基本的に、村上春樹の小説は「自分語り」の物語である。
自分の興味のある人は、村上春樹の小説を好きになることができるし、自分自身に興味のない人は、村上春樹の小説を好きになることもできない。
もしかすると、そんな仮説を立てることもできるのではないだろうか。
書名:ダンス・ダンス・ダンス
著者:村上春樹
発行:1991/12/15
出版社:講談社文庫