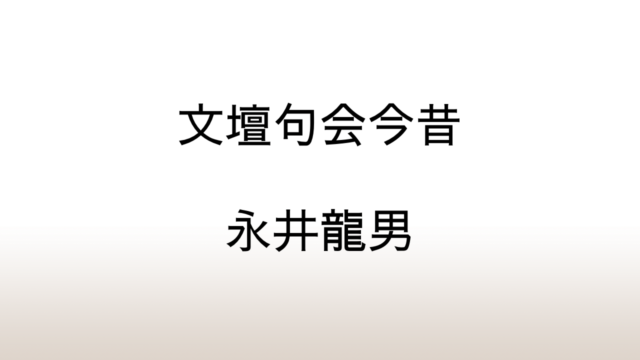鎌田敏夫『男女七人夏物語』は、1987年(昭和62年)7月にカドカワノベルズから刊行された長篇小説である。
この年、著者は51歳だった。
1986年(昭和61年)、明石家さんま・大竹しのぶ主演テレビドラマ『男女7人夏物語』原作小説(ノベライズ)。
自分自身と戦うアラサー男子たち
テレビドラマ『男女7人夏物語』の続編である『男女7人秋物語』は、1987年(昭和62年)10月から12月まで放映された。
その直前の夏に、カドカワノベルズから刊行された長篇小説が、本作『男女七人夏物語』である(ドラマでは数字だった「7人」が、小説では漢字の「七人」になっている。読み方は「しちにん」が正しい)。
『秋物語』の放映を前にして、『夏物語』の感動を再び!という思惑があったのかもしれない。
1986年(昭和61年)の夏に放映されて大人気となった『夏物語』が、1987年(昭和62年)の夏に(小説として)復活したのである。
『男女七人夏物語』は、タイトルのとおり、男性3人、女性4人、計7人のアラサー男女が繰り広げる恋愛ストーリーである。
80年代のバブル景気の始まりは、1986年(昭和61年)10月に発生したブラック・マンデーの直後である、1986年(昭和61年)12月頃からと言われる。
だから、『男女7人夏物語』が、最初にテレビ放映された1986年(昭和61年)の夏は、正確に言うと、まだ「バブル景気」ではない(バブル経済前夜だった)。
主人公(今井良介)は30歳で、転職を繰り返した末、現在はツアーコンダクターとして働いている。
今のツアーコンダクターの仕事は、もう四年になる。今まで、長続きしなかったのは、堪え性のせいではない。自分の可能性を信じていたからなのだ。自分というものを醒めた目で見るようになった時に、三十という年になっていた。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
良介にとって20代は、自分探しをする時期でもあった。
でも何かに嫌気がさして辞めたのではない。もっと自分に合ったことが他にあるのではないか、そんな気がしたから辞めたのだ。こんな自分ではない、違う自分がどこかにあるような気がした。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
結局、30歳になって、良介は新しい自分を探すことをあきらめた。
物語の最終場面で、恋人(神崎桃子・27歳)が、「マイケル・ジャクソンの全米ツアーの取材へ行きたい」と行ったとき、良介は「行ってこいや」と、桃子の背中を押す。
自分探しをした20代の良介が、そこには伏線として含まれていたのだ。
「おれ、夢が叶うってことが、どんなに嬉しいか、自分でもよう分かっとるんや。だから、桃子にも行かせてやりたかったんや。別に、自分一人カッコつけてたわけじゃないよ! カッコつけて、あんなこと言ったんじゃないよ」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
夢をあきらめた良介が、恋人(桃子)の夢の後押しをする。
そういう意味で、この物語は、主人公(今井良介)の成長物語として読むことができる。
「おれ。自分のすることを、人に決めてほしくないんや。自分のものやろ、自分の人生は……そやから、決めるのは、やっぱり自分やないか……」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
一度は恋人になった浅倉千明に、良介はツアーコンダクターの魅力について話してみせる。
「でもね、人間って面白い生き物やなあってだんだん思えてね……アホやってるみたいでも、みんなそれなりに一生懸命生きてるんやなあって……人間好きにならんと、コンダクターって商売は勤まらん……」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
ツアーコンダクターの仕事を通して、良介は、人間が持つ可能性の魅力について語っている。
「可能性の魅力」は、最終場面で、桃子の背中を押す大きな原動力となって現れるものだ。
「おれも、昔はそう思ってたよ、ええ年してって……でも、この商売やってるうちに、人間って幾つになってもようやるなあ……おもろいもんやなあって、思えるようになったんや」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
成田空港で桃子を見送ったとき、良介は、桃子を励まして送り出す。
「もっと自分を信用せえや……おれを信用せえや」良介の言い方には、心がこもっていた。「人間って、もっとええもんやで」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
半年も別れて暮らさなければならない二人の不安は、既に、複雑な家庭環境で育った野上君章や浅倉千明のエピソードとして提示されている。
つまり、「人間って、もっとええもんやで」という良介の言葉は、本作『男女七人夏物語』を象徴するものだったのだ。
良介の人間肯定の姿勢は、他の6人に対してもポジティブな影響を与えていく。
父親と離婚した母親(シングルマザー)に育てられた野上君章(32歳)は、女性を(恋愛を)信じることができない。
「君の親も、おれの親も、人を憎むことしか教えてくれなかったんだよ」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
いろいろな女性とセックスだけの関係を繰り返す野上に、良介は歯がゆい思いを抱いていた。
「女から逃げてばっかりやと、そら、女のいやなとこも見んですむかもしれんけど、女のいいとこも一生分からずじまいや」「……」「いっぺんくらい、女と正面向いて付き合えや」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
自分の性格を最も正しく理解していたのは、もちろん、野上本人だったに違いない。
野上もまた、自分の中の自分自身と戦っていたのだ(自己葛藤)。
「マザコンなの、彼?」「マザコンとは違いますよ。その時に、おふくろのいやなとこ全部見てますからね、どっかで女を好きになりきれんとこがあるのと違いますか……」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
「人生は楽しく生きなきゃつまらないの……どうせ百年たたないで死んじゃうんだから」と言ったのも野上だった(「ノー天気はペシミズムから生まれるのだ」)。
野上は、好きでもない女性と同棲している良介に頼まれて、良介の女を誘惑した(寝取った)ことがある。
「自分のしたことが、人を傷つけるなんて考えもしなかった」「おれも、そや」「若かったんだよ、お前もおれも」今でも若いとは思っている。でも、もっと若かったのだ。自分のことを考えるだけで精一杯で、他人の心の中を考える余裕なんかなかった。いっぱしに世の中を知っているつもりで、自分のことしか知らない若さ。自分のことさえ、分かっていなかったかもしれない。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
「自分のことさえ、分かっていなかったかもしれない」というところに、32歳になった野上の気づきがある。
野上と同じように、不仲な両親のもとで育てられた浅倉千明もまた、恋愛を信じることのできない女性だった。
「親をどっかで憎んでるんでしょう、あなたも?」君章が、千明を見た。「そういう人は、なかなか人を愛することができないのよ」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
敏感な千明は、野上が、自分と同種の人間であることを目ざとく見つける。
ビヤホールで会っている間、千明は君章に自分を見るような気がしていた。本気で人を好きになることはなく、女の自分に寄せる気持をただ楽しんでいるような付き合い方。自分もまた、男とそんな付き合い方を、してきたのではないか。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
みんなで部活動の思い出で盛り上がったときも、千明は「耐えて走るだけなの、あなたは?」と、自分自身に問いただしていた。
凍った千明の心を癒したのは、主人公(良介)の人間肯定の姿勢である。
「私、自分が女だってことがすごくいやだった……人間だってこともいやだった……自分が人間でなかったら、どんなにいいだろうって、いつも思ってた……」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
一度は良介と恋人関係になるものの、桃子に惹かれていた良介にフラれる形で、結局、千明は失恋してしまう。
しかし、失恋のエピソードは、千明の成長にとって必要な経験だったのだろう。
自分に思いを寄せる大沢貞九郎の純粋な愛情を、千明は最後に受け入れてみせる。
「あなたにとって、おれは男じゃないかも知れないけど、おれにとっては、あなたは女なんだ」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
まっすぐに生き続ける貞九郎もまた、自分自身と戦う一人の男だった。
「そんなこと言ったって……」貞九郎は、静かな声で言った。「千明さんは、おれのこと好きでも何でもないじゃないですか。おれ、それで盛岡に行く気になったんですよ」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
かつて、千明を捨てて桃子と恋人関係になった良介を、殴り飛ばした貞九郎である。
「貞ちゃんのこと、ほんとに好きになる」と泣いた千明を受け容れることは、貞九郎にとっても、ひとつの成長だったに違いない。
この物語で、最も大きな成長を遂げるのは、良介の恋人になった神崎桃子である。
唇を離すと、桃子は、まっすぐにゲートに向かって行った。もう振り返らなかった。エスカレーターを降りていきながら、桃子が、背を向けたままで、右手を振った。次に、左手を振った。それだけで気がすまなかったのか、両手を振った。両手を上げた。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
桃子の成長は、理想化された家庭像(象徴として父親が登場している)からの解放である。
「このまま帰ったら、私は、桃子を許さないわよ」千明の声が冷やかだった。「一度くらい、いい子やめなさい、桃子」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
かつて、千明は、桃子の家庭を理想の家庭だと信じていた。
平凡な家庭、平凡な幸せ、それは、千明の昔からの憧れだったのだ。平凡な幸せを一杯持っている桃子が、非凡な生き方に憧れるように、平凡な幸せとは無縁だった千明は、ありふれた幸せが欲しいと、ずっと思っていたのだ。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
家庭像がはっきりと明示されている千明と桃子は、この物語で重要な役割を果たしているが、それは、良介と野上との対比に表わされているものと同じものだっただろう。
逆に言うと、家庭像が示されていない大沢貞九郎・沢田香里・椎名美和子の三人は、他の四人を補完する役割として登場していることになる。
もちろん、野上と恋人関係を築く香里は、男に振り回される女からの脱皮として(「香里は、男に振りまわされてばかりいる女とは、違った自分になっているのを感じていた)、「だって、いつかは結婚したいけど、なるたけしたくないんだもの」と言っていた美和子は、お見合いを受け容れて結婚する女性として、それぞれに成長エピソードが語られることにはなるのだが。
「人間なんてさ、自分のしてることが全部はっきりと分かってるわけじゃないじゃない、千明?」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
桃子の言葉は、自分自身に問いただすものでもあった。
「何も知らないくせに!」桃子は、向こうから叫んだ。「あなたなんか、大嫌い!」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
後に、良介は、「あんたが、そんなに、おれのこと好きだなんて、おれ、思ってなかったから……」と、桃子に振り返る(「わざわざ大嫌いって言うのは、好きやって言うことやないか」)。
実直な桃子を育んだものは、温かい家庭環境である。
「桃子は、平凡な幸せをいっぱい持って生きてきたから、そんな風に言うのよ!」千明は、怒ったように言っていた。桃子に怒ったのではない。自分に向かって怒ったのかも知れない。平凡な幸せを持てなかった、自分の人生に向かって。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
平凡な幸せを育んだ温かい家庭は、もう少しで30歳を迎えようとする桃子にとって、自分自身の殻でもあった。
温かい家庭を持たなかった千明には、それが「みんなが、ちょっとずついい子ぶっている」家庭のように見えたのだ。
「みんなが、ちょっとずついい子ぶって、みんなが、ちょっとずついたわり合って……だから、あんないい家庭が出来ていたんだと思う……」(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
父親と一緒に、故郷・京都へと向かう新幹線の中で、千明からの電話を受けた桃子は、新横浜駅で列車を降りる。
温かい家庭の外へ、一歩踏み出したのだ。
マイケル・ジャクソンの全米ツアーの話を持ってきた音楽雑誌の女性編集者は、「女だからって、一生の夢を、そう簡単に放棄するもんじゃないわよ」と言った。
「ノンフィクションのライターになりたい」という桃子の夢は、自分探しの転職を繰り返した結果、ツアーコンダクターとして働いている良介の人生との対比である。
そこには、「30歳」という人生の節目となる年齢が持つ、ひとつの意味が暗示されている。
料亭で蟹を食べた七人が、夜の野球場で騒いで笑う場面があった。
夏の夜の街を、七人は、ただフラリフラリと歩いていった。誰も、どこへ行こうとも言わなかった。(鎌田敏夫「男女七人夏物語」)
「夏の夜の街を、七人は、ただフラリフラリと歩いていった」とあるのは、30歳を迎えた男たちの(30歳を迎えつつある女たちの)人生に対する投影として読むことができる。
村上春樹は、多くの作品で、30歳になることの焦りと不安を描いた(『羊をめぐる冒険』『ニューヨーク炭鉱の悲劇』など)。
そもそも、村上春樹が『風の歌を聴け』で小説家としてデビューしたのも、30歳のときだった。
村上春樹の愛読書である『華麗なるギャツビー』(F・スコット・フィッツジェラルド)の主人公たちもアラサー世代である(物語の語り手であるニック・キャラウェイは、作品中で30歳の誕生日を迎えている)。
つまり、青春の最後のきらめきであり、人生の次のステップへと踏み出さなければならない30歳という日々の葛藤を描いたものこそ、本作『男女七人夏物語』という物語だったのだ。
七人は、誰もが自身の葛藤と戦っており、自分だけのドラマの中では、誰もが主人公である。
男女七人の青春群像劇は、彼らの成長に必要なものだったのだ。
やがて、彼らは『男女七人秋物語』(1987)の中で、次のステージへと進むことになる。
我々の成長にゴールというものはないからだ。

80年代の(ましてバブル時代の)トレンディドラマというと、どうしてもチャラチャラとしたイメージが付きまとうが、本作『男女七人夏物語』は、真剣に生きているアラサー男女の、最後の青春物語だった。
彼らは、あまりに真剣だから、時に誰かを傷付け、自分自身で傷付いてしまう。
桃子が、アメリカで恋人を作って帰ってくる続編『秋物語』は、<罪と赦し>をテーマとしたヘビーな作品だが、彼らは、いつでも真剣に、自分の人生と向き合っていた。
彼らが教えてくれたものは、もしかすると、「ひたむきに生きる姿勢」だったのではないだろうか。
できることなら、『男女七人秋物語』を小説という形で読んでみたいが、『秋物語』のノベライズは出版されていない(シナリオブックはあるが)。
彼らは、テレビドラマの中でこそ、輝く存在だったのかもしれない。
書名:男女七人夏物語
著者:鎌田敏夫
発行:1987/07/25
出版社:カドカワノベルズ