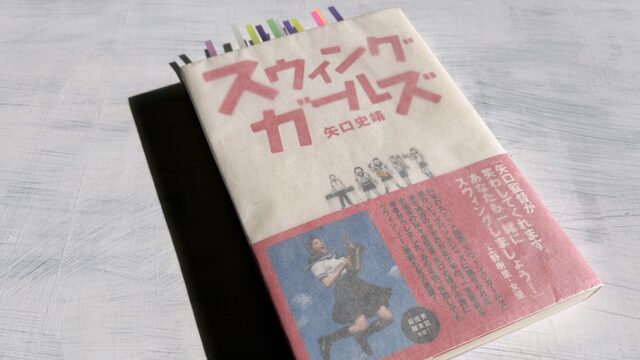庄野潤三「団欒」読了。
本作「団欒」は、1954年(昭和29年)6月『文芸』に発表された短編小説である。
この年、著者は33歳だった。
作品集としては、1955年(昭和30年)2月にみすず書房から刊行された『プールサイド小景』に収録されている。
第31回(昭和29年/1954年上期)芥川賞候補作(参考作品)。
戦争中の母の思い出を語る
本作「団欒」は、作家となった<私>(つまり作者である庄野潤三)が、母親孝行をしたときの体験を書いた物語である。
芥川賞候補作(参考作品)で、選考委員の評価は高くなかったが、僕は、庄野さんのこういう作品が好きだと感じている。
家族への愛情に満ちた小説は、庄野潤三にしか書けない種類の文学であり、やがて、その流れは「夕べの雲」を始めとする一連の家族小説として結実していくものになると思われるから。
その話は、母の日を記念して開催された「母と子の集い」において、<私>が実際に演説したものを再現している。
私は長い時間、人前に立つのは苦痛であった。弁舌は巧みな方ではないし、緊張すると手が震えるという難点があった。更に私はすべて役所のすることが嫌いであった。(庄野潤三「団欒」)
役所というのは、<私の住んでいる都市の教育委員会>のことで、<私の父>は、この都市の第一回の教育委員に当選して、任期満了の直前に脳溢血で亡くなった人であった。
庄野潤三の父・庄野貞一は、昭和23年に大阪府教育委員に就任。初代教育委員長にも選出されている。
このフォーラムで、<私>は、戦争中にあった、母との思い出について話をする。
それは、大阪の母と妹が、千葉県館山の海軍砲術学校にいる<私>に会うため、上京してきたときのことで、ちょうどマニラの航空隊への赴任が決まった<私>は、母や妹と何度も行き違いになってしまう。
大阪の父が発した電報による指示が、余計な混乱を招いたところがおかしいが、どうにか家族は久しぶりの対面を果たすことができる。
立川の航空隊にいる弟も呼んで、家族は団欒の時を過ごすが、それは、あまりにも一瞬のことだった。
演説の最後で、<私>は、こんな話をしてまとめる。
「その時から七年たちましたが、その間に私の母はずいぶん年を取りました。もしも今度また戦争が起って、もう一度あの時のような状況になったとしても、母には重い荷物と軍刀を持って満員電車に乗ってはるばる面会に来てくれることは到底出来ません。そのことだけでも、私は戦争はもう御免だと思っています」(庄野潤三「団欒」)
庄野文学における家族小説の原型
フォーラムの会場には、<私>の母も来場していて、他の聴衆と一緒に<私>の話を聴いていた。
「わたしの横にいた女学生が、行き違いになる度に、溜息ついてた」母はそう云った。それから、私の声が一番大きくて、はっきり聞えたと云った。私は、母が私のした話をこの上なくよろこんでいることを感じた。あの時のことは、母にとっても戦争中の最も印象の深い出来事で、いつも一つ話のように繰返していた話であったから。(庄野潤三「団欒」)
フォーラムが終わった後、<私>は母を連れて淀屋橋近くの鰻屋へ出かけた。
母と二人で鰻料理を食べながら、私は何だかこそばゆい気持ちになる。
親孝行というものを、このように顕著な形でしたことが、これまで三十年の間に一度でもあっただろうかと考えてみて、私には記憶がなかった。そしてこの日のことも、もし教育委員会からの気まぐれな通知が舞い込みさえしなければ起り得なかっただろう。(庄野潤三「団欒」)
つまり、この作品は、<私>が母親に親孝行をすることができたということを、丁寧に綴った物語なのである。
平凡といえば平凡かもしれないが、逆に、これ以上、庄野潤三らしい作品があるだろうかという感じもする。
そして、絶えず緊張を強いられていた戦時中に、故郷を離れた東京で家族と再会できたときの喜びは、いかほどのものであっただろうか。
舞台は、昭和19年の年末年始にかけてであり、この時、庄野さんは、まだ23歳の若者だったのだ。
平和な家族を、このような状況へ追い込んだ戦争というものの悲惨な性格が、この物語の裏側には潜んでいる。
そして、家族への熱い思いは、その後も変わることなく、庄野さんは独自の家族小説を書き続けて、他に例のない庄野文学の世界を築き上げることになる。
その一つの源流が、この「団欒」という作品なのではないだろうか。
作品名:団欒
著者:庄野潤三
書名:プールサイド小景
発行:1950/02/25
出版社:みすず書房
庄野潤三の文学世界をより深く知るために
庄野潤三の世界を、もっと深く知りたいという方に、おすすめの記事をご紹介します。
庄野潤三 完全ガイド│プロフィールから詳細な年譜まで
庄野潤三について詳しく解説しています。プロフィールや代表作のほか、全著作リストや詳細な年譜、各作品の詳細考察まで、このページを読むことですべてが分かります!

庄野潤三作品一覧|年代順で読む全長編と短編集
庄野潤三の全著作を年代順でまとめてみました。あなたの読みたい作品は、この中に必ずあるはずです。