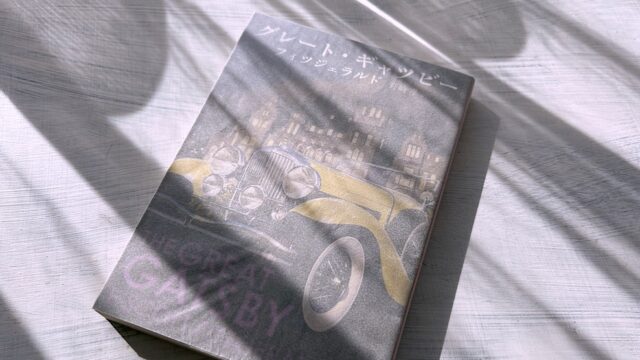ミゲル・デ・セルバンテス『ドン・キホーテ』読了。
本作『ドン・キホーテ』は、1605年に刊行された長編小説である(「前篇」)。
この年、著者は58歳だった。
10年後の1615年には「後篇」が刊行されている。
サンチョ・パンサは中世の「ドラえもん」
本作『ドン・キホーテ』は、騎士物語の読みすぎで、自分を騎士だと思いこんだ中年の男性郷士(アロンソ・キハーノ)を主人公とする冒険物語である。
妄想騎士のドン・キホーテには、あらゆる日常世界が、騎士としての「冒険」と映っている。
物語のタイトルは『ドン・キホーテの冒険』と言った方が正しいかもしれない。
実際に思慮分別をすっかり失くした郷士は、これまで世の狂人の誰ひとりとして思いつきもしなかったような、奇妙きてれつな考えにおちいることになった。つまち、自ら鎧かぶとに身を固め、馬にまたがって遍歴の騎士となり、世界中を歩きまわりながら、読み覚えた遍歴の騎士のありとあらゆる冒険を実行することによって、世の中のあらゆる種類の不正を取り除き、またすすんで窮地に身を置き、危険にも身をさらしてそれを克服し、かくして永久に語りつがれるような手柄をたてて名声を得ることこそ、自分の名誉をいやますためにも、また祖国に対する奉仕のためにも、きわめて望ましいと同時に必要なことであると考えたのである。(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
かくして、自ら「ドン・キホーテ」と名乗ることとなった主人公は(自らの妄想によって)数々の奇妙な冒険へと飛びこんでいく。
騎士の旅を支える、瘠せた愛馬には「ロシナンテ」の名が付けられた。
かくして記憶をたどり、想像をはたらかせて、数多くの名前をこしらえたり、またでっちあげたりしたあげく、ついにロシナンテと呼ぶことにした。彼の見るところでは、崇高にして響きの高いこの名はまた、この馬が以前(アンテス)は駄馬(ロシン)であったことを示すと同時に、現在は世にありとある駄馬(ロシン)の最高位にある逸物(アンテス)であることも表わしているのであった。(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
騎士の冒険には従者が必要である。
ドン・キホーテの冒険にも、愉快な従者(サンチョ・パンサ)が同行した。
ドン・キホーテは近所に住む農夫で、善良な人間(もっとも、この称号が貧乏人にも適用しうるものとして)だが、ちょっとばかり脳味噌の足りない男を口説いて、旅に連れ出そうとしていた。(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
この場合、物語のタイトルは『遍歴の騎士ドン・キホーテと愉快な従者サンチョ・パンサの冒険』となるかもしれない。
本作『ドン・キホーテ』は、ユーモア小説である(「なぜなら、ドン・キホーテに起こる冒険というのは、驚嘆か笑いのどちらかでもって称えられるべきものだからである」)。
狂気のドン・キホーテと、おしゃべりなサンチョ・パンサのコンビが提供する冒険ドラマは、世の中の人々に笑いと安らぎを提供する(本人たちは大真面目なのだが)。
遍歴の騎士に必要な「思い姫」として、ドン・キホーテが選んだ女性は「ドゥルシネーア」だった。
娘は名をアルドンサ・ロレンソといい、彼はこの娘こそおのが思い姫の称号を与えるにふさわしい相手と思いなしたのである。そこで、自分の名前とつりあいがよくとれていて、なおかつ、どこかの王女か貴婦人にでもありそうな上品な名をあれこれ探したあげく、娘がトボーソ村の生まれということもあって、彼女をドゥルシネーア・デル・トボーソと呼ぶことにした。(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
無論、ドゥルシネーアことロレンソは、ただの田舎娘にすぎない。
「あの娘っ子なら、ようく知ってますよ」と、サンチョが言った。「なにしろ、村中でいちばん力のある若い衆に負けねえほど遠くに鉄棒を投げとばす娘だからね」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
顔も知らない田舎娘のために、狂気のドン・キホーテは命を賭した冒険へと出かける。
最も良く知られるものが「風車の冒険」だ。
そのとき二人は、野原の行く手に立ち並んだ三十から四十の風車に気づいた。ドン・キホーテはそれらを目にするやいなや、従士にむかって、こう言った。「友のサンチョ・パンサよ。(略)ほら、あそこを見るがよい。三十かそこらの途方もなく醜怪な巨人どもが姿を現わしたではないか」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
風車を巨人と信じ、勇ましく飛びこんだドン・キホーテは、風車の翼に放り出されてしまう。
「やれやれ、なんてこった!」と、サンチョが言った。「御自分のなさることにようく気をおつけなさいまし。あれはただの風車で巨人なんかじゃねえと、おいらが旦那様に言わなかっただかね。おまけに、頭のなかを風車がガラガラ回っているような人間でもねえかぎり、間違えようのねえことだによ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
この物語のおもしろさは、常軌を逸したドン・キホーテの奇行と、ひと言多いサンチョ・パンサとの軽妙な会話にある。
おそらく、サンチョ・パンサの存在がなかったら、『ドン・キホーテ』はここまでの名作とはならなかったに違いない。
「御主人の名前、なんていうんだって?」と、アストゥリアス生まれのマリトルネスが尋ねた。「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」と、サンチョ・パンサが答えた。「冒険を求めて歩きまわる遍歴の騎士様でね。大昔から今日までこの世に現われた、いちばん強くて、いちばん立派な騎士方のおひとりだよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
「羊の冒険」では、羊の大群を巨大な軍勢と信じこんだドン・キホーテが、サンチョ・パンサとともに、羊の大群に圧し潰されてしまう(「実際には、主従が目にした砂煙というのは、同じ道を互いに反対方向からやってくる羊の二つの大群が立てたものであった」)。
読みながら思わず爆笑してしまう個所には、大抵の場合、サンチョ・パンサの存在があった。
「ドン・キホーテ様、どうか引き返しておくんなさい! 旦那様が攻めようとしていなさるのは、神に誓って、間違いなく羊でござりますぞ!」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
羊の大群が押し寄せていると分かっていても、ドン・キホーテに「あれは敵の軍勢だ」と言われると、それを信じてしまうところに、サンチョ・パンサのおかしさがある(「そして、ドン・キホーテがあまりにも熱心に軍勢だと言い張るので、サンチョもついにそう思うようになり(略)」)。
「床屋の冒険」では、金だらいをかぶった床屋を「頭に黄金の兜をいただいた騎士」と信じたドン・キホーテが、床屋に決闘を挑み、黄金の兜(金だらい)を手に入れる。
サンチョは主人がただの金だらいを面頬付き兜と呼ぶのを聞くと、思わず吹き出さずにはいられなかったが、主人の怒りが思い浮かんだので、笑いを途中で嚙み殺した。「なにを笑っておるのじゃ、サンチョ?」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
多くの「冒険」は、他愛のない笑い話のようなものだが、時には生命を賭けることさえ、ドン・キホーテは厭わなかった。
「ライオンの冒険」で、ドン・キホーテは、通りすがりのライオン使いに勝負を挑む。
「さあ、兄弟、そなたがライオン使いなら荷車から降りてその檻をあけ、拙者に二頭の猛獣をとびかからせてくれ。この野原のまん中で、ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャがいかなる男か、その豪胆ぶりをとくと見せつけ、拙者にライオンなどを差し向けた魔法使いどもの鼻をあかしてくれるわ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
まさに、狂気のなせる業を持って、ドン・キホーテの冒険旅行は続いた。
ドン・キホーテの狂気の凄いところは、正気の中に存在する、ということである。
「世界中の医師と知恵のある公証人が寄ってたかっても、彼の狂気を読みとることはできないでしょう。あの狂気は判読不能の草稿のようなものですから。あの人は狂気のなかに素晴らしい正気の交錯する変わった狂人ですよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
従者(サンチョ・パンサ)も、自分が使える騎士(ドン・キホーテ)が狂人であることに疑いは持っていなかった。
「まず最初に言っときたいのは、おいらは主人のドン・キホーテを極めつきの狂人とみなしているってことですよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
狂人であるドン・キホーテの中に、サンチョ・パンサは信奉するものを見つけていた。
彼もまた、一人の狂人であったからだ。
「友のサンチョよ。あんたの御主人はどう見ても狂人にちがいないね」「ちげえねえよ」と、サンチョが応じた。「だけんどあの人は、どこの誰にもなんにも負っちゃいねえ。なんでもかんでもみんな支払っちまうからね。狂気が金として通用するところじゃなおのことよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
間抜けなサンチョは、抜け目のない、狡猾な召使いでもあった。
思い姫(ドゥルシネーア)を連れてくるよう命じられたサンチョは、通りすがりの百姓娘をドゥルシネーアに仕立て上げ、「悪魔の仕業によって、ドゥルシネーアの姿が変えられてしまった」と主張する。
「やれやれ、なんて情けねえこった!」と、サンチョが応じた。「(略)あれがお前様には驢馬に見えるなんてことがあっていいもんだろうかね?」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
世の中の不都合なことは、すべて悪魔の魔法による仕業だと信じているドン・キホーテは、サンチョの主張を、そのまま受け入れた。
ドン・キホーテに「城」と見えるものが、サンチョ・パンサには「旅籠屋」と見える。
それは、すべて悪魔の仕業であると、騎士は従士に言い聞かせていたのだ。
「これはすべて」と、ドン・キホーテが言った。「いつもわしを付けねらっておる邪な妖術師どもの悪だくみであり奸策であろうな」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
もっとも、嘘をついて危機を逃れたサンチョは、後に、ドゥルシネーアの魔法を解くための犠牲とならなければならない。
自分でついたはずの「嘘」が、いつの間にか「真実」として、自分を追いこんでいくのだ。
信じることの強さがドン・キホーテを支えており、ドン・キホーテの信念に、サンチョは常に巻きこまれていた。
「お前様が懲りるなんてこたあ」と、サンチョがひきとった。「おいらがトルコ人になるのと同じくらい考えられねえことだね」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
狂った主人(ドン・キホーテ)を諫めようとしては失敗をして、主人ともどもトラブルに巻きこまれてしまう。
この物語の構図は、いかにも、我々が良く知っているものだ。
なぜなら、妄想騎士のドン・キホーテは、中世の「野比のび太」として読むことができるからだ。
知恵も体力も勇気もないくせに、しばしば勘違いの妄想によってトラブルの中に突き進んでいく「のび太」は、いかにもドン・キホーテ的な主人公である。
そして、のび太の介添役として登場する「ドラえもん」は、おっちょこちょいの従者(サンチョ・パンサ)そのものである。
もともと、藤子不二雄『ドラえもん』は、落ちこぼれの猫型ロボット(ドラえもん)と、何をやってもダメな少年(野比のび太)のコンビが織りなす笑いのドラマを描いた作品だった。
「幻の第1話」を収録した、てんとう虫コミックス『ドラえもん(0巻)』では、どのエピソードの「ドラえもん」も、おっちょこちょいの間抜けなロボットとして登場している。
悪乗りする「のび太」の忠告者としての「ドラえもん」は、まさに「ドン・キホーテ」にとっての「サンチョ・パンサ」だったのだ。
軽口の多いサンチョ・パンサの言葉の中には、心に残るものが少なくない。
「おいらはそんなこと、言いもしなけりゃ考えもしません」と、サンチョがひきとった。「人はそれぞれ自分のパンを食べればいいんであって、そんなことはおいらの知ったことじゃありませんよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(前篇)』牛島信明・訳)
おそらく、サンチョ・パンサの言葉だけで、ひとつの名言集ができあがるはずだ。
「うちの祖母様(ばあさま)がよく言ってたように、この世にはただ二つの家系しかねえ。つまり、金を持っているのと持たねえの二つだね。もっとも、祖母様は持ったほうをひいきにしてましたよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
サンチョ・パンサの言葉は、庶民の生々しい言葉である。
「おいらは王様を倒すわけでもなけりゃ、もりたてるわけでもねえ」と、サンチョが答えた。「ただ自分自身を助けようというんだ。何といっても、おいらの主人はおいら自身だからね」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
世直しの旅に出た理想の勇者(ドン・キホーテ)とは対称的なサンチョ・パンサの姿に、我々は熱い共感を抱くのだ。
「何でも着せてくれるものを着ることにしますよ」と、サンチョが言った。「どんななりをしていこうと、おいらがサンチョ・パンサであることに違いはねえんだから」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
領主の身分を手放したサンチョは、一介の庶民に戻ったことを激しく喜んでいる。
「まあ、お前さん方は、ここで楽しく暮らすがいいよ。公爵様には、こう言っておいてくれろ。サンチョは裸で生まれて、今も裸、損もしなけりゃ得もしねえってね」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
今年、読んだ小説の中で最もおもしろかった作品。
本作『ドン・キホーテ』の魅力は、あるいは、サンチョ・パンサの魅力だったかもしれない。
メタフィクションとしての『ドン・キホーテ』
1605年に『ドン・キホーテ(前篇)』が発表された後、1614年、「アロンソ・フェルナンデス・デ・アベジャネーダ」と名乗る作者による『ドン・キホーテ(続篇)』が出版された。
いわゆる『贋作 ドン・キホーテ』である。
「ニセモノ」の『ドン・キホーテ』は、真の作者であるセルバンテスに大きな刺激を与えたらしい。
「どうです、ドン・ヘロモニさん、夕食が運ばれてくるまでのあいだに、『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』の続篇をもう一章、読んでみようじゃありませんか」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
『ドン・キホーテ(後篇)』では、贋作版『ドン・キホーテ(続篇)』が、繰り返し登場する。
「お前様方、どうか信じてくださいよ」と、サンチョが言った。「この本に出てくるサンチョとドン・キホーテは、あのシデ・ハメーテ・ベネンヘーリが書きなさった物語の中で活躍してる本物のわしらとは別物ですからね」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
『ドン・キホーテ』は、「シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ」という名の人物によって描かれた物語であり、作者(セルバンテス)は、この作品の翻訳者である。
作者(セルバンテス)は、この設定上の原作者(シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ)に折々触れて、『ドン・キホーテ』という物語の客観性を生みだそうとしている。
『ドン・キホーテ(続篇)』がニセモノの作者によって執筆された作品であることを証明するため、『ドン・キホーテ(前篇)』についての言及が繰り返される。
「すると学士さんが、お前様の伝記が『機知に富んだ郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』という題の本になって、とっくに出まわっていると教えてくれましてね。しかも、そこにはおいらもサンチョ・パンサという本名で登場するし、ドゥルシネーア・デル・トボーソ姫のことも、さらにお前様とおいらが二人だけで話し合ったことなどもみな載っているというもんだから、その伝記の作者は一体全体どうしてそういうことを知ったものかとびっくり仰天して、思わず十字を切ったほどですよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
完全なるメタフィクションである。
「あの物語の欠点のひとつと見なされているのは」と、学士が言った。「作者がそこに『愚かな物好きの話』と題する小説を挿入していることです」(略)「すると、どうやら」と、ドン・キホーテが言った。「わしのことを書いた物語の作者は、賢者どころか無知なおしゃべりで、いっさい筋道を立てることもなく、出たとこ勝負で、やみくもに書きはじめたに違いありませんな」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
『ドン・キホーテ(前篇)』への評価に対する作者自身(セルバンテス)の見解が、物語の主人公であるドン・キホーテの言葉をもって語られている。
あるいは、原作者(シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ)の意図を、作者が補足説明することもあった。
そこで、この不都合を回避するために、『前篇』においては、そこに「愚かな物好きの話」や「捕虜の話」のごときいくつかの短篇を挿入するという工夫をしてみたのだが、それらはいずれも物語の本筋からは遊離している。というのも、その書におさめられたほかの話はすべてドン・キホーテ本人に起こった、書かずにすませるわけにはいかないことばかりだったからである、と。(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
ストーリー上の欠陥は「印刷上のミス」になっていたりする。
もっとも前篇では、印刷所の職人の過失で、驢馬がいついかにして盗まれたのかが記されなかったものだから、多くの読者がどう考えるべきかと当惑し、印刷上のミスを著者の物忘れのせいにしたりしたものであった。(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
『ドン・キホーテ(後篇)』において、主人公(ドン・キホーテ)は、既に「伝記」までが出版されて、高い評判となっている(狂気の)騎士である。
「ついに拙者は本に描かれ、すでに世界のほとんどすべての、あるいは大半の国々で印刷されて出まわるまでになりました。さよう、拙者の伝記がすでに三万部印刷され、天意がそれを妨げぬかぎり、これから千部の三万倍も増刷りされようとしておりまする」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
主人公(ドン・キホーテ)が、『ドン・キホーテ』という物語の主人公を演じ続けていくという、現実と虚構とが重なり合った構図は、伝説の騎士物語と現実との区別がつかないドン・キホーテそのものでもある。
「わしはただ、遍歴の騎士道が栄華を誇っていた、あの幸福な時代を再興しようとせぬ今の世の錯誤を、世の人に悟らせたいと腐心しておるだけでござるよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
ドン・キホーテの目的は、ただ「世直し」だった。
作者自身の正当性を主張しながら、贋作『ドン・キホーテ(続篇)』への攻撃は続く(「あの新しい作家の物語が嘘であることを暴きたてたいというドン・キホーテの願望はかくまでに強かったのである」)。
「勇敢なるドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ殿! 近ごろ出まわっている偽の物語がわれわれに示している、虚構にしていかさまの、えたいの知れぬドン・キホーテではなく、作家の中の華たるシデ・ハメーテ・ベネンヘーリが描いた正真正銘にして正統なるドン・キホーテ殿!」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
『ドン・キホーテ(前篇)』への言及と『ドン・キホーテ(続篇)』への批判は、『ドン・キホーテ(後篇)』の重要な基盤となっている。
『ドン・キホーテ(前篇)』では、ドン・キホーテ自身の妄想が「冒険」を創り上げていたが、『ドン・キホーテ(後篇)』においては、『ドン・キホーテ(前篇)』を読んだ人々が、ドン・キホーテに「冒険」の舞台を提供していく。
ドン・キホーテの狂気を嘲笑いながら、自分たちの狂気には気づかない滑稽な人々は、(当時の)現代社会の象徴でもあったことだろう(「人を愚弄する者たちも愚弄される者たちと同じく狂気にとらわれていると思う」)。
結局のところ、この物語は、ドン・キホーテという妄想騎士の狂気を描きながら、世の中の狂気そのものを描いていたのだ。
「銀月の騎士」との闘いに破れたドン・キホーテは、失意のうちに帰郷する。
「だが、拙者は惨めな身のほどをわきまえずに、何を言っているのだろう? 拙者は打ち倒された身ではないか? 負け犬ではないか?(略)何を偉そうな口をきいているのじゃ、このわしは?」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
彼らの旅は、道半ばだったかもしれない。
それでも、ドン・キホーテは、妄想騎士という自身の狂気を貫き通した。
「ああ、懐かしいおいらの古里。お前さんの息子のサンチョ・パンサが、あんまり懐は豊かじゃねえけど、鞭だけはどっさりくらって帰ってきたのをようく見とくれよ。それから腕を広げて、やっぱりお前さんの息子のドン・キホーテ様を出迎えとくれ。ドン・キホーテ様は他人に打ち負かされはしたものの、御自分には打ち勝って戻りなさったんだよ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
療養生活の中で、狂気から目覚めたドン・キホーテは、かつての郷士(アロンソ・キハーノ)へと戻っていく。
「友のサンチョよ、どうか赦しておくれ。この世に遍歴の騎士がかつて存在し、今も存在するという、わしのおちいっていた考えにお前をおとしいれ、わしだけでなく、お前にまで狂人と思われるような振舞いをさせて本当にすまなかった」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
正気を取り戻したドン・キホーテに、生きる活力はなかった。
ドン・キホーテは、狂気の中にあってこそ、(本当の)人生を生きることができたのだ。
ここに眠るは屈強なる郷士(略)/狂気に生きて/正気に死にしは幸いなり。(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
人は誰しも、夢に生きる瞬間というものがあるものだ。
世の中が彼を笑っても、その瞬間、彼は本当に幸せだったのである。
「およしなさいよ、ドン・キホーテ様」と、使者がひきとった。「魔法だとか変身だとかおっしゃるのは。そんなものは、これっぽっちもなかったんですから」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
風車に戦いを挑んだドン・キホーテを、世界は「狂人」と呼んだ。
その「狂気」の中に、我々に必要とされているものが、もしかすると含まれてはいなかっただろうか?
「だけど、まあ、なんでも書きたいことを勝手に書けばいいさ。《おいらは裸で生まれて、今でも裸一貫、だから損もしなけりゃ得もしねえ》(略)人になんと言われようと、おいらは痛くもかゆくもありゃしねえ」(セルバンテス『ドン・キホーテ(後篇)』牛島信明・訳)
諺(ことわざ)の好きなサンチョ・パンサの言葉とともに、ドン・キホーテの冒険は、現代社会を生きる人々に(神さまが与えてくれた時間を)生き延びていくだけの勇気を与えてくれる。
そして、この複雑な物語を、現代日本の(豊饒な)言葉で再現した翻訳の素晴らしさ。
本作『ドン・キホーテ』は、生きている間に一度ならずとも読んでおくべき、名作中の名作文学である。
『ドン・キホーテ』を読み終えた後には、『ドン・キホーテ』を読まない人生に、何の意味があるだろうかと、思わずにはいられないことだろう。
書名:ドン・キホーテ(前篇・後篇)
著者:ミゲル・デ・セルバンテス
訳者:牛島信明
発行:2001/03/16
出版社:岩波文庫