米川正夫「鈍・根・才」読了。
本書「鈍・根・才」は、ロシア文学者・米川正夫の自伝である。
1962年に河出書房新社から発行されているが、1997年に日本図書センターの「人間の記録」シリーズに入っている。
足助素一と有島武郎
ロシア文学者の自伝というから、随分と堅苦しいのだろうというイメージを持っていたけれど、米川正夫の生涯は案外と砕けている。
幼少期から辿っているから、もちろん、文学の話ばかりというのではない。
若い頃には、随分と女遊びが好きだったようなエピソードも多いが、下世話に過ぎると感じる向きもあるかもしれない。
私生活に小説の鍵が潜んでいる小説家とは事情が異なるとすれば、こうした文学者の自伝は、やはり文学の部分に集中して読みたい。
そういう視点で読んでいくと、興味深い内容も多い。
例えば、叢文社からプーシキンの『オネーギン』の翻訳を出版したのは、宮原晃一郎の紹介によるものだった。
宮原晃一郎は、終戦直後に物故した北欧文学の翻訳家だが、かつて新聞記者として札幌に在住していたことがあって、有島武郎とも親しかった。
叢文社の社主・足助素一は、札幌農学校で有島と一緒だったので、宮原ともつながりがあり、その縁で米川正夫に指名がかかったのである。
このときの『オネーギン』は評判が良かったが、次に出したメレジコーフスキイの戯曲『パーヴェル一世』が失敗して、かなりの返品となってしまう。
後に、新潮社の「近代劇大系」(大正13年)に、この『パーヴェル一世』を加えようとしたところ、足助素一が激怒して「返本分の印税を払い戻せ」と言ってきたそうである。
その後、上野の絵画展覧会で、たまたま有島武郎氏にあった。私は大正九年に、『惜しみなく愛は奪う』が出たとき、その批評を時事新報に二回にわけて掲載した。そのとき有島氏から丁重な長い手紙を貰ったが、直接会って言葉を交わす機会はなかったのである。そのとき有島氏は『パーヴェル』事件のことを言い出して、「あれはさぞ不愉快だったでしょうね。僕も足助に、君のほうがよくないと言ったんですよ」といってくれたので、私の気持ちが明るくなった。(米川正夫「鈍・根・才」)
ちょっとした大正文壇史の一幕といったところだが、有島武郎の登場が意外で楽しかった。
直木三十五と宮本百合子
興味深い大正文壇の話として、もうひとつ。
大正十年頃、冬夏社という出版社が、最初のドストエフスキー全集を出版し始めた。
冬夏社というのは、前述の春秋社の姉妹会社で、植村宗一(直木三十五)が、神田豊穂から独立した、第一回の事業であった。
これもトルストイの場合とおなじように、早大出身の作家の重訳が、大部分を占め、われわれロシヤ語の連中は、ほんのお義理で挟まれた形であった。私は『スチェパンチコヴォ村とその住人』をふり当てられた。はじめから役不足みたいな不満をいだいていた私は、その後、植村の態度が快からず思われ、かつ金払いも悪かったので、百枚ばかり訳した時、ついにこの全集の参加を拒絶してしまった。(米川正夫「鈍・根・才」)
直木三十五に対する反感は強かったようだが、本書の著者も、なかなかに難しい人だったようで、あちこちで関係をこじらせた話が出てくる。
最後に、モスクワで宮本百合子に会ったときのエピソード。
私がソヴィエトを去る少し前に、彼女をピリニャークの家へ案内した。そのとき彼は私の耳に口を寄せて、「今夜の彼女の訪問は、私にとって事件的な意味を有する」とささやいた。色ごのみの彼は、百合子に日本女性のよさを感じたのであろう。私も彼女の色白の顔が好きだったが、ただ肥り過ぎているのが残念だった。(米川正夫「鈍・根・才」)
宮本百合子が二度目にピリニャークを訪問したとき、彼は百合子を抱き上げて、寝室のベッドの上に放り投げたそうである。
それから、百合子は、ピリニャークのことを「バックボーンのない男」と言うようになった。
書名:鈍・根・才
著者:米川正夫
発行:1997/12/25
出版社:日本図書センター
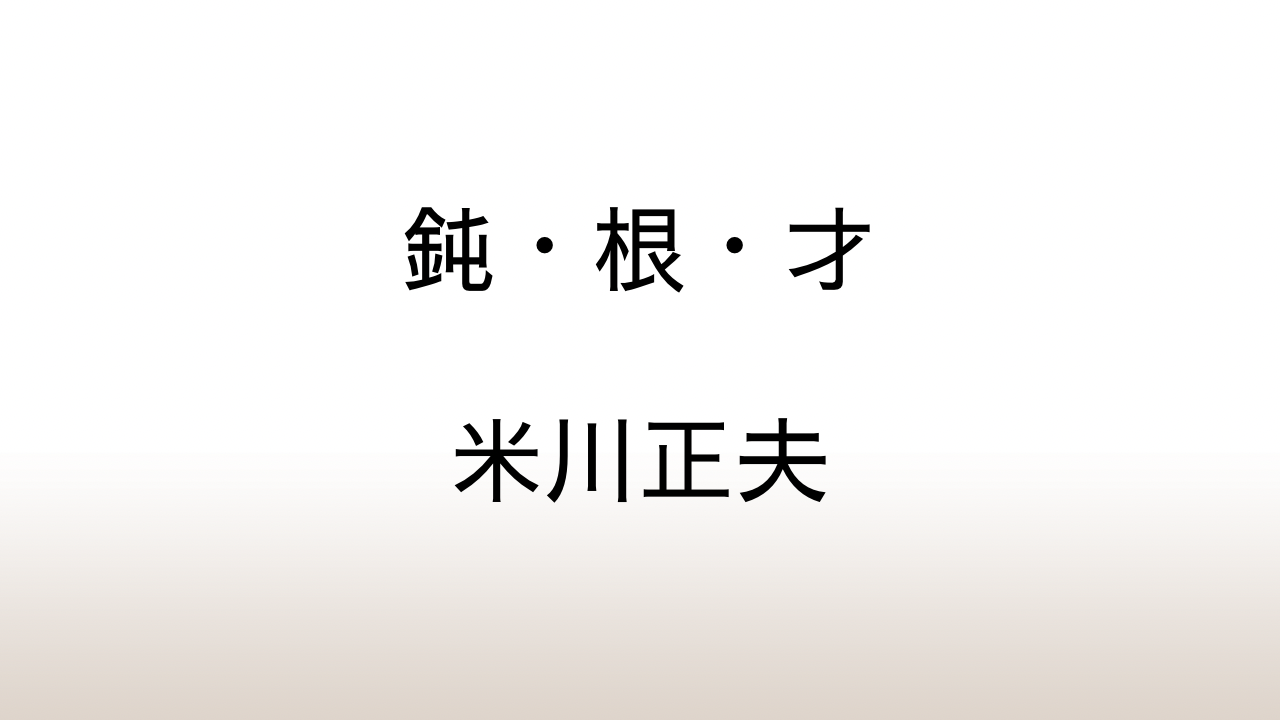
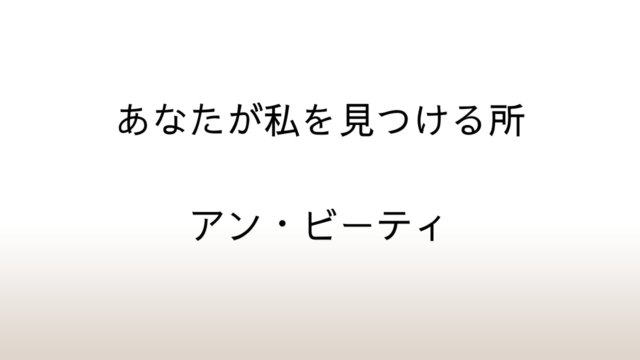




-150x150.jpg)









