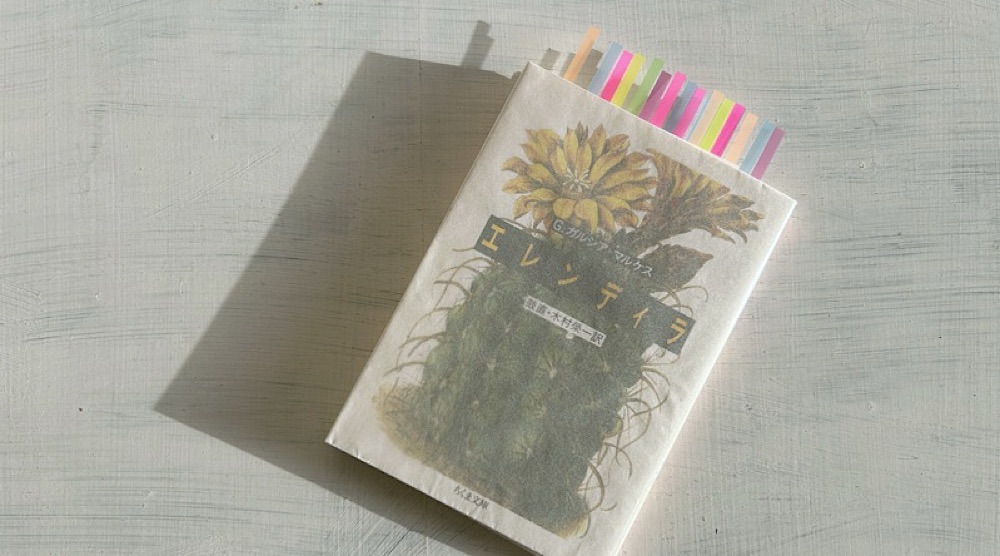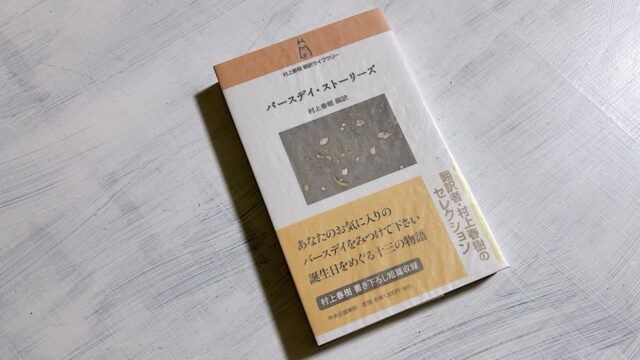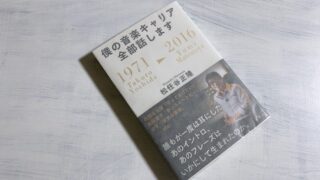ガブリエル・ガルシア=マルケス『エレンディラ』読了。
本作『エレンディラ』は、1978年(昭和53年)刊行された短篇小説集である。
この年、著者は50歳だった。
収録作品は次のとおり。
・大きな翼のある、ひどく年取った男
・失われた時の海
・この世でいちばん美しい水死人
・愛の彼方の変わることなき死
・幽霊船の最後の航海
・奇跡の行商人、善人のブラカマン
・無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語
メルヘンを越えた大人の童話集
本作『エレンディラ』は、ガルシア=マルケスにとって3冊目の短篇小説集である。
ガルシア=マルケスは、生涯で全4作の短篇集を刊行した。
リストは次のとおり。
①青い犬の目(1962)
②ママ・グランデの葬儀(1962)
③純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語(1978)
④十二の遍歴の物語(1992)
本作『エレンディラ』の正式タイトルは『純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語』だが、「便宜上短く『エレンディラ』と変えさせていただいた」と、ちくま文庫版「訳者あとがき」にある。
ガルシア=マルケスのマジック・リアリズム(魔術的リアリズム)は、長篇『百年の孤独』(1968)で完成し、『族長の秋』(1975)へと受け継がれていった。
本作『エレンディラ』に収録されている短篇小説は、『百年の孤独』から『族長の秋』までの間に発表された作品が収録されている。
大きな特徴は、前の短篇集『ママ・グランデの葬儀』にはなかったマジック・リアリズムによる効果的な展開である。
「これは、天使だよ」と彼女は言った。「きっと、子供のことで来たんだね。でも気の毒に、年を取りすぎていて、雨にはたき落とされたのさ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大きな翼のある、ひどく年取った男」鼓直・訳)
大きな翼のある老人がとらえられる物語は、既に童話(メルヘン)の世界に近いが、ガルシア=マルケスにとって「飛べない天使」は何を象徴していたのだろうか。
神父は、こいつはうさん臭いぞと思った。さらに近づいてみて、あまりにも人間に似ていることに気づいた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「大きな翼のある、ひどく年取った男」鼓直・訳)
はっきりしているのは、不思議な存在を前にしたときの、民衆の愚かな行動である。
ここに描かれているのは、年寄りの天使を中心として巻き起こる、民衆の物語なのだ。
民衆は、常に物語の主役となっている。
「バラの香りがしたろう」とトビーアスは続けた。「あれは海から来たんだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
美しいバラの香りは、海の向こうからやってくる異文化を象徴している。
海辺の小さな村にとって、それは大きな意味を持っていたかもしれない。
「最後のお願いがあるんですけど」と切りだした。「私を生きたまま埋葬していただけないでしょうか」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
バラの匂いにおびえる妻は、ヤコブ老人をうながして海から逃げようとする。
匂いを感じた人もいたが、大半のものはなにも感じなかった。しかし、老人たちは匂いをもっとよく嗅ごうと浜に降りていった。それは、以前のどんな匂いをも忘れさせるほど強いものだった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
海からやってきた「バラの匂い」に、人々の暮らしは翻弄された。
「バラの匂いなど願い下げだね」ヤコブ老人はそう言った。「ただひとつ、自分の人生で手遅れになったもの、それがこのバラの匂いなんだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
『百年の孤独』にも通じる歴史や文化への執着が、物語の背景にある。
それは、戦争や革命の時代を生きてきた人々の、痛々しいまでの歴史と文化だった。
「いくらだね?」とハーバート氏はたずねた。「五ペソです」「すると百人の男を相手にすることになるが」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
100人の男を相手にする娼婦は、表題作『エレンディラ』にも共通するモチーフだった。
「現実とはつまり、あの香りは二度と戻ってはこないということなのだ」とハーバート氏は続けて言った。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
失われていく歴史や文化への執着。
それは、耐えながら生きる人々の希望と言っていいかもしれない。
「海の底に」とトビーアスは話しはじめた。「小さな白い家の立ち並んだ村があるんだ。そこのテラスには花が無数に咲き乱れているんだよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「失われた時の海」木村栄一・訳)
本作『失われた時の海』は、長篇『百年の孤独』にも通じる、重量感のある短篇小説である。
『この世でいちばん美しい水死人』は、ひとつの英雄伝説として読むことができる。
あの水死人は海の溺死体のようにさみしそうな顔をしてはいなかったし、川で溺れた人間のように卑しくさもしい表情も浮かべていなかった。ごくふつうの水死体ではあったが、どこか誇らかなところがあった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「この世でいちばん美しい水死人」木村栄一・訳)
海から流れてきた「水死人」は、民衆に大きく作用していく。
本作品集の中では、前向きな読後感を与える物語だ。
次の「愛の彼方の変わることなき死」では、再び『百年の孤独』的な世界へと導かれていく。
「これまでわれわれは、祖国に見棄てられた人間、乾きと悪天候のなかに生きる神の孤児、自分の土地に住みながら流刑囚でしかなかったのです。諸君、今こそわれわれは生まれ変わらなければなりません。偉大な、そして幸福な人間にならなければならないのです」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「愛の彼方の変わることなき死」木村栄一・訳)
権威に振り回される民衆と、権力者の孤独。
「お前も私と同じで、人から愛されはしないのだよ」溜息をつきながら彼はそうささやいた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「愛の彼方の変わることなき死」木村栄一・訳)
「人から愛される」とは、つまり、「民衆から愛される」ということでもあったかもしれない。
生き続ける民衆の姿
『幽霊船の最後の航海』では抑圧された民衆が主人公となっている。
世間の奴ら、おれがどういう人間か、今に分からせてやるぞ! 最近やっと声変わりした男らしい声で、彼は呟いた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「幽霊船の最後の航海」鼓直・訳)
いつか来るかもしれない幽霊船を、彼は待ち続けていた。
世間の奴ら、おれがどういう人間か、今に分からせてやるぞ! そればかりを考えながら一年という月日を送り、もう一度同じことを繰り返すために、まぼろしの出現する一夜の訪れるのを待った……。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「幽霊船の最後の航海」鼓直・訳)
巨大な幽霊船へ立ち向かっていく彼は、あるいは、セルバンテス『ドン・キホーテ』に出てくるサンチョ・パンサではなかっただろうか。
それはもはや、三月の朝ではなく、太陽のぎらつく水曜日の真昼だった。彼は、この世でもっとも巨大な船と教会の前に乗り上げているもう一隻の小舟を、口をぽかんと開けて、とても信じられないという表情で眺めている群衆を見て、やっと腹の虫がおさまった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「幽霊船の最後の航海」鼓直・訳)
ここにも、民衆の愚かな姿が、共感の視線を伴って描かれている。
国家を(つまりは歴史と文化を)育んできたのは、いつの時代も民衆だったのだ。
『奇跡の行商人、善人のブラカマン』も、権力者に翻弄される民衆が主要なモチーフである。
お集りの皆さん、このわたしにもひとつだけできないことがあります。それは死者を蘇らせることです。といいますのも、死人がばっちり目をあけるのはいいのですが、せっかく人が気持ちよく眠っていたのに、なぜじゃまをしたのだ、と言って怒りだし、どんな乱暴を働くか、知れたものではないからです。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「奇跡の行商人、善人のブラカマン」木村栄一・訳)
この作品では、優れたマジック・リアリズムを楽しむことができる。
今になってようやく分かったのだが、このわしの運命を捻じ曲げてしまったのはおまえなんだ。さあ、ズボンをしっかり縛るんだ、おまえが捻じ曲げてくれたこのわしの運命をまっすぐにしてもらおうか。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「奇跡の行商人、善人のブラカマン」木村栄一・訳)
生と死は、ガルシア=マルケスにとって、常に大きなテーマだった。
墓の下で死ねば、また蘇らせてやるまでのことだ。というのも、ぼくが生きている限り、つまり永遠にということだが、あの男は墓の下で生きつづけなければならない。それが、あの男に課してやった、慈悲にあふれた懲罰なのだから。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「奇跡の行商人、善人のブラカマン」木村栄一・訳)
「墓の下で生き続けている」のは、権力者であり、民衆でもある。
マジック・リアリズムだからこそ再現することのできる世界が、ガルシア=マルケスの作品にはあった。
その象徴的な作品こそ、表題作『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語』(略称『エレンディラ』)である。
本作『エレンディラ』は、無数の男たちと寝ることを課された、悲しい娼婦の物語である。
「まだほんの子供だな。犬みたいに小さな乳首をしてる」男はその判断を数字で証明するつもりだろう、エレンディラを秤の上にあがらせた。四十二キロしかなかった。「百ペソ以上の価値はないな」と男が言った。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
エレンディラを売るのは、実の祖母だった。
祖母は憤慨して、叫ぶように答えた。「正真正銘の生娘だよ。それをまあどうだろう、たったの百ペソだなんて! いやだね、お断りだよ。それにしても、生娘もずいぶんと安くなったもんだねえ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
生娘には金をはずむということで砂漠中で評判の男を相手に、祖母は駆け引きを続ける。
「ぎりぎり百五十だ」と男が言った。「この娘のおかげで百万ペソ以上の損をしたんだよ」と祖母がやり返した。「この調子じゃ、払いきるまでに二百年もかかっちまう」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
祖母の言いなりとなって、エレンディラは、見知らぬ男たちに身体を売り続けた。
「この調子で行けば」と祖母はエレンディラに話しかけた。「八年七ヵ月と十一日で払い終わるよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
エレンディラの救世主として現れたのがウリセスである。
「あんた、名前は?」「ウリセス」「外国人みたいな名前なのね」とエレンディラが言った。「いや、船乗りなのさ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
自由を持たない女(エレンディラ)は、どこか、自由を持たない国で生きる人々の姿を思わせる。
「殺す勇気ある?」度肝を抜かれてウリセスは返事に窮した。「どうかな……君は?」「わたしはだめ」とエレンディラは答えた。「わたしのお祖母ちゃんだもの」(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
本作『エレンディラ』は、無垢の少女エレンディラが、祖母の支配から独立するまでの過程を描いた物語である。
ウリセスを犠牲にして、エレンディラは祖母からの逃避に成功した。
だが、独裁者の支配下で生きる民衆は、どうして逃げることができるだろうか?
格闘で力を使い果たしたウリセスは、屍体のそばにへたり込んでいた。顔を拭いてみたが、それは、拭けば拭くほど、自分の指から流れでるとしか思えない生きた緑色のもので汚れていった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」鼓直・訳)
あるいは、男たちの凌辱に耐え抜くエレンディラの姿は、懸命に生きる民衆の姿そのものだったかもしれない。
書名:エレンディラ
著者:ガブリエル・ガルシア=マルケス
訳者:鼓直、木村栄一
発行:1988/12/01
出版社:ちくま文庫