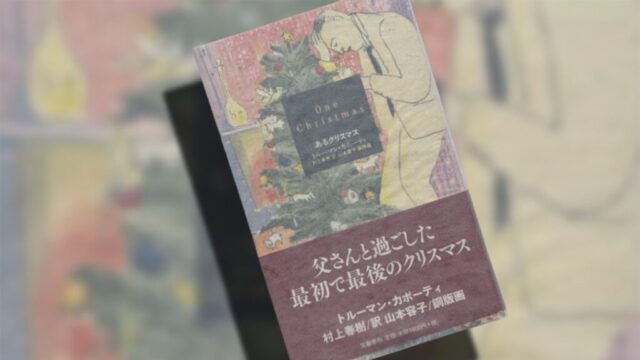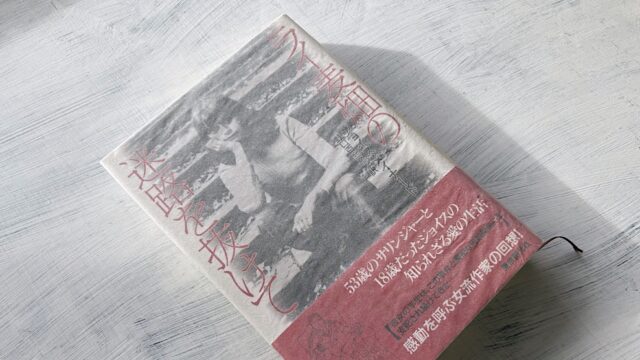村上春樹「レキシントンの幽霊」読了。
本作「レキシントンの幽霊」は、1996年(平成8年)10月『群像』に発表された短編小説である。
この年、著者は47歳だった。
作品集としては、1996年(平成8年)11月に文藝春秋から刊行された『レキシントンの幽霊』に収録されている。
なお、初出の『群像』に発表されたものは「ショート・バージョン」と呼ばれており、作品集には「ロング・バージョン」が収録された。
高等学校の国語教科書に掲載されているものは、いわゆる「ショート・バージョン」である。
幽霊の正体は「不思議な話」の中にある
本作「レキシントンの幽霊」は、継承と断絶の物語である。
読み終えながら、僕は、日本の古典『平家物語』を思い出したくらいだ(ガチガチにアメリカが舞台の小説なのに)。
国語の教科書に載っているとは言え、一般的に「レキシントンの幽霊」は、「何を意味しているのかわからない」という読後感想が多い。
本作を読み解く最大のヒントは、物語のいちばん最後の段落にある。
ときどきレキシントンの幽霊を思い出す。ケイシーの屋敷の居間で真夜中ににぎやかなパーティーを開いていた幽霊たちのことを。そして二階の寝室でこんこんと深く眠り続けるケイシーと、彼の父親のことを。犬のマイルズや、立派なレコード・コレクションのことを。(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
この部分は、単に感傷的な回想のフレーズを並べたものではない。
本作「レキシントンの幽霊」を読み解く上で鍵になる言葉が、まとめて提示されているのである(村上春樹の小説では、時々こういう手法が見られる)。
「賑やかなパーティーを開く幽霊」や「深く眠り続けるケイシーと彼の父親」、「犬のマイルズ」に「立派なレコード・コレクション」。
この4つのキーワードに注意しながら、物語を読み進めることで、作品テーマが把握しやすくなるだろう。
さらに、作品理解を進めるため、物語の構造をめちゃくちゃシンプルに単純化してしまうという方法もある。
例えば、この物語は、友人(ケイシー)の家に泊まった主人公(「僕」)が「幽霊」に遭遇する前半部分と、最後に会ったときにケイシーから聞いた「不思議な話」という後半部分の、大きく二つのエピソードに分けることができる。
前半の「幽霊」が事件で、後半の「不思議な話」が事件の種明かし、つまり謎解きという構造になるだろうか。
はじめに、具体的な事件となった「幽霊」のエピソードについて。
その銀色のコインは僕に、ソリッドな現実の感覚を思い出させてくれた。僕はそこではっと思い当たった。――あれは幽霊なんだ。居間に集まって音楽を聴き、談笑しているのは現実の人々ではないのだ。(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
真夜中の屋敷でパーティーをしている「幽霊」は、この物語における大きな謎となっている。
果たして、彼ら(幽霊)は何者なのか?
その正体は明かされていないものの、少なくとも主人公は、それは邪悪なものではなかったと感じている。
しばらくのあいだ僕はその玄関ホールのベンチに、まるで魅入られたように一人で座り込んでいた。もちろん怖かった。でもそこには怖さを越えた何かがあるような気がした。(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
「怖さを越えた何かがあるような気がした」という一文が、その「幽霊」が邪悪なものではなかったことを示唆している。
それでは、主人公の言う「幽霊」とは、いったい何を意味しているのだろうか?
その答え(というかヒント)は、後半の「不思議な話」として語られている中にあった。
友人ケイシーの父親は、彼の妻(つまりケイシーの母親)が死んだとき、三週間もの間、死んだように眠り続けたという。
そして、ケイシーが、そんな父親の気持ちをきちんと理解することができたのは、彼の父親が死んだときだった。
「それで不思議な話なんだが、父が死んだとき、母が死んだときに父がしたのと同じように、僕もまたベッドに入ってこんこんと眠り続けたんだ。まるで血統の儀式でも継承するみたいにね」(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
父が死んだとき、二週間もの間、「時間が腐ってしまうまで眠った」ことの意味について、ケイシーは、次のように語っている。
「僕の言っていることはわかるかな? つまりある種のものごとは、別のかたちをとるんだ。それは別のかたちをとらずにはいられないんだ」(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
ケイシーや彼の父は、大切な家族を失った喪失感を、死者との同化を意味する「長い眠り」という「別のかたち」で表現した。
「別のかたち」を取らなければならない「ある種のもの」とは、つまり、言葉では表現することのできないくらいの、強く激しい感情のことだったのだろう。
この「不思議な話」は、家族における世代間継承(父親から息子へ受け継ぐもの)を象徴するエピソードとして読むことができる。
つまり、注目すべきは「ある種のものが別のかたちをとること」そのものではなく、それが「父と子の親子二代に渡って行われたこと」にある、ということだ。
移り変わっていく世の中のはかなさ
それでは、この「不思議な話」から導かれる「幽霊」の正体とは、いったい何だろうか。
後半に語られている「不思議な話(長い眠り)」のテーマは「親子の世代間継承」である。
この「世代間継承」こそが、この物語の大きな鍵となっていることは、ケイシーが「父親の古いジャズ・レコードの見事なコレクション」を継承していることにも象徴されている。
一方で、兄弟のないケイシーは、50歳を過ぎているというのに、30代半ばの男性ピアノ調律師(ジェレミー)と二人で、ほとんど孤独に近い暮らしを送っていた。
母親の死を機会に、ジェレミーはケイシーのもとを去ってしまうから、もはやケイシーは完全に一人ぼっちである。
父親から受け継いだ遺産(レコード・コレクション)を、次に譲り渡すべき世代もいない。
ゼロだ。
つまり、親子の世代間継承がケイシーの代によって断絶されてしまうわけで、そこにこの物語の最も重要な主題がある。
主人公が遭遇した「レキシントンの幽霊」は、おそらく、かつてケイシーの父親が見ていただろう、若き日々の残像だ。
コール・ポーターやジョージ・ガーシュインの音楽をBGMに、賑やかなパーティーを催していた頃の、充実した父の時代。
犬(マイルズ)の姿が見えなくなっていたことは、幽霊のパーティーが行われている世界が、現実世界ではない「異界」であったことを示している。
「異界(過去の残像)」への案内役を、マイルズ(犬)が務めていたと考えてもいい。
時は流れ、父は亡く、ケイシーには父から受け継いだ遺産を譲り渡す次の世代もいない。
ここで、僕は、日本の古典『平家物語』を思い出す。
『平家物語』は、「祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」という有名なフレーズで始まっている。
世の中は、すべて移り変わっていくものであることを、象徴的に示した言葉だが、本作「レキシントンの幽霊」には、諸行無常の響きが流れているのではないだろうか。
それは、子どものいない人生を呪うケイシーの悲しみでもなければ、レコード・コレクションの行方を嘆く恨みの声でもない。
かつて、賑やかだった父の時代を懐かしく偲び、世の中ははかないものであるという事実を静かに受け入れる、虚無自在の心境だ。
「幽霊」と遭遇した後で「でもそこには怖さを越えた何かがあるような気がした」という主人公の言葉は、そんなケイシーの心境を反映したものだったのかもしれない。
「怖さを越えた何か」を具体的に示すと、それは「しみじみとした懐かしさ」ということになるだろう。
「ひとつだけ言えることがある」とケイシーは微笑みを顔に浮かべて言った。「僕が今ここで死んでも誰も、僕のためにそんなに深く眠ってはくれないということだね」(村上春樹「レキシントンの幽霊」)
「血統の儀式」を継承する者がいないという現実を、既にケイシーは素直に受け入れようとしている。
おそらくは虚無自在の心境になって。
本作「レキシントンの幽霊」の主役は、友人ケイシーであり、主人公(「僕」)は、ケイシーの物語を伝える語り部に過ぎない。
ケイシーの父親が見た若き日の残像(つまり「レキシントンの幽霊」)まで含め、主人公は霊媒的な役割を果たしつつ、ケイシーの伝説(諸行無常の物語)を伝え続けているのかもしれない。
昔の日本では、名もなき琵琶法師たちが、平家の物語を語り継いできたのと同じように。
作品名:レキシントンの幽霊(ショート・バージョン)
著者:村上春樹
書名:『群像』1996年10月号
発行:1996/10
出版社:講談社
村上春樹の文学世界をより深く知るために
もっと村上春樹の世界を知りたいという方に、次の記事もおすすめ。
村上春樹作品の読み方完全ガイド
村上春樹の読み方を解説した完全ガイド。村上春樹のプロフィールからオシャレな楽しみ方まで。本サイトの村上春樹はここから始まります。

村上春樹のおすすめ作品10選+α
どの作品から読み始めるべきか迷っている方に。全作品から厳選したおすすめ10作品+αを解説しています。